就業規則
転籍先の倒産で元社員を職場復帰させないとダメなの?

うちの関連会社のA社が倒産した。3年前にはうちから転籍した者もいる。その元社員から、A社が倒産したのでうちに復帰したい、との連絡があった。どうすればいいのか・・・
**
転籍した元社員からの申し入れに、戸惑う人事担当者さんです。というのも、転籍とは、社員と従来の雇用関係のあった企業との労働関係が解消され(退職)、新たに他の企業に雇い入れられる(採用)ことだからです。
転籍先企業が倒産したということで、転籍した元社員を受け入れなければならないのでしょうか。
そこで今回は、転籍先企業の倒産による元社員の復帰問題について、詳しく確認していきたいと思います。
残ってほしい人には早期退職優遇制度を認めなくていいの?

40代後半以降の中高齢層を対象に、転職・独立開業サポートを組み合わせた早期退職優遇制度を設けようという話になった。とはいえ、残ってほしい人が退職してしまうという事態は避けたい。制度の適用は会社が承認した人だけ、と限定してはダメなのかな?
**
社員のセカンドキャリア支援のため、早期退職優遇制度を検討する人事担当者さんです。社員の高齢化が進む中、会社としては管理職のスリム化という意味合いもあります。
制度の適用を会社の承認によるものにすると、社員に不利益を与えることになるのか?と考え込んでいます。
そこで今回は、早期退職優遇制度の適用に会社の承認という要件を設けてもいいのか、詳しく確認していきたいと思います。
会社が社員にワクチン接種を推奨するのはダメですか

感染症対策のため、ワクチン接種を推奨するポスターを作成して社内掲示板に貼ってはどうか、との案が会議であがった。ただ、ごくまれとは聞くけれど重いアレルギーなど、重症の副反応(副作用)が起きる人もいる。会社が社員にワクチン接種を推奨して問題ないのかな?
**
会社がワクチン接種を推奨し、ワクチン接種を接種した社員に重症の副反応が起きた場合、会社がその社員に対する安全配慮義務に問われることはないのか、と考える人事担当者さんです。
社員の健康保持のためにやったことが裏目に出ては・・・と心配しています。
そこで今回は、ワクチン接種と会社の安全配慮義務について詳しく確認していきたいと思います。
職場へのお土産が負担で出張を嫌がる社員にどうする?

若手のAさんは地方への出張が頻繁にある。でも、なんだか憂鬱そう。声をかけて聞いてみると、職場にお土産を買って帰るのが負担なんだそう。お土産がないと「Aさんがいない間代わりに仕事していたのに、何にもナシ?!」と言われるそうで・・・。「こんなことならもう出張に行きたくない」とAさん。困ったなあ、会社としてどうするべき?
**
職場でのお土産問題に頭を悩ませる人事担当者さんです。プライベートの旅行で、会社を休んでいる間のフォローに感謝を込めてお土産を配る・・・ということが習慣になっている職場もあるかもしれません。
とはいえ、出張は会社の業務のために行われるもの。職場へのお土産購入がネックとなって、出張する社員のモチベーションが低下するのでは、人材マネジメント上問題があります。
そこで今回は、出張に伴う職場へのお土産購入問題に会社はどう対応するべきなのか、詳しく確認していきたいと思います。
家族を海外出張へ連れていく社員に会社はどう対応する?

事業で海外とのビジネス接点が増えたため、最近海外出張の機会が多いAさん。ところが、出張時に家族を同伴させているらしい。出張が多いので家族旅行の機会も乏しいだろうから、本人は家族サービスのつもりなのかもしれないが、どう対応するといいのか・・・
**
オンラインでの連絡手段では業務の円滑な遂行を図ることが難しい、ということで現地への出張を命じているわけですが、家族を同伴させて、果たして業務に集中することができるのか?と疑問を覚える上司です。
また、もし出張費の濫用があるとすれば、海外出張者に対する人材マネジメント上見過ごすことのできない問題といえます。
そこで今回は、海外出張への家族の同伴にとるべき会社の対応について、詳しく確認していきたいと思います。
社員の持ち帰り?会社は備品管理をどうするか

あっ、またボールペンが無くなっている。消しゴムもクリップも・・・こないだ補充したばかりなのに。課長からはコスト意識を持ってきちんと備品管理に努めるように言われているけれど、どうすればいいの?
**
総務部新人のCさん、所定の場所に文房具を補充してもすぐ無くなるので、管理方法に悩んでいます。部内で相談すると、「備品の持ち帰りが発生しているのでは?」との声が。
「抜き打ちで所持品検査をやる」「いつ誰に何を渡したか細かく記録をとる」といった案も出ましたが、「みんなを疑っているようで気持ちよくないね・・・」と採用には至りませんでした。とはいえ、何らかの対応策を講じる必要があります。ポイントは就業規則への規定化です。
そこで今回は、会社がとるべき備品管理の方法について詳しく確認していきたいと思います。
問題アリな役員に就業規則は適用されるの?

役員が仕入先から不正な利益を得ているのでは、との疑惑が持ち上がった。その役員は創業者である社長と昔からの友人で特別な関係にあり、人事部では積極的に触れてはダメな雰囲気が。こんな時こそ就業規則に基づいて、役員に制裁処分を行えないのかな?
**
役員の問題行動(不祥事)に対して、就業規則に基づく懲戒処分を行うい、企業秩序を取り戻さなければならないと考える人事担当者です。
会社は企業秩序の維持のために、社員の違反行為の内容や程度を調査して、教育・指導によって改善することになります。ですが、そもそも役員には社員のように規律が求められていない(役員としての責務を果たせばよい)ので、どうすれば・・・。
そこで今回は、役員に就業規則による基づく制裁は可能か、また役員の問題行動への会社の対応について詳しく確認していきたいと思います。
出向に同意した社員が拒否に転じて会社はどうする?

企画部の課長が部下に関連会社への出向を打診したところ、快く承諾してもらえたそうだ。ところが数日後、一転して「出向したくない、このまま本社勤務を続けたい」と出向命令を拒否してきたとのこと。会社としてどう対応するべき?
**
一度は出向命令に同意したものの、特段の理由もなく命令の拒否に転じた社員。上司の説得に応じる様子もありません。
また、職場で「出向命令って嫌なら断ってもいいんだ・・・(*´з`)」との雰囲気が広がりつつあり、他の社員の手前もあるので、どのように対応するべきなのか頭を抱える人事担当者です。
そこで今回は、いったん出向命令に応じた社員が命令に従わない態度を示してきたとき、会社はどう対応するべきなのか、詳しく確認していきたいと思います。
地方に拠点を初開設したけれど社員が転勤を嫌がります

創業時は本社のみだったが、事業拡大に伴って初めて地方に拠点を開設することになった。そこで初めての転勤命令を社員に出したところ、「本社勤務だから入社したのに、転勤なんて話が違う」と言ってきた。無理強いして社員のやる気を落としたくないし、どうすればいいの?
**
「会社は、業務上の必要があるときには、社員に人事異動(担当業務、勤務地の変更(転勤)、職種等の変更)を命じることができる」との旨が、この会社の就業規則には規定されているものの、転勤を嫌がる社員を前にして対応に頭を悩ませる管理職です。
このような場合、社員を転勤させることはできないのでしょうか。
そこで今回は、人事異動は会社の自由に行ってはダメなのか、また転勤について会社はどんなことに気を付けるべきなのか、詳しく確認していきたいと思います。
懲戒解雇の普通解雇へのシフトは問題ないですか

懲戒解雇になると再就職とか本人の将来に差し障るかもしれないから、会社が普通解雇にすることに問題はあるのかな?
**
就業規則を手にとりながら、ふとギモンに思う人事部のBさんです。
というのも、懲戒解雇は懲戒処分の最も重い処分であり、通常は解雇予告も解雇予告手当の支払いもなく即時になされ、退職金にしてもその全部または一部が支給されません。
そして普通解雇と大きく異なる点として、再就職に際しての支障が挙げられるからです。
そこで今回は、懲戒解雇事由があることを理由に普通解雇することはできるのか、詳しく確認していきたいと思います。
メンタル不調を黙っている社員、会社の対応はどうする?

最近元気のない部下がいて、残業が多くなりすぎて長時間労働になっているらしい、と企画課の課長から相談があった。あまり眠れず動悸があって心療内科に通院しているそうだが、そのことについて本人から申告がなかったので、仕事の全体量を是正するなどの措置はとってこなかったらしい・・・
**
メンタル不調を黙っていた部下への対応について他部署の上司から相談を受け、頭を抱える人事担当者。
このようなケースでは、会社が安全配慮義務違反に問われるのではないか?との思いが頭をよぎるからです。
そこで今回は、メンタルヘルス問題を会社に申告しなかった社員への対応について、詳しく確認していきたいと思います。
希望退職の応募者が足りない、会社の対応はどうする?

不採算事業の見直しで人員削減の必要性があり、希望退職を募集することになった。だが募集を締め切ったところ、募集人数に達しない結果となってしまった。・・・削減予定数に満たないので余剰人員がいまだ発生することになり、どうすればいいのか?
**
希望退職は、会社の「退職のお誘い」に対する社員側からの労働契約の解約申入れであり、会社の一方的な意思表示による解雇とは性質が異なります。
とはいえ会社が削減人数を明らかにし、希望退職を募ったものの募集人数に届かなかったので、その分を余剰人員ということで整理解雇できるのか?と頭を抱える人事担当者です。
そこで今回は、希望退職の応募人数が足りなかった場合、整理解雇における人員削減の必要性は認められるのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
ドライバー社員が休日に起こした事故、会社の対応はどうする?

配送ドライバーの社員が、週末の休みにマイカーで事故を起こした。社会的に自動車事故への世間の目が厳しくなっているし、当社での本人の職種を考えると、教育的指導のため何らかのペナルティー(懲戒処分)を与えるべき・・・?
**
近年は飲酒運転だけでなく、社員の自動車事故全般について、会社に対して(本人はもちろんのこと)十分な事故対応策をとっていたのかどうかが厳しく問われる時代になっています。
とはいえ、会社が社員のプライベートでの事故に対して懲戒処分を行うことができるのでしょうか。
そこで今回は、ドライバー社員が私生活上の事故を起こした場合に会社がとるべき対応と懲戒処分について、詳しく確認していきたいと思います。
テレワーク社員が職場へ移動中に事故、会社はどう対応する?

朝から職場で機器トラブルやネットワークトラブルが頻発しているので、テレワーク中の担当者に急きょ来てもらうことに。だが、出勤途中に運転操作を誤って電柱に衝突し、首に軽度のむち打ちを負った。会社はこの社員に対する安全配慮義務違反に問われるのだろうか?
**
テレワーク中の社員に急きょ職場への出社を求め、例外的にマイカー通勤を許可したものの、その途上で社員が事故で負傷。「会社がわざわざ出社命令を出したのがまずかったのか?」と頭を抱える人事担当者さんです。
テレワークを行っている自宅から職場への移動時間に社員が事故に遭った場合、会社は安全配慮義務違反に問われるのでしょうか。
そこで今回は、テレワークからの移動中の事故と会社の安全配慮義務について詳しく確認していきたいと思います。
テレワークの作業環境を会社が整えないとダメですか

Aさんからテレワークに必要な椅子を購入してほしい、との申出があった。Aさんの家ではスチール製のスツールしかなく腰を痛めそうなので、オフィスで使用しているワーキングチェアが欲しいと・・・会社が椅子を買わないでAさんが腰痛になったら、会社の責任になるの?
**
この会社のテレワーク制度では、自宅での作業に必要な備品は、社員それぞれの費用負担で準備してもらうことにしているので、Aさんの申出に戸惑う人事担当者さんです。
テレワーク時の備品等の費用については就業規則で社員負担と定めているので、Aさんにだけ備品の費用を支給するわけにもいきません。とはいえ、Aさんが腰痛になったとしたら会社に問題がある(安全配慮義務違反)のでしょうか。
そこで今回は、テレワーク時の作業環境と会社の安全配慮義務について詳しく確認していきたいと思います。
会社は職場の熱中症対策をとらないといけないの?

「職場での熱中症による死亡者及び休業4日以上の業務上疾病者の数は、2023年に1,045人、うち死亡者数は28人」・・・職場全体で熱中症予防の知識を共有して、対策をとらないと最近の暑さは乗り越えられない・・・
**
厚生労働省の資料をみて、意識を改める人事担当者さんです。でも後輩社員は「会社がそこまでやらないといけないんですか、体調管理はそれぞれの問題では?」と不思議そうな顔。
職場における熱中症予防についての通達が厚労省から出されており、これを参考に具体的状況に応じた対策をしていない場合、会社の安全配慮義務違反が認められる可能性があります。
そこで今回は、職場でおこる熱中症と会社の安全配慮義務について、詳しく確認していきたいと思います。
就業規則に職場のメンタルヘルス対策を定めるポイント

「最近では30歳代のメンタルヘルス不調も急増しているらしい。若手社員が多いうちの職場。メンタルヘルス対策として、うちで何をやったらいいのかな?」
メンタルヘルス不調は、その要因のひとつに働きすぎがあります。新型コロナウイルス感染症の影響などからフレックスタイム制や裁量労働制、在宅勤務などが広まりましたが、これらの働き方は自己管理がうまくできないと長時間労働になる側面もあります。
メンタルヘルス不調の社員に対する対応を適切に行うには、就業規則を整備することが重要です。
そこで今回は、職場のメンタルヘルス対策を就業規則に規定する際の留意点について詳しく確認していきたいと思います。
意外と忘れがち!就業規則が労働契約の内容になるコト

労働条件の明示はきちんとやらないとね。でも、昔はこんなんじゃなかったなあ?自分が働き手だったときも極端な話、「時給はこれくらいで、何時から何時まで、明日からいい?」「いいです」みたいな感じ。でも特にトラブルもなかった・・・なんで?(飲食店 オーナー談)
法改正により2024年の4月から労働条件の明示のルールが変わった(労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます)ので認識を改めながらも、口頭の合意のみで成立した労働契約でトラブルが発生しなかったことについて、ふとギモンを覚えるオーナーさんです。
その理由は、日本では就業規則で統一的に労働条件を設定することが広く行われていることにあります。
そこで今回は、就業規則が労働契約内容となることについて、詳しく確認していきたいと思います。
社員の勤怠不良をどこまで許さないといけないの?

欠勤や遅刻なんかを頻繁に繰り返す部下がいる。そのたびに注意しても、「遅刻した分給与から引かれてるんで(ノーワーク・ノーペイ)、何か問題あります?」と悪びれる様子がない。遅刻ぐらいで解雇なんてできない、とは聞くけれどどのくらいまで許容しないとダメなの?
**
正当な理由もなく、欠勤・遅刻・早退を繰り返し、やたらと仕事から離れる(私用外出)部下に、いまにも堪忍袋の緒がブチッと切れそうな上司です。
とはいえ、解雇は社員の生活に与える影響が大きいので、会社の解雇権の行使には法的な規制があります。勤怠不良による解雇が、直ちに有効となるわけではありません。
そこで今回は、社員の勤怠不良にまつわる解雇問題について詳しく確認していきたいと思います。
主治医と産業医で復職の診断が分かれたとき会社はどうする?

私傷病で休職していた社員が、復職のため診断書を提出してきた。でも「復職できる」との主治医の診断に対して、うちの職場をよく知る産業医の診断はそうではなくて・・・。会社としてどうするべきなの?
**
社員が職場復帰できるかの判断にあたって、医師の診断書が重要なのは言うまでもありません。とはいえ、主治医の診断(就労OK)と産業医の診断(就労NG)が分かれた場合、会社としてどのように対応するといいのか、悩みが深くなる人事担当者さんです。
社員の職場復帰に期待を寄せながらも、無理な復帰によって症状がさらに悪くなってはいけないからです。
そこで今回は、休職社員の職場復帰にあたって主治医と産業医の診断が分かれたとき会社がとるべき対応について、詳しく確認していきたいと思います。
復職できるか会社の指定医での受診を義務づけてもいいの?

復職にあたって本人の申告だけでは、本調子ではないのにかえって無理させてしまうかもしれない。うちの職場や仕事内容をよくわかってくれているお医者さんに診てもらってからがいいけれど、会社の指定医の受診を就業規則で義務づけることなんてできるのかな?
**
休職期間が満了しても復職できないときは、解雇または退職の猶予期間が経過したので、期間満了時に退職または解雇となります(一般的に休職は「解雇猶予の制度」と解釈されている)。
そのため、復職できるかどうかの判断について、慎重に検討を重ねる人事担当者さんです。会社にとって休職は、単に職場復帰を待つだけではなく、職場復帰後も継続して雇用するための制度だからです。
そこで今回は、復職できるかを判断するために、会社の指定医での受診を義務づける就業規則の定めは有効なのか、詳しく確認していきたいと思います。
休職からの復帰で会社にはどんな配慮が求められるの?

病気で休職していたAさんが職場復帰することになった。でも仕事の量や内容がプレッシャーになって、せっかく戻った体調が悪くなっては元も子もない。会社としてどんな配慮をすればいいんだろう?
**
私傷病で休職していた部下が復職することになり、仕事面でどんな配慮をするとよいのか頭を悩ませる上司です。とはいえ気を遣いすぎて、本人に引け目を感じさせたり、やる気を失わせてしまうのもよくないし・・・との思いがあります。
こんなとき法律面では、会社には安全配慮義務があるので、業務上の負荷により復職した社員の健康状態が損なわれないよう、業務面でさまざまな配慮を行うことが求められます。
そこで今回は、私傷病で休職していた社員が職場復帰するとき、会社に求められる配慮について詳しく確認していきたいと思います。
懲戒の出勤停止日数を一律にすると問題はありますか

うちの就業規則では、出勤停止について「7営業日以内で懲戒事由によって日数を決める」ことになっている。その都度、出勤停止の日数を決めるのは時間や労力がかかってしまうから、一律の日数にしてはどうだろう。・・・問題あるのかな?
**
就業規則の見直しにあたって、時間や工数のかかる社内の手続きも検討することにした人事担当者さん。懲戒規定の内容も見直しの対象にしようかと考えています。
とはいえ、懲戒(出勤停止もそのひとつ)は解雇と同様に労働条件に含まれるため、労働条件の変更にあたります。ここは慎重に検討したほうがいいよな・・・と、はやる気持ちを抑えるのでした。
そこで今回は、出勤停止を一律の日数にしていいのか、詳しく確認していきたいと思います。
職場のセクハラ問題を本人任せにしていてはダメなの?

「なんで会社は職場のセクハラ問題を放っておいてはダメなの?単に人間関係の相性が悪いとか、本人同士の問題っていうこともあるんじゃないの?」
管理職のAさん、セクシュアルハラスメント(セクハラ)が社会的に許されない行為であることはもちろん理解していますが、どうも腑に落ちない様子です。
男女雇用機会均等法では会社に対してセクシュアルハラスメント(セクハラ)防止の措置義務が課せられていますし、会社には職場環境の適正良好保持義務が判例上認められています。
つまり、セクハラ問題で会社に損害賠償義務が生じるケースもあり得るということです。
そこで今回は、なぜ会社が職場のセクハラ問題に取り組まないとマズイのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
違反行為の調査で社員は会社に協力する義務があるの?

うちの部で就業規則の違反行為が疑われている。所属部員に対して会社側のヒアリングがあって、次は私の番だ。でも同僚の悪いことは言いたくない。刑事ドラマの取調べシーンみたいに黙秘権をつかってダンマリを決め込もうか・・・
**
社員が就業規則の違反行為を犯したおそれや疑いのあるときは、所属長やその他の管理者にはその事実確認や関係者から事情をヒアリングするなどの調査権限があります。会社としては、企業秩序を維持しなければならないからです。
問題は、所属長等はどこまでこの調査権限を行使でき、一方の社員はどこまでこれに応じる義務があるのかということです。
そこで今回は、就業規則の違反行為にまつわる調査権限について詳しく確認していきたいと思います。
解雇の理由を本人に伝えないと無効になるの?

「会社が解雇するとき“あなたを解雇します”っていう意思表示が本人に到達しないと効力は発生しませんよね。そのとき解雇の理由も伝えないと無効になっちゃうんですか?」
「・・・・・ウッ(;゚Д゚)」
人事部に配属されて半年たったBさん、知識も増えてきたので質問攻めに合う先輩はタジタジです。
Bさん曰く、注意を繰り返しても勤務態度など全く改善されないので解雇という事態に至ったのに、「あなたのこういうところが悪いからですよ」と理由まで通知しなければならないのなら相当骨の折れるミッションだ・・・と感じたとのこと。
そこで今回は、解雇理由を本人に通知しなければ解雇の効力に影響を与えるのか、詳しく確認していきたいと思います。
解雇が認められる「勤務態度の不良」とはどの程度をいうの?

いくら注意しても勤務態度が改まらない社員に、こっちがギブアップしそう。解雇も視野に入れるべきレベルだと思うけれど、就業規則の解雇事由にある「勤務態度が著しく不良」ってどのくらいのことをいうの? (新人が配属された部署の上司 談)
**
社員側の事由による普通解雇の解雇理由としては、勤務成績や勤務態度等の不良、精神又は身体の疾病又は障害、職務上の命令違反、無断欠勤や職務懈怠その他の職務上の義務不遵守、経歴詐称、職務上又は職務外の非違行為・・・などを理由とするものがあります。
解雇は社員の生活に与える影響が大きいため、「勤務態度の不良」といっても主観的であってはいけないと悩まれる上司の方も多いようです。
そこで今回は、勤務成績や勤務態度不良による場合の解雇事例について、詳しく確認していきたいと思います。
退職する社員との「口約束」は有効ですか

「在職中に知り得たうちのノウハウや機密をよそへ漏洩しないでね」「うちと競合する企業や組織に属したり、自分で会社を作ったりするのはやめてね」
・・・社員が会社を辞める時に口頭で合意をとっているけれど、これって何かあったときにも有効なのかな??(SOHO 人事担当者 談)
**
退職時の手続きで、「秘密保持義務」「競業避止義務」について口頭で誓約をとっているものの書面化はしていないので、果たして秘密保持、競業避止義務が成立しているのか、ふと気になる人事担当者さんです。
きちんと書面にして誓約書などを取り交わすべきなのでしょうか?
そこで今回は、秘密保持義務、競業避止義務について会社を辞める社員との口頭での合意は有効なのか、詳しく確認していきたいと思います。
就業規則に書いてある諭旨解雇と懲戒解雇はどう違うの?

うちの就業規則には、懲戒の項目に「諭旨解雇」というものが書いてある。「懲戒解雇相当の事由で本人が反省しているときは退職届を提出するよう勧める」とのこと。ん?どういうこと?反省すればフツーの退職扱いになるの?
**
多くの会社の就業規則において、諭旨退職や諭旨解雇という懲戒処分制度が定められていると思います。
諭旨解雇は懲戒解雇よりもワンランク軽減した解雇処分ですが、「懲戒処分とどう違うの?」「処分を一段階軽くすることに意味はあるの?」など、「結局どういうこと(;・∀・)?」とギモンに思われることは少なくないのではないでしょうか。
そこで今回は、諭旨解雇とはどういうことなのか、懲戒解雇とはどう違うのかについて詳しく確認していきたいと思います。
希望退職に応募者が殺到、会社の対応はどうする?

「足元の業績が好調で、転職したい社員を手厚くサポートできる状況なので、希望退職を募ることになった。もし当初の募集人数よりも応募があったらどうしよう?退職を引き留めればいいのかな?」
中長期的な経営方針で組織の若返りを図ることになり、一定の年齢以上の社員を対象に希望退職をはじめて募集することになったA社さん。
応募者に対して、退職金の割り増しや再就職支援などの優遇措置を考えているため、希望退職をうまく活用してキャリアの伸展を考える社員が予想以上に多かった場合、会社としてどのように対応すればよいのか、判断に悩まれています。
そこで今回は、希望退職で募集人数を超える応募があった場合にとるべき会社の対応について、詳しく確認していきたいと思います。
ライバル企業への転職を禁止してはダメですか

「転職先の会社の利益のために、うちの会社の機密情報が利用されるなんていることがあっては困る。うちとの競合企業への転職は就業規則で禁止することにしようか・・・」
キャリアアップのための転職を理解しながらも、会社の製品の製法や営業上の秘密を知っている社員が同業他社に転職することで、それらの情報が洩れたりしないだろうか・・・と心配な経営者や管理職。
そんなことになれば、これまでのみんなの開発努力が水の泡になってしまうからです。
そのため、競合する同業他社への転職を禁止することは会社として当然できるものと考えられがちですが、法律的には「合理的な範囲内なのかどうか」が問われることになります。
そこで今回は、退職後の同業他社への転職禁止が有効なのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
社員が会社を辞めるとき、退職と解雇はどう違うの?

「定年退職、自己都合退職、懲戒解雇、整理解雇・・・どれも会社を辞めることには変わりないのに、こんなに種類があるの?そもそも退職と解雇は法律的にどう違うっていうの?」
人事部に異動してきたBさん、先輩からのススメで自社の就業規則を読み込もうとするものの、退職をめぐる用語の多さに頭がグルグル・・・\(◎o◎)/!
社員が会社を辞めるとき、それが「退職」にあたるか「解雇」にあたるかは、法律上大きな違いがあるため、会社のとる対応にはえらく差が生じます。
特に解雇の場合は、いろいろな法的な制限があるので注意する必要があります。
そこで今回は、退職と解雇はどう違うのか、またそれぞれどんな種類があるのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
上司が部下を教育・指導しないとなぜマズイのか

今月もノルマの達成が無理そうな部下がいる。チームとしての数字が達成できないと、部下の指導がなっていないと自分の評価が下がってしまう。社会人なんだから仕事は自己責任でしょ。なんで上司がそこまで面倒みなきゃいけないの、法律とかで決まっているの?
(システム会社営業部 リーダー職 35歳 談)
**
チームに仕事の遅い人がいて、どうやら煮詰まっている様子のリーダーです。部下をもつと、仕事の指揮監督とともに日常の人材マネジメントが任せられるので、ストレスが溜まるのもわかります。
ただ、上司として自分の法律上の地位や権限、負っている義務について理解していないと、トラブルが生じることもあります。
そこで今回は、なぜ上司が部下を教育・指導しないことが問題になるのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
労基署に出していない就業規則は有効なの?

前の総務部長が退職したので、後任として職務にあたることになった。バタバタの引継ぎだったが、「戸棚の書類をみれば大丈夫」だって。
どれどれ・・・ガチャ。(←キャビネットの扉を開ける音)
はいはい、これが就業規則の原本ね。ん?職場代表の意見を聴いてないし、労基署へ出した形跡もないっっ?!これ絶対ダメなやつ!!
**
就業規則はその作成、変更の都度、労基署に届け出なければならない旨が労基法に定められています。
では、就業規則を作成したものの労基署への届け出をサボっていた場合はどうでしょうか。有効なものとして扱われるのでしょうか。
そこで今回は、労基署に届出ていない就業規則はそもそも有効なのか、またあわせて職場代表の意見を聴いていない、社員に周知していないときはどうなのか、について詳しく確認していきたいと思います。
パート用がないと正社員の就業規則が適用されるの?

「うちの会社ではパート社員向けの就業規則をつくっていないのですが、まさか正社員の就業規則が適用されることはないですよね?」
・・・この「まさか」の予感は的中してしまうかもしれません。
常時10人以上の社員が働く会社には就業規則を作成して労基署長に届け出る義務があります。そんな職場でパート社員がいるのに、パート社員について適用される就業規則が作成されていないとなると、困ったことが起きてしまいます。
ひとつは、法違反の問題。もうひとつは就業規則を下回る労働条件を個別に労働契約で決めたとしても、無効となって就業規則の基準で契約したものとされる問題です。
ライフスタイルに応じた働き方で、さまざまな雇用形態の社員が同じ職場で働くことは珍しくないですし、無用なトラブルは避けたいですよね。
そこで今回は、パート社員の就業規則にまつわる問題について詳しく確認していきたいと思います。
部下を叱責するのは教育?それともパワハラ?

上司が部下を大きな声で怒鳴りつける、暴言を吐く、机をバーンッと強く叩いて机上の書類を部下に投げつける・・・
↑いわゆる「パワハラ」です。皆さんこれには異論ナシですよね。
上司が部下の顧客対応に注意したり叱責する、反省を促すため顛末書の提出を命じる、業務態度不良を繰り返す部下に叱責がきつくなる・・・
↑これについてはどうでしょうか?
上司には部下を指導、教育する義務がありますが、それを受ける部下にしてみれば上司の叱責などを「いじめ」と受け取る場合もあるかもしれません。ここに、パワハラ問題の難しさがあります。
どこまで指導すればいいのか迷われる上司の方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、職場でのパワーハラスメントと上司の指導教育にまつわる問題について詳しく確認していきたいと思います。
ハラスメント対策は人材マネジメントの一環

職場では、社員同士が職場コミュニティをつくり、人間関係を築いています。あえてケンカしたいとは思わないまでも、やはり人間同士の集まり、人間関係上の軋轢、ハラスメント、もめごと、トラブルetc.・・・が生じます。
会社には職場環境配慮義務があり、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなど職場でのいやがらせ防止等などが求められています。
「法律で決まっているから会社がやらないといけないのか」
・・・と思われるかもしれませんが、ハラスメントによる社員の意欲ダウン、優秀な人材流出、訴訟リスク・・・といったことを考えると、経営に与える影響は甚大です。
そこで今回は、会社が気をつけたい「職場のハラスメント」対策について、詳しく確認していきたいと思います。
始末書を出さない社員をさらに重い処分にしてはダメですか

「始末書の提出が前提でけん責処分にしたのに、一向に始末書を出してくる気配がありません。反省の色が見えないので、さらに減給しようかと考えています。」
ここで問題となるのが、「一事不再理の原則」です。ひとつの違反行為に対して二重の処分をすることは許されません。
「それなら、そもそも“始末書を提出させてけん責処分にする”というのもダメなんですね?」
これは「併科」の問題であって、「一事不再理の原則」とは関係ありません。・・・「一事不再理の原則」のことを「二重処罰の禁止」ということがあるので、ややこしく誤解されがちかもしれません。
そこで今回は、始末書の提出拒否をもって、新たな懲戒処分を下すことがダメなわけについて詳しく確認していきたいと思います。
社内の掲示板で懲戒解雇の社員を公表するのはダメですか

「懲戒解雇をした場合、社内掲示板で対象者を公表することを検討しています。就業規則にも明記しようと思いますが、問題はありますか?」
懲戒処分の内容を公表することで、他の社員に対する警告にしようと考える企業さんです。事案を理解してもらい、今後の社員の指導・教育に努めたいとの意図があります。
とはいえ、公表することで、懲戒処分の対象社員から逆に名誉棄損で訴えられるリスクがあるのでは?との懸念も・・・
結論からお伝えすると、「懲戒解雇が有効」なのであれば社内公表することで特段の問題はありません。逆に言えば、「懲戒解雇が無効」であるような場合は違法となりますから注意が必要です。
そこで今回は、懲戒解雇について社内公表する場合の注意点について詳しく確認していきたいと思います。
退職願の提出期限を3か月前にしてもいいですか

「いきなり会社を辞めたいと言われると、会社側としては引継ぎやら後任者の選定、人員の補充など大変なので、“退職願は3か月前までに提出すること”と就業規則で義務付けてもいいですか?」
退職の申出が突然あったと思いきや、そのまま出社しなくなってしまった・・・そうすると、社内の業務だけでなく取引先との関係もあるので、残された周りの社員はそれらのフォローのためにてんやわんやになってしまいます。
そんな事態を防ぐために「退職願の提出は3か月前までに」と決めたいのは、心情的には理解できます。
ですが、あまりに長い予告期間を設けることは、社員を不当に拘束することにもなりかねません。
そこで今回は、退職願の提出時期はどのくらいにするのが適当なのか、詳しく確認していきたいと思います。
退職勧奨と希望退職の募集はどう違うの?

「ハローワークの手続きで困っています。離職証明書の離職理由で“希望退職の募集又は退職勧奨”という項目がありますが、希望退職の募集と退職勧奨はどう違うんですか?」
人事担当者さんのギモンですが、雇用保険被保険者離職証明書にある細かな記載によく気が付かれました(=゚ω゚)ノ
希望退職と退職勧奨の両方とも、「労働契約の合意解約の申入れ」という点では共通しているものの、会社と社員のどちら側による解約の申入れなのか、という点で両者は異なります。
そのため後日トラブルにつながる可能性もありますから、両者の違いを踏まえながら、特に退職勧奨について理解を深めておくことが大切でしょう(退職勧奨は場合によっては無効になることもあります)。
そこで今回は、退職勧奨と希望退職の募集の違いについて詳しく確認していきたいと思います。
すでに退職願を提出済みの社員を懲戒解雇できるの?

Dさんが退職願を出してきたが、その後に重大な服務規律違反が発覚、しかも懲戒解雇にあたるような事案だった。すでに退職願が出されているだけに懲戒解雇はできないのだろうか・・・
**
退職願の提出から業務の引継ぎが終了し、あとは退職日を迎えるだけのはずがよもやの事態に。会社としては対応に慌ててしまいますよね。
結論から申し上げると、たとえ退職願が出されていたとしても、まだ社員として雇用関係があるのなら、懲戒解雇しても問題ありません。
ですが、退職願と懲戒処分の関係については、民法での決まり事と情状酌量の2点について考慮しなければなりませんから注意が必要です。
そこで今回は、退職願が出されている社員を懲戒解雇してもよいのかどうか、詳しく確認していきたいと思います。
海外出張に行きたくない社員と懲戒処分

「国内出張はいいけれど海外出張は危険だから行きたくない、という社員がいます。業務命令違反ということで、懲戒処分にしても問題ないですか?」
いろんな人がいて、いろんな考え方があり、その対応に悩まされる・・・ということで、いろんなご相談をいただくわけですが、そのなかで出張にまつわるものもあります。
出張とは、働く場所である勤務地の変更をいいますが、一時的な勤務場所の変更であり、社員に対する指揮命令権には変更がありません(←転勤との違い)。
ただ、海外出張は国内出張と比べて働く環境が著しく異なり、社員本人やその家族に対する影響が大きいので、同じように考えるわけにはいきません。
そこで今回は、国内出張と海外出張の違いを踏まえ、海外出張を拒否する社員を懲戒処分できるのかについて確認していきたいと思います。
セクハラの申告があったとき会社がやってはいけないこと

あれ?Aさんって同僚のBさんから、やたら根掘り葉掘りプライベートのことを聞かれているなあ。波風をたてないように一見穏やかだけど、Aさんは決して喜んではいない、これってもしかして・・・(゚д゚)!
**
たとえ噂やなんとなくな雰囲気レベルの話であっても、セクハラの問題を察したときは、人事・担当者の耳に入れて対策を講じることが、事態を打開するポイントです。
実際、会社がセクハラの事実を把握するのは、本人からの直接の申告よりも、周囲が変だと察知して人事部へ相談することが多いようです。
職場のセクハラについては、男女雇用機会均等法により、会社にその対策(やらないといけないこと)が義務付けられていますが、今回は逆の視点から、セクハラの申告があったときに会社がやってはいけないことについて、詳しく確認していきたいと思います。
病気を抱える社員に転勤命令を出してはダメですか

「ある社員に転勤を打診すると、病気を理由に拒否してきました。持病のある社員に転勤命令を出すのはダメなのでしょうか」
病気の社員に対して勤務地を変更する配転を命じるということは、会社による転勤命令権の濫用にあたってしまうのか?というのが、このご相談のキモです。
会社は社員に対して健康配慮義務を負っているので、上司としてそのあたりを心配されたご様子でした。
自分の部下が実は病気を抱えていて働いていた、という事実を知ってショックなのに、さらに転勤命令の有効性を考えると、どんな対応をとるべきなのか?と悩んでしまいますよね。
そこで今回は、転勤命令の有効性とともに、会社として病気の社員に対する転勤命令をどう考えるといいのか、詳しく確認していきましょう。
休職期間の満了で自然退職とするのは有効ですか

「現在の就業規則では、“休職期間の満了時になお休職事由があるときは退職とする”とありますが、そんなのカワイソウですよね?」
休職期間中に休職事由がなくなった場合は、当然休職が解除されて復職となりますが、問題は休職期間が満了しても復職できない場合です。
結論から申し上げると、そもそも休職とは解雇を猶予する措置をとる制度なので、休職期間が満了しても復職できない場合について、冒頭の例のようにあらかじめ就業規則に明記しておくのが望ましいでしょう。
とはいえ休職制度の趣旨についてあやふやな理解でいると、休職中の社員に適切ではない、曖昧な態度をとってしまいがちです(←あとでトラブルになるもとです)。
そこで今回は、休職期間満了による自然退職は有効なのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
懲戒解雇イコール即時解雇は問題ありませんか

「当社の現在の就業規則では、懲戒解雇について“予告期間を設けることなく即時解雇する”と書いてあるのですが、30日分の解雇予告手当は必要ないのですか?」
懲戒解雇は、社員の秩序違反行為に対するペナルティーとして最も重いものであり、悪質な場合に課せられる最上級の処分です。解雇することで社員としての身分を消滅させる懲戒行為だからです。
そのため、懲戒解雇は「即時解雇」として解雇予告期間をおかないのが通常だとはいえ「30日分の解雇予告手当」との関係は気にかかるところですよね。
(もちろん即時解雇において、事案の性質、その事案を起こした動機、その影響の程度、本人の弁明を聞くなど慎重な配慮が必要です)
そこで今回は、懲戒解雇イコール即時解雇とすることに問題はないのか、無効とならないのか、詳しく確認していきたいと思います。
社員の安全と健康を守る義務があるのは会社だけ?

「会社には社員に対して安全配慮義務があるとはいえ、本人のウッカリした危険な行動までも会社だけの責任になってしまうの?」
安全配慮義務とは、企業が人材を採用するときに特別なとりきめをしなくても、労働契約に付随する義務として、「安全衛生上の管理をきちんとして社員を労働災害から守って働かせます」と約束することです。
とはいえ、冒頭のギモンにあるように、労働災害は社員の行動や作業動作などを抜きにしては発生しません。
つまり、労働災害を防止するには、社員にも自ら行動を律し、安全を遵守することが求められます。
そこで今回は、社員に求められる自己安全義務と健康保持義務とはいったいどういうことなのか?について、詳しく確認していきたいと思います。
社員が無断で退職しても会社は認めないとダメですか

「会社が社員を解雇しようとするときには、30日の解雇予告期間が必要なのに、社員が無断で会社を辞めるのはいいの?」
社員が会社を辞めるときには、上司(会社)に申し出る→仕事の引継ぎをしっかり行い、会社からの承諾を得る→退職日を迎える・・・という流れが原則です。
ただ、そのようなプロセスを踏まないで、突然「いついつに会社を辞めます」と社員が一方的に宣言したり、断りなく退職して他社で勤務する・・・といったケースも時として見られます。
社員が無断で退職したことによって、大わらわになった上司、同僚、人事部の方々が冒頭のような疑問を持つのも当然といえます。
そこで今回は、社員が一方的に無断で会社を辞めるといったことは、法律的に有効なのかどうか、詳しく確認していきたいと思います。
連絡がとれなくなった行方不明の社員、会社の対応はどうする?

「突然ある日から出社しなくなった社員がいます。連絡もとれないので困っています。これはもう退職したものとして、社会保険などの手続きを進めてもいいのでしょうか?」
社員寮から荷物をまとめて居なくなったように、その会社で働く意思のないことを態度で表明したと思われる場合には、「黙示の退職の意思表示として取り扱って問題ない」との旨が通達によって示されています。
ただ、「突然姿を消した社員さん」について問題なのは、連絡がとれず行方不明になった場合です。単に行方不明になっただけでは、前述のように取り扱うわけにはいかないからです。
そこで今回は、行方不明になった社員をどのように取り扱ってよいのか、詳しく確認していきましょう。
妊娠を公表しない社員VS会社の安全配慮義務

最近、女性社員Aさんの具合が悪そう。もし、おめでたなら会社として何らかの配慮が必要だけど、本人から申出はない・・・。体調が心配とだけど女性のプライベートに踏み込んでいいのかな?「セクハラ」として受け止められるかもしれないし・・・(人事部Bさん(男性)談)
**
法律上、妊娠中又は出産後1年を過ぎていない女性社員が、医師等から健康診査に基づいた指導を受け、この指導事項を守るための措置について申出をした場合、会社は申出に応じて勤務時間の変更、勤務の軽減等の必要な措置を講じる必要があります。
とはいえ本人からの申出がない以上、会社としての安全配慮義務と社員のプライバシーのバランスが悩ましい問題となります。
そこで今回は、妊娠したことを会社に申し出てこない社員に会社はどう配慮するべきなのか、詳しく確認していきたいと思います。
休職中の社員はどのくらいまで回復すると職場復帰になるか?

休職とは、社員側の事情で仕事に携わることが「できない」または「不適当な事由」が生じたとき、社員との労働契約関係を維持しながら、会社が一定期間の就労義務を免除する処分のことをいいます。
長い期間正常に勤務できないのなら、本来なら直ちに普通解雇事由にあたるところを、退職を猶予して休職期間に傷病が回復することを待って、社員を保護することが目的です。(解雇を猶予される代わりに、社員には療養に専念する義務があります。)
ただ問題となるのは、休職期間が満了したときの社員の回復状況です。無理な職場復帰によって症状が悪化すれば本末転倒だからです。
そこで今回は、会社として社員がどの程度の状態まで回復すれば復職できると判断するべきなのか、詳しく確認していきたいと思います。
何か月もの給料カットは社員の減給処分として有効なのか

企業の不祥事で、「役員報酬を〇か月にわたって減俸します」とか謝罪会見などで聞くけれど、これは一般社員にも適用されるのかな?( ;∀;)
**
不祥事に対する経営陣の責任の取り方として「報酬額〇%カット〇か月間」といった報道発表があると、こんな疑問が生まれませんか?
労基法では、就業規則で減給の制裁を規定する場合において、その減給の最高限度を定めています。減給の額があまりに多額となって、社員の日常生活を脅かすことがないようにするためです。
それなのに社員に対する減給処分「月給〇%カット〇か月間」は有効なのでしょうか?
そこで今回は、社員に対する数か月にわたる給料カットが有効なのか、詳しく確認していきたいと思います。
単身赴任したくない社員、会社の対応はどうする?

「新婚の社員が、地方支社への転勤命令を嫌がっています。配偶者は仕事の都合で一緒に行けないそうで、単身赴任をしたくないとのこと。会社は夫婦間のことまで考えないといけないの?」
今では夫婦共働きは珍しいことではなく、仕事の都合、こどもの教育、家の管理などのため、家族と別居して単身赴任せざるを得ない場合も十分ありうることです。
とはいえ会社側としては、「夫婦が別居せざるを得ない転勤命令が、人事権の濫用とみなされないか(転勤命令が無効にならないか)?」ということが、最も気にかかるところではないでしょうか。
そこで今回は、単身赴任をしたくないとの理由による転勤命令の拒否は果たして認められるのか(夫婦別居となる転勤命令は人事権の濫用となるのか)、会社のとるべき対応について確認していきたいと思います。
将来の転勤について誓約書をとっておくといいですか

「将来的に転勤や移動があった時、いざ社員から拒否されたら困るなあ。入社時に誓約書をとっておいたほうがいいのかな?」
労基法では、社員の入社時に「就業の場所・従事業務」(絶対的明示事項)について書面の交付により明示しなければならないことになっています。働く場所は社員にとって重要だからです。
では、新型コロナウィルスの感染防止のためテレワークを始めるにしても、いちいち就業の場所について労働契約を変更しないといけないのか?(早くテレワークに移行したいのに手間がかかる・・・(゚Д゚;))と困惑された経営者や管理職の方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、配置転換や転勤に応じる旨の誓約書を入社時にとっておけば、会社としての対応はノープロブレムなのか、詳しく確認していきたいと思います。
代休は必ず付与しないとダメですか

仕事の都合で部下に休日労働をしてもらうことに。代休をいつ取得できるのか、と社員から質問があったが、付与しないといけないものなの?
(メーカー勤務 営業課長談)
**
前に勤めていた会社では代休制度がなかったので、対応に戸惑う上司。部下にすれば当然の権利で代休を取得できる、と思っているよう。
誤解されているケースは多いかもしれませんが、実は、代休は法律上の制度ではありません。それぞれの企業において定めた任意のものです。
会社の就業規則に定めることによって、はじめて社員に代休の付与を求める権利が発生します。
そこで今回は、代休にまつわる質問が部下からあったとき上司(会社)がとるべき対応について詳しく確認していきたいと思います。
業績悪化の企業への出向を社員が断りそうで心配です

各方面からの事情で縮小営業を余儀なくされてきた、グループ子会社の業績悪化が進んでいる。今期の赤字転落は避けられない。通常営業に向けすでに対策をとってはいるが、ここで形勢逆転のため、優秀な社員を親会社から送り込んで、子会社の立て直しを図りたいが・・・
**
経営状態の芳しくないグループ子会社への出向命令に対して、心配事を抱える経営陣。
・・・というのも、「不本意な人事」ということで、社員が拒否してくるのが想像に難くないからです。
そこで今回は、こんな状況でそもそも社員は出向命令を拒否できるのか、そして会社はどのように対応するべきなのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
社員が自己破産すると会社のとる対応は解雇or異動?

「ローンやクレジットなど複数の業者からの借金で返済が困難になって(いわゆる多重債務)、自己破産を申し立てる社員が職場にいると判明したとき、会社としてどんな対応をとるといいですか?」
業者(債権者)から職場に電話が頻繁にかかってきたため、本人に確認したところ事情が明らかになったようです。
多重債務、自己破産というワードには「ギャンブル?」「お酒?」「浪費癖?」といったイメージがあるかもしれませんが、不況など経済環境の変化に伴う収入の減少によって生活費や教育費などを補うために借金を重ねた・・・というケースは少なからずあります。
一般的に、社員が自己破産した場合は企業の信用問題にかかわるので、会社としては解雇にするべき?少なくとも人事異動は検討するべきでは?と判断に迷われる場合も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、自己破産した社員への会社の対応について、「解雇」と「人事異動」の場合に分けて詳しく確認していきましょう。
社員の退職願VS会社による懲戒解雇、どちらが優先される?

「月末に退職予定のCさん、すでに退職願も提出されている。違反行為が発覚したけれど懲戒解雇の対象になるのか??」
企業秩序を乱す社員に対して、会社がその回復のために懲戒処分を行うことは当然の権利として認められています。
ただし懲戒処分を行うには、あくまでも本人が会社に在籍していることが前提なので、退職した元社員に対する懲戒処分は法的な根拠がなく無効です。(辞めた社員を企業の外に追い出す必要がありませんよね、懲戒解雇も必要ナシです)
では、社員が退職願を会社に提出してきた後に、本人の違反行為が発覚した場合はどうでしょうか?
そこで今回は、社員の退職願と会社の懲戒解雇はどちらが優先されるのか、会社としてとるべき対応について詳しく確認していきたいと思います。
法律でいう「配転」「転勤」とはどんな場合のこと?

「こんな配置替え、やってられない。会社は横暴だ~<`~´>」←人事異動に不満な社員の声です。
社員の就業場所や担当業務を変更することは、会社の人事権として認められていますが、会社の命令による配転や転勤は無制限に許されるわけではなく、その命令権の行使に合理性がなく、権限の濫用にあたるときは無効になります。
こんなとき、法律上の争いとして裁判所の審理に従うことになりますが、配転や転勤が「労働契約の(要素の)変更」として認められる場合に限られます。とはいえ、それはどんな場合なのでしょうか。
そこで今回は、法律上の紛争として扱われる「配転や転勤」とはどんな場合なのか、詳しく確認していきたいと思います。
遠方への転勤命令、家庭の事情を会社はどのくらい考えるべきか

「社員には事情をちゃんと説明して、転勤の同意を得ようと思うが、社員の家庭の事情をどこまで考えるべきなのか?」
経営状態によって、社員を他の支店や工場へ配置転換せざるを得ない場合もあるかもしれません。ただ、その転勤先が遠方で現在の住まいからの通勤が難しいなら少なくない負担を強いることになるので、会社としては社員の家庭の事情が気がかりです。
人事権の濫用とならないよう社員の不利益を軽減するにはどの程度までの措置をとればいいのか、悩まれる経営者、人事担当者の方は多いようです。
そこで今回は、遠方への転勤に際して、会社は家庭の事情を斟酌するべきなのか、するとしてもどの程度の措置をとれば権利濫用とならないのか、詳しく確認していきたいと思います。
海外出張中のケガに労災保険は使えますか?

「社員を海外に出張させたり、海外の支店や現地の企業に派遣する場合万一の事故やケガに、国内と同じように労災保険は使えるのかな?」
物理的に遠く離れた赴任途中や赴任先での社員の事故やケガは、経営者や管理職にとってとても気がかりなことです。
テレビ会議やウェブツールなどの導入により、社内会議にまつわる国内出張は一般的に減少傾向にあるようですが、月1回程度~年5回以上の頻度の海外出張は増えているそうです。
海外勤務は大きく区分すると、海外出張と海外派遣の2パターンありますが、それぞれで労災保険の適用はどうなるのでしょうか。
そこで今回は、出張をはじめ社員を海外勤務させるとき労災保険は適用はされるのか、詳しく確認していきたいと思います。
社員の不正で問われる上司の指導責任

最近、同僚の動きがおかしい。帳簿などの経理関係書類を、どうも不正操作しているような気がする。だが現場を実際に目撃していないので、はっきりは分からない。こんな状態で上司に報告はできない・・・
**
同僚の不正行為をうすうす感じていた経理部員のAさん。その後、抱いていた疑念が事実だったことがわかりました。では、同僚の不正行為を上司に報告や相談をしなかったAさんは、「不正を見逃した」として懲戒処分の対象となるのでしょうか?
ここでポイントとなるのは、Aさんがこの不正を行った社員に対して管理監督する職務上の注意義務を負っていたのかどうかです。
そこで今回は、職場で不正行為が発覚したときに問題となる管理職の指導責任とはどういったものなのか、について詳しくみていきましょう。
懲戒処分を決めるまで社員を自宅待機させてもいいですか

「重大な違反行為が判明したとき、会社が懲戒解雇を決めるまでの間、その張本人が出社すると職場の雰囲気がぎくしゃくすると思います。そんなときは本人に自宅待機を命じてもいいのでしょうか?」
少人数のアットホームな経営から規模を拡大していくときなど、会社をステージアップさせる機会に、懲戒処分の基準の見直しについてご相談をいただくことがあります。社内外での態度や姿勢について改めて社員の気を引き締めたい、というのがその意図です。
懲戒については、同じ違反行為を2回懲戒処分にすることは禁止されているのですが、「出勤停止からの懲戒解雇」という処分はこの二重処分の禁止にあたらないのでしょうか。
そこで今回は、懲戒処分を決めるまでの自宅待機は二重処分にあたるのかどうかについて、詳しく確認していきたいと思います。
社員が退職願を撤回できるのはどんなときか

ドラマを見ていると、その終盤で、主人公から預かっていた退職願を上司が「これはもういらないよな」と本人に突き返し、涙ながらに主人公が退職願をビリビリ破り捨てる・・・といったシーンがあります。
これをオフィスでの日常に置き換えると、「社員はどんなとき退職願を撤回できるのか?」という疑問がふと浮かんできます。
実は退職願は2パターンに分かれます。ひとつは、社員からの一方的な解約の意思表示である「辞職」、もうひとつは会社との合意に基づいて雇用契約を解約しようとする「合意解約」です。
会社が取るべき対応も変わってきますので、今回は、「辞職」と「合意解約」という退職願の2パターンの違いについて詳しく確認していきたいと思います。
社員の降格は会社の裁量で決めてもいい?
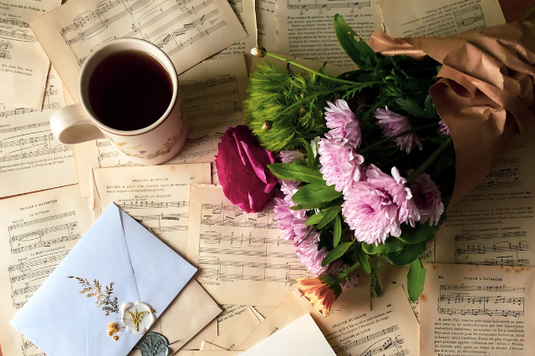
昇進とは、企業内での職務上のポジションが上がること(係長→課長→部長など)ですが、それには企業内における権限と責任を伴います。
昇進によって会社から経営権・人事権を分担され、会社の立場にたって業務の推進と部下のマネジメントを任されることになるので、昇進にまつわる人事は、原則として会社の経営権の裁量にゆだねられています。
では、降格についてはどうでしょうか。実は、降格については次の3パターンに分かれます。
- 企業内のポジション(職位)の降格または解任
- 人事制度による資格等級格付けの下位への変更
- ペナルティー(懲戒)としての降格処分
今回は、社員の降格は会社の裁量によって決めてもいいものなのか、上記の3つの場合に応じて詳しく確認していきたいと思います。
社員に海外勤務を命じるとき注意するべき点とは

「海外支店の増員のため、社員に転勤命令を出す必要性が生じた。」
「海外との取引が頻繁に行われるようになり、数人の社員を現地へ派遣しなければならなくなった。」
このように業務上の都合で、社員に海外勤務を命じなくてはならなくなったとき、どのようなことに注意すればいいのか?と、戸惑われる経営者や管理職の方は多いのではないでしょうか。
海外で働くことに憧れや興味を持っている人の割合は、一般的にみても高いようですが、いざとなると「国内とは事情が違う海外転勤に社員が不安になり過ぎて、モチベーションが下がっていて困っている」といったお話を伺うこともあります。
そこで今回は、海外勤務を社員に命じるときに留意しなければならないことについて、①海外支店への転勤命令、②海外子会社への出向の2パターンに分けて確認していきたいと思います。
社員が復職するときOK・NGの判断基準とは

GW明けにに体調不良で休職した社員の復職について、そろそろ考えなければならない職場も多いようです。
会社には安全配慮義務があるので、社員の健康管理に頭を悩ます上司、人事担当者の方もいらっしゃるかもしれません。
休職中の社員から職場復帰の申し出があっても、完全に回復していないのに無理をして、余計に体調を崩したりケガなどを負ってしまうと本末転倒だからです。
では、社員が復職するにあたって、その可否の判断基準をどのように考え、またそもそも会社がその判断を行ってもよいのでしょうか。
そこで今回は、休職中の社員から復職の申し出があったとき、会社が備えておくべき職場復帰にまつわる判断基準について詳しく確認していきたいと思います。
社員の親が書いた退職願は有効ですか?
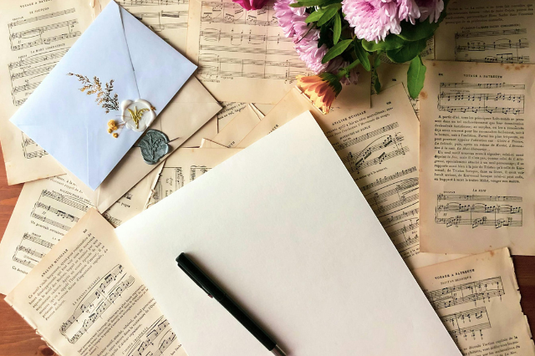
先日テレビをつけると、ドラマをやっていました。たまたま目にしたシーンは、(親が薦める)結婚相手と結婚してほしい父親が、婚姻届にサインしようとしない娘に向かって、「私が(父親が)婚姻届に署名捺印しておく」というようなセリフを放つところでした。
そこで思い出したのが、以前にいただいた「社員の親御さんが書いた退職願を会社として受理してもいいのでしょうか?」というご相談についてです。社員さんが入院されたため、代わりにご家族が退職願をお書きになり、会社へ提出されたとのことでした。
ちなみに前述のテレビドラマでは、婚姻届にサインしたのは父親であった(娘の意思ではない)ことが結婚相手の知るところとなり、結果として破談となる(親の書いた婚姻届は無効になる)ストーリーでした。
では、「親が書いた退職願」は有効になるのでしょうか?
今回は、退職願をめぐる問題について会社はどう対応するとよいのか、確認していきましょう。
単身赴任の経済的ダメージを会社はどこまで考えるべきか

「転勤先が都心部のため物価が高い、今までよりも給料の手取りが減るので手当を増額してほしい」地方の支社へ単身赴任する部下からこんな要望があった。当社では、引っ越し費用の全額の他、単身赴任の場合は月額3万円の手当を支給することになっているのに、これ以上聞き入れないといけないの?(ハウスメーカー勤務・営業課長 談)
**
この春から転勤で新しい環境となる人が多い中、転勤する社員、部下の悩みにできるだけ応えたいけれどその要望に困惑する上司や人事担当者も多いようです。
そこで今回は、単身赴任する社員の経済的負担について会社はどこまで考慮するべきなのか、詳しく確認していきたいと思います。
就業規則に記載がないままの変形労働時間制は要注意

就業規則に一カ月単位の変形労働時間制のことはまったく書かれていないけれど、記載なしのままで実施されている。しかも慣例的に長年にわたって行われている・・・また社員の方からも特に異議もなく・・・
**
このようにいわゆる労働慣行として変形労働時間制が実施されているケースもあるかもしれません。
ですが注意しなくていけないのは、就業規則に規定することが一カ月単位の変形労働時間制の導入要件になっている点です。
そこで今回は、就業規則に記載がないまま実施してきた変形労働時間制についてよくご相談いただく次の2点について詳しく確認していきたいと思います。
- 労働慣行となっている変形労働時間制は適法か
- 1日8時間、1週40時間をオーバーした分の割増賃金はどうなるか
転職オファー殺到のエース社員、引き抜きへの会社の対応は?

「事業拡大の山場を迎えているいま、中核の社員に抜けられるとまずい。就業規則で引き抜きによる転職を禁止することはできないのだろうか・・・」(メーカー勤務 開発職の管理職 談)
事業を成長させたいとき、組織の強化のため技術力や経験のあるベテランを採用したいとき等・・・社内の中心的役割をつとめるエース社員は、他社にとっても欲しい人材であることは間違いありません。
そこでエース社員が同業他社から好条件の処遇や重要ポストなどの転職オファーをもって「引き抜かれる」ケースも起こりがちです。
そこで今回は、エース社員の引き抜き転職を会社は禁止することができるのか、会社のとるべき対応について詳しく確認していきたいと思います。
妊娠した社員からの相談、会社はどう対応するべきか

「妊娠したのですが、残業など今まで通り乗り越えられるか不安があります・・・急に体調を崩したら周りの皆さんが困りますよね・・・」
妊娠した社員からこれからの働き方について相談があったとき、悩まれる管理職の方もいらっしゃるでしょう。
労働時間や休暇面もさることながら、「仕事のストレスが身体に影響しては大変」との配慮から、負担の軽い仕事内容への変更を検討することもあるかもしれません。
現場をマネジメントする立場であれば、妊娠した社員本人のやる気と体調を考えながら、どのような点に気をつけるべきなのでしょうか。
そこで今回は、女性社員から妊娠の報告を受けたとき、会社として特に留意すべき下記の2点について詳しく確認していきたいと思います。
- 負担の軽い仕事への変更や人事異動(配転)
- 妊娠の報告を受けたときの対応
グループ企業間の人事異動で気をつけたい出向と配転の違い

プロジェクトなどでグループ企業同士で強いつながりがあるので、これから人事異動、人事交流をもっと行っていきたい。その前に転勤と出向の違いを押さえておかないとなあ。 (ホールディングス 役員談)
**
秋は転勤など人事異動のタイミングです。子会社・関連会社への技術指導、社員のスキルアップのために親会社から子会社へ人材を送り出すなど、グループ企業間で人事交流が行われている場合もあるでしょう。
とはいえ、グループ企業内の関係性が密接であると、本来出向として対応するべきなのに単なる転勤として取り扱ってしまうなど、出向と配転を混同しがちです。
そこで今回は、グループ企業内の人事異動ではずしてはいけない出向と配転の違いについて、詳しく確認していきたいと思います。
仕事中デイトレードを行う社員にとるべき会社の対応とは

噂レベルだが、就業時間中に会社のパソコンでデイトレードをやっている社員がいるらしい。デイトレードは午前中の10分間程度だから会社にバレないし、結構儲かる、と自慢しているそうだ。就業時間中に、会社のパソコンを使って株取引を行うなんて、相当な懲戒処分にあたるのでは?とはいえ、噂の真偽を確かめないと。会社としてどんな対応をとるべきなのか・・・ (総務部係長 談)
***
就業時間中に行われた株取引が噂のとおり事実なら、懲戒処分を考えるべきなのか、またどの程度のものにするべきなのでしょうか。
そこで今回は、会社の取るべき対応についてポイントとなる下記の2点について詳しく確認していきたいと思います。
- 就業時間中の株取引を会社はどう考えるか?
- 懲戒処分の程度をどう考える?
仕事前の机ふき・湯茶準備で気をつけたい男女の扱いと労働時間

昔は、女性社員が始業前に簡単な掃除やお茶の準備をしてくれていた。「男女差別だ」との声があって、その習慣もなくなったが、いまや机には書類があふれて棚も散らかり放題・・・。また女性社員にお願いしたいけどダメかなあ・・・どうすればいいの?(゚Д゚;)
**
始業前に女性社員がみんなのデスクの上を水拭きして、給茶機をセットしてお茶の準備をする・・・ひと昔前では見慣れた朝の風景かもしれまません。とはいえ「女性社員だからやる仕事」というのでは、ハラスメントやコンプライアンスの点が気にかかります。
そこで今回は、ハラスメントやコンプライアンスの点から押さえておくべき下記の2点について、詳しく確認していきたいと思います。
- 仕事前の机ふき・湯茶準備でハラスメントについて気をつけるべき点は?
- その時間は労働時間としてカウントするか?
セクハラと誤解されない生理休暇への対応

先日、「生理休暇の申請への対応に困っている」と知り合いの男性の経営者から困惑気味にアドバイスを求められた。男性経営者・管理職にとって生理休暇の取扱いには「何か触れてはいけないもの」といった意識があるのかしら・・・(=_=)(女性経営者 談)
**
「セクハラとの誤解を受けないか?」「妙な空気にならないか?」と伝え方に迷う男性経営者・管理職は多いかもしれません。女性にしても「生理休暇を取ると周囲から特別な目で見られそう」と懸念する人も少なくないようです。
女性からも男性からも何やらタブー視されがちな生理休暇の取扱いですが、制度をよく知らないがゆえのこともあるのではないでしょうか。
そこで今回は、職場で誤解を生まない生理休暇の取扱いについて詳しく確認していきたいと思います。
就業時間中でもスマホを使いたい社員、禁止したい会社

とあるメーカーB社さんでは、オフィスで仕事をしながら私物のスマートフォンを使用する社員が多くみられます。
特に最近、Aさんはスマホの着信があるたびに席を離れることが多く、席にいるかと思いきやスマホを操作してSNSでメッセージのやり取りをしている様子。それを見た課長はイライラを募らせています。
一方、Aさんにもなにやら事情があるようです。
【課長の思い】
Aさんは最近スマホばかりいじって落ち着きがない。普段は真面目に仕事をやっているので、みたところ仕事に遅れはないようだが・・・。注意指導したいところだが、スマホを職場で使っている社員は他にもいるし、なんせうちの部長がヘビーユーザーだ・・・。とはいえAさんの振る舞いをみて、スマホで頻繁に席をはずす社員が他にも出て来やしないか心配だ。どうすればいいのか?
連休明けの体調不良、そのとき休職ルールは万全ですか

GW明けは、4月からの新しい環境での緊張が緩まって、連休明けに体調不良を訴える社員がでてきてもおかしくはありません。
メンタルが不安定で欠勤が続く社員に対して、会社が「休職」を命じるケースもありえるでしょう。会社としては、休んでしっかり療養して、また元気に職場へ戻ってきてもらいたいですよね。
休職制度を設けている場合であっても、職場復帰だけでなくその後も継続して働いてもらうための対策を立てておくことが大切です。
そこで今回は、休職ルールにまつわるよくあるギモンとして、下記の2点を詳しく確認していきたいと思います。
- 復帰後にリハビリ勤務する社員の賃金をどうすればいいの?
- 休職期間中の人材マネジメントをどうすればいいの?
名刺やポイント還元は会社vs社員どちらのもの?

新入社員から「名刺に肩書がないなんて嫌です。自分でつけちゃダメですか?」「仕事に必要な物品を買い出しに行ったとき、お店のポイントは自分のものにしていいですよね?」って聞かれたけど、ダメな理由をうまく説明できなかった・・・(;´Д`) (部署の先輩社員談)
**
入社したということは、その会社の社員の地位を得たということなので会社と社員との間にはいろいろな法律関係が発生します。
そこで日常の仕事をやっていくなかで、「これは会社のものなのか、それとも社員本人のものなのか?」と、ふと判断に迷うのはありえることでしょう。
そこで今回は、会社と社員の関係性に着目して、名刺やポイント還元は会社のものか、それとも社員のものなのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
職場をぎくしゃくさせない懲戒処分への対応

上司の方には、会社の業績を伸ばすために努力やチャレンジを促すよう、部下を教育・指導することが求められます。仕事の現場で日頃から人材マネジメントが任されているからです。
そのため、上司の活動のひとつに信賞必罰としてのペナルティー(懲戒処分)があるので、懲戒に関する知識を備えておくことが大切です。
知識不足による不適切な対応から職場の人間関係がぎくしゃくする・・・というのでは本末転倒だからです。また、そもそも懲戒処分は教育的指導として行うものなので、本人のプライバシーにも配慮しなければなりません。
そこで今回は、下記の2点を中心に職場の人間関係をぎくしゃくさせないペナルティーへの対応について詳しく確認していきたいと思います。
- そもそもペナルティー(懲戒処分)とはどういうこと?
- ペナルティー(懲戒処分)の公表とプライバシーをどう考えるか?
SNSのリスクを回避するために会社がとるべき対応とは

SNSは効果的に利用するとビジネス上のメリットも大きいので、積極的な活用を進める企業もあるでしょう。
とはいえ、プライベートでのSNSの利用について、社員の不適切な投稿によるトラブルへの懸念もあるのではないでしょうか。
社員のSNS利用を制限するとトラブルの隠ぺいから対応が遅れてしまうかもしれませんし、リスクを恐れて企業がSNSを活用しないのはひとつのプロモーションの機会を失うことになりかねません。
SNSにまつわるトラブルは知識不足によるものなので、会社としては社員にSNSの特性とリスクを正しく理解してもらい、リスクをできるだけ小さくしていくことを考えるほうが現実的かもしれません。
そこで今回は、SNSのリスクを回避するために、会社がとるべき対応について確認していきたいと思います。
飲み会の強要はパワハラ?それともコミュニケーション?

これから夏に向けて暑気払いなどを名目に、社員同士の接触を増やして親睦を深めるため、レクレーションを企画する企業もあるでしょう。最も簡単なので開催頻度が高いのは「飲み会」だと思います。
とはいえ、上司と飲みに行くよりプライベートな時間を尊重したいと思う若手社員がいたり、子育て中の社員にとっては参加しづらい、など働き方の多様化や価値観の変化から、今や飲み会の機会は減少傾向にあるかもしれません。
飲み会をコミュニケーションの場にしてきた、今の管理職世代にとっては、部下のマネジメントに戸惑ったりと、飲み会でコミュニケーションギャップが発生することもあるようです。
そこで今回は、せっかくの場でハラスメントが発生しないよう「飲み会あるある」が法律に抵触しないのか、詳しく確認していきたいと思います。
メタボ社員をダイエットさせなければいけないですか?

入社5年目の社員がメタボ気味で、体形がデカくなったため作業スペースも狭くなって効率も落ちている。真夏の作業場は暑いので、他の社員よりバテやすくて体力の消耗が激しい。もし作業中に倒れたりしたら、事故やケガにつながります。体形のことだけになかなか本人にも言いづらいですが、仕事にかかわることなので強制的に痩せさせる必要がありますよね?(メーカー勤務、現場責任者 談)
**
GWも明けた5月、以前なら新入社員に多い5月病についてのご相談を受けたものでしたが、最近増えたなあ、と思うトピックスはずばり「メタボ社員の健康管理」です。
会社には社員への安全配慮義務があるので、総務・人事担当者の方は社員の健康問題に関心が高いことだと思います。
そこで今回は、メタボ社員の健康管理を会社としてどのように対応するべきなのか、詳しく確認していきたいと思います。
就業規則を作って終わる会社、作って活かす会社

10人以上の社員がいる会社には、就業規則の作成義務があります。ところが・・・
就業規則を作成して、一読した社員から「年休は社員の権利だから明日休みます」との申し出が。権利だけ主張されて、こんなことなら作らなければ良かった・・・と、就業規則の作成を悔やむ会社。
一方、就業規則の作成をきっかけに「こんな理由で年休取得のルールがあるんですね」「だったらみんなが年休をとれるよう、あの仕事はこうしませんか」など、社員からの理解やアイデアを得て、仕事のやり方を見直して生産性がアップした会社。
今回は、就業規則の作成で「作って終わる会社」と「作って活かす会社」の違いがどこにあるのか、詳しく確認していきたいと思います。
就業規則が有効になるとき、無効になるとき

就業規則の効力が発生するタイミングは、社員に説明を行ったときであり、労基署への届出は必ずしも効力の発生要件ではありません。
ただし、就業規則の合理性を判断する際には、労基署への届出をはじめ手続きの遵守も問われるので、場合によっては、効力うんぬんよりも就業規則そのものが無効となってしまいます。
就業規則が有効になるかどうか、気をつけなければならないのは就業規則を変更したときであり、その変更パターンは4つあります。
つまり、この4つの変更パターンを把握して、やるべきことをやっていなければ、就業規則自体が無効になってしまいます。
そこで今回は、4つの変更パターンに着目して、就業規則が有効になるとき、無効になるときについて詳しく確認していきたいと思います。
就業規則は作って終わり、と思っていませんか?

「社員が常時10人以上いるなら就業規則を作らなければならない」
法律に規定されているので、みなさんよくご存じのことだと思います。
ですが、「作って終わり」になっていませんか?というのも、就業規則は単に作っただけではその効力は発生しません。
就業規則が有効となるには、合理的な労働条件を定め、その内容を社員に周知していることが必要だからです。
つまり就業規則に法改正に対応していないなど不備がある場合はもちろんですが、社員へ真摯に説明を行っていないと思わぬトラブルが発生するリスクをはらんでいます。
そこで今回は、手間暇かけた就業規則を無駄にしないため、会社としてやっておくべきことについて詳しく確認していきたいと思います。
仕事中のインターネット閲覧をどこまで管理する?

インターネットは日常生活だけでなく、ビジネスにおいてもとても便利なツールです。仕事に役立つヒントが見つかることもあります。
ですが昼間はずっとSNSや仕事に関係のないサイトを見ていて、その分毎日遅くまで残業・・・そんな社員が周囲にいたらどうでしょう?
ネットに繋がるパソコンを職場に1台しか置かない、ネットに繋がるパソコンを使わせない、など接続環境を制限する会社もあります(もちろん仕事へ支障がないことが前提です)が、業務効率のため個人へタブレット端末を貸し出す会社もあります。
そのためどこまで制限をかけるべきなのか、悩まれる経営者や管理職の方はとても多いようです。
そこで今回は、勤務時間中のインターネット閲覧を、会社はどこまで管理するべきなのかについて詳しく確認していきたいと思います。
派手なネイルを理由に部署異動させることはできるか

営業部のある女性社員は、「派手なストーンで飾った」「濃色の」「長すぎる」ネイルで毎日、取引先を回っている。爪が派手すぎないか?あんなに長くて、ゴテゴテした飾りが爪についていて営業車で事故らないのかな。取引先の印象も良いはずがない。
営業職で採用した社員だけど、社外対応がない他の部署へ異動させたい。それが無理なら懲戒処分の対象にならないのか?
**
仕事に関わることとはいえ、今どきのファッションとして許容するべきなのか、注意してもセクハラととられないか、など問題の扱い方について悩みは深くなるようです。
そこで今回は、営業職で採用した社員の異動に法的な問題があるのか、詳しく確認していきたいと思います。
社員の副業、会社の対応をどう考える?

会社にしても、働き手にしてもこのご時世において、副業について「気になる!」ことは多いのではないでしょうか。
働き手にしてみると、収入源を増やしたい、自分の好きなことをやりたい、幅広いネットワークを築きたい、など副業の業態やその動機は人によってさまざまでしょう。
一方の会社にしてみると、副業をやりたい事情や背景は理解できるけれど、いざ社員から副業の申し出があると対応に迷われることも多いようです。
2足のわらじで疲労困憊になって、社員が体調不良に陥らないか心配もありますし、就業規則で兼業禁止が規定されていることもあるからです。
そこで今回は、社員の副業について会社はどのように対応するといいのか、詳しく確認していきましょう。
ビジョンを明らかにするアプローチ

「社員と意識をひとつにするにはビジョンの共有が大切」
このようなフレーズを見たこと、耳にしたこと、みなさんもあるのではないでしょうか。
(かくいう私も「就業規則を作成するには会社(経営者)のビジョンが重要」とコンサルティングの現場でよくお伝えしています(^^♪)
とはいえ「ビジョンの共有が大切なのはわかるが、どうすればよいのかわからない。そもそもうまく言語化できない」とのお声を実際のところよくお聞きします。
では、ビジョンを自分の言葉で表現し、社員と共有するにはどうすればよいのでしょうか。
そこで今回は、ビジョンを明確化するアプローチについて詳しくみていきたいと思います。
就業規則の本当の意図を社員に伝えるには

社員のことを考えて社内制度を考えた。就業規則にもきちんと明記した。もちろん社員説明会も開催した。でも社員の顔はどこか冷めているようだ。社内制度を利用する社員も出てこないまま月日が過ぎて・・・
**
せっかく就業規則を作成したにも関わらず、ちょっと残念なことになってしまっています。「就業規則なんて作らなければよかった・・・」いえいえ、肩を落とさずに聞いてください。
それは、就業規則自体がいけないのではなくて、就業規則作成の本当の意図が社員に伝わっていないだけかもしれません。
実は、就業規則を活用して会社と社員の目標をひとつにして業績を伸ばしている会社は、就業規則が本当に意味するところをうまく伝えているのです。では、どのように伝えるといいのでしょうか?
そこで今回は、就業規則で社員へ本当に伝えたいことを伝えるコツについて、詳しく確認していきたいと思います。
作ってはいけない就業規則

さあ、みなさんの会社の就業規則を開いて1ページ目をみてみましょう。↓ こんな条文はありませんか?
「この就業規則はすべての社員に適用する」
もしあったとしたら、その就業規則は「作ってはいけない就業規則」である可能性がものすごく高いでしょう。
というのも、正社員向けの福利厚生、休職、退職金といった、パート社員には適用するつもりのない制度もパート社員に適用されることになるからです。
あとで「そんなつもりじゃなかった」と会社側が言い訳しても、「就業規則に書いてあるのに、なぜパートには適用されないのですか?」と、パート社員に不満を抱かせることになります。仕事に対するやる気を失わせてしまうかもしれません。
つまり、就業規則や諸規定は、誰に適用するために作成されているのかを確認することがとても大切なのです。
そこで今回は、作ってはいけない就業規則の内容を分析したうえで、本来とるべきであった対応について詳しく確認していきたいと思います。
就業規則を見直すタイミングはいつか

「就業規則を作成すると、この内容はいつまでもつのかな?」
”就業規則の賞味期限”(?)を疑問に思われたことはありませんか?
前回の改訂日付が20年以上前の平成ヒトケタ年、ガリ版刷りのインクが褪せた年代物の就業規則にお目にかかることがありますが、長年の放置は会社にデメリットをもたらしかねません。
なぜなら、就業規則は社員のやる気と行動を導き、会社を伸ばすための指針だからです。景気の波があるなかで社員に求める具体的な行動が、何十年前とまったく同じであるはずがないので、タイミングを逃さずに見直すことがとても重要です。
そこで今回は、就業規則を見直すべき3つのタイミングについて詳しく確認していきたいと思います。
就業規則を自力で作成するメリット・デメリット

「就業規則は自分で作れるものですか?」
経営を軌道に乗せるために何でも自分でこなされてきた、努力家の経営者から多い質問です。
「固い決意を持ってすれば、作れなくはありません。ですが何のために就業規則を作るのかをあらかじめよく考えておくことが大切です。」
私はこのようにお答えしますが、その理由は3つあります。
今回は、なぜ自力で就業規則を作成するには事前によく考えておかなければいけないのか、その3つの理由について詳しく確認していきたいと思います。
