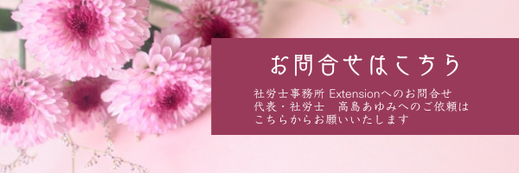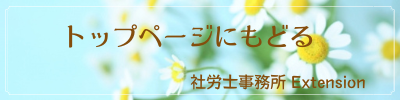GW明けにに体調不良で休職した社員の復職について、そろそろ考えなければならない職場も多いようです。
会社には安全配慮義務があるので、社員の健康管理に頭を悩ます上司、人事担当者の方もいらっしゃるかもしれません。
休職中の社員から職場復帰の申し出があっても、完全に回復していないのに無理をして、余計に体調を崩したりケガなどを負ってしまうと本末転倒だからです。
では、社員が復職するにあたって、その可否の判断基準をどのように考え、またそもそも会社がその判断を行ってもよいのでしょうか。
そこで今回は、休職中の社員から復職の申し出があったとき、会社が備えておくべき職場復帰にまつわる判断基準について詳しく確認していきたいと思います。
復職の申出には医師の診断書が必要

病気やケガで休職中の社員が職場に復帰するには、次の2つの要件が必要です。
- 「会社に復職したい」という会社に対する本人の意思表示
- 休職事由(病気やケガ)が消滅したことの証明
問題は2)についてです。休職事由が消滅したことを会社はどのように確認して、認定すればよいのでしょうか。
病気やケガで休職中の社員が会社に復職したいと申し出るとき、単に本人の申出のみで「休職事由が消滅した」と取り扱うことはできません。
裁判例でも「休職事由の消滅を認定する資料として、医師の診断書を必要とすることはいうまでもない。
病気やケガでの休職者が復職を申し出るときは、医師の診断書が必要と解釈される。」という内容が示されています。
そこで次に、休職事由の消滅を証明する主治医の診断書とその診断医の意見をどのように取扱うべきかという問題があります。
産業医に意見を求めること

安全衛生法では、健康診断における医師選択の自由を、会社で働く社員に対して保障しています。けれどこれは、社員の選択した医師の健診を受けることができるという自己保健義務の保障であって、復職を申し出るときにまでその適用は及びません。
とはいえ特約がない限り、社員の医師選択の自由は尊重されるべきものなので、復職を申し出る際に添付すべき診断書の「医師」について、「特に限定がなければ、医師であればどの医師でもよく、会社の指定する医師に限定されない」として判示されています。
ここでポイントなのは、会社は提出された主治医による診断意見に拘束されない、という点です。
主治医と患者・その家族との間には、治療において厚い信頼関係が築かれているため、主治医の診断書は患者本人や家族の希望に沿うものとなることが多い、と世間一般的に考えられているからです。
復職の可否にかかる判断は、会社にとって社員の健康管理に関わる大切な事項です。ですから使用者である会社として、産業医等の意見を聞いて判断しなければならないことになります。
会社に勤務する社員には、労働契約により約束された労務を提供する義務があります(労働義務)。命じられた仕事を完全にこなすことができる心身の状態で出勤しなければなりません。
つまり、病気やケガで休職中の社員が復職を申し出るにあたっても、その健康状態は原則として、通常勤務が可能な状態まで回復したものでなければいけない、ということです。
診断書の拘束力

では、「通常勤務が可能な状態」とはどんな場合なのでしょうか。裁判例では次のような内容が示されています。
- 診断書の結果がその会社における高度の労務に堪えうることを証明していたり、復職後に予定される具体的な勤務内容が書かれたうえで、その勤務に支障のないことが証明された場合には、会社側には復職拒否の余地はない。
- ただし、診断書の結果が「軽作業に支障なし」「平常作業に差し支えない」という程度の抽象的判断である場合には、労働契約、就業規則、労働協約等に特別の定めがない限り、この診断は絶対的な拘束力をもつものではない。復職の可否を決める一資料にとどまる。
- 医師による一定の勤務条件がつけられていた場合には、これを会社側で受け入れできる余地があるかを考えて、復職の可否を決定しなければならない。
これらのことから、担当業務において一般的な勤務ができる程度に回復していることが必要であり、「軽作業であれば」という条件が付けられている場合には、該当する業務とそれに配属できる人員の余裕がなければ、復職を拒否する正当な理由となることがわかります。
このような復職にかかる健康上の可能性の判断には、産業医の職務である医学的専門知識が必要です。社員に直接かかわる健康管理の問題のため、会社として産業医の判断を優先することになります。
**
適切な仕事ができる状態でなければ、たとえば現場作業では仕事に支障が出る程度ではなく、安全管理面で危険を伴います。復職を申し出た社員の意思は尊重しながらも、業務内容や職場環境を冷静に判断する視点が会社には求められます。
判断に困ったときには、会社内で抱え込まずに、専門家(ここでは産業医等)へ意見を求める姿勢が大切だと思います。


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事