黙示の残業命令ってどんな場合をいうの?

「資材部って、結構遅くまで残っている人いますよね?」
隣の部で残業していた人から聞いたひとことが気になる。資材部の課長から残業命令を出すことはほとんどない、と聞いていたから・・・
**
管理職から聞いていた状況と異なる残業の実態を聞いて、戸惑いを隠せない人事担当者です。
所定労働時間内に仕事が終わらなくて、残業が恒常的になっていたような場合には、上司の具体的な指示がなくても、黙示の残業命令があったと判断されるケースもあるからです。
ただ、この点についてはケースバイケースであって一律に判断することは難しいため、さっそく資材部に話を聞きに行くことにしたのでした。
そこで今回は、どんな場合に黙示の残業命令として判断されるのか、詳しく確認していきたいと思います。
研修合宿のグループ討論やレポート作成は労働時間?

先月の研修合宿ではレポート課題があり、各自作成して翌日提出するものだった。あるグループではディスカッションが白熱して、深夜に及んだらしい。「その時間は残業申請していいですよね」との質問があったけれど、これって残業時間になるの・・・?
**
普段とは異なる環境で集中して、スキルアップや社員同士のつながりを深めてもらうために開催された泊まり込みの研修。翌日提出のレポート課題に取り組んだ時間を残業扱いにするべきなのか、判断に迷う人事担当者さんです。
というのも、他のグループから同様の声は上がっていなかったからです(課題はサクッと終わった、お菓子を食べながら談笑をまじえて取り組んだ、などの様子)。
そこで今回は、研修合宿中の深夜のディスカッションやレポート作成時間を会社はどのように扱うべきか、詳しく確認していきたいと思います。
36協定の有効期限を3年にしてもいいですか

36協定の有効期限は、担当者にとって地味にプレッシャー。協定の締結はもちろんだけど、労基署への届出を忘れていたらアウト(゚д゚)!時間外・休日労働は違法労働になっちゃう・・・毎年、毎年ほぼ同じ内容なら、有効期限を3年くらいにしてもいいんじゃないの?
**
36協定の有効期限が1年ではなくて3年に延長されると、少しはプレッシャーから解放されるのでは・・・と思う人事部のBさんです。
36協定を締結して、所轄の労働基準監督署に届け出るという手続きを毎年行うのは煩雑なので、「業務の効率化」のため有効期限を3年とすることを上司に提案してみようと考えています。果たして、これは事務処理の向上に有用なのでしょうか?
そこで今回は、36協定の有効期限について詳しく確認していきたいと思います。
36協定違反でも社員に不調がないと会社の責任はないの?

たとえば、36協定の手続きをスッカリ忘れていて放置状態になっていたとしたら、労基署から指摘があるかもしれないのは当然のこと。ただ、そんな無協定の残業であっても、社員から体調不良を訴える声がなかったら、会社が安全配慮義務違反を問われることはないの?
**
36協定の有効期限が迫っているため、手続きが遅れないよう取り組む人事部のBさんです。手続きをすすめながら、冒頭のようなギモンが浮かんできました。
安全配慮義務違反が認められるということは、安全配慮義務違反と病気やケガの発症・増悪との間に相当因果関係があると解釈されているからです。
そこで今回は、社員の心身の不調がない場合、会社は安全配慮義務違反に問われないのか、詳しく確認していきたいと思います。
持ち帰り仕事で体調不良になった社員に会社はどう対応する?

営業部のBさんが過労で入院することに。度々自宅に仕事を持ち帰ってお客さんへの資料などを作成していたらしい。上司が持ち帰り仕事を指示したことはなく、Bさんからも申告がなかったので、持ち帰り仕事に費やした時間を把握していなかったが、会社としてこれからの対応をどうしたらいいのか?
**
社員が身体を壊すほど持ち帰り仕事をしていたことを把握していなかったので、会社として責任を問われるのではないかと、対応に頭を悩ませる人事担当者さんです。
持ち帰り仕事は自宅でテレビをみながらでもでき、会社の管理監督下になく自由のため労働時間にカウントされません。ですが、持ち帰り仕事をせざるを得ないような業務量になっていたことを会社が把握しないのは問題となります。
そこで今回は、社員の持ち帰り仕事に会社がとるべき対応について、詳しく確認していきたいと思います。
副業・兼業で社員が働きすぎて体調不良、会社はどうする?

Xさんが仕事中に倒れてしまった。Xさんは勉強のため、うちの勤務時間外に別のY社でも働いていて、うちとY社での労働時間を合算すると月に100時間を超える時間外労働をしていたらしい。Y社での労働時間を把握していなかったが、会社としてどうしたらいいの?
**
労基法では「労働時間は異なる職場で働く場合でも通算する」との旨が定められています。
本業の職場での労働時間とその社員からの申告等により把握した、他の企業における職場(副業・兼業)での労働時間を通算することになりますが、社員からの申告等がなかった場合には、労働時間の通算は必要とされません。
そんななか、社員が過労で体調不良になってしまい、会社としてどう対応すればいいのか、悩みが深くなる人事担当者さんです。
そこで今回は、副業・兼業による長時間労働に会社がとるべき対応について詳しく確認していきたいと思います。
海外出張では遅くまで働いても残業代は出ないの?

先日まで課長と海外出張に行ってきた。アポのキャンセルや変更、打合せ場所の確保が難航するなど、連日トラブルで遅くまで仕事だった。当然残業代がつくだろうと思っていたら、課長曰く「海外出張はフツウ残業の対象じゃないはずだよ」とのこと。ウッソ、時差があるからなの?(;´Д`) (総合商社勤務 若手社員 談)
**
慣れない海外出張から戻ってきたところ、海外での残業は手当の対象にならないはず、と聞いてショックを隠し切れない若手社員。
とはいえ、海外出張では労働時間の配分などは本人まかせになる(現地でのミッションを臨機応変にこなさないといけないので)ため、実際に働いた時間の把握が困難なのもまた事実です。
そこで今回は、海外出張中の時間外労働を会社はどのように扱うべきなのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
妊娠中の管理職を深夜まで働かせていいの?

営業部のA課長は妊娠中。でも担当のプロジェクトが山場を迎えているようで、先日も深夜まで仕事をしていたらしい。責任感があるのは頼もしいけれど、本人の身体が心配なので人事部としてストップをかけようか・・・(中堅の人事担当者 談)
**
労基法では母性保護の観点から、労働時間等に関する制限が規定されています。妊産婦(妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性)に対する労働時間等の制限は、あくまで本人から申し出があってはじめて会社に実施する義務が生じます。
では、妊産婦が管理職である場合はどのように考えるべきでしょうか。そもそも管理職には、労基法が定める労働時間、休憩、休日についての規定が適用されないからです。
そこで今回は、妊産婦である管理職が深夜残業をしている場合の会社がとるべき対応について詳しく確認していきたいと思います。
駅から職場までの送迎バスに乗っている時間は労働時間?

うちの工場は最寄り駅から遠い。送迎バスを導入しようか、ん?会社の専用交通機関だから乗車している時間は労働時間になるのか?それなら、同じ方面から通勤する社員はマイカー通勤者に便乗すれば労働時間にならないのかな・・・(メーカー勤務 人事担当者 談)
**
労基法の規制する労働時間とは、「会社の指揮命令下で仕事をしている時間」をいうので、「会社の提供する」専用交通機関(送迎バス)を利用している時間は労働時間にあたるのか?とギモンの人事担当者さん。
送迎バスの時間が労働時間になるなら、わざわざ送迎バスを導入しなくてもマイカー通勤者に便乗するよう割り当てると問題は発生しない、と考えていますが、果たして・・・?
そこで今回は、会社の送迎バス乗車中は労働時間になるのか、またマイカー便乗についてはどう考えるのか、詳しく確認していきたいと思います。
WEB学習は残業代の対象になりますか?

「仕事が終わった後に、会社が薦めるWEB学習をやっていますが、残業代申請の対象になりますか?何本も教材をこなしたので、結構な時間になるんですけど・・・」
新型コロナウイルス感染症対策のため、対面での研修や教育などが制限されたことをきっかけにWEB学習(eラーニング、オンライン研修)を導入した企業もあるでしょう。
インターネット環境が整っていれば、パソコンやタブレットを用いて時間や場所を問わず学べるのがWEB学習のメリットのひとつですが、会社としては冒頭のような社員からのギモンにきちんと答えられるようにしておきたいものですよね。
そこで今回は、WEB学習は労働時間としてカウントされて終業後の学びの時間は残業代の対象となるのか、詳しく確認していきたいと思います。
残業にならない持ち帰り仕事とテレワークの違いとは?

部下「自宅に仕事を持ち帰ってやるのは残業にならないのに、なんでテレワークだと通常業務の扱いになるんですか?」
上司「・・・・(たしかに・・・←心の声)」
自宅への持ち帰り仕事は労働時間にカウントされないのに、テレワークがカウントされるのはどうしてなのか・・・部下から質問を受けて言葉に詰まる上司。
「自宅で仕事を行う」ということで、両者は一見同じようにみえるかもしれませんね。ですが、ポイントとなるのは労基法上の労働時間についての定義です。つまり、「会社側の指揮命令下に置かれている時間として評価できるか?」という点が問われることになります。
そこで今回は、自宅への持ち帰り仕事とテレワークは労働時間の扱いでどのように違うのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
トラブル対応で残業時間の規制を守れない?!会社はどうする?

「トラブルが発生したら、「初動対応」VS「残業時間の上限規制」の間で現場はパニックになりそう、どうすればいいの?(;゚Д゚)」
時間外労働や休日労働をさせる場合は、36協定の締結と労基署への届け出が必要ですが、36協定を結んだ場合でも時間外労働の上限規制があります。
そこで労基法には例外として、災害等による臨時の必要がある場合には行政官庁の許可を受けて時間外・休日労働の上限規制を解除する規定があるのですが、働き方改革関連の法改正によって「行政官庁の許可が下りる新基準」が示されました。
そこで今回は、災害等による臨時の必要がある場合に残業が許可される新しい基準はどういうものか、詳しく確認していきたいと思います。
36協定の過半数代表者になりたがる人がゼロで困っています

「36協定の過半数代表者の立候補者を募集しているのに、誰も手を挙げてこなくて困っています。かといって会社から指名するのはダメだし、いっそのこと(職場の)親睦会の会長を過半数代表者にしてしまおうかな?」
36協定だけでなく、労基法その他の法律において過半数代表者との労使協定を必要とする事項は増えています。ですが、過半数代表者を選ぶにあたって立候補者がまったく出てこない・・・といったお話を伺うことがあります。
会社側が指名することは、法律で定める過半数代表者の要件を満たさないのでできませんし、「じゃあ一体どうすればいいの?」となりますよね。
そこで今回は、過半数代表者の選出手続き、また社員親睦会の会長を過半数代表者にすることの可否について詳しく確認していきたいと思います。
副業・兼業で残業と休日はどう取り扱うの?

「会社の休みの日に、別の会社でスキルアップ(⋈◍>◡<◍)。✧♡」
副業・兼業で、いまの仕事(本業)で必要な能力を伸ばしたい社員と伸ばしてほしいと思う会社。会社として押さえておくべきは、労働時間マネジメントと残業代(割増賃金)の取扱いです。
労基法では、複数の職場で勤務する(本業&副業・兼業)場合、労働時間を通算することになっています。労働時間を通算して法定労働時間を超えるとき、会社は自社で発生した法定外労働時間について、36協定を締結したうえで残業代(割増賃金)を支払う必要があります。
とはいえ、「これは時間外になるの?休日労働扱いになるの?」と、具体的にどうすればいいのか、判断に迷われることもあるのではないでしょうか。
そこで今回は、副業・兼業での残業時間にまつわる問題(割増賃金、休日労働)について、詳しく確認していきたいと思います。
副業・兼業で労働時間はどうカウントするの?
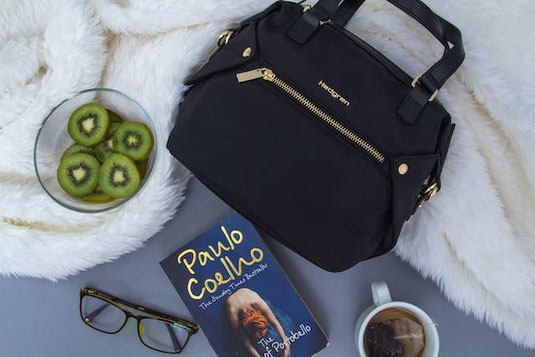
副業申請が出ているDさん、最近ぐったりしてる。申請されている時間よりも、実は副業の労働時間が長いのかな?体調が心配だわ~(;´Д`)
(商社勤務 人事担当者談)
**
テレワークの浸透などによって働き手には「副業・兼業をしやすい環境になってきた」との感覚があっても、会社にしては労働時間マネジメントのあり方が気にかかるところです。
本業以外の仕事によって、メンタル的にも肉体的にもへとへとになっていないか社員の健康状態が心配だからです(企業が社員の副業・兼業を禁止する理由のひとつでもあります)。
実務的には、副業・兼業による自社の36協定とのバランス、どのラインから時間外労働になるのかをまずは理解しておくことが大切です。
そこで今回は、副業・兼業で2つ以上の職場で働く場合に労働時間はどうカウントするのか、詳しく確認していきたいと思います。
疲労回復に効く「勤務間インターバル」ってなんですか

当社は業界的に深夜残業が普通で、睡眠不足になっても疲れがたまって眠りが浅い・・・といった社員の声も聞く。睡眠障害や不眠はメンタル不全につながりやすいから、会社としてどう対応すればいいのか・・・
**
社員の健康対策に考えをめぐらす経営者、人事担当者は多いでしょう。疲れるとストレス耐性が落ちるので、「休む=自分のコンディションを整える」時間を取ることはとても大切です。
社員の生活時間や睡眠時間を確保する方法のひとつとして、比較的新しい制度ですが、「勤務間インターバル」の導入があります。
そこで今回は、勤務間インターバルを導入する具体的な例などについて、詳しく確認していきたいと思います。
テレワークの中抜け時間を会社はどう取り扱うといいの?

「子どもが夏休みで遊んでもらおうとして、仕事の邪魔をしてくる」
「ネット注文の商品が自宅に届くたびに、仕事が中断される」
自宅でテレワークをしているとよくある困りごとだと思いますが、会社としてはこの「中抜け時間」をどう取り扱えばいいのか、判断に迷うところではないでしょうか。
また、自宅で仕事をしているとどうしても、仕事とプライベートのオン・オフの切り替えが難しくダラダラずっと仕事を続けてしまう・・・といった状況も起こりがちです。
会社としては労働時間の把握に工夫が必要となることもあるでしょう。
そこで今回は、いわゆる「中抜け時間」をはじめとするテレワークにまつわる労働時間マネジメントについて、詳しく確認していきたいと思います。
昼休みを2時間にしても問題ありませんか

新商品の資材搬入が、供給元の都合でいつも終業時刻近くになる。材料待ちでただでさえ生産ロスが発生するのに、到着した材料の運搬で毎回残業になるというのは困る。昼休みを2時間にして対応するのはどうだろうか?(メーカー勤務 資材部課長談)
**
長時間の待機時間のある業務形態のため、終業時刻を1時間今よりも後ろにずらして業務に対応するため、現行の休憩時間1時間を2時間にしようと考える課長さんです。
労基法では、与えるべき休憩時間の長さの最低ラインを規定しているので、最長の長さについては規制していません。
ただし、考えないといけないのは、途中の休憩時間が長くなると必然的に拘束時間が長くなってしまうという点です。
そこで今回は、休憩時間を2時間に設定するにあたって検討しておくべきことについて詳しく確認していきたいと思います。
出張期間中の休日は休日労働になりますか

「出張期間中に休日があった場合、どう取り扱えばいいのかな?」
今年のカレンダーの並びをみると、ゴールデンウィークは最大で10連休にもなるようです。長い休みの合間に商談などのため出張に出かける場合もあるかもしれません。
勤怠の処理に頭を悩ませる、経営者や管理職の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
たとえば、出張期間の中日に日曜日があるような場合は休ませないといけないのか(それなら出張に来た意味なくない?)、ただでさえ出張スケジュールをたてるのは大変なのに、頭がぐるぐるします・・・といった声もお聞きします。
そこで今回は、出張期間中であっても休日には社員を休ませないといけないのか、その取扱いについて詳しく確認していきたいと思います。
社員がズルしてタイムカードを打刻、会社の対応はどうなる?

退社時に「俺のも押しといて」と、同僚にタイムカードを押させる社員。見かけては注意しているけれど、他人に自分のタイムカードを押させるなんて許されない行為、懲戒処分モノじゃないの? (上司談)
**
同僚と同じタイミングで退社する際、ズボラで自分のタイムカードも一緒に押してもらう・・・というのは容易に想像できますが、違法行為とまでは言わないにしても、決してよい行動とは言えませんよね(^^;)
というのも、労働時間マネジメントのためタイムカードの打刻は正確に行われないといけないので、不正打刻は許されないからです。
単なるズボラというのではなく、他人による不正なタイムカードの打刻は完全にアウトです。
そこで今回は、タイムカードの不正打刻の問題について詳しく確認していきたいと思います。
ワークとライフのどっちが優先するの?
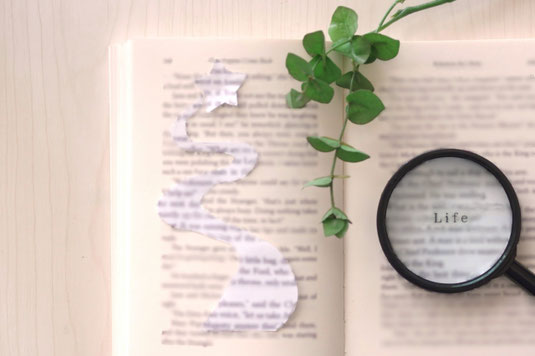
この記事のタイトルをご覧になって、どうも腑に落ちない、なんだかひっかかると思われる方もいらっしゃるかもしれません。
「ワークとライフ、仕事とプライベートのどちらかなんて選べない、そんなのどっちも大切に決まっているよ!」といった意見は、いまの時代ではとても多いでしょう。
とはいえ、会社の残業命令(ワーク)に社員が「NO」を突き付け、自分の都合(ライフ)を優先させる・・・なんていうことはできるのでしょうか?
なぜなら、就業規則に時間外労働のあることが規定されており、かつ、36協定が結ばれていれば、原則として社員はこれに応じないといけない義務があるからです。
そこで今回は、仕事と私用のどちらが優先するのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
36協定の日付をさかのぼってもいいですか?

「ヤバっっ!新年度のバタバタで36協定の手続きをスッカリ忘れていた!!気がついたら有効期間(←いつも締結している日付)をだいぶ過ぎている!!((((;゚Д゚))))
・・・36協定って日付をさかのぼってもいいのかな?」
企業の総務部や人事部の担当者にとって、背筋が凍りつく瞬間です。というのも、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて社員に時間外労働や休日労働をさせる場合は、36協定の締結と労基署への届け出が必要だからです。
冒頭のような事態がないに越したことはないのはもちろんですが、あとでカバーできるのかどうかは気になるところですよね。
そこで今回は、36協定の日付を遡及しても有効になるのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
法定労働時間と所定労働時間ってどう違うの?

「うちの就業規則には“法定労働時間”と“所定労働時間”という単語がありますが、どう違うんですか?」
部下や後輩からこんな質問があったとき、みなさんどう答えますか?
言葉は似ていても、“法定労働時間”と“所定労働時間”の意味はまったく違います。36協定の時間外労働の制限の適用も、法定労働時間を超えた時間が対象であって、所定労働時間を超えた時間ではありません。
長時間労働は社会的な問題(過労死など)ですし、ココロとカラダの健康管理やワーク・ライフ・バランスの観点からも、労働時間マネジメントの基本を押さえることは、ビジネスパーソンとしての必須課題といえます。
そこで今回は、“法定労働時間”と“所定労働時間”の違いは何なのか、詳しく確認していきたいと思います。
労働時間の把握のため社員のPCを無断でチェックしてもいいの?

「勤務時間の自己申告制をとっている部署では、実際は記録よりも遅くまで働いているようだ。会社として正確な労働時間を把握するために、社員のパソコンの起動・終了時刻をチェックしたい。無断でやって問題ないのかな?」
労働時間の「自己申告制」は、社員に労働時間を自主的に記録させて、どれだけ働いたのかを自己管理させる方法です。
ただ労働時間が長くなる傾向があり、上司や人事担当者には、本人まかせにしないで労働時間をきちんと把握することが求められます。
そのため、抜き打ちのパソコンチェックを思いつくも「プライバシーの問題が発生するのでは?」と、みなさん不安に思われるようです。
そこで今回は、労働時間の把握のため会社が社員のパソコンを無断でチェックしてもいいのか問題について、詳しく確認していきたいと思います。
商品到着待ちの時間を休憩時間としてはダメですか

商品到着の遅延で売り場に陳列できず、何もすることがない。やっと商品が搬入されてきたら、「昼休憩の時間だから」とパートさんもアルバイトくんもランチに行ってしまった。午前中は何もすることがなかったのだから休憩しているのと同じでしょ。私ひとりで陳列することになって・・・"(-""-)" (小売業 リーダー職26歳 談)
**
商品の到着を待っている時間は、休憩時間と同じようなものなのだから、その分ランチ休憩を削って商品の陳列を優先してほしい・・・というのが、リーダー社員の心の叫びです。その気持ちはよく分かりますが、休憩時間かどうかの判断基準に注意しなければなりません。
というも、休憩時間とは単に作業に従事しない時間をいうのではないからです。
そこで今回は、商品の到着を待つ時間を休憩時間としていいのか、休憩時間かどうかの判断基準について詳しく確認していきたいと思います。
タイムカードによる労働時間の推定で問われる会社の対応

「仕事が終わっているのに同僚らと雑談しているのか、タイムカードの打刻時が終業時刻よりだいぶ後の社員がいて対応に困る・・・」
タイムカードの打刻にまつわる悩みを抱える総務や人事の担当者は多いかもしれません。実はコレ、要注意の案件です。
というのも、「部署の懇親会のため(タイムカードの打刻が遅くなった)」「社内の部活動のため」「本人の私用によるため」といったことを会社側が立証しない限り、タイムカードの打刻時近くまで働いていたものとして取り扱わなければならないからです。
このことから、会社は社員の労働時間マネジメントをしっかり行わなければならないことがわかります。
そこで今回は、タイムカードの取扱いで問われる会社の対応について、詳しく確認していきたいと思います。
フレキシブルタイムに打ち合わせをいれてはダメですか

「取引先の要望でうちのフレキシブルタイムに重要案件の会議が入ったが、法的にいいのかな?」(困り顔の営業課長 談)
フレックスタイム制には通常、コアタイムとフレキシブルタイムの時間帯があります。コアタイムは必ず勤務しなければならない時間帯なので、ここに会議や打ち合わせを予定するのはノープロブレムです。
一方のフレキシブルタイムは社員が自由に出勤・退勤の時刻を選択できる時間帯です。会社側が「会議や打ち合わせに参加しなさい」と時刻を指定しての勤務命令はできるのでしょうか?
仕事上やむをえない事情で取引先が来社することはありえますし、その時間帯がフレキシブルタイムで担当者は不在、というのでは会社の対応として合理的とはいえません。
そこで今回は、フレキシブルタイムに会議や打ち合わせを予定することに問題はないのか、会社がとるべき対応についてみていきたいと思います。
出張中の新幹線やバスでの移動は労働時間になりますか

新幹線や在来線を使う地方への出張が社員から敬遠されがちだ。日帰り出張では帰宅時間が遅くなるのに残業代も出ない、と不満を耳にする。訪問先の都合で時刻指定で乗車してもらうこともあるので、移動も労働時間としてカウントするべきなのだろうか・・・
**
交通機関に乗っている時間を労働時間としてカウントするのか?問題です。出張で遅い時間に帰ってくるのに、残業代を出さなくていいのだろうか・・・と後ろめたく思われる上司や人事担当の方もいらっしゃるようです。
出張の疲れによる愚痴を聞くと、どうしてもそう感じてしまうのが人情というものですよね。ですが、まず大切なのは労基法上ではどのように取り扱うのか?について正確に把握することです。
そこで今回は、出張中において単に交通機関に乗っているだけの時間は労働時間としてカウントされるのか、確認していきたいと思います。
変形労働時間制で働きたくない社員を認めないとダメですか

「自分の生活スタイルを崩したくない、と変形労働時間制はイヤだという社員がいます。プライベートに対して強く言えず、これを認めるべきでしょうか?」
感染症対策と経済活動の両立を図るため、法定労働時間の柔軟な枠組みをめざす変形労働時間制を職場に導入するケースもあるでしょう。業務の繁閑にあわせて労働時間の効率的な配分を行い、全体として労働時間を短縮することができるからです。
そんな会社側の思いとは裏腹に変形労働時間制で働きたくない社員が。対応に戸惑ってしまいますよね。その理由を真摯に聞けば聞くほど、「会社として何か配慮が必要なのか?」と悩まれるようです。
そこで今回は、変形労働時間制で働きたくない社員を会社は認めないといけないのか、その対応について詳しく確認していきたいと思います。
休憩時間も休日もフレックスにしていいですか

「ランチは、午前の仕事に目途をつけてから自分のペースでとりたい」
「休日のオフィスの方が落ち着くので、休日に出勤して仕事したい」
フレックスタイム制が導入された職場では、このように“休憩も休日も自由に自分で決めたい”との声が上がることは想像に難くありません。
ですが、フレックスタイム制は、始業・終業時刻のみを社員が自分で決める労働時間制なのであって、休憩や休日についてはフレックス制とはなっていません。
とはいえ、たとえば11時30分に出勤のフレックスタイム社員に対して、ほんの30分後に「昼休憩は12時から1時間なので必ずランチにしてください」というのも現実的ではなく、柔軟性に欠けますよね。
そこで今回は、フレックスタイム制で休憩時間や休日をどう運用すれば、そのメリットを十分活かせるのか、詳しく確認していきたいと思います。
みなし労働時間制でも会社は労働時間を把握するべき?
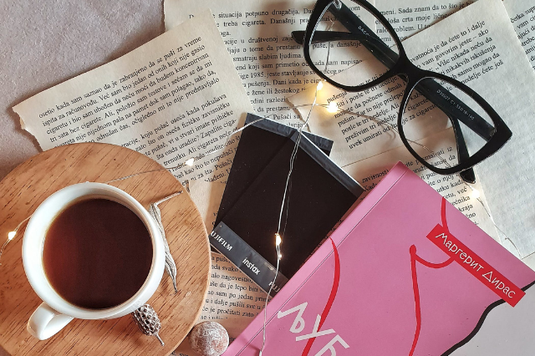
「みなし労働時間制にしても、結局上司が部下の労働時間を把握しないといけないなら、意味なくないですか?」
会社は常に労働時間を把握して、社員にいま何時間働かせているのか、法律上で許されるタイムリミットまであと何時間なのかを知っておく必要があります。労働時間にまつわる法律の規定に違反してはいけないからです。
とはいえ、オフィスを出てセールスする営業職などでは、労働時間の算定が一般的に難しいため「みなし労働時間制」をとるわけであって、それなのに社員の労働時間を把握しないといけないのなら、「どうしろというんだ」という気持ちになりそうです。
そこで今回は、みなし労働時間制をとっている場合でも、会社には労働時間を把握する義務があるのかどうか、詳しく確認していきましょう。
36協定は本社だけ結べば手続きOKですか?

社員の勤務する場所が、本社や店舗、あるいは工場など、それぞれ別拠点にある場合も多いでしょう。そこで気をつけておきたいのが36協定の締結単位です。
職場が本社と店舗で分かれているけれど、「(36協定を)本社で締結しているからバッチリ、手続きに不備ナシ♪」と安心しているケース。
「本社も店舗も締結しているから問題ナシ・・・あっ、今年の春に新店舗がオープンしたが、バタバタしていて忘れていた・・・」といったケース。・・・これらのケースは要注意です。
というのも、36協定は本社だけでなく、支店、店舗、工場、営業所などそれぞれの事業場において締結しなければならないからです。
こういったうっかりミスは、よくやってしまいがちですから、今回は、36協定の締結単位をどう考えるべきなのか、そもそもについて詳しく確認していきたいと思います。
フレックスタイム制での深夜業は社員の自己責任?

フレックスタイム制を始めた部署で、遅い時間から仕事を始めて深夜までやっている社員が出てきた。「深夜業が当たり前」といった雰囲気になるのは避けたいし、やはり防犯上まずい。フレックスタイム制だからといって、深夜業は社員の自己責任として片づけていいものか?
**
フレックスタイム制は、始業・終業時刻を社員本人による自主的な決定にゆだねる制度です。ですが、これは労働時間についてのみ適用があり、休憩時間・休日・深夜業については適用されません。
とはいえ、(会社が命令していないのに)本人の都合で深夜になり、深夜労働に対する割増賃金を支払うのはちょっと疑問が・・・というのもわかります。また、頻繁に深夜のオフィスで仕事をするというのは、社員の防犯・健康面での安全が心配です。
そこで今回は、フレックスタイム制における深夜業の取扱いについて、詳しく確認していきたいと思います。
お茶や英語などの習い事は労働時間になりますか?

「社員が習い事をしている時間は労働時間にカウントされますか?」
社内で茶道や華道、書道の「部活」があり、社外から講師を招いて活動を行っていて、「部活動」の時間が労働時間にカウントされるのか、されるのなら残業代を支払う必要があるのか?とのことでした。
また、仕事に役立てようと終業時刻後に英会話スクールに通う社員さんから、残業代の対象にならないのか?との質問もあったそうです。
社員の前向きな姿勢に水を差すことのないよう、法律面のことをクリアにしておきたいとお考えで、このような悩みをお持ちの経営者、人事担当者の方は少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、社内・社外における「習い事」が労働時間にあたるのかどうかについて、詳しく確認していきたいと思います。
日曜日に出勤、休日の振替と代休はどう違うの?

新型コロナウィルスの予防対策から、職場での社員同士の接触を減らすために、(通常はお休みの日である)土曜日や日曜日も出勤日にあて、1日あたりの出勤率を削減しようとするケースもあるでしょう。
とはいえ、休日は毎週1日の週休制が原則であり(例外として4週4日休日制)、労基法で「会社は社員に毎週少なくとも1回の休日を与えないとダメ」とされています。
そのため、「通常の”お休みの日”と”出勤日”を入れ替えて週1日の休日を確保・・・」と考えに考えて、出勤表を作成することになりますが、ややこしくなりがちなのが休日の振替と代休の違いについてです。
特に取引先の緊急対応などで、せっかく考えた出勤表とは異なる「イレギュラー出勤」が発生するとさらに複雑に・・・( ゚Д゚)
そこで今回は、休日の振替と代休の効果がどう違うのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
ウィズコロナで分散勤務を実現させる3つの方法
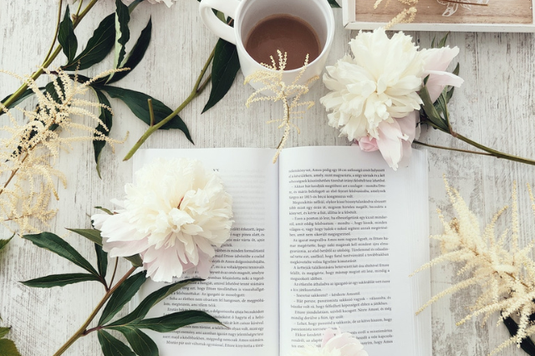
新型コロナウィルスの感染拡大から、今は出勤率の削減や職場での社員同士の接触を減らすなどの対策が企業の課題になっています。
とはいえ、パソコンの配備、個人情報の取扱いなど、テレワークの実施にハードルの高い職種もあるでしょう。テレワークが通常モードの職種でも、仕事の都合で出社しなければならないときもあると思います。
そんなとき会社として心配なのは、混雑した電車等での通勤によって社員に負担がかかることです。
できるかぎりの感染症の予防対策を行いながら、社員の負担を軽減し、仕事を続けていくには、今までは“当たり前”とされてきた勤務体制を状況に応じて見直し、選択肢を増やすことがポイントになってきます。
そこで今回は、ウィズコロナ時代に分散勤務を実現させる3つの方法についてご紹介したいと思います。
なぜ会社は社員の労働時間を把握しなければダメなのか?
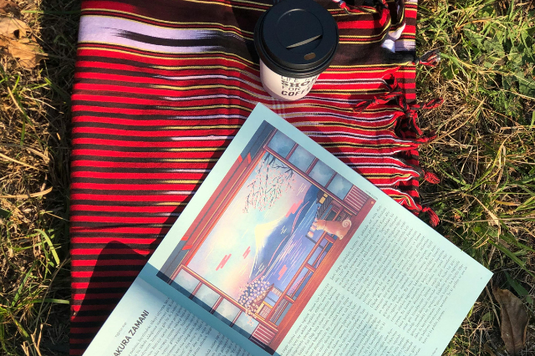
「また、タイムカードを押してない人がいる(怒)。面倒だけど注意して、出勤時間を確認しないと。あーあ、なんでこんなことしなきゃいけないんだろう・・」(メーカー勤務・人事担当26歳談)
実際に社員がその日に働いているのなら、会社には労働時間を把握してタイムマネジメントを行う義務が課せられています。
言い換えると、「タイムレコーダーの打ち忘れは本人のミス」という理由で、欠勤扱い(労働時間はゼロカウント)にすることはできません。
人事担当者にしては「モヤッ」とすることがあるかもしれませんし、社員にしても「タイムカードはめんどくさい」との思いがあるかもしれないのに、なんでそこまで・・・(一一")
そこで今回は、なぜ会社は社員の労働時間を把握しなければダメなのか、またその根拠はどんなところにあるのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
仕事の準備や後始末が労働時間になるのはどんなとき?

「会社に着いてからの制服や作業服への着替え、朝の掃除や整理整頓、仕事が終わってからの片づけは労働時間にカウントされるの?」
実際に作業をしている時間(会社の指揮命令下にある時間)が労働時間にカウントされるのは、誰もが頷けると思います。
ですが、それらに付随する前後の時間について判断に迷うことは多いのではないでしょうか。
「〇〇〇の場合は労働時間にあたらないけれど、×××なら労働時間になる」というような覚え方をしていると非常に煩雑ですし、「じゃあ△△△のときはどうなるの?」と、イレギュラーなケースに対応できませんよね。
そこで今回は、実作業に付帯する作業時間が労働時間になるのはどんなときか、その「判断基準」について詳しく確認していきたいと思います。
フレックスタイム制なら会社は時間管理しなくていい?

「フレックスタイム制は社員の自主性にまかせるもの。・・・会社は社員の時間管理をしなくてもよい、ということ?」
新型コロナウィルスの予防対策のための時差出勤や悪天候による公共交通機関の遅延によって、始業時刻までに出勤できないことなども想定内にしなければならない時代です。
そのため、フレックスタイム制の導入を検討されている企業もあるでしょう。時間に対する社員の自己管理意識を向上させるという点で、フレックスタイム制にはプラス効果があります。
冒頭のようなギモンもあるかもしれませんが、結論をお伝えすると、フレックスタイム制でも、会社には労働時間を把握する義務があります。
そこで今回は、フレックスタイム制と時間管理の関係について、詳しくみていきたいと思います。
定時を過ぎてからの仕事はすべてサービス残業?

今日も30分も残業した。毎日これだから、1か月の営業日が20日だとして、単純計算でトータル10時間だ。結構な時間だ。それなのに、18時までの残業は申請しないのがうちの常識のようだ。毎日サービス残業なんてやってられない・・・(新入社員のAさん談)
**
Aさんの会社の就業時間は、朝の9時に始まって、途中1時間の昼休憩を挟み、夕方17時半で終わりの7時間30分労働です。
つまり「17時半から18時までの所定時間外の働きに対して賃金が支払われない」というのがAさんの不満です。・・・ですが、これは正しい認識ではありません。
そこで今回は、いわゆる「サービス残業」とはどんな状態のことをいうのか、詳しく確認していきたいと思います。
36協定の時間外労働のなかに休日労働は含まれますか

「時間外労働の上限は原則、月45時間、年360時間ということですが、この時間外労働時間のなかに休日労働も含まれるのですか?」
法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて社員に時間外労働や休日労働をさせる場合は、36協定の締結(+労基署への届け出)が必要です。
36協定を結ぶにあたって、その内容についてよくご質問をいただくのが、「時間外労働時間」と「休日労働」の関係です。
特に今年は、4月から時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されるので、「休日労働が時間外労働に含まれるなら、月45時間の上限を超えてしまうかもしれない」と、心配される経営者、管理職の方からの声をたびたびお聞きしました。
そこで今回は、36協定において「休日労働」は時間外労働時間に含まれるのかどうかについて、詳しく確認していきたいと思います。
35%アップで割増計算する休日労働の日とはどんな日?

「社員を日曜日に働かせる場合3割5分増しで給与を計算しないといけないですよね?」
→回答は「惜しい!(8割がた正解?)」
・・・週休2日制で週2日の休日がある場合には、そのうち1日分の休日に社員を働かせても、もう1日分の休日が確保されている限り、法律上の休日労働にあたらず、割増賃金を支払う必要もないからです。
コンサルティングのなかで「休日労働の日に徹夜勤務をさせるときはどう考えるといいのか?」など、特に休日労働の取扱いがよくわからない、というお声をよくお聞きします。
そこで今回は、3割5分増で割増賃金を計算することになる休日労働とは、いったいどんな日なのか、あわせて休日に徹夜勤務となる場合について詳しく確認していきたいと思います。
上司が社員の居残り残業を放置していてもいい?

上司が時間外労働を命令していなくても、部下の社員が居残り残業をしている・・・職場でわりと見られる光景ではないでしょうか。
ちょうどいまなら、新型コロナウィルスの影響で平常通りに行かなかった雑務の処理や担当業務の整理、諸々の連絡などのため、終業時刻後もデスクに向かう・・・という姿もあるかもしれません。
上司が部下の居残りを知りながらも、残業を中止させずにほったらかしにしていた場合、残業命令があったものとみなされるのでしょうか。つまり、労働時間としてカウントされるのかが問題です。
この状況が恒常的なものであれば、法律にもとづく時間管理が問題になるだけでなく、社員の健康状態が心配です。特にいまは、遅くまでの仕事による疲労で、身体の免疫力を落とすようなことは避けるべきですよね。
今回は、社員の自主的な残業を放置した場合、法律的に労働時間マネジメントはどのように考えられているのか、確認していきたいと思います。
上司が主催の勉強会は労働時間にカウントされますか

「課長から部内の若手に向けて、勉強会をやらないかと案内があった。これって課長からの業務命令なのかな?それともあくまで同好会レベルの話なのかな?(;・∀・)」
新年度がスタートすると、メンバーの能力を伸ばすために、社内で勉強会や研修を実施する機会が増えてくるのではないでしょうか。
仕事に必要な知識や新しいスキルを、一定の期間内でかつ効率よく身につけてもらうことを目的とされているのだと思います。
ただ、人材マネジメント上問題となるのはそれが「労働時間にカウントされるのかどうか」ということです。
そこで今回は、課長など管理職が主催する勉強会は労働時間にカウントされるのか、されないのか、詳しく確認していきたいと思います。
フレックスタイム制で気をつけたい遅刻・早退の取扱い

「通勤電車での混雑を避けて、自分のパフォーマンスがあがるタイミングで社員が出勤できるようにしたい」
そこでフレックスタイム制を検討する人事担当者さん。これは、一定期間における総労働時間を労使協定で定めておき、社員がその範囲内で毎日の始業・終業時刻を選択して働くことのできる制度です。
社員が生活と仕事のバランスをうまくとり、効率よく働けるようにするのが目的なので導入の検討はよいことですが、皆勤手当や精勤手当といった、この制度になじまない手当が存在していたりするなど、制度と給料体系の理屈が一致していないケースもみられます。
「制度と理屈があわない」そのカギは、遅刻と早退の取扱い方です。
そこで今回は、フレックスタイム制導入の検討にあたって、気をつけるべき遅刻と早退の取扱い方について確認していきたいと思います。
お正月セールで出勤、労働時間はどうなる?

「今年はカレンダーの並びでお正月休みが長いけれど、初売りの準備でみんなに出勤してもらわないと。・・・いつもの就業形態とは違うけれど、労働時間はどうカウントすればいいのかな?」(小売業 店長談)
年末年始、お正月セールや福袋の売り出しで営業するお店も多いですいよね。休みの日に社員に出勤してもらったり、お客さんの呼び込みのため屋外での販促活動をお願いすることもあるでしょう。
お正月休みに社員に出勤してもらった場合、休日労働と事業場外労働のみなし労働時間は適用されるのか?という問題があります。
そこで今回は、休日に社員が事業場外業務に従事した場合の取扱いについて詳しく確認していきたいと思います。
年末の挨拶回りで営業車の見張りは休憩時間?

12月に入り、そろそろお得意様に挨拶回りをされる企業も多いのではないでしょうか。
年末の挨拶回りに営業車で出かけるとき、特に運転者には盗難防止のため、車両を監視する義務が生じます。もし、社員が管理を怠って社有車を盗まれでもしたら大変だからです。(盗難車両により交通事故が起きた場合、車の所有者である会社は多大な損害を被るおそれアリ)。
この場合、人材マネジメントの観点から問題となるのは、盗難防止などのために車両を監視している時間が休憩時間といえるかどうかです。
そこで今回は、年末の挨拶回りなど営業車での外出で、車両の監視義務と休憩時間の関係をどう考えるとよいのかについて、詳しく確認していきましょう。
1日単位のフレックスタイム制をうまく活用するコツ

「毎日の出社や退社の時刻を社員本人に自由に決めてもらいたいです」
朝の冷え込みで布団から出たくなくなる季節になりました。もう少し布団の中にいたいけれど仕事があるし・・・誰もが抱える寒い季節の葛藤ですよね。だからというわけではないと思いますが、冒頭のようなご相談をいただくことがあります。
始業・終業時刻を社員本人の自己選択によるものにするには、「1日単位のフレックスタイム制」という方法があります。
これは法律上のフレックスタイム制ではなく、社員本人の自己選択による自動的な始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ制度で、運用にあたっては注意点があります。
そこで今回は、1日単位のフレックスタイム制をうまく活用するためのポイントについて詳しく確認していきたいと思います。
法定休日の日曜日に出勤すると社員はトクをする?

「どうせ休日出勤するなら、土曜日より日曜日に出たいです。土曜日に出ると損だからイヤです」
週休二日制(土・日曜日がお休み)の企業で、日曜日を法定休日として就業規則で特定していたとき、社員のなかで「土曜日より日曜日に休日出勤したほうがおトク♪」という認識が社員にあるようです。
というのも、法律上法定休日に会社が社員を働かせると割増賃金率が高くなるからです。
とはいえ、1週1日の労基法で定める休日を付与しながらも、特定された法定休日に働かせたことで35%増の割増賃金になる・・・なんとくなくモヤッとされる上司の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、日曜日に働かせると、土曜日の会社で定めた所定休日に休みを与えていても労基法上の休日労働になるのか、詳しく確認していきたいと思います。
振替休日の社員による指定制と代休はどう違うの?

代休(代償休日)とは、休日労働の事実が生じた後に、その代償として休日を与えることです。
いったん発生した休日労働の事実は消せませんが、社員に休息の機会を与えることで社員の健康を維持できます。
代休と似たものとして「振替休日の社員による指定制」があります。法律上は、振替休日と代休の両者では明らかに異なりますが、一般的に同じものとみられがちです。
企業における実務でも、振替休日の社員による指定制と代休は厳密には区別されておらず、ごちゃまぜになっているケースも多いようです。その企業の慣行的な取扱いによって処理されることがほとんどでしょう。
そこで今回は、振替休日の社員による指定制と代休の違いについて、詳しく確認していきたいと思います。
週休2日制で土曜日に出勤すると休日労働?

労基法において休日は、週1日を原則としています(例外として4週4日休日制)。よって、この法定休日を上回った、会社が決めた法定外の休日に働いたとしても、労基法上の休日労働にはなりません。
「ええっ!じゃあ、うちの会社は週休2日制なので、土曜日に出勤してもらっても休日労働にはならないんですね・・・休日労働の割増賃金(3割5分増)で給料計算していました・・・」
コンサルティングのなかで、休日と休日労働の関係についてお伝えすると、企業のご担当者からこのようなリアクションをいただくことがよくあります。
テレビドラマなどでは、がらんとした休みの日のオフィスに出勤して「あ~こんないい天気の日に【休日出勤】か・・・」といったボヤキのシーンはよくみられますから、労基法上の扱いと混同してしまうのも無理はありません。
そこで今回は、週休2日制における休日労働の取扱いについて、詳しく確認していきましょう。
休憩時間の自由利用を制限できるときとは

「うちでは就業規則で昼休み休憩の外出は許可制にしています。昼食は食堂がありますし、これで問題はありませんよね?」
ランチタイムなどの休憩時間とは、社員が権利として、労働時間の途中に仕事から離れることを保障されている時間のことです。そのため、会社が社員の当然の権利を侵害していることになってはいないか?と、就業規則の規定にギモンを持たれた人事担当者さんです。
実は、休憩時間の利用について、「職場の規律を守るために必要な制限」を設けることは、休憩本来の目的を妨げない限り問題ありません。
そこで今回は、休憩時間の自由利用を制限できるときとは、具体的にどんなときなのかについて詳しく確認していきたいと思います。。
女性社員が育児時間を請求したとき会社のとるべき対応とは

女性社員「1日2回の育児時間を連続してとれますか?」
上司「?!何それ、そんな制度うちの会社にあるの?」
**
「育児時間」とは、1歳未満の子どもを育てる女性社員が、昼休みなどの休憩時間のほかに1日2回それぞれ少なくとも30分、授乳など育児のための時間を会社に請求できる、という労基法上の制度です。
かつては結婚・出産で退職する女性社員は少なくなかったため、育児時間の存在自体を知らずにいた、というケースは多いようです。
では、冒頭のような質問を受けたとき、「1日2回を連続してとるのはダメだ」「この時間帯にとってはダメだ」など制限を会社が設けることはできるのでしょうか。
今回は、意外と知らない会社の育児時間の与え方について詳しく確認していきたいと思います。
列車の遅れや運休で会社の始業時刻を遅らせてもいいですか

台風のシーズンは電車やバスが遅れたり、運休になることもしばしば。社員が出勤できるのは、始業時刻をだいぶ過ぎてからということもある。 納期がひっ迫しているときならパニックだ(;゚Д゚)。
そんなとき、始業・終業時刻を後ろにずらせないにかな?うちではフレックスタイム制をとっていないからダメかな?
**
職場にフレックス制を導入していないと、始業・終業時刻を動かすことはできないのでしょうか?
結論からお伝えすると、就業規則に規定すれば、いわゆる就業時間帯の繰上げ・繰下げを実施することができます。これは、変形労働時間制やフレックスタイム制にはあたらないからです。
そこで今回は、就業時間帯の繰上げ・繰下げとはどういったものなのか、詳しく確認していきたいと思います。
飲み会が労働時間になるとき、ならないとき

「テレビドラマで会社の飲み会を勤務時間として申請しているシーンをみた社員から、”うちの会社ではダメなんですか?”と質問されて、しどろもどろになってしまいました。法律的にはどうなるのでしょうか?社員が納得するような根拠はありますか?」
今の季節は社内や仕事関係者で暑気払いの会を催す機会も多いのではないでしょうか。そのためか、コンサルティングの中でも「飲み会」にまつわるご質問をいただくことがあります。
「飲み会」とひとくちにいっても、仕事にまつわる飲食の機会といえば、得意先の接待、会食付きの打合せ、取引先の開店パーティ、社内の送別会や忘年会・・・などなど、いろいろなものがあります。
そこで今回は、これらの飲み会(仕事関係の飲食の機会)が労働時間になるとき、ならないときについて整理していきたいと思います。
ランチタイムの電話対応は労働時間になる?

「昼休み中に電話が鳴ったときには、オフィスのデスクで弁当を食べている社員が対応してくれます。とてもありがたいのですが、会社として休憩を与えていないことになりませんか?」
貴重なリフレッシュタイムに本来ならお弁当をパクついているだけでいいはずなのに、休憩をとらせていないことになって労働時間として残業代の対象になるのでは?・・・と懸念された人事担当者の方からご相談いただいたことがありました。
お昼休みは店舗で食べるよりも、コンビニやファストフード店でランチを買ってきてオフィス内で食べる社員さんも多いようなので、 みなさんの職場でもよく見られる光景かもしれませんね。
そこで今回は、ランチタイム中の電話応対は労働時間にあたるのかどうかについて、詳しく確認していきたいと思います。
仕事に必要な資格の試験勉強は労働時間になりますか
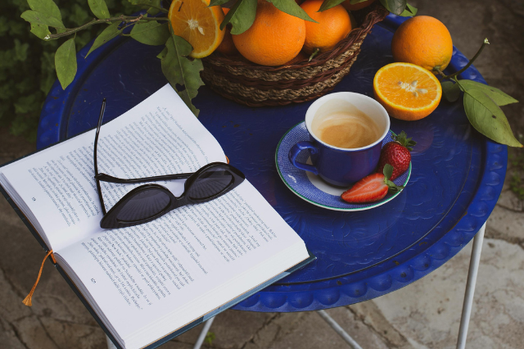
「うちの仕事に必要な資格をできるだけ多くの社員に取得してもらいたい。ただ、社員からは”会社がやれというなら勉強しますが、その時間に残業代はつきますよね”と返ってきた。どう対応するといいのか・・・」
仕事への意欲を高めるために、資格取得をすすめる会社と、資格試験へのチャレンジを対価でもって認めて欲しい社員。
社員のやる気に水を差さないように、資格試験の勉強時間を労働時間にカウントするべきなのか、頭を悩ます経営者・人事担当者の方は少なくないようです。
個人的にはどちらの気持ちも理解できるのですが、春らんまんの美しい季節に気持ちよく勉強のスタートをきれるよう、法律的にどのように扱われるのかをまずは押さえておきたいですよね。
そこで今回は、資格試験の勉強が労働時間にカウントされるのかどうかについて詳しく確認していきたいと思います。
仕事後の後片付け・整理整頓、ダンドリに残業代はつきますか?

職場が整理整頓されていると、仕事がはかどる。朝から気持ちよく仕事にとりかかるためにも、部下には仕事が終わったら仕事道具を片付けてから帰ってほしい。でも部下からは即行で「それやると残業代はつくんですか?」との返しが・・・(;´Д`)
**
片付いた職場では必要なモノが適切に収納かつ管理されているので、効率よく仕事を進めることができます。そのため、片付けの意識を浸透させようとする上司ですが、部下は残業代の有無が関心事のよう・・・
部下を動かすため(片付けの意識改革のためにも)、まずは労働時間マネジメントの知識を押さえておこうと思う上司なのでした。
そこで今回は、仕事が終わったあとの、翌日に向けた仕事のダンドリは労働時間としてカウントするのか、詳しく確認していきたいと思います。
制服通勤を禁止するとき注意したい労働時間マネジメント

3月も半ばを過ぎ、街中ではスプリングコート姿をよく見かけます。
個人的には、朝晩の寒さに冬物のコートが活躍中ですが・・・
さてコートといえば、「コートの下に制服を着ていくので、コートの季節は一本遅くの電車で通勤できる」という話を聞いたことがあります。
以前、この制服通勤について人事部の管理職の方からご質問をいただきました。
「会社に着たら仕事をする、仕事が終わったらダラダラ居残っていないで帰る。オンとオフをしっかり切り替えるため、制服通勤を禁止しようと考えています。マネジメント上で注意する点はありますか?」
制服での通勤を認めないとなると、当然会社で制服に着替えることになりますが、問題となるのは、会社で制服に着替える更衣時間をどう考えるかです。
今回は、この更衣時間を労働時間にカウントするのか、しないのかについてみていきたいと思います。
仕事の途中で歯医者に行ったらその日の労働時間はどうなる?

とある職場のAさん、今日は朝から少し落ち着きがありません。どうやら、放置していた親知らずがズキンズキン痛むようです。
パソコンに向かうも時間を追うごとに痛みが強くなり、仕事はおろか、居ても立っても居られなくなりました。
そこで上司と同僚に事情を話して許可をもらい、仕事を抜け出して歯医者さんに向かうことにしました。
歯医者さんから戻ってきたAさん、応急処置をほどこしてもらって落ち着きを取り戻したようです。
「歯医者さんに行った分の仕事の遅れを取り戻すゾ!('ω')ノ」・・・張り切って終業時刻後も仕事に取り組む様子です。
このように私用外出から戻ったあとで残業した場合、1日の労働時間としてはどのようにカウントするとよいのでしょうか。今回はこの件について、詳しく確認していきましょう。
前乗り出張、終業後の移動は残業代の対象になる?

今日から通常モードで仕事開始。さっそくエンジンをかけて仕事に取り掛かるも、夕方近くに地方の営業所から緊急トラブル発生の報告が入った。適切に対応するため現地入りしなくてはならないようだ。現地で朝イチから対応にあたるには、前日入りが必要だ。担当者には定時後に新幹線で現地へ向かってもらうしかない・・・
**
思いがけない緊急事態が発生、ピンチをチャンスに変えるためにも素早い対応が必要です。そこで年明け早々、担当者には前乗り出張のため終業時刻後に新幹線で現地へ向かってもらうことにしました。
さて法律上は、終業時刻後の出張旅行は労働時間にカウントされ、また残業代の対象となるのでしょうか?
終業時刻後に新幹線で遠方に向かう社員の状況を思うと、経営者や上司の方は心苦しいかもしれませんが、詳しく確認していきたいと思います。
労働時間の管理はタイムカードで行わないとダメですか?

「社員がいつ出勤してきて、またいつ帰ったのか、労働時間を把握して管理するのはタイムカードでしか認められていないのですよね?そういうことが法律で決められているのですよね?」
会社には、社員がどのくらい働いたのか、労働時間を把握する義務があります。
そのため会社の労働時間を把握する義務について、冒頭のようなギモンをお持ちの人事担当者、管理職の方は少なくないようです。
・・・ですが、実は、ちょっとした誤解もあるようです。
そこで今回は、労働時間の把握や管理はタイムカードでしか行ってはダメなのか、詳しく確認していきたいと思います。
残業の自己申告制をうまくいかせるコツ

「社員に働く時間の長さを自覚してほしいから、残業は自己申告制にしようか。でも法律的にいいのかな?法律的にかなった方法は??」
ホワイトカラーの仕事は、工場でモノづくりをする仕事とは違って、その成果が必ずしも時間に比例するものではありません。工場労働をベースとした労働時間の厳格な管理になじまないという性質があります。
そのためホワイトカラーの職場では、残業時間の管理について「自己申告制」をとる場合もありますが、冒頭のようにギモンもあるでしょう。
そこで今回は、次の2点に焦点をあてて残業の自己申告制について詳しく確認していきたいと思います。
- 残業の自己申告制は有効なものか?
- 自己申告制をスムーズに運用させるには?
振替休日は社員の指定で個別に取ってもいいですか?

来年のGWは10連休となる見通しで、ニュースなどで話題になっています。1か月の3分の1がお休みになるのはインパクトがありますね。
休日といえば、振替休日にまつわる質問をとてもよくいただきます。ご質問で多いトピックには、
- 振替休日をいつにするかを社員が指定してもいいのか?
- 振替休日は会社一斉にとらないといけないのか?
といったものがあります。
前述のとおり、来年のGWは10連休となるなら、たとえ随分前から仕事の段取りをつけていたとしても、突発的な何らかの事情で社員が出勤せざるを得ないこともあるかもしれませんよね。
そんなときにはどのように対応するとよいのでしょうか。そこで今回は、上記の2点について確認していきたいと思います。
徹夜で現場対応にあたるとき、労働時間をどうカウントする?

台風や大雪という悪天候時には、事業を継続させるための現場での対応が必要です。突発的な災害の復旧支援の場合だけでなく、サーバー攻撃でのシステムダウンへの対応や大規模リコールなどの場合も同じです。
事前に想定できない事象の発生時には緊急対応の業務が増え、刻々と変わる状況のもと調査や情報伝達が求められます。業務の停滞が許されない状況では夜通しで作業を行わなければならないこともあるでしょう。
徹夜で現場対応にあたらなければならないとき、勤怠管理において労働時間をどうカウントすればいいのか?と迷われるかもしれません。
徹夜での継続勤務については、次の2パターンに分けて考えるとわかりやすいので、詳しく確認していきたいと思います。
- 平日の朝から晩まで作業が続き、なおも翌日の始業開始時にまで及んだとき
- 前日の作業が長引いて翌日の法定休日に及んだとき
会社が副業の勤務日数や労働時間を制限するのはダメですか?

「社員の健康が心配で、副業での勤務日数や労働時間をある程度制限したり、仕事内容や勤務先を届けてもらいたいのですが、法的に問題はありますか?」
社員は、基本的には、労働時間以外のプライベート時間を自由に使うことができます。そのため最近では、裁判例をみても副業自体を一方的に禁止することはできないとの考え方が主流です。
とはいえ、際限なく副業を認めてしまうと、疲労の蓄積によるミスの多発や(競合企業での副業による)自社の機密情報の漏えいが懸念されます。
そこで今回は、副業にまつわる懸念事項2点について、詳しく確認していきたいと思います。
- 副業に勤務日数や労働時間の制約を設けてもいいのか
- 副業の仕事内容などを会社に届け出てもらってもいいのか
仕事を抱え込むリーダーの悩みー残業命令を拒否する部下

【チームリーダーの主張と悩み】
会社から早く帰りなさい、とよく注意される。でも、やらなくてはいけない仕事があるのに帰れない。チームメンバーに残業をお願いしても、いい顔をしてくれない。早く帰らないといけないムードなので強くも言えずリーダーとして手一杯・・・うちの会社は所定労働時間が7時間なので、1時間残業しても他の企業では普通のこと。それなのに残業を嫌がるなんて、社会人としてどうかと思う・・・
**
働き方改革で長時間労働の見直し策が世間的に求められているため、仕事の采配、スケジュールのやりくり、残業を嫌がるメンバーに頭を悩ますチームリーダー。
そこで今回は、いわゆる法内残業の場合で残業命令を拒否することに正当性はあるのかどうかについて、詳しく確認していきたいと思います。
残業前の腹ごしらえは労働時間になるのか休憩時間か?

朝から夕方までずっと仕事に没頭、気がつけばもう終業時刻。でも納期のために残業だ。ああ、でも小腹がすいて仕事に集中できない。コンビニでパンでも買って腹ごしらえしよう・・・
**
残業前に小腹を満たしたい気持ちはよくわかりますが、おいしいおやつをつまむとホッとして、ついダラダラしがち・・・それで帰る時間が遅くなるのなら本末転倒です。
また、上司や人事担当の方にしてはおやつタイムまで労働時間としてカウントするのか、それとも休憩時間として残業申請の時間から差し引くべきなのか、対応に困ることもあるかもしれません。
仕事にメリハリをつけるためにも、労働時間なのか休憩時間なのか、線引きをきちんとしておきたいですよね。
そこで今回は、残業前の夕食時間は労働時間なのか休憩時間なのか、線引きはどうすればいいのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
仕事が終わってからの健康診断は残業代の対象?

仕事の都合がつかなくて時間外に健康診断を受けたい、という社員がいる。これは時間外労働として残業代の対象となるのかな?残業代が出るなら、みんな時間外に健康診断を受けたいと言い出しそう・・・(-.-)
**
社員の健康維持のために、会社には一定の健康診断を行う法律上の義務があるので、このようなジレンマを抱える担当者さんもいらっしゃるようです。
(長い梅雨の期間が明けたと思いきや、今度はジリジリ照り付けるような猛暑で、会社としてみなさんの健康状態が心配なのに・・・)
労働時間とは、社員が会社の指揮命令下のもとで仕事を行う、拘束時間のことですが、そもそも健康診断の時間は労働時間なのでしょうか?
そこで今回は、健康診断は労働時間にカウントされて、時間外の健診は残業代の対象となるのかについて詳しく確認していきたいと思います。
現場へ直行するときどこまで通勤、どこから労働時間?

「作業現場が遠方の場合、いったん会社に出勤してもらうのもアレなんで、直接自宅から作業現場に行ってもらって直帰するような場合も多い。現場へ直行直帰のとき、労働時間はどうカウントするべき?」
普通ならいったんいつもの職場に出勤して、上司の業務命令によって目的地へ出発します。
ただ、時間的なロスを省き効率的に仕事を進めために、自宅から上司の指示による目的地へ直接出かけるようなとき(またそこから自宅へ直帰するようなとき)もあるでしょう。
とはいえ、どこまでが通勤時間でどこから労働時間なのかを考えると、判断に迷うところではないでしょうか。
そこで今回は次のような場合、「どこまでが通勤でどこから労働時間なのか?」について詳しくみていきたいと思います。
- 途中で集合して目的地へ行くとき
- 作業現場へ直行直帰するとき
朝から応援勤務で他店舗へ行くのは出張?それとも通勤?
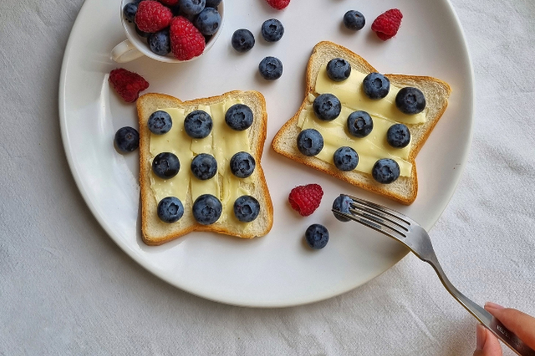
複数の店舗や事業所を運営している企業では、人手が足りないときや、緊急事態が発生したときには、臨時の対応を行わなければなりません。
社員にいつもの勤務先とは異なる場所へ応援勤務を命じて、駆けつけてもらわないといけないこともあると思います。
トラブル等ではなくても、遠隔地の現場へ作業に行く必要のある企業では、同様のシチュエーションが考えられるでしょう。
そんないつもと違う場所へ直接出勤するとき、そこまでの往復の移動時間は、「通勤時間」にあたるのか、「出張としての労働時間」にあたるのか、という質問をいただくことがあります。
特に「いつもと違う場所」が遠方にあると、社員さんに通常よりも早起きして自宅から出かけてもらわなければなりません。
そこで、どのように勤怠管理をして、どんな説明をすれば社員に納得してもらえるのか・・・と悩まれているようです。
そこで今回は、朝に自宅から直接、他の店舗や事業場へ応援勤務に行くのは出張にあたるのか、それとも通勤時間にあたるのか、詳しくみていきたいと思います。
研修・セミナーが労働時間になるとき、ならないとき

「これから社員には、スキルアップのために自社の勉強会だけでなく、外部で実施されている講座や研修にどんどん参加してもらいたい。ただ、講座を受講している時間は労働時間にカウントされますか?」
社員が参加する研修や講習は、どんな内容のものでも労働時間になるのか、その判断のポイントを知りたい、とのご相談をよくいただきます。
また、終業時間後に実施されるセミナーであれば、残業代の支払いの有無など勤怠管理で頭を悩ませる、とのこと。
そこで今回は、「労働時間になるかどうか判断のポイント」下記の2点について詳しく確認していきたいと思います。
- セミナーの内容(担当業務に関連するものなのか?)
- 業務命令か否か(自由任意参加なのか?)
どのくらいの役職につくと管理職扱いになりますか

A社では課長は管理職扱いで残業手当の支給がなくなるそうだが、B社では主任で管理職の扱いらしい。管理職にあたる・あたらないの基準がわからない。どのくらいのポジションで管理職扱いになるのかな?
**
会社組織で一定の管理監督的地位にある社員については、労働時間や休日・休憩等の適用が除外されるので、会社に残業代(割増賃金)の支払い義務はありません。そのため、管理職扱いになるかどうかのボーダーラインはみなさんの関心事ではないでしょうか。
そこで今回は、コンサルティングでよくご質問をいただく次の2点について詳しく確認していきたいと思います。
- 労働時間等が適用除外される管理職とは?
- 管理職にあたる、あたらない、の具体的な判断基準
労働時間の効率化で残業代が少なくなるのは不利益変更?
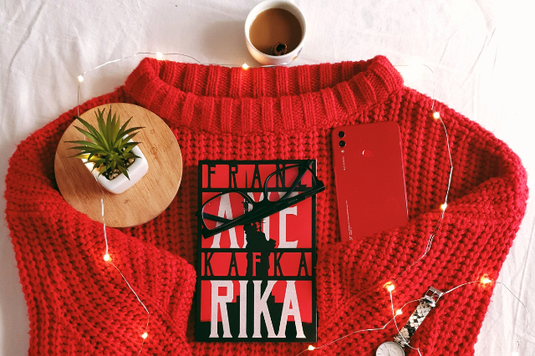
「変形労働時間制の導入で残業時間が減ると、その分残業代もカットされる。残業代が減るのは労働条件の不利益変更にあたるのかな?」
(メーカー勤務、人事担当者のギモン)
会社における労働時間制度とは、労働時間の配分を決める仕組みのこと。繁忙に応じて年間の労働時間の配分をあらかじめ決めておく変形労働時間制や、仕事の進捗に応じて社員が出勤時間を選ぶフレックスタイム制などの導入で効率良く働くことができる。
それらの効果によって残業時間が減少すると、それに伴って残業代も減少するのは事実です。
とはいえ、社員にとっては自分の生活のために使える時間が増えるので、生活と仕事の両立がしやすくなるという面もあり、労働時間(残業時間)の効率化は、社員にとって悪い話ばかりではなさそうですが・・・
そこで今回は、労働時間の合理化が進むことで、残業代が減少することは不利益変更にあたるのかについて詳しく確認していきたいと思います。
国民の祝日に社員を出勤させてもいいですか?

「春分の日も社員に出勤してもらわないと、年度末の納期に間に合いません。でも祝日を休日にしないで、出勤させてもいいのですか?」
春分の日を過ぎて、ようやく春らしい陽気になりました。さて春分の日は国民の祝日のひとつですが、このようなご相談をいただいたことがあります。
祝日の取り扱いをどうすればいいのか、判断に迷うケースは実際によくあるかもしれません。
そこで今回は、祝日、また似たケースとして会社独自の特別休日(創立記念日など)の取り扱いについて詳しく確認していきたいと思います。
- 国民の祝日を必ず休日にしないといけない?
- 国民の祝日に出勤させると割増賃金はどうなる?
- 会社独自の特別休日(創立記念日など)に届出は必要か?
間もなくの(少し気が早い?)ゴールデンウィークには、国民の祝日が続きますから、この機会にぜひチェックしておきましょう(*´ω`)
休日の接待ゴルフは休日労働?単なるプレー?

「ゴルフコンペ開催の費用は、会社の交際費として会社側が負担している。だからコンペが休日に行われた場合、休日労働になるのでは?」
春らしい暖かな陽気に誘われて、お出掛け気分も高まります。そんな春はゴルフのベストシーズンなので、休日に取引先との接待ゴルフ大会が開催されることもあるかもしれません。
日本の企業社会において、いわゆる接待ゴルフは取引先との関係性をスムーズにする社交として慣行になっていて、「接待ゴルフは仕事の一環」との意識があるため冒頭のようなご相談をいただきます。
そこで今回は、休日に開催される接待ゴルフ大会に参加するとき、労働時間にカウントされるのかどうかについてみていきましょう。
休日の社内行事が労働時間になる人、ならない人

「社員親睦のイベントを全員参加としたいのですが、休日に開催すると参加した人は休日労働扱いになりますか?」
春の兆しが感じられる今日この頃、社員旅行など社内イベントを計画されるエピソードを、お伺いすることがあります。
平日は仕事もあるので、社内行事を休日に開催せざるを得ないこともあるため、冒頭のようなご相談をいただきます。
問題は、社内行事は労働時間としてカウントされるのか?ということです。そこで今回は、その判断判断基準となる下記の3点について詳しく確認していきたいと思います。
- 仕事と認められるものなのか
- 単に参加するだけなのか
- 準備、運営、後始末などを担当するのか
終業後のミーティングや飲みニケーションは労働時間?

「仕事終わりの打ち合わせって、労働時間にカウントするべきなのかな?でもお菓子をつまみながらのまったりモードだしなあ・・・」
「反省会」「懇談会」「会議」などの名称で、社員たちが職場に居残って議論する、といったことは日常的にあるあるだと思います。
とはいえ労働時間マネジメントを考えるとき、労働時間なの?(←お菓子も食べているし)と判断に迷うこともあるのではないでしょうか。
また、こういった「会議」のあとで懇親会が開かれることもあるでしょうが、これは労働時間になるのか?得意先の接待の場合とは違うのか?・・・考え出すと「沼」にハマってしまいそうです。
そこで今回は、次の2点について詳しく確認していきたいと思います。
- 終業後の打ち合わせやミーティングは労働時間になるのか?
- 接待や宴会をはじめ終業後のいわゆる飲みニケーションは労働時間になるのか?
社員が在宅勤務を選んだときの労働時間マネジメント

記録的な大雪から、列車や車の立ち往生が各地でみられます。鉄道ダイヤが乱れると、通勤ラッシュに影響が出ることもあるかもしれません。
交通機関の混雑で通勤への支障が予想されるとき、オフィスへ出勤せずに、自宅で仕事をする「在宅勤務」の制度があるといい、と考える企業も増えてきているようです。
在宅勤務をはじめとするテレワークを導入するには、セキュリティや労務管理の面でハードルが高いと思われることも多いようですが、働き方改革推進の流れを受けて多方面から対策が進むかもしれません。
何より、大雪や台風のとき、また家庭や業務の事情など、都合に応じて勤務先へ行かずに働ける選択ができれば、時間を有効活用でき、非常時でも仕事を継続できるなど、社員と企業の双方に大きなメリットがあります。
そこで今回は、テレワークにおける在宅勤務の労務管理、特に頭を悩ませがちな労働時間マネジメントについて、詳しくみていきたいと思います。
出張中はどこまで労働時間にカウントするか?

年明け早々、取引先へ新年のあいさつ回りを兼ねて、遠方へ出張に出かける機会も多いことでしょう。
出張期間は会社の業務命令に基づくものであっても、法律上の労働時間という観点からみると「拘束時間=労働時間」とは一概にいえません。
オフィスのように上司が直接的に労働時間マネジメントをできる状況になく、会社の業務命令による拘束時間とはいえ抽象的なものだからです。たとえば新幹線の座席で小説を読んだり、ウトウト居眠りをしたり、駅弁を食べたりすることはごくフツーの状況です。
とはいえ、これらは果たして労働時間と言えるのだろうか・・・と出張中の勤怠管理や残業計算で「どこまでが労働時間?」と頭を悩ませることも多いようです。
そこで今回は、出張にまつわる次の3点について詳しく確認していきたいと思います。
- 出張の往復で新幹線や飛行機に乗っている時間は、労働時間なのか?
- 出張期間中の休日はどう対応すればいいのか?
- 休日に出張の場合は休日労働になるのか?
残業命令VS社員のプライベート、優先されるのはどっち?

年末年始のスケジュールがタイトで、仕事がびっちり詰まったメーカーのA社さん。そこへ得意先から緊急の注文が入りました。残業で対応すれば、なんとか先方の要望に応えられそうです。
課長がある社員に残業を指示したところ、「仕事帰りに空港で家族と待ち合わせして、今夜の便で海外旅行に行くので残業は無理です」とのこと。「お先に失礼します!」と終業時刻に笑顔で退社していきました。
A社の就業規則には「残業命令には正当な理由なく拒否することはできない」旨が規定されていますから、「仕事を残してさっさと帰るなんて、懲戒処分にあたるんじゃないのか?!!!」と、緊急の仕事を前に課長は渋い顔です。
**
こんなとき、残業命令と社員の私用はどちらが優先されるのでしょうか。また社員の主張する「海外旅行」は、就業規則に規定される「正当な理由」にあたり、残業を拒否できるのでしょうか。それとも懲戒処分の対象となるのでしょうか。次から詳しく見ていきましょう。
労働時間マネジメントは上司の責任

部下が毎晩遅くまでやっているようだが、時間がかかるのは本人の力不足だろう。本人の勝手でやっているのに、上司がどこまで面倒みないといけないんだ?
**
上司と部下の経験の差から、作業に要する労力の見積もりにギャップが生まれがちです。
新入社員の過労自殺に端を発した電通の違法残業事件は、2017年10月6日、罰金50万円の有罪判決となりました。判決では、長時間労働が常態化していたにも関わらず、抜本的な対策を講じないで、労働時間の削減を現場まかせにしていたことが指摘されています。
「残業管理は上司の責任」との見方が明確に示されたともいえますし、また近年では、上司の指示に従わずに残業していた社員への会社の対応義務が問われる裁判例もみられます。
そこで今回は、社員(部下)の残業にかかる上司の責任について、詳しく確認していきたいと思います。
タイムレコーダーで時間管理するときの留意点

会社には、社員の労働時間をマネジメントする責任があるので、タイムレコーダーの取扱いについてたびたびご相談をいただきます。
多くの会社の就業規則には「始業時刻9時、終業時刻18時、うち休憩時間12時から13時の1時間」などと規定されていても、9時に職場のどこにいなければ遅刻扱いになる、とまでは定められていません。
具体的な規定がないからといって、毎日の勤怠管理で大きな混乱が起きているかといえば特にそんなこともなく、ごく普通に出勤が行われていると思います。
とはいえ、毎月の給料計算でタイムカードをチェックしていると「これは遅刻になるのか、ならないのか?」など、いざ真剣に考え始めると判断に迷うことも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、タイムレコーダーの打刻と労働時間のカウント方法について詳しく確認していきたいと思います。
接待や夜間対応は労働時間になるか?

「こんな時間にお客さんの対応・・・これって労働時間になるの?」
顧客が商品開発や人材育成へ与える影響は大きいため、顧客満足に価値を置いている企業ほどよく抱える悩みとは、ズバリ顧客対応にまつわる労働時間マネジメントです。
いまやオンライン、オフライン問わず、日常業務のなかで顧客と直接やりとりを交わす機会は多くあるからです。
顧客との良好な関係性を維持するために、「定期的なご接待」や「お問合せには即対応」が会社のモットーだとしても、上司の立場としては労働時間マネジメントは頭を悩ませる問題でしょう。
そこで今回は、顧客対応にまつわる「あるあるお悩み」の下記2点について、詳しく確認していきたいと思います。
- 接待での飲食や宴会はどう考える?
- 携帯電話を常時ONにさせておくのはOK?
オンライン研修の自宅学習は労働時間になるか

社員の能力を効果的に高めるには、経験を積ませながら上司のフィードバックや研修の機会を設けることです。
終身雇用制が前提の時代には、経験と教育がセットの人材育成プログラムとしてOJTが行われていましたが、今は指導の立場の人材が不足していて、OJTがやりたくてもできない職場もあるようです。
また働き手のなかで有期雇用者の割合が増えてきていますが、一般的な無期雇用者と比べると短期間で戦力化する必要があります。とはいえお店のように、メンバーのほとんどがシフト制の有期雇用者という状況で、集合研修を行うことが難しい場合もあるかもしれません。
そこで最近は、オンライン学習(eラーニング)を導入する企業も増えてきているようです。オンライン学習は、全員が同じ時間、同じ場所にいる必要がなく、研修施設での講義や討議がない自宅学習がメインの学習スタイルですが、会社として気にかかるのは労働時間マネジメントではないでしょうか。
そこで今回は、オンライン講座の自宅学習(オンライン研修)が労働時間にカウントされるのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
労働時間にカウントするとき、しないとき

たとえばお店に「営業中」の札を掲げていても、常にお客さんが来るとは限りません。けれど「営業中」としているだけに、接客自体はしていなくても、こまごまとした準備や店番などは必要です。お客さんがいないと、経営者としては「仕事をやっていない」という感覚になってしまいがちですが、これが社員ではどうでしょうか?
店番などはたしかに立っているだけかもしれませんが、休憩している状態でもありません。このような時間のことを「手待ち時間」といい、会社の指揮命令下に置かれている状態、つまり労働から完全に解放されていないとの見解から、労働時間になります。
このように労働時間が、必ずしも実際の作業時間と一致しないことも少なくありません。そのため「こういった場合は労働時間としてカウントしなければいけないのか?」とご相談をいただくこともよくあります。
そこで今回は、労働時間にカウントすべきなのか判断に迷いがちな「あるある事例」をもとに、具体的に確認していきたいと思います。
残業を減らす3つの視点と実践ポイント

「仕事の処理が速い優秀な社員なので、つい仕事を頼んでしまいます」
「この人はどんな仕事にもとても時間がかかります」
「この人しかできない仕事をやってもらっています」
残業時間の記録を拝見すると、他の人よりも突出して残業時間が多い人がいる場合があります。前記のような理由からそうなるのだそうです。
残業時間を削減するのに大切なのは、次の3つの視点です。
- できる人に仕事が偏っていないか
- 優先順位をたてず無計画に仕事していないか
- チームで仕事が共有できているか
まずはこの3つの視点から、社員の残業状況がどうなっているのか、実態を把握することが大切です。
そこで今回は、この3つの視点から残業の削減には具体的にどうすればいいのか、実践ポイントを確認していきたいと思います。
残業を減らす特効薬はありますか?

うちの部の残業が全然減らない。人事部から警告がくるし、たしかに残業代も電気代もバカにならないよなあ。・・・残業する社員にはペナルティーを与える、ということにすれば残業しなくなるかな?
**
残業削減に頭を悩ます部長さんです。ビジネスを行う上でコスト感覚は大事とはいえ、それが強すぎると、手早く問題解決ができる手段を求めて「残業削減に効く特効薬があるはず」と考えてしまいがち。
年末の納期など、期間限定で残業が続くことはもちろんあるでしょう。ですが、それが恒常的になっているのはどうでしょうか?
「残業禁止」やそれに伴う「ペナルティー」によって、一瞬にして魔法のように解決する問題ではないかもしれません。
そこで今回は、社員が残業を手放すのに効果的な残業削減の取り組みについて詳しく確認していきたいと思います。
社外研修でやってはいけない扱いとは

「今回の社外研修は終日だけど、出張扱いにしていいのかな?もし休日にやるんだったら、休日労働扱いになるのかな?」
これは、社外研修にまつわるよくある疑問です。社外研修に出席する予定の社員さんから質問があって即答できなかった・・・といった人事担当者のお悩みもよくお聞きします。
社外研修における勤怠の扱いを誤ったり、社員からの疑問にあやふやな回答をしてしまっては、社外研修に対する不信感を社員に与えかねないからです。せっかくの社外研修が逆効果になっては勿体ないですよね。
そこで今回は、社外研修の効果を削がないよう(←会社がやってはいけない扱い)、参加した場合の勤怠関係について詳しく確認していきたいと思います。
休日の研修は出勤日としてカウントするか

「社員には仕事に必要な資格を取得してほしいので積極的に研修を受けてもらいたいが、研修の実施が休日ならどうなるんだろう?」
新人を職場に配置しても、すぐ能力を発揮して会社に貢献する人材になるわけではないので、会社としては社員のやる気を引き出して育てることが必要です。
社員のスキルアップを応援したい会社としては、社員に不利益のないようにするには「研修を休日に行った場合に休日出勤になるのか?」と判断に迷われることもあるようです。
そこで今回は、休日の研修にまつわる勤怠関係の処理について詳しく確認していきたいと思います。
残業禁止命令の効果を高めるには

「残業は当たり前」との意識が職場にあって、みんな毎日遅くまで頑張っている。それはありがたいけれど、社員の健康が心配だ。また、残業代の高騰、深夜までのオフィスの光熱水費アップも頭が痛い・・・
**
残業問題、みなさんの会社ではいかがでしょうか?
社員の健康管理とコスト増対策のため、定刻になると強制消灯して退社を命じる会社があります。
とはいえ、「強制的に帰らされるなんて横暴だ(もう仕事のことなんて知りませんよ)」と社員から抗議があがると、痛いところを突かれて対応に困ることもあるかもしれません。
そこで今回は、残業禁止命令の効果や法律的に問題があるのかどうかについて詳しく確認していきたいと思います。
