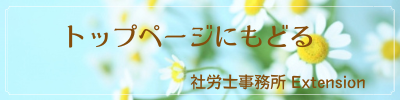女性社員「1日2回の育児時間を連続してとれますか?」
上司「?!何それ、そんな制度うちの会社にあるの?」
**
「育児時間」とは、1歳未満の子どもを育てる女性社員が、昼休みなどの休憩時間のほかに1日2回それぞれ少なくとも30分、授乳など育児のための時間を会社に請求できる、という労基法上の制度です。
かつては結婚・出産で退職する女性社員は少なくなかったため、育児時間の存在自体を知らずにいた、というケースは多いようです。
では、冒頭のような質問を受けたとき、「1日2回を連続してとるのはダメだ」「この時間帯にとってはダメだ」など制限を会社が設けることはできるのでしょうか。
今回は、意外と知らない会社の育児時間の与え方について詳しく確認していきたいと思います。
育児時間とは

蝶育児時間は、「生後1年未満の子どもを育てるには、授乳やその他いろいろな世話のための時間が必要だ。休憩時間とは別にそのための時間を確保して、作業から離脱できる余裕を与えよう」との趣旨のもと、労働基準法に定められました。
したがって、会社は育児時間中の女性社員に仕事をやるよう命令してはダメです。
なお、育児時間はその女性社員の請求によって与えられるものであり、(1歳未満の子どもを育てる女性社員が)請求しない場合、育児時間を与えないということには差し支えありません。
また、育児時間を有給とする法的な義務はないので、有給にするか無給にするかは会社の自由です。
さらに「1日2回」というのは、1日の労働時間を8時間とする通常の業態を想定しているため、1日の労働時間が4時間以内であるようなパートタイマーなどの場合には、1日1回の育児時間をもって足りるとされています。
育児時間の与え方

育児時間は1回あたり「30分」ですので、この30分のなかに仕事場から託児所までの往復時間も含んでも、法律上の問題はありません。ただし、往復時間を除いた実質的な時間を与えることが望ましいとされています。
では、女性社員の育児時間の請求に対して、会社が「1日2回を連続してとるのはダメだ」「この時間帯はとってはダメだ」など制限してもいいのでしょうか。
法律では育児時間をいつ与えるかについて定められておらず、会社と本人(女性社員)の当事者間にまかせられています。午前と午後で各1回ずつ与える、というのが一般的なケースではないでしょうか。
よって、どの時間帯に女性社員が請求しても、会社はこれを拒否できないと考えられます。また、休憩時間のように労働時間の途中に与える必要はないため、たとえば、勤務時間の始めまたは終わりに請求があった場合にも、特別な理由がなければ与えなければなりません。
(つまり、女性社員からすると、30分遅く出勤して30分早く退勤する、という形態での取得も可能ということです。)
同じく、「1日2回の育児時間を(一括で)連続してとること」についても、法律で制限しているわけではありませんので、特別な理由なく拒むことはできないと考えられます。
**
仕事はチームでやるものなので業務に支障があるときは、会社は本人にその状況を説明して理解を求めるなど、取得時間帯の調整が必要なのは言うまでもありません。
そこで、仕事と育児の両立を実現するためにはどのような配慮やサポートが必要かをすり合わせるため、本人の個別事情を確認することを忘れずにいたいですね。
もし、本人が仕事と育児で混乱しているようなら、まずは話をじっくり聞いてみることが必要かもしれません。
心に余裕がないと、物事を前向きに考えられませんものね。


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事