人事異動で社員がメンタル不調、会社は責任を問われるの?

当社では就業規則に基づいて春に人事異動を行っているが、対象者のAさんがメンタル不調を訴えてきた。もし、その原因が人事異動にあるとしたら、人事異動を命令した会社は責任を問われることになるの?
**
春に人事異動となった社員からメンタル不調の相談を受け、社員の配置転換と会社の安全配慮義務について考えを巡らせる人事担当者さんです。
社員の就業場所や担当業務を変更することは、会社の人事権として認められていますが(もちろん無制限に許されるわけではなく、合理性がなく、権限の濫用にあたる命令は無効になります)、このような場合どのように考えるといいのでしょうか。
そこで今回は、配置転換と安全配慮義務の関係について、詳しく確認していきたいと思います。
パートの勤務時間がバラバラで就業規則にどう定める?

人手不足なので、子育て中の主婦の人にもパートでいいから来てほしい。育児や家事に充てる時間を確保してもらうためにも、勤務時間の希望を聞いて柔軟に対応したい。とはいえ、パートさんの数だけ勤務時間がバラバラになるなら、就業規則にどう定めたらいいの?
**
主婦層にも求人に応募してもらいたいので、家庭や子育てとの両立が無理なくできるようにと考える店長さんです。
ですが、たとえばパート社員を10人採用したとして、10通りの勤務時間を就業規則に書くのか?これからさらにパート社員が増えたとして、その都度勤務時間を書き足さないといけないの・・・?勤務時間の章だけでものすごいボリュームになってしまう・・・と悩んでいます。
そこで今回は、パート社員によって始業・終業時刻が異なる場合の就業規則の定め方について、詳しく確認していきたいと思います。
営利目的で社員を出向させるのは適法ですか

「自社の社員を取引先に出向させて業務を行い、それを会社の売上げとして計上しようと思います」
ビジネスプランに関する勉強会に参加した、人事部のBさんです。参加者のビジネスプラン発表を聞いていて、ふとギモンを覚えます。「それって、出向じゃなくて人材派遣にあたらない?」
出向とは、第三者の会社に出向元の人事異動により派遣されて第三者(出向先)のために働くものですが、見た目としては労働者派遣(人材派遣)と似ています。
ですが、出向と労働者派遣とは根本的に違うもの。
そこで今回は、出向が「業」として行われる場合、労働者派遣に該当するのかどうか、詳しく確認していきたいと思います。
営業社員にスマホを持たせているとみなし労働時間の対象外?

営業社員には外回りがつきもの。取引先から会社に電話があったとき、担当の営業社員が外回りでいつも不在なのはよくないので、社用携帯を持たせている。・・・とはいえ、社用携帯に会社からすぐ連絡がつくわけだから、みなし労働時間制の対象外になってしまわないのかな?
**
部下に社用携帯を所持させていることで、みなし労働時間制が適用されないのでは?と心配する営業課長さんです。
会社の具体的な指揮監督が及んでいる場合には、労働時間をきちんとカウントできるので、事業場外労働のみなし労働時間制は適用されないからです。
とはいえ、現代社会ではスマホ(携帯電話)が一般的に普及しているので、社用携帯を所持させているからといって、業場外労働のみなし労働時間制が適用されないのでは無理があります。
そこで今回は、社員に携帯電話を持たせているとみなし労働時間にならないのか、詳しく確認していきたいと思います。
解雇回避のための出向を拒否する社員に会社はどうする?

経営状況の立て直しのため、人員削減の必要性が出てきた。整理解雇を避けるため、関係会社へ出向させることにしたが、なかには拒否する社員も・・・どうすればいい?
**
不況等の経営上の理由で人員整理の必要が生じた場合、会社が整理解雇を回避するため余剰人員を他の支店に配置転換したり、子会社や関係会社に出向させることは一般的によくあることです。
そんな解雇回避策である配転や出向を拒否する社員に対して、会社は解雇することが可能なのかが問題として浮上します。カギは、会社に配転命令権・出向命令権があるかどうかです。
そこで今回は、整理解雇を回避するための配転や出向を拒否する社員への対応について、詳しく確認していきたいと思います。
派遣先が派遣社員に副業禁止を命令できるの?

派遣社員のAさん、うちの仕事が終わったら他社でも働いているそうだ。今のところ、仕事に支障はないようだけど、うちの社員には就業規則で原則副業を禁止しているし、他社での仕事を辞めてもらえるようにはできないだろうか?
**
他社でのアルバイトを辞めて、当社の仕事に集中してほしいと思う、派遣社員が所属する部署の上司です。
就業規則に原則副業を禁止する旨が定めてあるとはいえ、派遣社員に派遣先の就業規則が適用されるのでしょうか。
そこで今回は、派遣先が派遣社員に対して他社でのアルバイトを辞めるように命令できるのか、詳しく確認していきたいと思います。
派遣社員の安全配慮義務を負うのはどこなの?
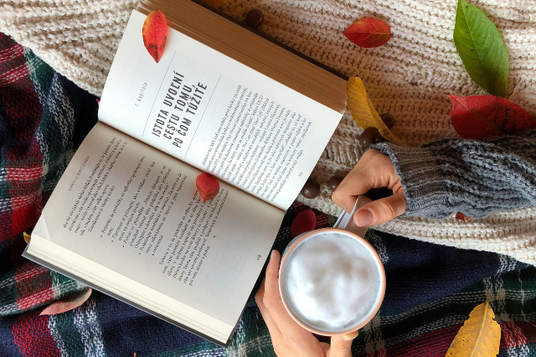
「職場でいっしょに働いてもらっている派遣社員さんは、派遣元の会社で健康診断を受けるから、来月の健康診断をうちの会社で受ける人は〇人。・・・じゃあ、うちには派遣社員さんの安全配慮義務はないってことなの?」
来月に実施する一般健康診断の準備に忙しい、人事部員のBさんです。「健康診断→働く人の健康→会社の安全配慮義務」と連想が働き、普段いっしょに働く派遣社員さんの安全配慮義務についてギモンが浮かんだのでした。
労働者派遣は雇用と使用が分離する形態なので、人材マネジメントにおいてややこしく感じる場面もあるかもしれません。
そこで今回は、派遣社員の安全配慮義務を派遣先と派遣元のどちらが負うのか、詳しく確認していきたいと思います。
出向社員の安全配慮義務があるのは出向先と出向元のどっち?

会社には、社員の生命、身体等を危険から保護するよう配慮する義務がある(安全配慮義務)。でもうちの職場ではなく他社で働いている出向社員はどうなるの?だって物理的に離れていて、日頃どんな様子で働いているのかわからないし・・・
**
出向社員にまつわる安全配慮義務について、ふとギモンに思う人事担当者さんです。
出向(在籍出向)は、出向元の社員としての地位を持ったまま出向先で働かせるものなので、出向元と出向先の両方で二重の労働関係が成立します。
出向元企業の社員であると同時に、出向先の社員でもある出向社員の安全配慮義務について、どのように考えるとよいのでしょうか。
そこで今回は、出向先と出向元のどちらが出向社員の安全配慮義務を負うのか、詳しく確認していきたいと思います。
役員出向で会社が気を付けるべきこととは?

上の方針で、今後のキャリアのため本社勤務のAさんが、関連会社に役員として出向することになったそうだ。初めてのことなので、人事部(会社)として気をつけることはなんだろう?
**
中堅社員のキャリア形成やシニア社員の処遇などを目的として、その社員を子会社や関連会社に役員として出向させるケースがあります。
とはいえ、このような役員出向が人事部員として初めての経験なので、通常の業務命令として役員出向を取り扱ってよいのか、何か特別に会社としてやるべきことはないのか、戸惑う人事部員さんです。
そこで今回は、社員を役員として出向させるときに会社が気を付けるべきことについて、詳しく確認していきたいと思います。
出向命令の正当性はどんなことで判断されるの?

関連会社への出向を「嫌がらせ人事」とか「報復的人事」なんて社員に思わせないために、出向命令の有効要件はきちんと守りたい。・・・でも、出向命令の正当性はどんなことで判断されるのかな?
**
出向社員のモチベーションを下げることのないよう、考えをめぐらす人事課長です。
出向とは、出向社員が出向元企業に在籍したまま、出向先企業でかなり長い期間にわたって出向先企業の仕事に就くことをいいます。
会社が社員に対して出向命令を行うには、その社員の承諾やその他法律面の条件に合った特段の根拠が必要とされています。
そこで今回は、出向命令の正当性はどんな基準で判断されるのか、詳しく確認していきたいと思います。
社員が転籍先で入社を断られたとき会社はどうする?

人件費の削減に迫られる中、できる限りよそで雇用維持してもらえるようサポートしたいので、関連企業や取引先と交渉して、転籍を実施することになった。対象の社員たちに退職金を上乗せ支給して退職してもらったが、そのうちのひとりが転籍先の面接で断られてしまった・・・
**
在籍出向ではなく転籍出向というかたちをとったものの、転籍を予定していた企業から採用を拒否され、対応に戸惑う元の会社の人事担当者さんです。
転籍先での受入れがかなわなかったので、退職金も支払ったものの、元の会社からの退職(労働関係の解消)は認められないことになるのでしょうか。
そこで今回は、転籍先企業と労働関係が成立しなかったときの会社(転籍元)のとるべき対応について詳しく確認していきたいと思います。
海外で現地採用の社員が国内本社へ異動になりました
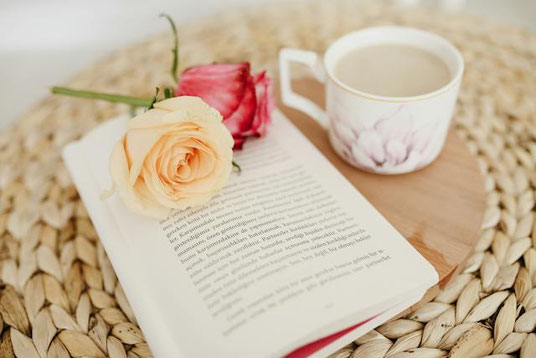
上の方針で、海外支店で現地採用した社員を国内本社に3年間異動させることが決まったそうだ。あとは人事部で対応よろしく、ということだけど、どんなことをすればいいんだろう?
**
海外支店の外国人社員が国内本社へ異動してくることが初めてなので、何から手を付ければいいのか戸惑う人事担当者さんです。
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)で定められている在留資格の範囲内において、日本での活動が認められています。まずは、異動の対象となる外国人社員について、その社員の職歴や学歴から利用できる在留資格があるかを確認しなければなりません。
そこで今回は、海外支店の外国人社員の国内本社への異動で会社がとるべき対応について詳しく確認していきたいと思います。
出向先でのトラブルでも身元保証人は責任を問われるの?

うちの社員に出向先での横領疑いが浮上した。少なくない金額なので、出向先企業はこの出向社員の身元保証人に対して損害賠償を請求するかもしれない。・・・とはいえ出向先でのトラブルであっても、身元保証人は責任を問われるのだろうか?
**
身元保証契約は、社員本人との契約ではなく、身元保証人と会社との契約です。内容は、その社員が会社に損害を与えた場合に身元保証人がその損害を賠償するというものです。
そのため社員を採用する際に、多くの企業では身元保証契約書を求めますが、身元保証人にはどこまで(出向先でのトラブルも?)責任が問われるのでしょうか。
そこで今回は、出向における身元保証人の責任について詳しく確認していきたいと思います。
育児短時間勤務の社員に残業命令を出すのはNG?

うちの部には育児中で短時間勤務の社員がいる。実は今、うちは空前の繁忙期。ありがたいこととはいえ手が全然回らない。短時間勤務の社員にも残業命令を出したいのがホンネだけど、法律的にダメだよなあ・・・(;´Д`) (営業部 課長談)
**
育児・介護休業法では、3歳未満の子を養育する社員で一定の要件を満たす者は、その希望により短時間勤務の適用を受けたり、残業を免除してもらうことができるようにしています。
社員にとっては仕事と育児のバランスが取りやすくなる制度ですが、冒頭の例のように、急な受注量増で対応にてんやわんやの時などマンパワー不足に悩む上司の方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、育児短時間勤務の社員に残業を命じることはできるのか、詳しく確認していきたいと思います。
1名だけの衛生管理者が長期入院で会社はどうする?

「衛生管理者のAさんが長期入院することに(゚Д゚;)療養を含めると半年は出社できないって。衛生管理者がそんなに不在ってマズいよね?すぐに資格なんて取れないし、どうしよう?」
衛生管理者は、安衛法において、業種にかかわらず常時50人以上の社員を雇用する職場(企業単位ではなく支店や工場、営業所などの単位)ごとに選任することが義務付けられています。
社内に衛生管理者はAさんしかいないので、突然の入院で衛生管理者の定期業務も滞ってしまいます。また、こんな状況でもし何かトラブルがあれば、会社に法的な責任が問われる一因になるかもしれません。
そこで今回は、代わりのいない衛生管理者が長期間会社を休む場合に会社がとるべき対応について、詳しく確認していきたいと思います。
育児短時間勤務の社員が年休をとると給与はどうなるの?

Aさんから年休届が出ている・・・あれ、Aさんは育児短時間勤務中だから年休日の給与額はどうなるんだろう?(人事部の新人Bさん談)
**
会社は、3歳未満の子どもを育てる社員が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮する制度(原則として1日6時間)を設けなければなりません(育児・介護休業法23条)。
勤務しなかった期間(時間)について給与を支払わないことは差し支えないとされており、AさんとBさんの会社では短縮時間相当分を控除していますが、年休取得日についてはどうすればいいのか・・・と戸惑うBさんです。
そこで今回は、育児短時間勤務中の年休日の給与についても欠勤控除を行ってもいいのか、詳しく確認していきたいと思います。
営業車を運転するとみなし労働時間制の対象外?

「タクシーの運転手はみなし労働時間制の対象外だから、営業担当が社用車で得意先を回るのもホントは適用しちゃダメなのかな(;゚Д゚)?」
タクシーの運転をはじめ運転そのものが業務の場合は、事業場外労働のみなし労働時間制の対象とはなりません。
では、営業社員が会社の自動車を運転して担当の顧客を訪問したり、出張に赴く場合はどうなるのでしょうか。通常の営業業務とは別に、自動車の運転業務がプラスされるのはその通りなのですが・・・
そこで今回は、会社の自動車を運転して営業活動や出張に出かける場合、事業場外労働のみなし労働時間制の対象となるのかについて詳しく確認していきたいと思います。
販促のための店員派遣と人材派遣はどう違うの?

販促キャンペーンがあるたびに、うちの営業部員をスーパーやデパート、大型量販店に“派遣”している。ある部員に「人材派遣とうちの店員派遣はどう違うんですか?」と聞かれたけれど、そういえばどう違うんだろう? (メーカー勤務 営業部リーダー談)
**
自社製品の販売促進のための店員、宣伝要員、説明員として、代理店など他社の職場で他社の社員と混在して働く・・・というのは、セールやフェアなどの機会でよくあるでしょう。とはいえ、人材派遣との違いを問われても返答に詰まることも多いかもしれません。
社員の「派遣」とひとくちにいっても、その態様や形態はいろいろあるので、単なる言葉づかいだけで区別できないからです。
そこで今回は、店員派遣・代理店派遣と労働者派遣との差異について、詳しく確認していきたいと思います。
出向社員と派遣社員で人材マネジメントはどう違うの?

この部署ではプロジェクトが完了するまで出向社員、派遣社員、そしてうちの社員が一緒になって働いている。よその会社から来てもらっているのは出向社員も派遣社員も同じだけど、法律的には全然違うのでマネジメントに気をつけるように、と人事部からお達しが。・・・具体的にはどう違うの? (プロジェクト推進リーダー 談)
**
出向とは、第三者の会社に出向元の人事異動により派遣されて第三者(出向先)のために働くものですが、見た目としては人材派遣と類似している面があります。
ですが、出向と労働者派遣とは根本的に違うものなので、人材マネジメントのあり方もおのずと異なってきます。
そこで今回は、出向と労働者派遣との人材マネジメント上の具体的な違いについて詳しく確認していきたいと思います。
子育て中の社員に転勤命令を出してはいけないの?

「育児中の社員には転勤への配慮が必要らしい。転勤させるのはダメなの?転勤の多いウチの部署には若手が多いから大変だ・・・( ゚Д゚)」
子育て社員には、会社として育児休業制度や母性保護への配慮はもちろん必要です。ですが転勤の問題は性別を問わずに発生することなので、会社組織に属する一員として、基本的に社員には転勤に応じるスタンスが求められることになります。
では、育児・介護休業法によって会社に求められる「社員の配置(転勤)に関する配慮」とはどのようなことをいうのでしょうか。
(育児・介護休業法に規定されているため、対象は子育て&家族の介護を行っている社員です)
そこで今回は、子育てや家族の介護をしている社員に対する転勤への配慮について詳しく確認していきたいと思います。
会社はパート社員からの無期転換の申込を断ることができるの?

「もうすぐ6年目になるパート社員がいますが、無期転換の申込があっても断れますか?」
該当するパート社員さんはここ1年ほど体調を崩しがちなので、無期転換後の仕事内容に耐えられるのかな・・・と心配している店長さんです。(この会社では無期転換後に職務内容と労働条件の変更があるようです)
有期労働契約が会社との間に継続して、通算した期間が5年を超えた6年目に無期転換申込権が発生しますから、会社としては差し迫った問題です。
健康状態を優先してもらうためにも、法律的に無期転換の申込を拒否できるのかについて把握しておきたいというのはよくわかります。
そこで今回は、6年目のパート社員から無期転換の申込があったときに受理しないことができるのか、詳しく確認していきたいと思います。
定例会議に出席しないフレックスタイム社員にどう対応する?

「毎週月曜日は始業の9時から定例会議をやっているのですが、参加メンバーのフレックスタイム社員がこの頃毎回サボるようになり、会議の雰囲気も悪くなって困っています」
半年前から営業部でフレックスタイム制を始めたところ、残念なことに自分勝手に振る舞う人が出てきてしまいました。
こんな社員には注意するのが当たり前というところですが、「フレックスタイム社員にコアタイムでもないのに時刻指定で勤務を命じていいのか?」との疑問から、強く言って法律違反にならないのだろうか・・・と判断に迷う上司の方の心情もわかります。
そこで今回は、定例会議を毎回サボるフレックスタイム社員に会社としてどのように対応すべきなのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
働くママに変形労働時間制で働いてもらうのはダメですか

「営業部は変形労働時間制ですが、働くママには適用しちゃダメですよね?!あれ、でもAさんは小さいお子さんがいるワーママなのに変形勤務で働いている・・・?」
人事部に異動してきたBさんはキラキラした瞳で先輩を質問攻めですが、一方の先輩は当惑したような顔で・・・。というのも、Bさんの知識が少々ごっちゃだからです。
変形労働時間制がとられる場合にも、妊産婦が請求した場合には適用制限がありますし、育児や介護をしている社員には育児などに必要な時間をとれるよう配慮しなければなりません。
「その点では、働くママと変形労働時間制の関係について考えてみていいかも・・・」と新人さんへの指導を前向きに考え始めた先輩です。
そこで今回は、妊産婦・育児・介護社員等に対する変形労働時間制の適用について、詳しく確認していきたいと思います。
健康診断を拒否するパート社員に会社はどうする?

「パート社員にも健康診断を受けてほしいが、今まで対象外だったのになんで受けないといけないのか、と拒否する人もいてどう対応すればいいのか・・・」
社員の健康管理ができていなくて、仮に労災でも発生したら大変です。
会社には安全配慮義務がありますが、これを怠ったため労災が発生すると、労災保険だけでなく民法上の損害賠償義務が生じます。
そのため会社の方針として健康診断の対象を全社員にしたものの、受診したがらないパート社員に対して、法律上では受診の対象ではないのに受診を義務づけてもいいのだろうか?と悩んでしまう人事担当者さんなのでした。
そこで今回は、健康診断を受けたがらないパート社員への会社の対応について、詳しく確認していきたいと思います。
無期転換の申込期限を設けてはダメですか

「6年目のパート社員から無期転換の申込みがなく、契約期間の満了日も近いのに手続きを進めようもないのでヤキモキしています。今後のことを考えて、無期転換の申込期限を設けるのはダメですか?」
会社としては人員管理のため後任者の採用なども考えないといけないので、滞りなく仕事を回すためにもいつまでもこのパート社員の意思表示を待っていられない・・・というのがホンネでしょう。
とはいえ、法律上6年目の契約期間満了日まではいつでも無期転換の申込ができることになっていますし、申込をするかどうか、またいつ申込を行うのかは、本人の自由となっています。
そこで今回は、無期転換の申込期限を設定することに法律的に問題がないかどうか、詳しく確認していきたいと思います。
無期転換の申込にかかわるクーリング期間ってなんですか

「パート社員の前の有期労働契約と次の有期労働契約期間との間に、契約のない期間があっても契約期間は通算しないといけませんか?」
無期転換の申込とは、5年を超えて有期労働契約を継続更新した場合には、その働き手の申し込みよって、雇用期間の定めのない労働契約に移行するものです。
つまり、有期労働契約が会社との間に継続して、通算した期間が5年を超えた6年目に無期転換申込権が発生します。契約の通算の仕方がとても重要になってくるので、冒頭のようなご相談をいただきます。
このような「契約の空白期間」については法律で定められており、クーリング期間といいます。
そこで今回は、無期転換申込権に大いに関係するクーリング期間について詳しく確認していきたいと思います。
繰り返された労働契約を更新しないで解雇にならないの?

当社のパートさんは3か月更新で来てもらっている(更新手続きは「来月もよろしく」「はい」であやふやだったが)。だが、このご時世で経営が悪化、やむなく辞めてもらうことになった。
今回の更新が最終回であること、残りの年休は全部使ってほしいこと、感謝の気持ちを伝えたところ、こころよく納得してもらえた(内心複雑だったろう)。こんな「解雇」というかたちになって申し訳ない・・・
**
長い間にわたって繰り返し更新された労働契約をある時点で「更新しません」と会社側が意思表示して雇止めすることは、解雇といった法律の規制に抵触する場合があります。
では、冒頭の例のように「更新しないことの合意」ができているときはどうなるのでしょうか?
そこで今回は、反復更新された労働契約を不更新にして解雇にならない場合とはどんなときなのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
無期転換すると労働条件を格上げしないとダメですか

「パートのAさんには時給1,050円で週3日(週18時間)、うちの店に来てもらっていいます。無期転換すると、この労働条件をグレードアップさせないといけませんか?」
パートさんが入社してからもうすぐ6年目に突入するので、無期転換について考え始めた店長さん。Aさんは働きぶりも優秀で条件面のグレードアップに異存はないものの、まずは法律ではどうなのかを把握しておきたい様子です。
無期転換したときの労働条件について、結論からお伝えすると、基本は今までと変わりません。労働契約の期間が有期から無期になる(期間の定めのない労働契約)だけです。
とはいえ、「別段の定め」をすることで、期間の定め以外の労働条件を変更することは可能です。
そこで今回は、無期転換時の労働条件はどうなるのか、「別段の定め」があるときとないときについて詳しく確認していきたいと思います。
そもそも同一労働同一賃金ってどういうことですか

「正社員の〇〇さんと仕事内容はほとんど変わらないのに、給料に差があったりボーナスがないのはおかしい、とパートから不満を漏れ聞いて困っています」
・・・パートと正社員が同じ職場でごっちゃになって働いていて、同じような仕事をしていたら賃金面も同等にしないとだめなのだろうか、「同一労働同一賃金」というし・・・
このように「同一労働同一賃金」という言葉をめぐって、お悩みを抱える経営者、人事担当者の方は少なからずいらっしゃるようです。
法律で定める意味としては(ごく簡単にいうと)「パートと正社員の待遇に不合理な差をつけてはダメ」ということで、すぐさま「同じ仕事=同じ給料」といっているのではありません。
そこで今回は「いわゆる同一労働同一賃金」をめぐる問題について、詳しく確認していきたいと思います。
無期転換した社員の定年はどうなるの?

「パート社員が無期転換すると、それからもうずっと働き続けないといけないということですか?言い方は悪いですが、辞めるときはイコール“死んだとき”になってしまいますよね?!」
有期雇用の社員が無期転換した場合、文字通り、労働契約期間の定めがない雇用となります。つまり、雇用の終了は解雇か、社員の自己都合退職、死亡ということになるので、このようなご相談をいただいたことがあります。
解雇となると解雇の無効をめぐる問題が生じるので、もめごとに発展する法的リスクが発生します。それを避けるには、定年制を導入して雇用期間の「終わり」を決める必要があります。
そこで今回は、無期転換した社員と定年制をめぐる問題について詳しく確認していきたいと思います。
パート社員に契約期間の途中で辞めてもらうのはダメですか

「正社員なら簡単に辞めてもらうのは法律的に難しいかもしれないけれど、パート社員ならいつでも辞めてもらえますよね?」
これは大きな誤解です。このように思われていることは多いかもしれませんが、実は逆なんです。
民法上は「期間の定めのある契約(パート)」は、会社はその期間中に原則として解雇できず、「期間の定めのない契約(正社員)」の場合はいつでも解雇できると規定されています。
とはいえ、雇用期間を定めて採用したパート社員の勤務成績がめちゃくちゃサイアクで、これ以上続けてもらうのはムリじゃないの・・・?といったケースもあるかもしれません。
そこで今回は、有期の雇用期間の途中でパート社員を解雇するにあたって、会社が気をつけなければならないことについて詳しく確認していきたいと思います。
ストレスフルな出向社員に会社の対応はどうする?

Aさんを関連会社に出向させて2か月半。うちではほぼ残業がなかったが、出向先では毎日3時間ほどの残業があり、休日出勤もあるそうだ。仕事の進め方や手順などうちとは異なる点もあり、ストレスを感じているらしい。精神状態が不安定になれば、出向の打ち切りなども考えないといけないのだろうか・・・
**
出向先でストレスを抱える出向社員から相談された上司が、会社としての対応に悩んでいます。会社には社員に対する安全配慮義務があるからです。とはいえ、出向先との関係もあるので、出向元としてはどのような対応をとるべきなのか・・・
そこで今回は、ストレスを抱える出向社員に対して、出向元の会社はどのような対応をとるべきか、詳しく確認していきたいと思います。
パートでも正社員並みの年休になるのはどんなとき?

パート社員のAさんとBさんは、うちで働いてくれてもうすぐ半年。ふたりとも週30時間未満の勤務だから、まる10日の年休は与えなくていいはずだよね?(*‘ω‘ *) (ベーカリー店長 談)
**
週30時間未満勤務のAさんとBさんの年休を考える店長さんですが、ポイントは「1週あたり何日働いているのか?」という点です。
週所定労働時間が30時間未満のパート社員の年次有給休暇の日数は、その勤務日数(週所定労働日数)に応じて比例付与されますが、週の勤務日数が5日以上なら、正社員と同じ日数の年休を付与しないといけないからです。
そこで今回は、週30時間未満で働くパートタイマーの年休の取扱いについて詳しく確認していきたいと思います。
出向中に会社が破綻すると出向社員はどうなるの?

この夏から他社へ出向することが決まったAさん。初めての経験だけに不安で胸がいっぱいです。
それだけに良からぬ想像をしてしまいます。
「出向中にもし、出向先の会社が潰れたら私はどうなるの?出向期間がまだ残っていても元の会社にすぐ戻れるの?」
**
出向(在籍出向)では、出向元と出向先の両方で二重の労働関係が成立します。つまり、出向社員は、出向元企業の社員であると同時に、出向先の社員でもあるということです。
そのため、Aさんのように不安を抱くのも無理はないかもしれません。
そこで今回は、出向期間中に出向先が破産したとき、出向社員はすぐ出向元に復帰できるのか、詳しく確認していきたいと思います。
パート社員の期間満了前に解雇予告は必要ですか

今は忙しいので期間限定で入ってもらっているパートさん。その期間が終わる前に解雇予告をしないとダメなのかな。更新があるかも、って期待していたら申し訳ないし・・・(小売店 店長談)
**
「解雇予告をしておかないと誤解が生まれてトラブルになるのでは?」と心配な店長さんです。
パート社員など期間限定の働き手の場合、期間満了で雇用が終了することになります。雇用期間が満了すれば自動的に退職となるものであって、「解雇」にはあたりません。
そのため、期間満了の場合は労基法20条(解雇の予告)の問題は発生しないといえますが、期間雇用の契約を反復更新されていると働き手には継続雇用の期待が高まるというもの。
そこで今回は、パート社員の期間満了(更新された場合も含む)にあたって、解雇予告が必要かどうか、詳しく確認していきたいと思います。
パート社員より先に正社員を人員整理してはダメですか

「うちのパート社員は時間をうまく使って、よく働いてくれています。正社員よりもよくやってくれている、と思うこともしばしばです。もし、経営がうまくいかなくなって人減らしが必要になったとき、パート社員より先に正社員を対象にするのはダメですか?」
不況、業績の低迷など経営上の理由で過剰人員となった場合、経営の縮小や部門の閉鎖・廃止によって人員整理を考えないといけないこともあるかもしれません。
いわゆる「整理解雇」を行うとき、整理の順序としてパート社員と正社員のどちらが先なのか、というのがこの相談内容のポイントです。
人員整理の対象者を考えるときには、雇用形態の順序が問われるからです。
そこで今回は、人員整理を行うときの対象者の順序について、詳しく確認していきたいと思います。
昼休みナシで早く帰りたいパート社員、会社はどう対応する?

当社のパート社員は、朝の10時から夕方4時までの勤務。残業アリの場合もあるので、子育てママさんから「きっちり4時に帰りたいので、残業にならないよう昼休みナシでその分働きます」との申出があった。昼休みナシで法律的に問題ないのかな? (小売店 店長談)
**
職場の子育て世代のため、会社としてできるだけ柔軟な対応をとっていきたいので、頭を悩ます店長さんです。
休憩は、所定労働時間が6時間以下であれば与えなくてもいいですが、残業によってその日の労働時間が6時間を超えた場合には与える必要があります。このことを大前提に対応策を講じることがポイントです。
そこで今回は、所定労働時間6時間のパート社員への休憩時間の与え方について、詳しく確認していきたいと思います。
他社への転籍命令を会社は一方的に出せるものですか

当社の就業規則に「業務上の都合により会社は配転、出向、転籍を命じることがある」と記載されている。ということは、よその会社への転籍も業務命令ということで会社が一方的にやってもいいということ?
**
人事部のAさん、仕事のなかで就業規則を見直していると、ふと疑問を覚えました。転籍とは、今までの会社(転籍元企業)の社員としての地位を失って、他の企業に雇用されるものです。
社員の人生に大きな影響を与えることなのに、「転籍を命じることがある」というような就業規則の規定(包括的同意といいます)だけで、あっさりと社員を転籍させていいものなの?・・・と感じたようです。
そこで今回は、他社への転籍をめぐる問題について、詳しく確認していきたいと思います。
パート社員を正社員に登用、試用期間はどうなるの?

当社では、新卒でも中途でも正社員採用の場合は、3か月間の試用期間を設けています。パート社員を正社員に登用することを考えているのですが、この場合も試用期間を設けるものでしょうか。
試用期間について就業規則に規定があるので、適用するべきなのか判断に迷います。(サービス業 人事担当者 談)
**
パートの戦力化のため、正社員登用制度を導入する企業もみられます。ある程度の責任を伴う仕事を任される正社員をめざす選択肢があるというのは、働き手のモチベーションアップにつながるからです。
そのため、冒頭のようなご相談をいただくことがあります。
そこで今回は、パート社員から正社員に登用した場合に試用期間はどうなるのか、設けるべきなのかについて確認していきたいと思います。
採用面接で聞いた希望の勤務場所から異動させてはダメですか

採用面接では、配属をなるべく希望通りにしたいので、希望の支店や部門等を聞いている。入社2年目の社員に支店への異動を打診すると、「本社勤務だから入社したのに」と不満気な様子。採用面接で聞いた希望の勤務場所から異動させるのは法的にダメなのか?
**
採用面接だけでなく、求人広告に募集する職種や勤務場所を記載するのはよくあること。採用面接時に勤務場所や仕事内容の希望を聞くと、勤務場所や職種を限定した採用になるか?というのが、問題のキモです。
職種や勤務地を限定して採用した場合、職種変更や限定勤務地外への転勤には本人の同意が必要となるからです。
そこで今回は、勤務場所や職種について、採用面接時に希望を聞いたり、求人広告で職種・勤務場所を明示すると「勤務場所・職種の限定」となるのか、詳しく確認していきたいと思います。
契約更新を最長5年までに限定してもいいですか

「契約社員を新しく採用するとき、“契約更新による有期雇用期間の限度は最長5年間まで”とするのは、法律的にダメなのかな?」
正社員を解雇するのは法律的に厳しく規制されるので、景気変動に対応できるよう、企業は有期で人材を雇用します。
かつては、有期労働契約を更新するときに法律上の制限は何らなく、会社と働き手の当事者間にゆだねられていました。ですが、今は法律によって5年を超える有期労働契約の更新について、働き手に無期転換申込権が発生します。
そのため「無期雇用転換によって雇用調整できなくなるのでは?」と冒頭のように不安に思われるケースもあるようです。
そこで、今回は5年を超える契約更新はしないとすることは有効なのか、そして注意するべき点について詳しく確認していきたいと思います
出向中の期間は退職金の在職年数にカウントされますか

「社員の出向期間は、退職金の計算で在職年数に通算されますか?」
退職金は、法律で支給が義務付けられているものではないですが、就業規則によって退職金制度を定めている企業は多いでしょう。
退職金の計算は、一般的に「基本給×在職年数×一定係数(人事評価などよる)」といった方式によることが多いので、在職年数は退職金の金額に少なくない影響を及ぼします。
「社員が定年するのはまだまだ先だ・・・」と思いたいところですが、現実的には中途退職が一定の割合で発生するため、いざ社員の退職時になって慌てないようにしておきたいですね。
そこで今回は、出向期間は退職金の計算で在職年数に通算されるのか、また退職金の負担をを出向先企業にも求めることができるのか、詳しく確認していきたいと思います。
出向規程でどんなことを決めておくといいですか

うちの就業規則をみると、「社員に出向を命じることがある」と書いてあるものの具体的な内容は載っていない。いざというときのため具体的に細かく規定化しておいたほうがいいよなあ。出向規程をつくったほうがいいのかな? (メーカー勤務 人事担当者談)
**
就業規則(本則)に社員の出向命令に応じる義務のみを定め、別規程として出向規程を設け、出向における労働条件を定める方法があります。
出向(在籍出向)では出向元と出向先の両方で二重の労働関係が成立しします。そのため、出向元・出向先・出向社員での三者間の取り決めによる権限と責任に応じて、出向元・出向先のそれぞれが使用者としての責任を負います。
そこで今回は、会社(出向元)として考えておくべき出向規程の内容のポイントについて詳しく確認していきたいと思います。
フレックスタイム社員の出張時間をどう考える?
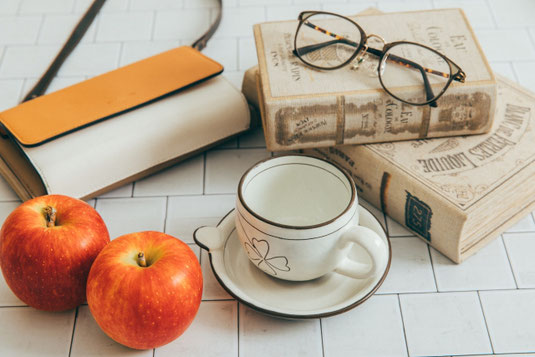
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、フレックスタイム制を導入したり、検討中の企業も多いのではないでしょうか。
ただ、フレックスタイム制は“始業・終業時刻をいつにするかを社員が決めてもよい”労働時間制度のため、「フレックスタイム制ではスケジュールが確定した出張を命じてはダメなのか?」と悩まれる上司の方もいらっしゃるようです。
フレックスタイム制が適用される社員に対して、コアタイム(必ず働かなくてはいけない時間帯)は別として、フレキシブルな時間帯について「〇〇時に出勤しなさい」や「〇〇時まで働きなさい」と、始業・終業時刻を指定する業務命令は原則できないからです。
そこで今回は、フレックスタイム制の対象社員にはスケジュール指定の出張命令を出していいのか?、詳しく確認していきたいと思います。
今さら聞けない「正社員」と「契約社員」はどう違うの?

「正社員と契約社員が別物とは感覚的にはわかるけれど、具体的に何がどう違うのかな?給料が異なるだけ??」
そもそも日本の雇用形態は、従来から大きなくくりとして終身雇用制と期間雇用性に分けられていました。景気変動に対応するため雇用調整的な意味合いを含め、有期労働契約による「not正社員」の雇用はやむを得ないと法的にも認められてきたからです。
いまでは、キャリアに対する考え方、(育児や介護などによる)労働時間の制約の有無など、人材の多様化が進んでいます。そのなかで安定的に人材を確保していくには、「正社員」と「契約社員」の違いをきちんと理解し、人材マネジメントにおける柔軟な発想が必要です。
そこで、今回はまずは基本のキの字、いわゆる「正社員」と「契約社員(not正社員)」はどう違うのか、詳しく確認していきたいと思います。
営業車でのセールスや営業日報の作成はみなし労働時間制になる?

営業部では社用車で取引先を訪問している。1日の予定が終えて会社に戻り、日報を作成して上司に報告するのが日課だ。営業社員はみなし労働時間制の対象だが、この状況では労働時間をカウントできるのでは?
・・・もしかすると、みなし制の適用外じゃないの?
**
オフィス外での仕事では、何時から何時までが休憩時間なのか、手待ち時間なのか、と具体的には把握できません。
そのため事業場外での仕事であって、実労働時間がつかめない場合には、会社からあらかじめ別段の指示がない限り、「通常の労働時間働いたものとみなして処理する」というみなし制が認められています。
ですが、営業社員のタイムマネジメントで判断に迷うことは多いもの。
そこで今回は、社用車の営業活動や営業結果の報告の義務付けがみなし労働時間制の対象になるのか、詳しく確認していきたいと思います。
パート社員の就業規則でも正社員の意見を聴かないとダメですか?

「パート社員用の就業規則は、パート社員の代表に意見を聴取するだけでいいですよね?正社員には聴かなくてもいいですよね?」
就業規則を作成・変更する権限と義務は会社側にありますが、社員の過半数で組織する労働組合もしくは社員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないことが、労基法によって定められています。
そのプロセスで就業規則を社員に周知するとともに、就業規則の内容を合理的なものにしようとするのが目的です。
いまの時代では、さまざまな雇用形態の社員がいっしょに働くのはごく当たり前のことです。労働契約の内容の多様化に対応するため、就業規則を雇用形態別に作成することもあるでしょう。
そこで今回は、パート社員の就業規則はパート社員の意見を聴くだけでいいのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
出向先での不正発覚、懲戒処分を行うのはどっち?

当社の社員を関連会社に出向させていたが、当人が出向先企業で経理関係書類を不正操作していたことが判明した。横領の発覚で懲戒処分モノとはいえ、これはあくまでも出向先で起きた事案。出向元のうちは、懲戒処分の決定に関与できないのだろうか・・・(経理部課長 談)
**
「懲戒処分を行うのは出向元の当社なのか、それとも出向先の関連会社なのか?」両社間での協議はうまくまとまらず、悩みが深くなる課長さんです。
出向社員は出向元企業の社員であると同時に出向先の社員でもあるため、出向社員に対する懲戒について判断に困惑するのはよくあること。
そこで今回は、出向先での違反行為に対する懲戒処分に会社(出向元・出向先とも)はどのように対応すべきなのか、詳しく確認していきたいと思います。
パート、アルバイト、契約社員の違いはなんですか?

「正社員以外の社員には、パートやアルバイト、契約社員などがありますよね。これらにはどんな違いがあるのですか?法律上の区別はありますか?」
社会構造の移り変わりから、現在は働き方が多様化しています。
いまでは、さまざまな雇用形態の社員がひとつの会社で働くことは、ごく一般的なことです。
そのため、パートやアルバイトなど、いろいろな名称で呼ばれる「期間雇用の社員(=not正社員)の定義が知りたい」とのご質問をいただくことがあります。求人広告を出そうとするときに、ふと疑問に思われることが多いようです。
それぞれの企業における雇用戦略と業務内容に応じて、正社員やパート社員などを適切に組み合わせて連携を図っていくことは、これからの時代の人材マネジメントの課題のひとつといえます。
そこで今回は、期間雇用の社員の雇用形態はどのように違うのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
リストラのときでもシニア社員の継続雇用は若手より優先される?

「企業には65歳までの継続雇用が法律で義務付けられているけれど、経営不振でリストラが必要なときでも、定年後の高年齢者を再雇用しなければいけないの?」
新型コロナウィルス関連の経営破綻など、世界中に広がる感染は経済活動にインパクトを与えています。そこで、リストラと高年齢者の継続雇用措置のバランスは企業として気がかりなところでしょう。このような疑問が生じるのはもっともです。
定年後のシニア社員の雇用継続はキープで、これからの企業の再建に必要な中堅社員や会社の将来を担う若手社員をリストラしなければならないのでは、企業経営は立ち行かないでしょう。雇用制度のあり方としてもちょっとヘンです。
そこで今回は、経営不振でリストラが必要でもシニア社員を継続雇用しなければならないのか、また人員整理の優先順位をどう考えるべきなのか、詳しく確認していきたいと思います。
年休の出勤率、短時間社員の場合はどう計算する?

「Aさんがご家族の介護でフルタイム勤務がキビシイらしい。営業部のエースなのにどうしよう?( ;∀;)」
育児や家族の介護、大学院への通学、通院による治療・・・こういった社員の事情に対応する方法のひとつに短時間勤務制度があります。
短時間社員は、職場の他の社員と比べて所定労働時間が短いですが、年休の発生要件である出勤率をどう考えるのかが問題です。
年休の発生要件には「全労働日の8割以上の出勤」が必要ですが、出勤率の計算で「労働日」がフルタイムの出勤を指すとしたら、短時間社員では難しくなります。
そこで今回は、短時間社員をはじめ労働時間の短い社員の出勤率をどのように計算するかについて詳しく確認していきたいと思います。
パートが年休で休んだ日の給料はいくらになりますか

年次有給休暇は、文字通り「有給休暇」なので、年休の取得日にはもちろん給料が支払われることになります。「そんなの当たり前だ」と思われる人がほとんどでしょう。
ですが、「年休で休んだ日あたりの給料の額は?」と聞かれると、即答できる人はそう多くないかもしれません。特に月給制で給料を支払っている企業、またそこで働いている人の場合はそうだと思います(その理由は後述しますね)。
そこで問題となるのが、時給制で働くパートさんの場合です。「年休で休んだ日の給料はいくらになりますか?」とパートさんに聞かれて、はじめて疑問に思った、というお話を実際に経営者や管理職の方からよくお伺いします。
そこで今回は、パート社員の年休日の給料はどう計算するのか?について、確認していきたいと思います。
営業時間の短縮がパートの賃金に与える影響とは

「うちは1年単位の変形労働時間制をとっていて、月によって所定労働時間が大きく変わります。月間の労働時間の長い短いで賃金単価も変動させないといけませんか?」
複数の店舗を経営する企業では、人手不足の対応策に営業時間を短縮する場合があります。労働時間の短縮のため、変形労働時間制を導入する職場もあるでしょう。
結論から申し上げると、月給制の社員にとって、月間の所定労働時間が異なったとしても賃金に影響しません。
とはいえ、日給や時給で賃金が計算されることの多いパートにとって、影響は少なくありません。
そこで今回は、労働時間(営業時間)が短くなることによって、パートの賃金(日給・時給)はどのような影響を受けるのかについて詳しく確認していきたいと思います。
子育て社員の労働時間を会社はどう考える?

「職場に疲れ果てている様子の子育て社員がいるので、無理せずに働けるようにしたい。子育て社員の労働時間をどうにかできないかな?」
労働時間の設定は、今いる人に少しでも長く勤めてもらい、優秀な人材を確保するために、企業経営にとって重要なテーマです。
「仕事と家事を両立させないと」とのプレッシャーを和らげ、健康的に前向きに仕事に取り組んでもらえるよう、子育て社員の労働時間マネジメントについてご相談をいただくことがあります。
子育て社員への対応には、「育児のための所定労働時間の短縮措置」と「育児時間」について理解しておく必要があります。
そこで今回は、育児のための所定労働時間の短縮措置と育児時間、この2つの関係について詳しく確認していきたいと思います。
出向社員に給料の支払い義務があるのはどっち?

まだ夏のような暑さですが、空の高さで秋の気配を感じます。秋は人事異動の季節。10月に配置転換や出向を行う企業もあるでしょう。
出向社員は、出向元企業に在籍したまま出向先企業で業務に従事することになります。出向前には出向元企業から支払われていた給料や賞与、出向後はどちらの企業から支払われることになるのでしょうか?
また、出向元と出向先で異なる昇給基準はどちらの基準によるのでしょうか?
賃金は重要な労働条件のひとつであり、社員の関心も高いトピックなので、しっかり押さえておくことが肝要です。
そこで今回は、出向社員に対する賃金や賞与の支払い義務はどちらにあって昇給基準はどうなるのか、詳しく確認していきたいと思います。
フレックスタイム社員は早朝の会議に出なくていい?

「緊急の案件を打ち合わせるため、部全体の会議を早朝に行わないといけないことも。そんなとき、フレックスタイム制が適用される社員には、早朝会議への招集をかけてもいいの?」
この春から働き方改革関連法が施行されたこともあり、柔軟な職場環境づくりに尽力される企業は多いと思います。
社員がライフスタイルに合わせて働けるよう、その選択肢を提供するべくみなさん知恵を絞られているなか、冒頭のようなギモンを持たれる人事担当者さんもいらっしゃるようです。
フレックスタイム制においては、始業・終業時刻をいつにするかを社員の自由に委ねられるので、早朝の会議に出なくていい?いや、そもそも招集してはいけない?と悩まれるのでしょう。
そこで今回は、フレックスタイム社員に対する早朝の会議への出席を要請してもいいのかどうかについて、詳しく確認していきたいと思います。
出向社員に適用される就業規則はどっち?

改正法の施行に伴って、この春に就業規則の見直しを行われる企業も多いでしょう。
就業規則を見直すにあたって、少なくとも一度は話題に上るのが出向社員への就業規則の適用についてです。
出向社員は、出向元企業の社員であると同時に、出向先の社員でもあります。ですから、出向社員には出向元と出向先のどちらの企業の就業規則が適用されるのか?とのご質問をよくいただきます。
ある具体的な事項について出向元と出向先企業の就業規則の規定が異なっている場合、どちらの規定が適用されるかによって、出向社員の労働条件に少なくないインパクトを与えることになるからです。
そこで今回は、出向元と出向先企業の就業規則の適用関係について確認していきましょう。
出向先による再出向の命令はできますか?

とある企業では、関連グループの数社で合同プロジェクトを運営することになりました。
プロジェクト推進担当のAさんは関連会社に出向中です。ところがプロジェクトが進むにつれ、その規模は当初よりも大きなものになっていきました。
そこでプロジェクト全体を円滑に進めるため、中心的な役割を担当しているAさんを、さらに別の会社に出向させたほうがよいのではないか?といった話が持ち上がりました。
Aさんの出向先の人事部では、その話を聞いて大慌てです。
プロジェクトを運営する現場では、Aさんをさらに別会社へ出向させることが、ほぼ決定事項としてまさに今、動きだそうとしているとのことだったからです。
そこで今回は、「出向してきた社員を他社に再出向させることはできるのか?」について詳しくみていきたいと思います。
出向社員の年休日数をどうカウントするか?

この4月から、法改正によって年次有給休暇の取扱いが変わります。そこで最近、年休の取扱いについてのご質問をよくいただきます。
(詳しくは、過去記事「法改正で年5日休むため会社と社員でやるべきこと、捨てること」をご覧ください)
そのなかには、「この春から子会社へ出向する社員の年休日数は、どうカウントすればいいですか?」と、出向社員の年休の取扱いに関するものもあります。
ちょうど今は新年度の人事異動を検討する時期でもあるので、人事担当者の方は「今の会社で発生している年休を出向先の子会社でも使えるのか?」「いったんリセットすることになるのか?」などと、頭を悩ませることもあるかもしれませんね。
そこで今回は、出向社員の年休日数をどうカウントするとよいのか、について詳しく確認していきましょう。
パートの契約終了、残った年休を買い上げないとダメ?

「忙しい時期なのに、”年休を買い上げてほしい”とパートさんから申し出があった。会社としてどう対応するべきなの(;´Д`)?」
**
サービス業では、年末は1年で一番忙しい時期なのでパートやアルバイトを増員することもあるでしょう。
雇用期間の定めのあるパートタイマーであっても、採用してから6ヵ月間継続して勤務し、その間8割以上の出勤率であった場合には、年休請求権が発生します。
そこでよく問題となるのが、パートの契約更新が行われると思って年休を取得しなかったものの、会社の経営上の都合や仕事量の減少によって実際には更新がなされなかった、というような場合です。
そこで今回は、パートの契約終了の際に残った年休の取り扱いを会社としてはどう対応するべきなのか、詳しく確認していきたいと思います。
出向社員の不安解消は会社の義務

出向によって、賃金や休日、労働時間などの労働条件が変わることは考えうる状況です。よくある例で言うと、今の会社(出向元)とは違って土曜日も出勤しなければならない、といったこともあるでしょう。
出向先での労働条件が出向元に比べて低下することが見込まれるとき、社員にとっては不安があるでしょうが、会社としてはなんとかなだめすかして我慢してもらう・・・しかないのでしょうか?
もしそうだとすると、出向先での社員のモチベーションが落ちてしまうことが懸念されます。さらに社員に出向を拒否されることになれば、事態はこじれる一方です。
こんなとき、社員の不安感を取り除いて出向先でもパフォーマンスを発揮してもらうために、会社はどのように対応するとよいのでしょうか。
今回は、出向による労働条件の低下に対して会社が行うべき是正措置についてみていきたいと思います。
雇用契約の継続or中断でパートの年休日数はどう変わる?

「パート社員の年休は、雇用契約の内容に応じて管理しないといけないから大変、間違っていないか不安・・・(;´Д`)」
人材活用のため、パート社員の雇用契約を継続したり、またはいったん中断したり、柔軟な対応をとるケースは多いでしょう。
パート社員にとっては仕事と家事・育児の両立といった事情があり、企業にとっては経営状況や業務量の増減に応じて人手を調整したい背景があるからです。今は小売業やサービス業だけでなく、様々な業種でパート社員が活用されているので、お悩みを抱える担当者の方は多いかもしれません。
そこで今回は、パート社員の年休管理にまつわる下記の2点について詳しく確認していきたいと思います。
- パート契約の「継続」とはどんな場合のことを言うのか?
- パート契約を「中断」したとき、付与日数はどうなるのか?
配達員の労働時間をどうカウントすればいいですか

配達に出かけた配達員が定時を過ぎてもなかなか帰ってこないことがある。帰り道の大雨で立ち往生していたようだが、労働時間のカウントはどうなるのかな?(小売業マネージャー 談)
**
帰社が遅くなった配達員の労働時間マネジメントについて、お話を伺っていると、営業社員の事業場外みなし労働時間の場合と混同されていることも多いようです。
また、帰りが遅くなったのは天候のせいではなく、会社に戻る途中で私用を済ませていたために遅くなっていたような場合はどう対応すればいいのか?とのご相談を伺うこともあります。
そこで今回は下記の2点に集約される、配達員の労働時間マネジメントにまつわるよくあるお悩みについて詳しく確認していきたいと思います。
- 交通渋滞、交通事故、道に迷うなどで遅くなった場合、労働時間をどうカウントするの?
- 配達や帰社の途中、私用やサボリで遅くなったと推定される場合、労働時間をどうカウントするの?
新年度の準備で気をつけたいパートの年休管理

「週5日シフトに入ってもらっているパートさんが、おうちの事情で新年度から週3日になる。シフトの調整を考えないといけないが、年休の日数はどうなるんだろう?」(給食調理員 部門長 談)
3月半ば、たくさんのパート社員が働く職場では契約更新の手続きとそれに伴う事務対応で忙しい時期になりました。
週所定労働時間が30時間未満のパートタイマーの年次有給休暇の日数は、その勤務日数(週所定労働日数)に応じて比例付与されるので、契約変更に応じて適切に年休管理を行う必要があります。
そこで今回は、パートの年休管理についてよくご相談いただく次の2点について詳しく確認していきたいと思います。
- パートが年休で1日休むと当然「有給」となるが、いくら払うべきなのか、またその計算根拠は?
- 新年度の契約を更新するにあたって、パートの週の勤務日数を変更した場合、年休をいくら付与するといいのか?
正社員とパートの賞与・諸手当をどう考える?

「正社員とパートという違いでなぜ手当が出る、出ないがあるの?」
パート社員等から求めがあった場合、会社は待遇の相違の内容や理由などについて説明しなければなりません。
待遇の差が単に「年齢や勤続年数によるもの」という理由しかないなら、合理的な説明とならないので、会社として説明義務を果たすことは難しくなります。
合理的な説明になっていないケースとしてよくあるのは、賞与や手当についてです。同一労働同一賃金の議論が高まるなかで、正社員とパートの賞与や諸手当も含めた賃金のあり方について、両者の役割や貢献度がどのように違うのか、明確な説明をできるようにしておきたいですね。
そこで今回は、これからの正社員とパートの賞与や諸手当のあり方について詳しく確認していきたいと思います。
これからの正社員とパートの賃金体系のあり方とは

同一労働同一賃金の実現に向けた立法化が検討されていますが、政府が目標とするヨーロッパ諸国では職務評価制度が確立されています。
産業別労働組合と経営者の間で賃金が決定され、「受付」という職務で、同じ地域であればどの企業でも同等の賃金です。「技能」「努力」「責任」「作業条件」といった職務評価基準が運用されているのです(定期昇給がなく職務間を移動(例:「受付」→「秘書」)しないかぎり賃金は上がりません)。
日本でこのような企業をまたぐ横断的な賃金制度が確立されていないのは、新卒を職務別にではなく、一括採用するケースが多いからです。企業ごとに年齢、勤続年数、仕事の内容、学歴、会社への貢献度といったさまざまな要素で、賃金が決定されています。
では現在、検討されている同一労働同一賃金とはいったいどのようなもので、企業はどう対応していくといいのでしょうか。
無期転換への対応の準備できていますか?
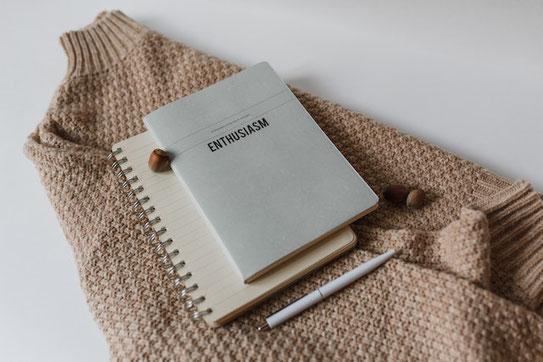
労働契約法による無期転換制度が2018年4月からスタートしますが、みなさんの会社で準備は万全でしょうか?
無期転換とは、同じ企業において有期労働契約が反復更新されて、通算5年を超えたときに、社員の申込みによって無期労働契約に転換されるルールのことです。
「うちは契約社員が多いが具体的に何をしないといけないの?」
「うちのような小さな会社にどんな影響があるの?」
「正社員しかいないのでうちは関係ない」
企業によって無期転換にまつわる事情は異なるかもしれません。
ですが、人手不足の時代において、会社を伸ばすために人材をどのように活用していくのかを考えることは、規模を問わずどんな企業にも共通する大切なことです。
そこで今回は、企業があらかじめ考えておくべき無期転換への対応について詳しく確認していきたいと思います。
社員のモチベーションを高める人事異動とは

会社には人事異動についての裁量が広く認められています。ですが、事前によく考えておかないと「なぜ今の部署で頑張っている私が異動になるのか」「経験のない仕事をイチから始めるのは無理だ」と逆に社員のやる気をダウンさせてしまうおそれも・・・
そのため会社としては、中長期的な視点で社員に働きがいをもたらす人事異動を考える必要があります。
社員が希望する仕事をやらせる(異動希望を実現させる)ことは、本人の仕事に対するモチベーションをグッと引き上げるからです。
ズバリ人事異動とは、社員の力を活かして会社を伸ばしていくために、どのように人材の配置や役割を考えるか?ということです。
そこで今回は、社員のやる気を引き出す人事異動のポイントについて、確認していきたいと思います。
専門職コースの活用法

「プロフェッショナルな人材を一人でも多く育てたい」
顧客の課題が複雑で高度になっているので、企業にはそれらの要望に的確に応えることが、今までよりも求められています。
課題解決の質とスピードを上げるべく、冒頭のように考えられるケースも多いようです。そこで、社内でのキャリアのひとつに「専門職」を設けることもひとつの方法です。
とはいえ、次のような理由から専門職を設置すると、プロをめざす社員を育てる仕組みづくりとは程遠くなってしまいます。
- 管理職ポストが不足しているから
- 管理職にするには実績やリーダーシップに欠けるが、昇進させないとモチベーションが下がるから
今回は、社員のやる気を引き出し、会社の業績を伸ばす専門職コースの活用法について詳しく確認していきたいと思います。
出世したくないベテラン社員のモチベーションを上げる方法

新人として入社したとき、作業現場ではオロオロするだけだったが、先輩・上司の指導や本人の努力で力をつけてきた。経験を積んで、イレギュラー事態の対応や取引先とのやり取りもスムーズだ。面倒見がよいので現場でも後輩らに慕われていている。やるじゃん。
・・・入社してはや10年目。平均的な昇格を考えると、そろそろ管理職に昇格して責任を担ってほしい。
***
頼りになるベテラン社員、コツコツとした働きぶりで周囲からの人望も厚いようです。けれども管理職へのステップアップを拒否してきました。さあ、思いがけない事態が発生してしまいました。
昇進への打診を断る中堅・ベテラン社員に対して、会社としては処遇をどのように考えればいいのか、今回はこのあたりについて詳しく確認していきたいと思います。
外回り営業社員の労働時間をどうカウントする?

「顧客に寄り添って細やかな提案を行うため、営業社員の労働時間が長くなる傾向にある」
「外回り営業ならちょっと休憩にはいっていてもわからない」
「その分も労働時間にカウントして残業代を支払わないといけないのか?内勤社員から疑問視する声もあって悩んでいる」
これらは、外回り営業社員の労働時間にまつわるお悩みです。
今の時代では顧客のニーズは多様化しているので、あらゆる要望に柔軟に応えて適切なフォローができるかが営業社員には問われています。
とはいえ、外回り営業という仕事の特性を損なうことなく、営業社員と周りの社員の納得感を得るにはどうすれば・・・
そこで今回は、外回り営業社員の労働時間マネジメントについて詳しく確認していきたいと思います。
役割・仕事内容を考えれば働き方は定義できる

「人手が足りないので数人まとめて正社員として採用しましたが、パートにしておけばよかったな、と後悔しています」
正社員にすればやる気をだして働いてくれるはず、とのねらいが期待はずれになってしまった・・・
実は、このようなエピソードをよく伺います。
これは正社員、パートタイマーそれぞれにどんな働き方をしてほしいのか、役割分担をあらかじめきちんと考えておかなかったために起きる問題です。
今回は、正社員とパートタイマーの役割と働き方について詳しく確認していきたいと思います。
正社員とパートタイマーの違いを説明できますか?

「せっかくパートタイマーを正社員にしたのに、期待していたように働いてくれない。これなら、単に人件費が上がっただけ・・・(;´Д`)」
これは、自社における正社員とパートタイマーのそれぞれの定義を説明できていないために生じる問題です。
正社員とパートタイマーのように雇用形態の違いによって、社員をいくつかのグループに分ける仕組みのことを雇用区分といい、人材マネジメントの基本構造を決めることになります。
定義をきちんと説明できると、「あなたの役割はこれこれで求める成果はこうだから」と社員に対して具体的な行動を促しやすくなり、仕事がスムーズに運ぶようになります。
そこで今回は、社員に説明できる雇用区分をめざして自社における正社員とパートの役割の違いについて、詳しく確認していきたいと思います。
