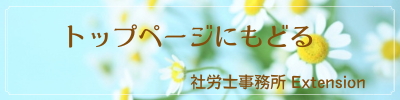「パート社員が無期転換すると、それからもうずっと働き続けないといけないということですか?言い方は悪いですが、辞めるときはイコール“死んだとき”になってしまいますよね?!」
有期雇用の社員が無期転換した場合、文字通り、労働契約期間の定めがない雇用となります。つまり、雇用の終了は解雇か、社員の自己都合退職、死亡ということになるので、このようなご相談をいただいたことがあります。
解雇となると解雇の無効をめぐる問題が生じるので、もめごとに発展する法的リスクが発生します。それを避けるには、定年制を導入して雇用期間の「終わり」を決める必要があります。
そこで今回は、無期転換した社員と定年制をめぐる問題について詳しく確認していきたいと思います。
定年を定めるときに注意すべきこと

そもそも「定年制」とはどういうものなのかというと、「社員が一定の年齢に達したときに労働契約が終了する制度」をいいます。
期間の定めのある労働契約(有期雇用)と違って、定年制においては定年を迎えるまでの退職や解雇が制限されません。そのため、無期雇用といえども、定年を定めた場合には定年までの雇用となります。
定年を定めるにあたって注意しなければならないのは、原則として高年齢者雇用安定法で「定年を定める場合には、定年の年齢は60歳を下回ってはダメ」との旨が示されていることです。
また、65歳未満の年齢で定年を定めた場合、同法において高年齢者雇用確保措置を講じなければならないとされています。高年齢者雇用確保措置を講じることで高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保してくださいね、というのがその趣旨です。
具体的には、次の①~③の措置のいずれかを講じる必要があります。
- (65歳未満の)定年の引き上げ
- 継続雇用制度(いま雇用している高年齢者が希望するときは、その高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度)の導入
- 定年を廃止
無期転換制度と定年制の関係

高年齢者雇用確保措置の趣旨を考えると、無期転換制度の適用は(定年のある会社は)定年に到達するまでであって、定年後の高年齢者雇用確保措置の適用に至った後には無期転換制度の適用がないものと解釈できます。
そこで、「専門知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(平成27年4月1日施行)によって、定年(60歳以上)に到達した後引き続いてその会社に雇用される有期雇用の社員については、「第2種特定有期雇用労働者」として取り扱われることになりました。
具体的には、会社が「第2種特定有期雇用労働者」の特性に応じた雇用管理の措置(配置、職務及び職場環境に関する配慮その他の雇用管理措置)の内容を定めた「第2種計画」を決定して、都道府県労働局長に提出して認定を受けると、定年後の有期労働契約には無期転換制度の適用は行われないとされています。
ただし注意しなければならないのは、60歳以上の有期雇用のシニア社員はすべて無期転換制度の適用を受けないわけではない、という点です。
適用除外となるのは、あくまで「定年後に引き続いてその会社に雇用される有期雇用社員」であって、当初から有期労働契約であった社員が、60歳をまたがってその契約期間が通算して5年を超えたときは、やはり無期転換権が生じます。
このような場合に65歳をもって第2定年とすることもできます。第2定年は、一定の年齢で一律に退職させるので、みんな平等に扱えるというメリットがあります。
**
「65歳以上で無期転換権が生じたシニア社員の定年はどうしたらいいの?」
こう思われた方もいらっしゃるかもしれません。確かに65歳以上の無期転換社員の定年を、就業規則で一律に決めることは難しいですよね。
たとえば「無期転換してから1年経過後の誕生日の年齢まで」との旨を就業規則に定めるといったことが考えられます。その他としては、「本人の健康状態や業務上の能力などによって個別契約で定める」といった旨を規定することもアリでしょう。


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事