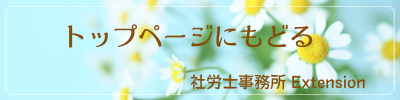「正社員と契約社員が別物とは感覚的にはわかるけれど、具体的に何がどう違うのかな?給料が異なるだけ??」
そもそも日本の雇用形態は、従来から大きなくくりとして終身雇用制と期間雇用性に分けられていました。景気変動に対応するため雇用調整的な意味合いを含め、有期労働契約による「not正社員」の雇用はやむを得ないと法的にも認められてきたからです。
いまでは、キャリアに対する考え方、(育児や介護などによる)労働時間の制約の有無など、人材の多様化が進んでいます。そのなかで安定的に人材を確保していくには、「正社員」と「契約社員」の違いをきちんと理解し、人材マネジメントにおける柔軟な発想が必要です。
そこで、今回はまずは基本のキの字、いわゆる「正社員」と「契約社員(not正社員)」はどう違うのか、詳しく確認していきたいと思います。
いわゆる正社員とはどんな働き方?

冒頭でお伝えしたとおり、日本の雇用形態は終身雇用制と期間雇用性に大別されます。
終身雇用制による雇用は、「正社員」とよばれ、募集・採用選考から定年に至るまで一貫したキャリア形成が構築される、長期雇用の仕組みとなっています。正社員の特徴をまとめると下記のようになります。
- 新卒一斉採用を定期的に行うことで、企業組織の働き手を確保
- 若手社員から定年までの長期雇用が前提
- 系統立った人材教育と人事異動を実施することでキャリアを形成、発展させる
- 年齢・勤続によるキャリア形成を重視した年功賃金制・昇進制
最近では、グローバル経済のなかでの国際競争の激化や少子高齢化の流れによって、企業内の人員構成に変化がみられます。たとえば、50歳を超えると役職定年制や早期退職制、企業グループ外への出向・転籍などの対象となるケースが挙げられます。
一方で法律により高年齢者の継続雇用措置が企業には求められるので、定年の引き上げ、再雇用、勤務延長、定年の廃止といった、新たな制度構築(中高年、シニア社員の労働条件の変更設定)が課題となっています。
いわゆる契約社員(not正社員)とはどんな働き方?

市場経済において景気の波があるなか、不況で単に仕事がなくなったからという理由で、終身雇用のもとにある正社員を簡単に解雇するわけにはいかない、と考えられてきました。
とはいえ、雇用調整を図らなければ倒産の危機に陥るリスクが企業経営にはつきまといます。
正社員の長期雇用システムを補完し、雇用量の弾力調整を図るために、「雇用期間を定めた」not正社員の雇用制度が行われています。not正社員の雇用形態は、日雇い、臨時工、季節労働者、契約社員、アルバイト、嘱託社員、パートタイマーなど、さまざまなタイプがあります。
この期間の定めのある雇用契約には、下記のように2種類あります。
- 社員の労働契約期間の途中退職を禁止し、労働契約期間の勤務を強制拘束するもの(労基法第14条の適用のある労働契約期間の定めに該当する社員)
- 労働契約期間を定めていても、社員はいつでも退職できるもの(雇用量の弾力調整員としての期間雇用)
1.の場合、社員の退職禁止の効力があるため(人身拘束の弊害を排除するために)、契約期間の最長期間を原則として3年(高度専門業務と満60歳以上は5年)に制限したものです。
2.の場合、雇用期間の定めは業務量の充足を判断するためであり、つまり業務量が減少して雇用更新の必要性がなくなれば期間満了をもって雇い止めを行う雇用形態です。
社員側は雇用契約期間の途中で退職することは自由ですが、次期更新の保障はなく、その都度業務量や勤務成績などを考慮して更新していくことになります。もし、反復更新して長期にわたって続けば雇用の実態は常用化し、契約期間は形骸化してしまいます。そのため、長期間にわたって雇用期間が更新されてきた場合には、余剰人員が生じるなど特段の理由がなければ、雇い止めは会社側の権利の濫用にあたるので、注意しなければなりません。
**
少子高齢化によりこれからは、家族の介護でフルタイム勤務(正社員としての働き方)ができなくなる社員の出現が考えられます。
小規模企業のマンパワーであれば、決して小さくない打撃を受けるので、「正社員のあり方」を考える時期といえるかもしれません。限定正社員制度をとるのも方法のひとつです。
【限定正社員の例】
- 職務限定正社員(期間の定めのない労働契約であって、職務内容に制約を設けたもの)
- 勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約であって、勤務地に制約を設けたもの)
- 短時間制社員(期間の定めのない労働契約であって、労働時間に一定の限定を設けたもの)

自由な発想での人材活用の仕組みが、社員のやりがいになるだけでなく、企業のアピールポイントとなり、ひいては採用力アップにもつながることが期待できます。

■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事