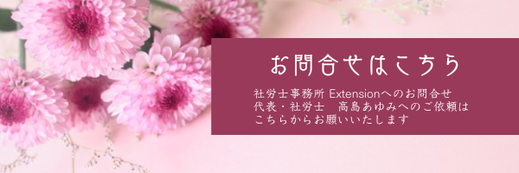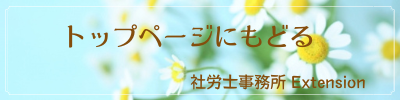「せっかくパートタイマーを正社員にしたのに、期待していたように働いてくれない。これなら、単に人件費が上がっただけ・・・(;´Д`)」
これは、自社における正社員とパートタイマーのそれぞれの定義を説明できていないために生じる問題です。
正社員とパートタイマーのように雇用形態の違いによって、社員をいくつかのグループに分ける仕組みのことを雇用区分といい、人材マネジメントの基本構造を決めることになります。
定義をきちんと説明できると、「あなたの役割はこれこれで求める成果はこうだから」と社員に対して具体的な行動を促しやすくなり、仕事がスムーズに運ぶようになります。
そこで今回は、社員に説明できる雇用区分をめざして自社における正社員とパートの役割の違いについて、詳しく確認していきたいと思います。
自社オリジナルの定義づけを

「パートさんにもっと長い時間働いてもらいたいが、社会保険加入の対象になる。だったらパートさんを正社員にしなくてはいけないですよね?」と経営者や人事担当者の方からお話しを伺うことがあります。
社会保険に加入するならば正社員に登用しなければいけない、と考えてしまうのは、「社会保険に加入=正社員」との「思い込み」があるからです。
実はこの場合、「(パートタイマーであっても)社会保険の加入基準を満たすので加入する」というだけです。
正社員やパートタイマーといった雇用区分は、法律で定義づけされているわけではありません。会社独自の基準によって、社員を区分する仕組みを考える必要があります。この仕組みが曖昧であると、連携がうまくいかないので仕事がスムーズにはかどらないことも多くなります。
「社員をどう配置しても仕事がうまく回らず、納期間際にバタバタする」
「全員が同じようなことをやっていて、仕事の進行が遅いうえに抜け・漏れがある」
「これは私の仕事じゃない、と社員同士で仕事を押し付け合っている」
また、これらのような問題や不満を抱えることにもなりかねません。社員にしても自分が活躍できるフィールドや役割、仕事の目的がよくわからないので、やる気もパフォーマンスもあがりません。では、どうすれば自社の雇用区分を明確にできるのでしょうか。
仕事をシンプルに分解してみよう

まず、いま職場にある目の前の仕事をシンプルに解体してみましょう。
今ある仕事を、すべて書き出すことからはじめます。「すべて」というところがポイントです。
たとえば「顧客対応業務」ひとつにとっても、
- 来客対応
- 電話対応
- メール対応
- 文書対応
- 営業訪問対応
- クレーム対応
などなど、時と場合によって求められる「対応」はさまざまです。ですから、ちょっとした疑問や問い合わせの返信、履歴や情報のデータ入力、ファイリング、出荷サポートなど、付随する仕事もいろいろあるはずです。
さあ、日々の業務を振り返りながらやってみましょう!
仕事を細分化するとわかること

このように、「顧客対応」「経理業務」「商品管理」などひとくくりにせず、具体的に細かく分解してみることがポイントです。
細分化することでひとつひとつの仕事がシンプルになれば、「この仕事は○○さんしかできない」と思い込んでいた属人性をなくすことができます。
仕事の流れがみえやすくなるので、誰をどこに配置して、何の仕事をまかせて、どんな役割を担当してほしいのかも明らかになってきます。
そうすれば正社員、パートタイマーのそれぞれに何を期待するのかがわかってきます。各々の役割について、現場の実態にあわせて定義づけができますし、社員にもわかりやすく説明することができます。
そうすると、社員にとっても具体的な行動に移しやすいはずです。
さらには、正社員、パートタイマーそれぞれのパフォーマンスを最大限に発揮させるには、労働時間、休日はどう設定すればよいか?と、労働条件の設定についても、きっと考えやすくなることと思います。
そして、すべての社員で仕事の情報を共有して、社員一人ひとりが仕事全体のことを考えられるようすることが大切です。そのうえで役割分担をする、ということです。
全体のことがわかっているのと、そうでないのでは社員のやる気も違ってきます。
ただ割り当てられた仕事を淡々とこなすのは、誰だってつまらないですよね('ω')。


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事