年休の買い上げ制度を廃止しても問題ないですか
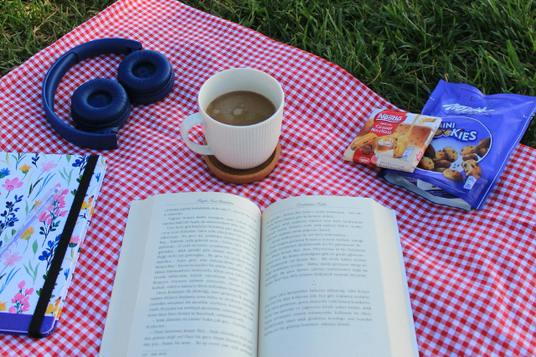
当社では、時効が成立した年休を買い上げてきた。取得しそびれてしまっている人も多かったからだ。とはいえ世の中の流れを受け、できるだけ年休を取得してもらおうと買い上げ制度を廃止することになった。今まであった制度を廃止することに、何か問題はないのかな?
**
時効成立後とはいえ、買い上げという取扱いではなく、できるだけ年休を取得させるという方向で検討を進める人事担当者さんです。
従来の制度を廃止することで、社員にとって不利益変更の問題は生じないのか?と判断に迷っています。
そこで今回は、年休の買い上げ制度の廃止に不利益変更の問題は発生しないのか、詳しく確認していきたいと思います。
来月退職の社員にも新規の年休を付与しないとダメですか
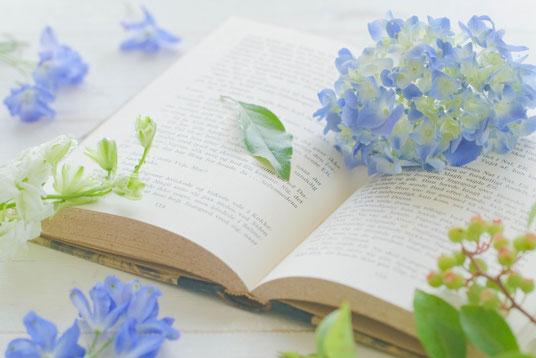
来月1日は年休付与の基準日。Aさんが来月末日で退職する予定だけど、みんなと同じく基準日に新規の年休を付与しないといけないのかな?新規分を案分して付与するのはダメなの?
**
年休付与の基準日を前に、社員のみんながこれまで取得した年休日数と残りの日数を確認している人事部員さんです。
作業中にふと、退職を来月末日に控えた社員にも、他の社員と同様に基準日に所定の年休日数を付与しなければならないのか、案分して付与するのではダメなのか、とのギモンが頭をよぎります。
そこで今回は、退職予定の社員にも基準日に新規分を付与しなければならないのか、詳しく確認していきたいと思います。
休職中の社員から産休の請求があったとき会社はどうする?

私傷病で休職中のAさんから、産前産後休業をとりたいとの申し出があった。すでに休んでいるわけだから、産前産後休業を取得するとダブらない?どうすればいいんだろう・・・
**
休職中の社員から産前産後休業を取得したいとの意向を聞いて、困惑する人事担当者さんです。
すでに休職していて労働義務のない日に重複して産前産後休業を取れるのか、そしてそれを会社として認めないといけないのか、ギモンが頭に浮かびます。
そこで今回は、私傷病で休職中の社員から産前産後休業の申請があった場合、会社はそれを認める必要があるのか、詳しく確認していきたいと思います。
社員の高齢化で治療と仕事の両立に会社はどう対応する?

世間では働き手の高齢化が進んでいると聞くが、うちも同じだ。疾病の有病率は年齢が上がるほど高くなるが、うちの休職制度では復職するには治ゆすることが前提で、入退院を繰り返したり、病気と長く付き合っていくため通院が必要なケースなどに対応しきれていない。会社として早く対応を考えないと・・・
**
職場の高齢化に伴って、様々な健康問題に対応しなければならないので頭を悩ます人事担当者さん。治療と仕事の両立への対応が必要な場面は、ますます増えることが予想されるからです。
重大な治療を伴う疾患については、メンタルヘルス不全を前提とした休職期間(3~6か月)では対応しきれない可能性があります。このような問題に対して「年休の積立制度」を運用するのもひとつの方法です。
そこで今回は、年休の積立制度の概要とともに、治療と仕事の両立に会社はどう対応するべきなのか、詳しく確認していきたいと思います。
産休と育休の間の年休申請を認めないとダメですか

産休明けのAさんから年休申請があった。しばらくしたら育休をとりたいらしいし、いっそのこと育休に入るのを早めたらいいんじゃないのかな。本人の意思を尊重して年休申請を認めないとダメなの?
**
産休と育休の間に年休をとるより、育休の開始を早めたほうが年休の日数を温存できるので、これからの子育てにおいて、子どもの急な発熱や通院などに対応しやすいのでは・・・と気を回してヤキモキする人事部のBさんです。
そこで今回は、会社は「年休より育休の開始を早めてほしい」との理由で、産休と育休の間の年休申請を断ることができるのか、詳しく確認していきたいと思います。
フリーランスを直接雇用にすると年休付与はどうなる?

フリーランスとして来てもらっているAさん、来月からうちでの直接雇用に切り替えて働いてもらうことになった。・・・そういえば年休はどうなるんだろう?
**
フリーランスとして業務を行う人(業務委託契約)を自社で直接雇用するにあたって、本人の直属の上司から相談を受けた人事担当者ですが、初めてのケースで返答に困っています。
というのも会社に入社した後、最初に年次有給休暇の権利が発生するのは、入社日から6か月間継続して勤務した場合ですが、この「勤続6か月」とはどの時点から起算すればいいのか、フリーランスで来てもらった時からなの・・・?とギモンに思ったからです。
そこで今回は、フリーランスを自社の直接雇用にシフトした場合の年休付与について、詳しく確認していきたいと思います。
職場に時間単位年休を導入しようか迷っています

子育て社員のことを考えると、学校行事の参加とか時間単位年休があると便利よね。通院とか家族の付き添いをしやすいよね・・・とはいえ、うちは一斉でやる作業が必要だから業務的になじまない点があるし、導入して職場が回らなくなっては本末転倒だし・・・
**
社員の抱える色々な事情に応じて、柔軟に休暇を取得できるよう時間単位年休の制度があります。そこで制度の導入に魅力を感じながらも現場の運営を考えると、判断に迷ってしまう人事担当者さんです。
とはいえ、企業全体ではなくたとえばある営業所や支店のみ時間単位年休を導入することも可能だったりしますし、自社にフィットした選択を柔軟に考えられるといいですよね。
そこで今回は、(意外と知られていない?)時間単位年休の取り扱いについて詳しく確認していきたいと思います。
年休の発生要件の算定で出勤停止の期間はどうするの?

次年度の年休付与にあたって、そろそろ出勤率を算定しないといけない時季だなあ。そういえばAさん、出勤停止処分を受けていたけれど、この期間ってどう取扱えばいいんだろう?
**
次年度の年休付与の要件には、前1年間における「全労働日の8割以上の出勤率」があります。
そのため、会社としてはこの出勤率を算定するにあたって、出勤とみなされる日、全労働日から除外される日をきちんと把握しておく必要があります。(出勤率が8割を切ると次年度の年休付与がゼロになってしまいますから大事なミッションなのです)。
とはいえ、出勤停止期間を取り扱うことが過去になかったため、面食らう人事担当者さんです。
そこで今回は、年休の発生要件にかかる出勤率の算定で出勤停止期間をどのように取り扱うのか、詳しく確認していきたいと思います。
年休から生理休暇への振替を会社は認めないといけないの?

生理休暇は法律上無給でも問題ないとのことだけど、有給扱いにしようかとの案が社内で出ている。でも、事後に「年休取得日を生理休暇に振替えてほしい」との申出が社員からあったとしたら、会社はそれに応じないといけないのかな?
**
生理休暇の有給化にあたって、もし年休から生理休暇への事後振替を認めることになれば、「3日間の年休中に生理日が来たので振替えてほしい」といった申出にも応じないといけない・・・少し違和感を覚えて、心配になってしまう人事担当者さんです。
そこで今回は、あらかじめ年休日になっていた日でも事後申請で生理休暇に振替えないといけないのか、詳しく確認していきたいと思います。
臨時休業の日に年休申請があったらどうすればいいの?

先日の雨で店舗の屋根が経年劣化していることが判明。1日だけ臨時休業して修理することになった。社員には休業手当を支払う予定だけど、その日に年休を申請している人がいる。別の日に年休日を変えてもらったほうがいいのかな? (カフェオーナー 談)
**
お店が臨時休業の日にあえて年休をとっても仕方がない、社員にとって勿体ないんじゃないか?と気をもむオーナーです。
あらかじめ年休が申請されていた日に臨時休業することになった場合、会社として年休の時季変更権を行使できるのか、というのがこのお悩みのキモとなります。
そこで今回は、休業とした日に事前に年休申請が出されていた場合、会社としてどう対応するべきか、詳しく確認していきたいと思います。
会社はよく休む人にも5日の年休を取得させる義務があるの?

「社内には年休をよく取る人もいれば、ほとんど取らない人も。よく休む人にも5日の年休を取らせる義務が会社にはあるんだっけ?“基準日から1年ごとに5日取得させる”って、4月1日入社だといつから1年になるの??」
人事部に異動してきたBさん、先輩の指示で社内の年休の取得状況をチェック中ですが、疑問が浮かんできては作業の手が止まります。
労基法の改正で会社に年休の5日付与義務が課されることになりましたが、Bさんのようにふとギモンを覚えることはありませんか。
そこで今回は、下記の2点を詳しく確認していきたいと思います。
- よく休む人にも5日の年休を取得させる義務があるの?
- 基準日から1年ごとに5日取得ってどういうこと?
トラブル発生で退職日まで年休消化中の社員を呼び出せますか
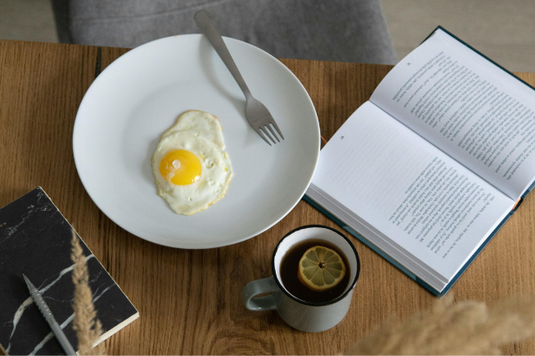
先ほどAさんが担当の取引先から苦情の電話があった。本人は月末に退職するので今は残りの年休を消化中、退職日まで出社してこない。後任のBさんに聞いても引継ぎが曖昧だったようで対応できない。年休中のAさんを呼び出すのはコンプライアンス的にマズイのだろうか・・・
**
トラブル対応のため、退職予定で年休消化中の社員に出社を求めたいものの、「退職日が近いのに年休を消化できないなんて権利侵害だ!」との反応だったら・・・と迷ってしまう上司。
確かに、退職予定日以降に年休を与えることはできませんし、退職日が迫っているのでは時季変更権の行使もできません。では、トラブル真っ只中の顧客対応はどうすれば・・・(;´Д`)
そこで今回は、退職予定で年休消化中の社員を出社させていいのか、詳しく確認していきたいと思います。
最短で産後復帰したワーママからの年休申請に会社はどうする?

産後8週間よりも前に仕事に復帰したい、と医師の診断付きでママ社員からの申出。家族の協力もあるので、年休を利用しながらやっていきたいとのこと。最短で職場復帰したい社員を会社としても応援したいが、本来ならまだ産後休業中なのに年休って取れるものなのかな?
**
産後復帰について相談を受けたワーママの上司ですが、産後休業と年休の扱いについて判断に迷っています。
本来なら産後8週間を経過しない女性は就業禁止となっている(産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が差し支えないと認めた業務に限って就業可能)ので、年休を申請する余地があるのか?との疑問があるからです。
そこで今回は、産後6週間経過で職場復帰したときの年休申請の扱いについて、詳しく確認していきたいと思います。
半休や時間休を年休の5日付与義務にカウントしてもいいですか

年度末が近いので、部員には5日以上の年休を確実に取ってもらわないといけない。だが風邪、コロナ、インフルエンザでダウンする人が出て人手が足りずに、休んでほしい人に休んでもらいにくい状況だ。半休か毎日1時間ずつ時間休を取ってもらって、年休取得5日以上にもっていくか・・・?(とある商社の営業部長談)
**
会社には、年10日以上の年次有給休暇が付与される社員に対して、年休日数のうち年5日の年休を取得させることが義務付けられています。
そのため上司としては5日以上に至っていない社員の年休取得と、業務の進捗具合の間で「半休と時間休が5日付与義務にカウントされるならなんとかなるかも?」と焦っています。
そこで今回は、そもそもの半休と時間休の取扱いの違いと、半休と時間休が年休の5日付与義務にカウントされるのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
年末年始休暇は年休の5日付与義務にカウントされますか

休職していたAさんが10月から復職することになった。今年度の残り6か月でAさんにも5日以上の年休を確実に取得してもらわなければならない。とはいえ、年末年始休暇もあるし、2月はもともと営業日が少ないし・・・大丈夫だろうか?
**
会社には、年10日以上の年次有給休暇が付与される社員に対して、年休日数のうち年5日の年休を取得させることが義務付けられています。
そのため、上司としては年度途中で復職したAさんの年休取得が心配で、「年末年始休暇が5日付与義務にカウントされるならひとまず安心なのに・・・」とひやひやしています。
そこで今回は、年度途中で復職した社員の年休の取扱いと、年末年始休暇をはじめ特別休暇が年休の5日付与義務にカウントされるのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
計画年休日に年休の足りない社員を会社はどうする?

「来週の金曜日は計画年休日なのに、欠勤が多いBさんには年休がもうないらしい。Bさんだけ出勤させるのもビミョーだしなあ・・・」
年休の「計画的付与」とは、社員のプライベートな事情で自由に取得できるよう一定の日数を保持しながら、これを超える日数については、会社と社員の間での労使協定によって計画的付与を認めることにしたものです。
年休の計画的付与制度を実施する場合に問題なのは、計画年休の日数分の年休がない社員がいる場合にどうするかです。
その社員の年休日数を増やせば簡単なのもしれませんが、職場のなかでちょっとした不公平感が漂うのもまた事実・・・
そこで今回は、計画年休にあてる年休日数のない社員に会社はどのように対応するべきなのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
仕事の合間に半休を取ってはダメですか

「うちの会社の午後休は4時間分だから、10時から3時までの4時間を午後休として休んでもいいですよね?」
午後半休が午後1時から5時までの4時間なのだとしたら、4時間単位をもって半日(0.5日)とするべきで、午前10時から午後3時までの4時間でも半日単位として取り扱っても問題ないでしょ?・・・というのがこの言い分の趣旨です。
半休(半日単位年休)は法律上の制度ではありません。そのため、社内で「半日単位」をどのように扱い、半休制度をどう運用していくのかをきちんと決めておくことが、社員に誤解を与えないためにも重要になってきます。
そこで今回は、「半日単位」の取扱いと半休制度の運用ポイントについて詳しく確認していきたいと思います。
午前10時で早退しても出勤日の扱いになるの?

病気の治療で通院するため、欠勤や早退の多い社員がいる。早退した日を出勤日にしたらいいという声が社内であるが、午前10時に早退した日なんかは1時間しか勤務していないのにどうなのか、という声もある。どう対応しようか・・・
**
労基法では、年休取得の要件を「所定期間内の全労働日における8割以上の出勤率」としています。そのため、出勤率が8割を切ると次年度の年休付与がゼロになってしまい、通院が難しくなるのではないか・・・と心配する人事担当者さん。
とはいえ、早退で1時間しか勤務していない日でも出勤したものとして、出勤率に含めてもいいのか、と判断に迷われるのもわかります。
そこで今回は、年休の発生要件である出勤率に午前10時で早退した日を含めてもいいのか、について確認していきたいと思います。
年休日に組合活動をしていた社員、会社はどう対応する?

「社員が年休日に出社していたことが判明しました。組合活動のたまった事務を片付けるためだったようですが、この日は年休日として扱っても大丈夫ですか?」
会社は、年10日以上の年次有給休暇が付与される社員に対して、年休日数のうち年5日の年休を取得させなければなりません。
そのため、会社としては積極的に年休を消化させたいけれど、「出社していたのに年休日として成立するの?」と疑問に思われたようです。
結論からお伝えすると、取得した年休をどのように利用するかは社員の自由なので、年休日として成立します。ですが年休日の組合活動に対して、会社として注意すべき点もあります。
そこで今回は、年休を取得して組合活動を行う社員への会社の対応について、詳しく確認していきたいと思います。
30分の遅刻を時間休でチャラにしたい社員にどう対応する?

「遅刻常習犯の社員が、つい先日も30分遅刻してきました。1時間の年休(時間休)を取得して遅刻と差し引きゼロにしてほしい、と言ってきましたが、会社として聞き入れないといけませんか?」
あまりに遅刻が度重なるとボーナスの査定に響くから・・・というのが、どうやら社員のホンネのようです。
とはいえ上司や人事担当者としては、遅刻をあとで年休に振り替えることが適法なのか、という点をまずは押さえておきたいところでしょうし、また周囲に与える影響(モラルハザードが生じるなど)も気がかりではないでしょうか。
そこで今回は、遅刻を年休でチャラにしたい(年休充当したい)社員への会社の対応について、詳しく確認していきたいと思います。
当日になって会社が社員の休みを取り消してもいいですか
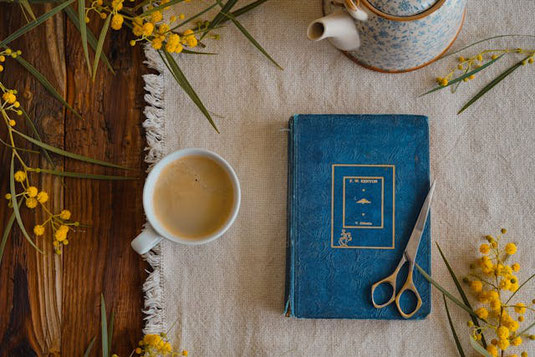
「取引先から緊急の要請があったときに担当者が休みだったら、会社に呼び出しても問題ありませんか?」
昭和の時代なら「そんなん企業戦士として当たり前や!!」と片付く案件だったかもしれませんが、令和の時代ではコンプライアンスやモラルの意識が高まり、対応に悩まれることも多いようです。
問題は、すでに年休日が開始している(午前0時以降)のに、社員を呼び出したい案件(年休の取り消し事由)が発生した点です。
その日になって、すでに年休日としてスタートしているのに一方的に取り消すことは労基法違反となるからですが、取引先の期待にも応えたい・・・どうすれば・・・(一一")
そこで今回は、突発的な案件が発生した場合の年休取り消しの問題に会社としてどのように対応すべきなのか詳しく確認していきたいと思います。
育休中の社員に年休は付与されますか?

「当社ではもうすぐ年休の起算日がやってきます。育児休業中の社員がいるのですが、新規分の年休は発生するのでしょうか?それなら、育休中でも年休が取れるということですか?」
年度末に向けて、職場のメンバーの年次有給休暇の取得状況を正確に把握しようと、管理簿と向き合っている人事総務部の方もいらっしゃるでしょう。
育児休業中の社員について、年休の扱いをどのようにすればいいのか?と疑問に思われた担当者の方からご相談をいただくことがあります。
そこで今回は、そもそもの年次有給休暇の付与要件を確認するとともに、育児休業と年休の関係について、くわしく確認していきたいと思います。
定年で再雇用、正社員時代の年休の残日数はどうなるの?
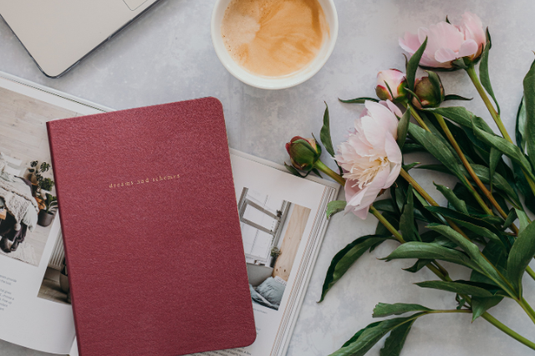
定年を迎えたAさんは再雇用制度でパート社員として働くことになっている。正社員時代の未消化の年休は繰り越さないでリセットするんだよね、新しい労働契約になるんだし・・・?(新人の人事担当者談)
**
定年退職者をパート社員や嘱託社員として再雇用した場合、未消化の年休についてどのように対応すればいいのか・・・
正社員時代の労働契約と再雇用後の労働契約は形式的には別のものなので、年休の扱いに迷ってしまう担当者さんです。
ズバリ、判断のポイントは「継続勤務なのかどうか?」です。
そこで今回は、定年後の再雇用者にまつわる正社員時代の未消化の年休をどう取扱うべきなのか、詳しく確認していきたいと思います。
会社の創立記念日と日曜日、どちらの休日が優先される?

「来年のカレンダーを確認すると、当社の創立記念日と日曜日がかぶっています。こんな場合、どっちの休みになるのでしょうか。祝日のように振替えないとダメでしょうか?」
次年度の年間カレンダー(会社の営業日)を考えるにあたって、このようなご相談をいただくことがあります。
毎週日曜日を労基法上の休日と定めている場合、その日と創立記念日のような特別休日が重複した場合、その日は法定休日になるのか、それとも特別休日なのか、疑問に思われるのは当然のことだと思います。
そこで今回は、特別休暇(創立記念日など)と労基法上の休日が重なった場合、どちらが優先されるのか、詳しく確認していきたいと思います。
半日単位年休を午前のみ取れることにしてもいいですか

うちの会社では午前と午後の営業時間が違うので、それに合わせて半日休を設定している。午前のほうが短いから「午前休は午後半休より損」との声もあるが「家族の通院の付き添いで午前休は助かる」との声もあり、いっそのこと半休は午前休だけにしようか?
**
年休を取得しやすい環境を整えようとする経営者や人事担当者からご相談をいただきます。
なかでも、半日単位年休は「日単位年休」のなかでの任意の制度なので、どこまで自由に運用を決めてもよいのか?と、判断に迷われるケースは多いようです。
そこで今回は、半日単位年休の取得を午前中に限定してもよいのかどうかについて、詳しく確認していきたいと思います。
一方的に代休をとりたいと主張する社員と会社の対応

繁忙期のため休日出勤を担当部署に伝えると「その代わり代休をとります」と社員からの返答が。うちでは代休の前例がありませんが「フツーは休みの日に出勤すれば代休ってとれますよね?」とのこと。
彼は中途入社の社員で、以前勤めていた会社では代休制度があったそうです。周りの社員も「代休がないうちの会社って変なの?」とザワついて対応に困ってしまいました。
(※ここでの「休日出勤」とは、法律上の休日労働のことをいいます)
**
休日労働と代休をめぐる社内の問題、よく伺います。労基法では代休についての規定はなく、代休を付与するかは企業の自由なのですが、「会社の義務」と誤解されているケースは多いようです。
そこで今回は、社員は一方的に代休とることができて、会社はそれに応じないといけないのかについて詳しく確認していきたいと思います。
病欠を必ず年休に振り替えないとダメですか

当日の朝の電話で欠勤した社員。あとで「年休で処理してください」と言ってくる。毎回「病気なんだから当然でしょ」といった態度がなんだかなあ。仕事の段取りをつけて計画的に年休をとる人との差が・・・。会社として病欠を必ず年休に振り替えないといけないもの?
**
こういった年休取得にまつわるお悩みを、企業の人事担当の方からよくご相談いただきます。ご相談のキモは「病気による欠勤日を後日年休に振り替えることができるのか」ということです。
法定の年休を社員が権利として取得できるのは、あくまでも事前請求が要件となっているからです(事前とは前日の終業時刻より前ということです)。
そこで今回は、社員は当然の権利として欠勤日を後日年休に振り替えることができるのか、そして会社は後日の年休振替を行わないといけないのか、確認していきたいと思います。
休暇の取得ルールは会社が勝手に決めていいですか

「部署間で休暇の取りやすさが違うのは不公平なので、休暇の取得ルールを全社的に統一したい。・・・ルールは会社が一方的に決めてもいいのかな?(社員の意見を聴かないで不利益にならないのかな?)」
回答としては、「会社休暇についてはOKですが、法定年次有給休暇については法律で規制があるので何もかも自由に決めてはダメです」となります。法定休暇と会社休暇では、法律上の取扱いなどで大きな差異があるからです。
なお、法定休暇とは法律で付与義務が定められているもので、会社休暇とは法定休暇以外に就業規則で自由に設定したものをいいます。
そこで今回は、法定休暇と会社休暇の違いに触れながら、会社休暇についてどのくらい“自由に(勝手に)”ルールを決めてよいのかについて詳しく確認していきたいと思います。
夜勤を1回休むと何日分の年休にあたりますか?

「シフトで夜勤にあたっている社員が急な事情で休みになった。夜勤は午後9時30分に出勤して翌日の午前6時まで。・・・何日分の年休をつかうことになるのかな?(-.-)」
昼と夜がひっくりかえった交替制のシフト勤務は2暦日をまたぐことになります。ということは2日分の年休をつかうの?昼間の勤務と同じ実働7時間30分の勤務なのに不公平では?・・・というお悩みです。
労働時間と年次有給休暇では、同じ「1日」という概念であっても、それぞれ考え方や取扱いが異なります。前者の「1日」は労働時間の長さを計る基準であり、後者は社員に与える休息時間の単位だからです。
そこで今回は、ややこしくなりがちなシフト勤務制で年休日の取得単位をどう考えるべきなのかについて詳しく確認していきたいと思います。
部下からの年休申請でリーダーがとるべき対応とは

チームメンバーが「休みたい」と言ってきたらどう対応をするといいのかな?自分の対応次第で年休の取りやすさに差が出ると不公平だし、法律的にやったらダメなこととかきちんと押さえておきたい。
(エンジニア リーダー職 談)
**
パワハラ、コンプライアンス・・・みんなが敏感なご時世なので、きちんと法律面の知識を持っておきたいリーダーです。
というのも、「こんな忙しいときに年休を取りたいの?!(゚Д゚;)」と納期とマンパワーの間で、(どこまで年休申請を認めないといけないの?)と、顔がひきつることもままあるからです。
そこで今回は、メンバー(部下)から年次有給休暇の申請があったとき、リーダー(所属長)をはじめ、その承認の権限をもつ管理職はどう取り扱うべきなのか、詳しく確認していきたいと思います。
時間単位年休の導入には〇〇〇〇をお忘れなく

社員の年休取得率が思っていたより進まない( ;∀;)年休を取得しやすくするために時間単位年休を導入してみようか。注意点はあるのかな?
(素材メーカー勤務 人事担当者談)
**
結論からお伝えすると、時間単位年休の導入にあたって、まず押さえておくべきはその導入要件についてです。
これを踏まえないで、たとえ会社が「これからは時間単位年休を取ってもいいですよ」と社員に認めたとしても、そもそも導入の根拠がないので、法律的には年次有給休暇の取得として扱われないからです。
そこで今回は、時間単位年休を職場へ導入する際にはずすとマズイ、導入要件とはいったい何なのか、詳しく確認していきたいと思います。
社員が裁判員で休むとき年休扱いにしてもいいですか

「社員が裁判員として裁判に参加する場合、年休扱いにするとダメなのかな?('◇')ゞ」
会社には、年10日以上の年次有給休暇が付与される社員に対して、年休日数のうち年5日の年休を取得させることが義務付けられています。会社としては積極的に年休を消化させたいので、冒頭のようなギモンをお持ちの人事担当者の方もいらっしゃるかもしれません。
裁判員の仕事は国民に課せられた公の職務にあたるので、労基法の定めにより、その職務を全うするために必要な時間について、会社は社員の労働を公民権行使の保障として免除しなければなりません。
とはいえ、会社として有給の休暇とする必要があるかは別の問題です。
そこで今回は、社員が裁判員として裁判に参加するとき、年休との兼ね合いを会社としてどう扱うべきか、詳しく確認していきたいと思います。
出勤率8割で年休発生―休んでも出勤扱いになるのはどんな日?

「Aちゃんの会社では生理休暇で休んだ日は出勤扱いにならないそうだけど、うちの会社ではどうなんだろう?」
労基法では、所定期間内の全労働日における8割以上の出勤率を年休取得の要件としています。
そのため、会社としては法律上の年休付与の出勤率を計算するにあたって、出勤とみなされる日、全労働日から除外される日をきちんと把握しておく必要があります(冒頭のような質問が社員からあるかも)。
たとえば生理休暇で休んだ期間について、労基法上では出勤したものとはみなされませんが、会社と社員の合意によって出勤したものとみなすことは差し支えありません。
そこで今回は、法律上の年休計算にあたって出勤とみなされる日とはどんな日なのか、詳しく確認していきたいと思います。
急な納期変更やトラブル発生で計画年休日を変更できますか

「突然の納期変更や機械トラブルがあったとき、計画年休日が目前にあると対応できない。そんなとき計画年休日を変更できるの?」
年休の「計画的付与」とは、社員が私的な理由で自由に取得できるよう一定の日数を留保しながら、これを超える日数については、会社と社員の間での労使協定によって計画的付与を認めることとしたものです。
年休取得率をアップさせるための制度とはいえ、業務上の突発的な出来事と計画年休日が重なってしまうような事態を考えると、とても悩ましいですよね。
そこで今回は、会社が計画年休日を変更することは認められるのか、詳しく確認していきたいと思います。
年休の買い上げが有効になるとき、ダメなとき

「社員も喜ぶので会社が年休を買い上げたいのですが、法律的にダメなんですか?」
年休の買い上げとは、社員が取得できなかった年休の残日数を会社が一定の金銭で買い取り、行使できなかった年休請求権(年休の残日数)に応じて、会社が補償的な取扱いをすることです。
ただ、年休はそもそも社員の心身の疲労を回復させ、働くためのモチベーションを支えることを目的としています。年休と金銭をバーターにしては、心身の休養と疲労回復は果たせません。
そのため労基法では買い上げによって年休を実際に与えない行為を禁止しているのですが、実は年休の買い上げが有効となる場合もあります。
そこで今回は、年休の買い上げがどんなときに有効になって、法律的にアウトになるのか、詳しくみていきたいと思います。
当日の電話での年休請求をどう取り扱う?

始業前に「今日は休みます」と電話があったら、どうすればいいの?事前申請の人もいるのに不公平じゃないの?(総務部の新人談)
**
実は、法定の年次有給休暇の取得は、「この日に休暇をとりたい」いう社員の意思表示だけで成立するので、年休日を決めてその旨を伝えれば会社の承認は必要としません。
会社の時季変更権の行使がない限りそのまま休んでもよいわけですが、社員の権利を主張できるのは、あくまでも事前に年休申請があったときの話です。
問題は、冒頭のように当日に「休みたい」と電話があった場合です。当日の申請は、法的には事前申請ではなく事後申請になるからです。
そこで今回は、当日の朝になって「休みたい」との電話があったとき、年休の取扱いをどうすればよいか詳しく確認していきたいと思います。
時間単位年休の取得をどのように記録管理すればいいですか

「社員が時間単位年休を取得すると、年休の残日数をどんなかんじで年休管理簿に記録していくといいのかな?(+_+)」(人事担当者談)
新型コロナウィルスの影響もあり、職場での柔軟な働き方を検討していかなければならない状況です。取得状況の記録がややこしいから、という理由で時間単位年休の導入をためらうなら勿体ないと思います。
たしかに、職場に時間単位年休制度を採り入れた場合、年休管理の記録簿の取扱いは、今までのように「年度当初の残日数-取得日数=残日数」というわけにはいきません。
日単位での取得分と時間単位での取得分が入り混じることで従来のように単純ではなくなるので注意を払う必要があります。
そこで今回は、時間単位と日単位年休の管理をどのように管理するといいのか、詳しく確認していきたいと思います。
フレックスタイム社員の年休管理できていますか?

「フレックスタイム社員に、実際に働いた時間が清算期間中の総労働時間に足りない者がいます。年休を取得したことにして、総労働時間に足りない分を穴埋めすることはできますか?」
法改正があったためか、フレックスタイム社員の年休管理についてご相談をいただきます。年10日以上の年次有給休暇が付与される社員に対して、年休日数のうち年5日の年休を取得させることが会社に義務付けられました。
ご相談のキモは、フレックスタイム制で実際に労働した時間が、清算期間における総労働時間として決められた時間と比べて不足があった場合に、年休でその足りない時間をチャラにできるのか?ということです。
そこで今回は、フレックスタイム社員の足りない労働時間を年休で穴埋めできるのか、年休管理について詳しく確認していきたいと思います。
辞める社員の年休請求は認めなくてもいいですか

春といえば旅立ちのシーズンですが、年休の日数がたくさん残っている社員が年度末に退職することになったとします。
年度末の忙しさで退職前に年休をとることができなかった場合、その社員の年休請求権はどうなるのでしょうか。
年休は原則として社員の希望通りに与えなければなりませんが、退職予定者の場合には、年休の残日数があっても退職日を迎えると行使することができません。
退職予定の社員には「年休申請があっても年休を与えなくてもいいのでは?」と思われることもあるかもしれません(←ちゃんと理由があるので後述しますね)が、法律面をクリアにしておきたいですよね。
そこで今回は、退職予定者の年休請求について会社がとるべきについて、詳しく確認していきたいと思います。
どんなときなら年休の時季変更権をつかえますか

現場のリーダー社員が、どんなときなら時季変更権をつかっていいのか?と悩んでいる。みんなの希望を聞き入れると、その分フォローするリーダーの負担になっているようだ。なんとかしてあげないと・・・
(メーカー勤務 総務部長 談)
会社に認められた年休の時季変更権はいつでも行使できるものではありません。年休付与は社員の希望通りに、というのが原則だからです。時季変更権は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限定して認められますが、「事業の正常な運営を妨げる場合」とはどんな場合でしょうか。
年休取得の義務化の流れから、マネジメントの負担増に悩む管理職のために具体例を示してあげたいところですよね。
そこで今回は、時季変更権の行使が認められる「事業の正常な運営を妨げる場合」の具体例について、詳しく確認していきたいと思います。
法律で決められた年休と会社が決めた休暇はどう違うの?

休暇とは、労働義務のある日に「働かなくていいですよ」と就労義務が免除された日のことです。このような休暇は、「法定休暇」と「会社休暇」の2パターンに区別されます。
法定休暇は、法律で社員に必ず付与しなければならないと決められたもので、年次有給休暇や産前・産後休暇などがあります。
会社休暇は、就業規則などに定められることによってはじめて成立する、その会社オリジナルのものです。たとえば冠婚葬祭のための慶弔休暇や、勤続年数の節目に与えるリフレッシュ休暇などが挙げられます。
この法定休暇と会社休暇は、休暇が発生する要件や法律上の効果がそれぞれ異なっています。
そこで今回は、日常のオフィスで「どう違うの?」と問題になる、法定の年次有給休暇と会社休暇の違いを詳しく確認していきたいと思います。
年休を消化してから産前休暇に入るのはダメですか

社員「12/10から産前休暇ですが、あるだけの年休を12/10から消化して、そのあとで産前休暇に入りたいのですが・・・」
上司「・・・(産後復帰後のために年休を残しておいたほうが・・・年休より産前休暇を優先してほしい(;´Д`))←心の声」
**
労基法では、産前産後休暇中における賃金について有給とすべきことを義務付けていません。その取扱いは当事者間の自由にゆだねられ、就業規則に有給の定めがない限り無給になります(ただし健康保険による出産手当金が支給されます)。
生活に影響を与えるため、冒頭のように「産前休暇の一部を年休に替えたい」との申出も少なからずあるようです。
そこで今回は、「年休を消化してから産前休暇に入りたい(産前休暇の一部を年休に替えたい)」との社員の申出に会社としてどう対応すべきか、詳しく確認していきたいと思います。
正規の申請をしないで休んだ社員にとるべき対応とは

【人事担当者のよくある悩み】
うちの会社では、年休申請書をを直属の上司に提出することになっている。各部署から人事部に申請書が集約されて、社員それぞれの年休日数を管理している。
ところが、ある部署でこの正規の申請をしないで休んだ社員がいる。直属の上司には口頭で翌日休むことを伝えたそうだが、「用紙を提出しなさい」との上司の注意を無視して、当日休んだらしい。日頃からルーズな社員のようで、上司は「無断欠勤の処理にすべし!!」とお怒りだ。
正規の手続きで人事部に情報が届かなければ、勤怠管理でミスして給料計算にも影響が出てしまう。だからといって、ペナルティーとして無断欠勤にしてしまうのもやりすぎでは?
**
今回は、このように正規の申請手続きをしないで休んだ社員に、会社としてどのように対応するべきなのか、詳しく確認していきましょう。
同じ休みでも休日・休暇・休憩はどう違うの?

梅雨の時期は、休日でも外出せずに家のなかでのお楽しみタイムが増えます。しとしと雨音に耳を傾けながら、DVDや音楽鑑賞、読書など趣味の時間を過ごすのもいいですよね。
そんな休日について、「休日と年次有給休暇はどう違うの?」というギモンがふと浮かぶことはないでしょうか。「仕事を休む」という行為では、休日と休暇も同じですし、仕事中の休憩時間についても「仕事を休む」という意味ではいっしょです。
これらの本来の意味合いは、実は、まったく違うものですが、たとえばお休みの日が人ごと、週ごとに異なるといったシフト制をとっている職場では、これらの管理が煩雑になりがちではないでしょうか。
ですが、万が一混同してしまうと(特に休日と休暇)、会社の年間休日数をミスカウントしてしまうおそれがあるので、うっかりミスは防がなければなりません。
そこで今回は、休日、休暇、休憩はそれぞれどのように違うのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
休まない社員を強制的に休ませてもいいですか

A君はものづくりが心底好きで現場の仕事を愛している。ゆえにめったに年休をとらない。ちゃんと休んで、と伝えても出社してきそう・・・
**
この春から、会社には社員に少なくとも年5日の年休を取得させることが義務付けられていますが、休まない部下に頭を悩ます上司の方もいらっしゃるかもしれません。
GW明けの職場では仕事の再開にエンジンをかける人、まだ休んでいたいと思う人、もう夏休みに向けて仕事のダンドリを始める人・・・いろんな人がいて、休みに対する考え方も多様性に富んでいます。
とはいえ、まったく休みを取らないのでは健康状態やモチベーションの維持といった面で会社としては心配になりますよね。
そこで今回は、休まない社員を強制的に休ませてもいいのか?について詳しくみていきたいと思います。
会社を欠勤したとき年休を消化するルールにしてもいいですか

「社員が体調不良や家族の事情で、前もって年休申請ができずに欠勤することになったとき、欠勤日を自動的に年休日にして年休を消化する、というルールにしてはダメですか?」
この4月からすべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される社員に対して、年休日数のうち年5日の年休を取得させることが会社に義務付けられています。
ただでさえ週休二日制で会社の営業日が少ないなか、年休の消化をこれ以上進めるのは難しい・・・と悩みを抱える職場も少なくないようで、冒頭のようなご相談をいただくことがあります。
そこで今回は、欠勤日を自動的に年休とすることは法的に認められるのか?について詳しく確認していきたいと思います。
労働時間・休日・休暇の1日はイコールではない

最近は日の入り時刻が遅くなり、18時を過ぎてもまだ明るいですね。日(昼)が長くなるにつれて、季節が夏に変わっていくのを感じます。
日といえば、労働時間、休日、年次有給休暇では、同じ「1日」という概念であっても、それぞれ考え方や取扱いが異なることをご存知でしょうか。
もともと勤務シフトに夜間勤務がある場合や、トラブルシューティングのため徹夜勤務が発生した場合など、この「1日」をどう考えるかで社員の働き方が変わってくるのでマネジメント上注意が必要です。
今回は、労基法の「1日」の概念と、労働時間、休日、休暇それぞれの取扱いについてみていきましょう。
半日単位年休をうまく活用するコツ

みなさんの会社では、半日単位年休の制度をじょうずに運用されているでしょうか。
半日単位年休の存在自体を知らないというケースに意外と多く出会いますし、半日単位年休と時間単位年休の違いがわからない、といったこともよくお聞きします。
後で詳しくお伝えしますが、時間単位年休は法律上の年休制度ですが、半日単位年休は法律上の制度ではありません。 そのため両者をちゃんと区別する必要はありますが、年休取得に関する選択肢の幅が広がります。
そこで今回は、半日他に年休にまつわる次の3点について詳しく確認していきたいと思います。
- 半日単位年休と時間単位年休の違い
- 半日単位年休の取扱い
- 就業規則で定める半日単位年休の活用法
時間単位年休を仕事の合間や遅刻の穴埋めに使ってもいいですか

「時間単位年休を仕事の合間にとったり、遅刻したときの穴埋めに使っていいですか?」と部下からの質問。仕事の合間に職場を出たり入ったりするとセキュリティに問題が出そう。遅刻の穴埋めに年休を使えるなら職場のモラルが低下しそうで心配(;´Д`) (営業部の課長談)
**
年次有給休暇は、もともと日単位による取得しか認められていませんでしたが、平成22年4月1日施行の改正労基法によって、労使協定による時間単位の年次有給休暇制度が新しく認められました。
制度のスタートから10年近く経ちますが、導入にためらうケースもみられます。問題点は次の2点に集約できますが、今回はこれらについて詳しく確認していきたいと思います。
- 時間単位年休を仕事の合間でとることを制限できるのか
- 時間単位年休を遅刻に充当しなければならないか
年休の時季変更権はどんなとき、いつまでに行うのか

「えっ、こんな忙しいときに年休とりたい?!繁忙期は年休を別の日に替えてもらってもOKだとは聞くけど、ホントにいいのかな・・・」
年休の時季変更権をどんなときなら使ってもよくて、またいつまでに使わないといけないのか、と悩む上司の方は多いようです。部下のせっかくの休みを邪魔してはいけない、との思いがあるからですね。年末年始は、年休の申請件数も増える時期でしょう。
「事業の正常な運営を妨げる事由」があるときには、その日でない日を年休とするように指示する、会社の時季変更権の行使が認められていまが、「事業の正常な運営を妨げる事由」については、個別の具体的な状況において客観的に判断する必要があります。
そこで今回は、年休の時季変更権をどんなときに行使すれば正当と認められ、またいつまでに行使するとよいのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
年5日休むため会社と社員でやるべきこと、捨てること

法改正で年10日以上の年次有給休暇が付与される社員に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、会社が時季を指定して取得させることが必要となりました。
来年(2019年)4月からすべての企業において実施となり、中小企業も例外ではありません。
とはいえ「休むと仕事が回らない」「休めば納期に間に合わない」「休んだ分だけチャンスを逃す」との声があるかもしれません。
年休取得への不安感を捨て、休みながらも今までと変わらないもしくはそれ以上の結果を出すには、会社と社員の双方が意識を変えていく必要があります。
そこで今回は、年5日以上休むため会社と社員でやるべきこと、反対にやらずに捨てることについて詳しく確認していきたいと思います。
取れなかった年休への対応策―年休の積立制度とは

「当社もやっと完全週休2日制になって休みが増えたのは社員にとって良いにしても、年休を取るのが難しくなってしまいました。取れなかった年休を貯金みたいに積み立てることはできませんか?」
取れずじまいの年休が積みあがるのが心配なので、このようなご相談をいただくことがあります。年休取得率はアップさせたいけれど、やり残しの仕事が増えてしまうのも避けたいですよね。
いまの時季は夏休みもあるので、仕事を滞りなく進めることを考えると、さらに年休取得が難しくなる、といった事情もあるでしょう。
このような問題への対応のひとつとして、「年休の積立制度」というものがあります。
そこで今回は、年休の積立制度とはどういったものなのか、また運用上の注意点について詳しく確認していきたいと思います。
年休の利用目的を社員に書かせるのはダメですか?

「当社の年休申請届には、年休の利用目的を書いてもらう欄があります。そもそも、会社は社員がどんな理由で年休をとるのかを聞いてもいいのでしょうか?」
企業の人事担当の方から、年休の申請用紙にまつわるご質問をいただくことがあります。「年次有給休暇の利用目的」の記入欄があるフォーマットを使われている会社は多いのではないでしょうか。
ところが、「利用目的を記入するのは強制なのか」「プライベートのことに会社が口を出すのか」といった社員の不満の声への対応に悩まれるケースは多いようです。
結論から申し上げますと、利用目的の記載欄を設けること自体には問題はありませんが、運用次第では違法となる場合もあります。
そこで今回は、年休の利用目的を社員に書かせてもいいのかどうかについて、詳しくみていきましょう。
社員が体調不良で休むとき問われる会社の対応

厳しい冷え込みが続く毎日だと、冷えや乾燥、室内外の寒暖差から体調を崩す社員が職場で出てくるかもしれません。
具合が悪いまま仕事をしていると普段よりもパフォーマンスは落ちますし、何より本人の健康状態が心配です。休んでしっかり体調を整えてもらいたいところですよね。
とはいえ下記のようなシチュエーションで、会社としてどんな対応をとるべきか判断に迷うことも多いようです。
- 病気で欠勤した社員が、後日年休に振り替えたいと申し出てきた。必ず聞いてあげないといけないのか?
- 体調が良くなったので、午後から出社してきてさらに残業する社員。残業代の支払いはどう考えるといいのか?
- 休んでいる社員を会社に呼び出さなければならない緊急事態が発生。果たして呼び出していいものなのか?
そこで今回は、社員が体調不良で休むとき会社のとるべき対応について詳しく確認していきたいと思います。
年休管理を簡単にできませんか―基準日の統一・買い上げ

「入社日と年休の付与日が異なると管理が大変だ。入社日と年休の付与日を統一することはできないのかな?(;・∀・)」
4月に新入社員が入社してから半年が経過したので、年休が10日発生します。中途入社の人もいると入社日がバラバラなのはよくあることとはいえ、それぞれの年休付与日を管理するのは大変です。
また、あわせて年休の時効にかかわるこのタイミングで担当者として頭を悩ませるのは年休の買い上げについてです。
そこで今回は、担当者のよくあるお悩みである下記の2点について詳しく確認していきたいと思います。
- 年休の基準日をそろえる方法
- 年休の買い上げ
チームの余裕を生み出し年休取得率を上げる方法

チームの仕事をこなすのにどれだけの人数が必要なのか、実はわかっていない。子育て中のメンバーもいるので、急な休みの場合でもみんなでフォローできるようにしたい。(新任の若手チームリーダー談)
**
仕事をみんなで把握して、お休みや時短のメンバーがいても、残りのメンバーで主体的に仕事をこなそうとするチームは理想的ですね。では、具体的にはどうしていくと、そんなチームが実現するのでしょうか?
そこで今回は、理想的なチームづくりのポイントとなる次の3点について確認していきましょう。
- チームの仕事量を把握する
- かかる労働時間から必要な人数を割り出す
- IT化・外注化・パート・アルバイトを検討する
計画年休で夏休みを大型連休にするときの注意点

当社では、お盆近くに計画年休日を設定して大型連休にしている。「家族旅行を楽しめる」と社員からも好評だ。・・・そんな大型連休中にトラブルが発生、夏休みなんて言っていられない!!はやく担当の社員を呼び出して、対応にあたらせよう・・・
**
まとまった休みを取ることができると、旅行やイベントで家族との団欒を楽しめるなど、社員にとって大きなメリットになります。
会社にとっては年休の消化が進み社員の年休取得率アップにつながるメリットもあります。そのため、計画年休制度を積極的に取り入れている企業もあるでしょう。
ただし、ここで問題なのは当初定めていた計画年休日を変更して、他の日に振り返ることはできるのかという点です。もし法律に違反するようなら、せっかくの計画年休が台無しですよね。
そこで今回は、計画年休日の変更をはじめ、大型連休を設定するとき会社が注意すべき点について詳しく確認していきたいと思います。
年休の申請期限を過ぎると休めないルールにできますか?

「年休を取りたいけど、申請期限を過ぎてしまった。今日言って明日休むのはマズイよなあ・・・(;´∀`)」
昔、「日本を休もう」というCMがありましたが、あれから30年近くたった今も世間的にうまく休めるようになった、とはまだまだいえない状況なのかもしれません。
休まない(休めない)理由は様々かもしれませんが「年休取得のルールがない」ということも、実は大いに影響してきます。
ルールがないから遠慮して休めない(遠慮しない人だけが休めてしまう)、という事態を招きがちですし、冒頭の例のようにルールを硬直的に取り扱うと法律的な問題が生じます。
そこで今回は、年休取得のルールの作り方とその運用について詳しく確認していきたいと思います。
研修中の年休申請に会社がとるべき対応は

「明日は研修ですが、用事ができて会社を休んでもいいですか?」
「・・・えっ?!(ちょっと待って、なんでこのタイミング?)」
会社が人材育成を行う目的は、個人の能力を高めて組織の能力を高めること。そのため会社は社員へ先行投資するのです。研修の実施もそのひとつです。
会社としては、実施する研修の効果を高めるため、期間、内容、対象者の範囲、講師など熟考したカリキュラムを実施します。
そんなところに参加対象の社員から年休の申請が( ゚Д゚)・・・研修日を避けて他の日に休ませても果たしていいのか・・・
そこで今回は、会社として研修期間中の年休申請にどのように対応するべきかについて、詳しく確認していきたいと思います。
年休の当日申請に会社はどう対応するといいのか

「こどもが急に熱を出したので」「ちょっと体調が悪くて」
当日の朝に休みたいとの電話連絡。小さいお子さんの急な発熱は心配だし、無理して出てきて体調を悪化させてしまっては本末転倒だ。とはいえ、これを年休扱いにしないと法的にマズイのかな?
**
事情が事情なだけに休むのはやむを得ないとしても、これを年休扱いにすべきなのかを迷ってしまう上司です。というのも、納期が迫って人手が足りない状況だからです。
事情に関わらず、当日申請の年休が当たり前になってしまうと仕事の進捗に差し障りかねません。どこまで聞き入れるのがいいのか・・・
そこで今回は、当日朝の年次有給休暇の申請を会社として聞き入れないとダメなのか、欠勤扱いにしてもOKなのか、詳しく確認していきたいと思います。
辞める人も残る人も困らない年休取得への対応とは

「退職日まで残りの年休を消化したいです。今までずっと忙しくて取れずじまいだったので、いいですよね?」
辞める社員からの年休取得の申し出。引継ぎがないまま休まれると後任の社員に過度の負担をかけることになってしまうので、仕事の引継ぎをきちんと行ってくれるかどうかが気になります。
かといって、会社としては退職日を超えて年休の時季変更権を行使することはできません。
では、会社としてどのような対応をとると、仕事に支障をきたすことなく、辞める社員も残る社員も困らず、うまくいくのでしょうか?
そこで今回は、辞める社員の年休取得の申し出に慌てることのないよう、とるべき会社の対応について詳しく確認していきたいと思います。
