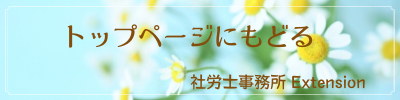A君はものづくりが心底好きで現場の仕事を愛している。ゆえにめったに年休をとらない。ちゃんと休んで、と伝えても出社してきそう・・・
**
この春から、会社には社員に少なくとも年5日の年休を取得させることが義務付けられていますが、休まない部下に頭を悩ます上司の方もいらっしゃるかもしれません。
GW明けの職場では仕事の再開にエンジンをかける人、まだ休んでいたいと思う人、もう夏休みに向けて仕事のダンドリを始める人・・・いろんな人がいて、休みに対する考え方も多様性に富んでいます。
とはいえ、まったく休みを取らないのでは健康状態やモチベーションの維持といった面で会社としては心配になりますよね。
そこで今回は、休まない社員を強制的に休ませてもいいのか?について詳しくみていきたいと思います。
会社が強制的に年休日を指定して休ませてもいいか

今回のゴールデンウィークのように、連休が創出されて休日が増えると休息を取れる日が自動的に増えるので、社員にしてはあえて年休をとる必要性もその分だけ減る、ということも一理あるでしょう。
そのため年休取得が難しくなるのは避けたいので、形骸化していてあまり取得する人がいないような特別休暇の日数を減らすことも、企業によっては理にかなっている場合もあるでしょう。
ですが、法定の年休日数を減じることは、いかなる場合であってもできません。
そこで、事業の閑散期など比較的忙しくないときに、会社が指定して集中的に年休を社員に取得させることも考えられますが、会社が法定の年休日数を上回って付与している年休については可能です。運用としては、次のような方法があります。
- 社員本人が取得申請する年休は法定年休をあてる。
- 法定を上回っている年休分については、「この社員には少し休養が必要だ」と会社が判断したときに指定して休ませる。
ただし、社員に「会社に無理やり休まされた!」といういらぬ誤解を与えないよう、就業規則において「会社が法定を上回って付与している年休日数については、会社が指定して付与することができる」旨の規定を設けておくことをお勧めします。
健康管理のため法定年休をどうしても取得させたいとき

では、社員の健康管理のために会社が法定年休を指定して強制的に休ませるにはどうすればいいのでしょうか。
会社は社員が「この日に休みたい」と請求する時季に年休を与えなければなりません。
従って、会社が法定年休を指定して強制的に休ませるには、計画年休制度を労使協定によって導入することになります。
計画年休制度は、業務との調整を図りながら気兼ねなく年休を取得できるよう、年休取得率をアップさせようとする仕組みのことです。
社員のプライベートな事情による取得のために5日を残しつつ、それを超える年休日数については労使協定による計画的付与を認める、という運用になります。
とはいえ、そもそも社員の請求によって付与するところに、年休取得率アップの進まない原因があるのも事実です。
ですから社員の健康状態を考えて、会社が社員に日や時期を指定して年休をとるように指示すること自体は問題ありません。
ただし、繰り返しになりますが、年休の取得はあくまでも社員の請求によらなければなりません。
社員が会社の指示に応じて年休を請求する必要があります。社員が「この日に年休を取りなさい」という会社の指示を拒否したときには、会社の一方的な指示で社員を年休日として休養させることはできません。
**
私の個人的な実感ですが、適度に休むことは仕事のパフォーマンスを高めてくれるな、と思います。仕事に没頭する時間はもちろん大切ですが、それが行き過ぎるとアイデアが煮詰まったり、ケアレスミスするなど、仕事の流れが悪くなります。
そんなときは特に、休むことで流れを変えることが必要だな、と強く感じます。
最近は「人生100年時代」と言われ、楽しみながら長く仕事を続けていくことを心がける必要があります。こまめな充電を「意識して」行うことの大切さを、「どうしても休まない」社員さんに伝えていきたいですね。


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事