出勤停止による無給処分は減給の制裁にあたるの?

Aさんが、懲戒処分で5日間の出勤停止になった。出勤停止期間は無給だから、給与計算をすると10%を超える減額になる。あれ?これって減給制裁の制限に抵触しないの?
**
出勤停止期間に応じて控除する給与額を計算しているうちに、減給制裁の制限との関係についてギモンを覚えた給与担当者さんです。
減給は労基法で厳しく制約されていて、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とされているからです。
そこで今回は、出勤停止による無給処分と減給制裁の制限との関係について、詳しく確認していきたいと思います。
人事評価でマイナス昇給、遡って給与を引いてもいいの?

昨年度の人事評価が、5月になって確定した。6月の給与で遡って4月までの新年度分の昇給差額を支払うことになっているが、問題は、人事評価の結果で降給になった社員の分だ。4、5月の降給分を6月の給与からまとめて引いても問題ないのかな?
**
昇給差額の遡及払い時(6月の給与支払い時)に、マイナス昇給分(4月、5月の降給分)をまとめて給与から控除してよいのか悩む人事担当者さんです。
人事評価による適正な給与額(人事評価で下がった給与)を支払うべく、賃金の過払い調整のために行う相殺(調整的相殺)が認められるのかがポイントとなります。
そこで今回は、降給に伴う調整的相殺で実務上注意すべき点について、詳しく確認していきたいと思います。
退職日前に退職金が欲しい社員に会社は応えるべき?

3か月後に退職予定のAさんが「退職日前に退職金を支給してほしい」と言ってきた。住宅ローンの繰り上げ返済のため急いでいるそう。こんな事情なら、早く退職金支払いの手続きをしてあげないとダメよね?!
**
退職予定者から退職金について相談を受けた人事部のCさん。相手の深刻な顔つきに、退職金支払いについての稟議書を早く上司に提出しなければ!と腰を浮かします。
ですが人事部の先輩は、そんなCさんをよそに「就業規則を確認してからすぐお返事しますね^^」と冷静な対応。そう、人事担当者としてはまず退職金の支給時期の慣行について確認する必要があります。
そこで今回は、退職予定の社員から要望があったとき、退職日前でも会社は退職金を支払う必要があるのか、詳しく確認していきたいと思います。
役職手当が支給されている部長は深夜割増の対象になるの?
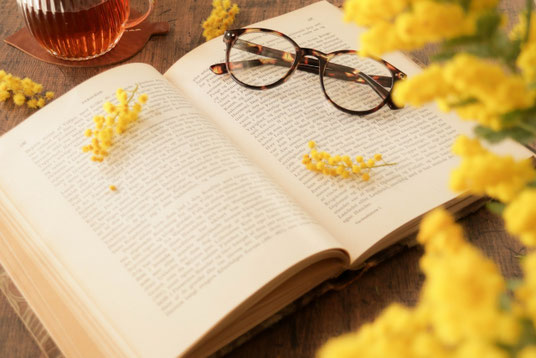
昨日、営業担当に顧客から納期遅延のクレームが入り、制作担当チーム総出で深夜まで作業にあたったらしい。昔取った杵柄で、部長まで作業に付き合ったそうだ。部長にも深夜残業の申請をしてもらう必要ってあるのかな?
**
管理職の深夜残業で、深夜業の割増賃金についてふとギモンを覚える人事担当者さんです。
そもそも管理監督者には、労基法の定める、会社による労働時間の把握・算定義務は免除されていますが、「深夜業にかかる割増賃金についてはどうなるのか、部長には役職手当が支給されているけど・・・?」と気になったからです。
そこで今回は、管理職の深夜業にまつわる割増賃金と役職手当の関係について、詳しく確認していきたいと思います。
人事評価をもとに整理解雇の対象者を決めるのはダメですか

企業再建のため余剰人員を削減することになった。経営の建て直しを図るため、誰を整理解雇の対象とするかは大きな問題だ。必要な人材かどうかを見極めるには、人事評価を人選の基準にするのが合理的なんじゃないだろうか?
**
余剰人員削減のためのいわゆる整理解雇は、他の普通解雇と決定的に異なる点があります。それは、大勢の社員の中から解雇対象者が選ばれることです。
そのため、整理対象者の選定には合理性(人選の基準が具体的かつ客観的なものであること)が求められることになります。
そこで今回は、人事評価を整理対象者の選定基準とすることの合理性について詳しく確認していきたいと思います。
行方不明の社員の給与を家族に支払うのはダメですか

ある社員が3か月前から音信不通となり、行方不明になった。ご家族のご心痛を思うと、せめて本人の未払い給与をご家族に支払いたいが、法律的にどうなんだろう?
**
行方不明となった社員のご家族の生活状況を思い、未払いとなっている本人の給与の扱いに悩む人事担当者さんです。
というのも、労働基準法においては賃金の直接払いの原則があるからです。これは、社員本人以外の人に給与を支払うことを禁止しているわけですが、状況が状況だけに許されるのでは・・・?と気持ちが揺れるのでした。
そこで今回は、行方不明になった社員の未払い給与と直接払いの原則との関係について、詳しく確認していきたいと思います。
給与締め日の変更で支払額が少なくなっても問題ないの?

会社の決済ルールの変更で、月末に売上、仕入や給与のタイミングをまとめることになった。給与締め日がこれまでから後にずれることになるので、給与計算期間が短くなって支払額がえらく低くなるけれど、これで問題ないのかな?
**
給与計算の締め日の変更で給与計算期間が短くなり、その結果支払額が低くなった場合、全額払いの原則(労基法で賃金は全額支払わなければならないと定められている)に違反しないのか?と心配になる担当者さんです。
給与計算の締め日と支払日の変更で、ただでさえ手続きが煩雑になるのに、社員さんから問い合わせがバンバンやってくることが予想されるからです。
そこで今回は、給与締め日の変更と全額払いの原則との関係について、詳しく確認していきたいと思います。
終業時刻をかなり過ぎたタイムカードに会社はどうする?

「始業時刻より早くにタイムカードが打刻されても、実労働時間のカウントは始業時刻から。じゃあ、終業時刻をだいぶ過ぎて打刻されたタイムカードはどう扱ったらいいんですか?」
人事部に配属された新入社員にタイムカードのチェックをお願いしていると、質問攻めにあう先輩社員です。
終業時刻とタイムカードの打刻の関係は残業代(時間外労働)にダイレクトにかかわってきますし、社員が自主的に職場に居残っているケースもままあることから、「質問にきちんと丁寧に答えなくては!」と意気込むのでした。
そこで今回は、終業時刻をかなり過ぎたタイムカードと社員の自主的な居残りにとるべき会社の対応について、詳しく確認していきたいと思います。
始業時刻より早いタイムカードで残業代は発生するの?

「タイムカードを集計していると、みなさん9時より早い出社です。それは残業時間としてカウントしなくていいんですか?」
人事部に新入社員が配属されてきました。タイムカードのチェックをお願いしていると、不思議そうな顔で質問を受けた先輩社員です。
この職場では始業時刻が9時ですが、それより前に出勤するのは当たり前で、タイムカードの打刻時刻との差が生じるのもいつものこと。その「いつもの当たり前」についてストレートに聞かれると、「なんて答えるといいのかな?」と戸惑いをおぼえるのでした。
そこで今回は、始業時刻とタイムカードの打刻時刻に差があるとき会社のとるべき対応について、詳しく確認していきたいと思います。
勤務シフトの改編で給与が減っても問題ないですか

業務負荷の軽減のため、この春から勤務シフトを改編して勤務日数を減らし、労働時間を短縮させようとの案が社内で浮上している。勤務日数が減る分、給与も減ることになるけれど、これはノーワーク・ノーペイということで問題ないよね?(゚д゚)!
**
勤務シフトの改編による減少した勤務日数分の給与の引き下げは、ノーワーク・ノーペイの原則に則って大丈夫なのかな・・・少しばかりの不安を覚える人事担当者さんです。
その不安のとおり(?)、勤務日数の減少に伴って給与を減額するということは、労働条件の変更に関わってくるので、その変更が「不利益変更」になるのか、そしてそれが有効なのかという問題が生じます。
そこで今回は、勤務日数の減少分に応じた給与の引き下げは可能なのか、詳しく確認していきたいと思います。
転勤を嫌がる総合職に一般職より高い給与を返してほしい

うちに総合職で入社すると、仕事の責任と成果を求められるし転勤の可能性もあるので、一般職と比べると給与は高い。なのに、ある総合職の社員に転勤を打診するとイヤらしい。示しがつかないし、一般職より高い基本給の差額を会社に返してもらうことにしようか?
**
転勤ができないような事情(本人や家族の健康面など)がないにも関わらず、転勤を拒否する総合職の社員に戸惑いを隠せない上司です。
総合職には転勤を含めたジョブローテーションでキャリアを積んでもらい、会社を支えるコア業務を担ってほしいからです。そのため、転勤命令拒否に対してペナルティーを与えるか?との案が出ましたが、給与の一定額を返還させるのは有効なのでしょうか。
そこで今回は、転勤命令拒否に対して会社が行う処分について、詳しく確認していきたいと思います。
減給の制裁で最低賃金を下回るとマズくないですか?

就業規則の違反行為がわかった社員に対して、減給処分が決定した。懲戒規定に則って減給の処理を行うも、エエッ、最低賃金を割っているじゃないの(゚Д゚;)これってマズくない?
**
労基法では減給の制裁について、減給の最高限度が定められています。その限度とは、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」となっています。
この決まりを守って減給すると、給与額が最低賃金を下回っていた・・・法律違反では?とドキドキする給与計算の担当者さんです。
そこで今回は、減給の制裁で最低賃金を割ると最低賃金法違反になるのか、詳しく確認していきたいと思います。
通勤手当を不正受給していた社員を懲戒解雇できますか

社員のCさんが通勤経路を変更したのに会社に申告しないで、本来よりも多い額の通勤手当を5年間不正受給していたことが判明した。差額は1か月あたり2千円くらいだったようだが、やはりこれは懲戒解雇を検討しなくてはいけない案件なのでは・・・
**
通勤手当の不正受給が、就業規則に定める懲戒規定の「重大な虚偽の届け出または申告を行ったとき」にあたり、懲戒解雇にするべきでは(ほかの社員に示しがつかない)・・・ということで判断に迷う会社側。
通勤手当の支給について、社員の自己申告による(自宅から会社までの経路を本人が申告する)場合、こういったトラブルが起こりがちです。
そこで今回は、通勤手当の不正受給で懲戒解雇にして問題はないのか、詳しく確認していきたいと思います。
社員が解雇予告手当を受け取らないと解雇は成立しないの?
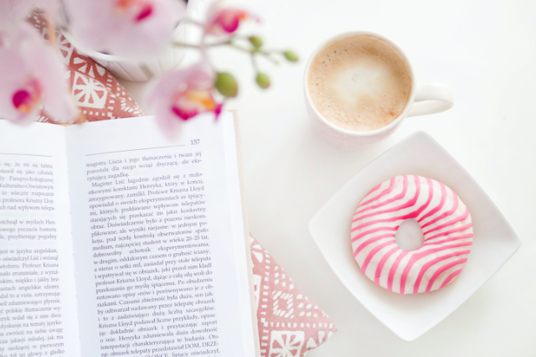
「即時解雇にするために解雇予告手当を支払おうとしても、社員が受け取り拒否したら会社は解雇できないの?」
勤務態度が悪い、無断欠席を繰り返すといった場合には、懲戒解雇の事由として就業規則に定められているのが一般的です。
懲戒解雇の場合、即時解雇にするなら解雇予告手当の支払いが必要となります。
ところが「(解雇予告手当を)受け取ったら解雇になるから受け取りたくない」と社員が受領を拒否してきたのなら、会社は解雇できないのでしょうか。
そこで今回は、社員が解雇予告手当の受領を拒否した場合に会社がとるべき対応について、詳しく確認していきたいと思います。
人事評価で他人を貶めることにならないか不安です

今年から評価者としてメンバーの人事評価をやることになった。「これはあなたの主観的な評価であって、正当な評価じゃありません、こんなの人格否定です」なんてメンバーから言われてしまったら、どうしよう。そもそも、人が人を正確に評価できっこないよ・・・。
**
人事評価にプレッシャーを感じて憂鬱そうなチームリーダー、みんなから反発を受けて人間関係にヒビが入ると、今後の仕事に差し障りが出るかもしれないからです。
そして「人が人を評価することは、不当に人を言いなりにさせることにつながり、人格権を侵害するので違法だ」といった主張に対して、どうも自信が持てないようです。
そこで今回は、人事評価は人格権を侵害するものでなく、人を貶めるものではないということを法律目線で詳しく確認していきたいと思います。
社員が感染症で会社を休むと休業手当の対象になるの?

「今年の冬は新型コロナウイルスや季節性インフルエンザとか感染症がはやるかも、って聞きましたけど、感染症で会社を休んだら休業手当の対象になるんですか?」
「・・・・えっ??(;・∀・)(そんな制度あるの?)」
感染症の流行に備えようとする、部下からの突然の質問に戸惑いを隠せない上司です。
会社の責めに帰すべき事由(会社都合)による休業の場合、社員は働くことができないので、その休業期間中の社員の生活を保護するため、会社が社員に対して休業手当を支払わなければなりません。
とはいえ、様々な感染症がいつどんなときでも「会社の責めに帰すべき事由」に該当し、休業手当の対象となるのでしょうか。
そこで今回は、社員が感染症で会社を休んだ時に、会社に対して休業手当の支払義務が生じるのか、詳しく確認していきたいと思います。
社員が早出出勤に遅れたとき会社はどう対応する?

資材搬入のため2時間の早出出勤を若手に指示したが、なんと遅刻してきた( ゚Д゚)
「いつもの出勤時刻には間に合ったからセーフですよね?」と悪びれずに聞いてきたが、給与カットの対象なんかにはならないの?
(メーカー勤務 資材部課長 談)
**
「反省はないんかいっ(怒)」という言葉をグッと飲み込んで、早出の時刻に遅刻してきた場合の対応について考えを巡らす課長です。
給与カットやペナルティーを科すには法律的に問題があってはいけませんし、遅刻の理由を聞いて根本原因を解決しない限り、繰り返されるのではとの思いもあります。
そこで今回は、早出出勤に遅刻した場合の給与カットや懲戒処分について詳しく確認していきたいと思います。
遅刻について減給の制裁を賞与でまとめてやるのはダメですか

遅刻ばかりする社員に何度注意しても反省の色がない。減給の制裁を行うことになったが、遅刻の回数があまりに多く、給与計算の担当者から「毎月ミスしないかヒヤヒヤするので賞与でまとめて減給するのはダメなんですか」との声が。そのほうがいいのかな・・・
**
事務処理を滞りなく進めるため、労基法で厳しく制約されている「減給の制裁」を賞与でまとめて行ってもいいのかな?と判断に迷う人事課のリーダーです。
本人に原因があるとはいえ、減給の制裁は社員に対する経済的なダメージが軽いものではないので、事務の効率を優先させていいのか、との疑問があるためです。
そこで今回は、事務処理の効率のため減給の制裁を賞与でまとめて行ってもいいのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
役職手当をもらっていると管理監督者になるの?

「Aさんには役職手当が支給されているので、残業代の対象外でいいですよね?」
こんなギモンを持つことは多いかもしれませんが、判断は慎重にまいりましょう。というのも、役職手当(部長・課長・係長などの役職に伴う手当。役付手当とも)の受給者イコール管理監督者ではないからです。
その役職の会社内における地位、責任と権限などからみるとともに、その地位にふさわしい給与面の待遇を受けているかどうかなど、実態から判断しなくてはなりません。
(管理監督者ではない、という判断になれば残業手当を支払う必要があります(゚д゚)!)
そこで今回は、役職手当と管理監督者の関係について詳しく確認していきたいと思います。
懲戒解雇でも会社は退職金を支給しないといけないの?

「うちの就業規則では、“懲戒解雇の場合は退職金の全部または一部を支給しない”と書いています。逆にいうと、悪いことをしても退職金をもらえるかもってことですよね?」
悪いことをして辞めさせられる社員に退職金が出るのなら、周りに示しがつかないのでは・・・と、ご相談をいただくことがあります。
心情的によくわかりますが、退職金の全額没収(全額不支給)については運用に注意が必要です。
というのも、就業規則などで退職金の支給について明白に定められていると、退職金は賃金にあたるからです。労基法では、賃金について種々の保護規定が設けられているので、会社は冷静な判断が求められます。
そこで今回は、懲戒解雇による退職金の不支給は認められるのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
定期昇給やベースアップを毎年しないのは違法ですか

「なんでうちは他所みたいに毎年給与が上がらないんですか、違法じゃないですか?」と社員から不満の声。法律的なことも含めてちゃんと説明しないとなあ・・・
**
あちこちで賃上げや初任給の額について見聞きすると、「うちの会社はどうなんだろう?」と期待する社員。一方、会社としてはその期待に応えたいものの、経営を続けていくためシビアに判断しなければならないので、社員への説明の仕方に頭を悩ませていて・・・。
定期昇給やベースアップが法律的に義務付けられる場合もありますし、また定期昇給とベースアップは法律的に異なっていますから、法律面を押さえておくことは大切です。
そこで今回は、定期昇給やベースアップは必ず行わないといけないのか、また賞与についても毎年支給しないといけないのか、お金関係をまとめて確認していきたいと思います。
職場で1回200円の罰金制度をつくってはダメですか?
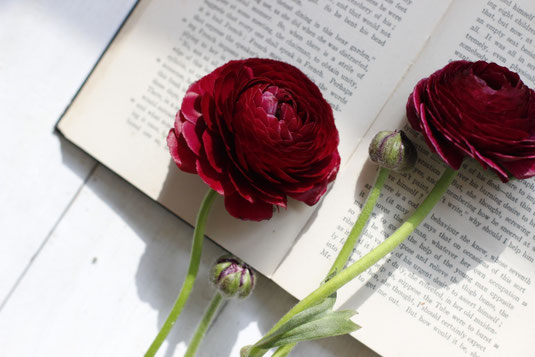
「作業場では必ず作業帽を被れと注意しているのに、しばらくすると被らない者が出てきます。作業帽の不着用1回200円、みたいに罰金制度をつくってはダメですか?」
着帽を呼びかけるものの、「頭が蒸れて気持ち悪いから被りたくない」「ダサいから被りたくない」と不満をもらす社員がいて困っています・・・といった現場のお悩みをお聞きすることがあります。
会社としては何としてでも社員の安全を守らないといけないので、罰金制度をお考えになる気持ちもわかります。とはいえ、会社が設ける罰金制度については、労基法が定める「減給の制裁」、「損害賠償額の予定の禁止」の内容を押さえておくことが大切です。
そこで今回は、社員の意識づけ向上のための社内罰金制度の取扱いについて詳しく確認していきたいと思います。
社員の給与を奥さんに支払ってはダメですか?

「社員の給与を奥さんに支払っちゃダメだと聞きました。奥さんとはいえ他人なのでダメなんですか?」
お金がなくては生活できないので、ちゃんと給与が社員に支払われないと大変なことになってしまいます。
そのため、労基法では賃金の支払いについていろいろな保護規定が定められています。そのひとつに、賃金は直接社員本人に支払わないとダメなことになっています。
とはいえ、やむをえない事情(本人が病気欠勤中、もしくは死亡したなど)があって、会社として「配偶者に支払ってあげたい」というときには、どうすればいいのでしょうか。
そこで今回は、給与の代理受領が禁止されていることを確認しつつ、本人死亡の際に配偶者に支払うことの可否について、詳しく確認していきたいと思います。
職場改善の報奨金は社員の給料にあたりますか

「職場改善のアイデアを社内で募ることになりました。優秀なアイデアには報奨金を出したいのですが、これも社員の給料にあたりますか?」
会社が社員に支払うお金について、すべてが賃金に該当するかというとそうではありません。「〇〇手当という名称だから賃金」「〇〇補助という名称だから賃金にあたらない」というわけでもありません。
どんな名称であるかを問わず、会社が社員に支払うもののうち、社員が使用従属関係の下で行う労働に対して、その対価として支払うものを「賃金」といいます。
・・・とはいえ、日常の具体的なシーンにおいては判断に迷うことも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、職場改善アイデアの報奨金はどうなるのかはじめ、「賃金の定義」について詳しく確認していきたいと思います。
賃金カットしなければ違法になるのはどんなとき?

「本当は給料から差し引くべきところですが、かわいそうなのでそのまま出しました。法律的にアウトじゃないですよね?」
法律的に照らし合わせると賃金カットとなるところを、社長の温情で実行せずに、通常通りに満額支給した・・・
「温情なんて公平さに欠ける"(-""-)"」との声があるかもしれませんが、ここで扱いたいテーマから逸れるので、ひとまず置いておきます。
お伝えしたいのは、賃金カットしなかったことで、実は、法律に反することになる場合(不当労働行為)もあり、注意しなければならないということです。
そこで今回は、賃金カットしないことが違法(不当労働行為)となるのはどんなときなのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
給与の支払いを完全出来高払いにすると違法ですか

社員の給与形態を完全出来高払い制にすると、法律的にアウトになるの?やった分だけ成果につながるなら、社員もやる気が出るんじゃないのかな?(店舗経営オーナー談)
**
給与の支払い形態を、社員が行った仕事の量に応じて支払う出来高払いにすると法律的にダメなのか問題です。出来高払い制や請負制について、労基法では出来高払い制などについて一定の規制を設けています。
会社が仕事の単位量への対価を不当に低く決めたり、原料・資材不足や仕事の繁閑があると、受け取る給与が激減して社員の生活が脅かされるおそれがある・・・というのがその理由です。
ですが、出来高払い制や請負制による給与の決め方自体を禁止しているわけではありません。
そこで今回は、出来高払い制や請負制をとる場合の注意点について詳しく確認していきたいと思います。
社員の給料が差押え!会社の貸したお金は返ってくる?

営業部のBさん、貸金業者への返済が滞っていたようで会社に電話がかかってきた。「給料や退職金を差し押さえる」ってことだったけど、Bさんは社内貸付制度の返済もまだ残っている。会社が貸したお金は返ってくるの?!(゚Д゚;) (メーカー勤務 人事担当者談)
**
貸金業者から社員の給料や退職金の差押えを受けてしまった。差押え債権者の方が優先すると、会社が貸したお金は返ってこないんじゃ・・・と不安に襲われる人事担当者さんです。
社員に給料を支払っている会社としては、給料からの天引きによる返済方法をとっていることが多いでしょうから、もしもなんていう事態にもなりかねません。
そこで今回は、社員の給料が差押えを受けたとき、会社が社員に貸したお金はどうなるのか、また、返済を受けるために会社が注意しておくべき点について詳しく確認していきたいと思います。
社員の給料カット、降格処分なら労基法の制限に違反しない?

「減給をもって社員を懲戒処分するとき、降格処分なら労基法が制限している“減給の制裁”については考えなくていいですか?」
減給については労基法91条で厳しく制約されていて、1回の懲戒事由では平均賃金の半日分以内、総額にしても一賃金計算期間で1割以内しか減給することはできません。
(減給の額があまりに多額となって、社員の日々の暮らしを脅かすことになってはいけないので、減給の上限が決められています。)
そのため冒頭のようなご相談をいただくこともあるのですが、結論から申し上げますと、降格処分しても、まったく今までと同じ仕事をさせながら給料のみをマイナスするのはダメです。
そこで今回は、降格処分と労基法が規定する「減給制裁の制限」との関係について詳しく確認していきたいと思います。
退職日までの給料を支払日まで待てない社員への対応は?

「年末に退職する社員が、退職日までの分の給与を年明けすぐに支払ってほしいそうです。年末年始は何かと物入りなので給料日まで待てないらしく。そのとおりにしないといけませんか?」
年末年始はお休みで給与計算や経理業務の事務処理スケジュールはどうしても通常よりはタイトになります。そのさなかに退職する社員からの要望。担当者が「え~~っマジ?!」とプチパニックに陥ってもおかしくありません。
ですが、退職時の賃金にまつわる問題はちょっと注意が必要です。なぜなら労基法では、退職者の給与の支払いを迅速に行うことを会社に義務づけているからです。
そこで今回は、退職時の賃金について退職者から「はやく支払って」との要望があった場合に、どのように対応するべきなのかについて確認していきたいと思います。
貯金したい社員、会社は3つの口座に分けて給与を振り込むべき?

「給与を3つの口座に分けて振り込んでほしい」と社員からの依頼。マイホーム購入に向けてうまくお金を貯めたいそうだけど、法律的に会社は聞き入れないとといけないの('◇')ゞ? (給与担当者 談)
**
ミス防止のためややこしい事務手続きは極力避けたい給与担当者。事務処理の効率化を第一に考えたいからです。
このように給与の振込先の取扱いは、地味なようで、実は会社の担当者が対応に悩まされる問題のひとつでしょう。
たとえ事務処理が煩雑になろうとも、個々の社員の希望を会社として聞き入れないとダメなのでしょうか。
そこで今回は、貯金したい社員の希望通りに会社は3つの口座に分けて給与振り込みを行うべきなのか、詳しく確認していきたいと思います。
定年退職者に賞与の支給日在籍要件は適用されますか

うちの会社では、賞与の支給日に在籍している社員にのみ賞与を支給している。賞与の支給日の2週間前に定年退職するAさんにも、この要件は適用されるのかな?(給与担当者のギモン)
**
社員が自己都合で辞めるのなら、支給日に在籍していないということで賞与が支給されないのは仕方のないこと(本人もわかっていて退職するはず)。
・・・だとしても、定年退職者は自分の意思で退職するわけではないのに、同じように扱っていいのものだろうか(運が悪くない?(゚Д゚;))と、判断に迷う担当者さんです。
そこで今回は、そもそも賞与の支給日在籍要件とはどのようなことなのか、そして定年退職者にも適用されるのか、詳しく確認していきたいと思います。
企業秘密の漏洩で社員に損害賠償させるのはダメ?
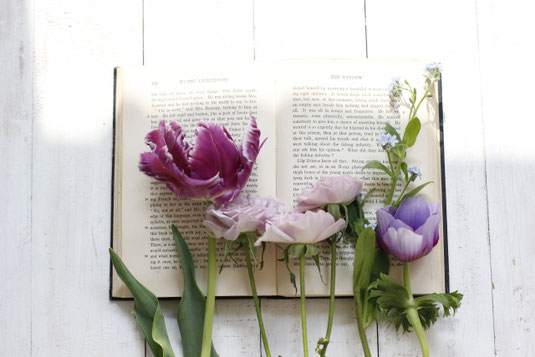
新商品の開発が順調に進むなか、企業秘密の漏洩リスクに備えて、「社員がそんなことしたら損害を賠償させることがある」と就業規則に規定しておきたい。危機感をみんなに持ってほしいが法律的にどうなんだろうか・・・(新商品開発プロジェクトマネジャー 談)
**
リスクマネジメントのため、会社の秘密情報と個人情報を適正に管理する体制づくりは会社の規模を問わず大切なことです。
冒頭のお悩みのキモは、社員に自覚を促すべく損害賠償について就業規則で明確化したいが、労基法16条の「賠償予定の禁止」に違反しないか?ということです。
そこで今回は、秘密事項を漏洩した場合に損害賠償を求めることは有効なのか、労基法16条との関係について確認していきたいと思います。
入社前の研修は給料支払いの対象になりますか

もうすぐ入社前研修だけど、参加者には給与を支払わないといけないのかな?まだ学生さんだし、どのくらいの額が妥当なんだろう・・・('◇')ゞ (メーカー勤務 採用担当者談)
**
内定式を10月1日以降に行う企業は多いと思いますが、今年はコロナの影響で通常の集合形式か、オンライン開催か、中止か悩まれたのではないでしょうか。
内定式を経た入社予定者に対して、実際の入社日までに入社前研修を実施しようとする企業もあるでしょう。
参加者に給与を支払うなら、その金額設定、時間外割増の問題など、判断に迷うケースも多いようです。
そこで今回は、入社前の研修と給料支払いの関係について詳しく確認していきたいと思います。
リハビリ出勤は通常の勤務扱いになりますか

「療養中の社員が復職前にリハビリ出勤を希望しています。リハビリ出勤で出社した場合、通常の給料を支払うものなのでしょうか。リハビリ出勤中にもしケガでもしたら、労災は適用されるのでしょうか?」
正常な勤務ができるまでには健康状態が回復していない社員を対象に、短時間の出勤や軽作業などからはじめ、リハビリ的な働き方で復職の支援を行う(試し出勤制度)企業もあるでしょう。
このリハビリ出勤の制度について、厚労省は「処遇や災害が発生した場合の対応、人事労務管理上の位置づけ等あらかじめ労使間で十分検討すること」として、法的な位置づけは明らかにしていません。
そのため、社員の病状の回復につながるなら・・・という思いがある反面、会社として職場の受入れ態勢をどうすればよいのか不安だと、冒頭のようなご相談をいただくことがあります。
そこで今回は、給料面をはじめリハビリ出勤の取扱いをどのようにするといいのか、確認していきたいと思います。
入社する前提で奨学金を学生へ支給してはダメですか

卒業後、うちへの入社を前提に、奨学金を在学中の学生に支給するのは法律的にダメなの?うちとしては優秀な学生を確保できるし、学生にしても経済的な不安なく勉強に励んでもらえるのに・・・
**
新型コロナウイルス感染症の影響で、学業の継続が困難な学生を支援しようと、このようなことをお考えの企業もあるようです。
企業の採用力強化につながれば、との思いがあったとしてもここで気をつけなければならないのは、労基法で「前借金相殺の禁止」が定められているということです。
お金の貸し借りがあると身分拘束につながるおそれがあるので、お金の貸し借りの関係と労働契約の関係は完全に分けなければならない、というのがその趣旨です。
「よかれ」と思ったことが法律違反にならないよう、今回は入社前提の契約金はなぜダメなのかについて、確認していきたいと思います。
産前産後休暇中の賞与をどう計算するといいですか?

賞与の算定期間の一部と産前産後休暇の期間がカブっている社員がいる。賞与の計算はどうすればいいんだろう?(?_?)(給与計算担当談)
**
会社には、女性社員の結婚、妊娠、出産、育児と仕事の両立について企業に課せられた責任を理解し、労働働環境を整えることが求められています。
時代とともに変化する働き方に対応するとは、常に新しい課題と向き合うことの連続だといえます。
産前産後休暇は会社に対して「有給にしなさい」と義務付けられていないので、「賞与はどうなるの?」との疑問が浮かびます。
そこで今回は、産前産後休暇の取扱いとともに、その期間中の賞与の計算をどうするといいのか、詳しく確認していきたいと思います。
休日が増えると給料の単価がアップするって本当ですか?

8月に休みを集中させて大型の夏休みをつくれば社員も喜ぶだろう。ただ、今よりも休みを増やすと給料の単価がアップするらしい。なんでそうなるんだろう?(@_@)
**
会社休日(労基法を上回って会社で定めている休日)や、国民の休日である祝祭日・・・休みとひとくちにいっても色々あります。ですが、「休日」が増えるとその分労働時間が減るということなので、賃金単価へダイレクトにかかわってきます。
これは、同じ休みといえども休日と休暇の法的な違いによって発生するものです。
そこで今回は、休日と休暇の違いを踏まえ、なぜ休日が増えると賃金単価アップにつながるのか?について詳しく確認していきたいと思います。
管理職が深夜に働いても残業代は支払わなくていいの?

うちの会社では深夜業を原則禁止している。36協定の制限もあるが、みんなの健康が心配だ。先日、ある部署で緊急案件が発生したときもそう伝えたが、そこの部長から「管理職が深夜残業して対応すれば、36協定も残業代も何も関係ないからいいだろう!」と押し切られてしまった。これでよかったのかな・・・(メーカー勤務・人事担当者 談)
**
部下を帰宅させて管理職が深夜まで残って対応しよう、ということで上司の方の責任感を感じますが、人事担当者としての葛藤もわかります。
管理監督者には労基法における時間外・休日労働、そしてそれに対する割増賃金にまつわる規定は適用されませんが、深夜業の割増賃金については注意が必要です。
そこで今回は、管理職の深夜残業に対して割増賃金を支払わなくてよいのか?問題について、詳しく確認していきたいと思います。
物損事故を起こした社員に損害賠償や違約金を求めてもいいですか

いきなりですが、あなたは次の問題に答えることができますか?(〇か×で答えてみてください。レッツチャレンジ!)
Q1「社員が業務命令に逆らって物損事故を起こした場合、会社は生じた損害の賠償を社員に請求してもいい」
Q2「あらかじめ “事故1回1万円”と決めておいて社員に請求してもいい」
Q3「会社が負担した海外留学費用を、帰国後5年以内に自己都合で退職した場合は留学費用を全額返還するよう決めて、社員に請求してもいい」
いかがでしたでしょうか?このQ1からQ3の内容は、実はコンサルティングのなかでよくいただくご質問内容だったりします。
これらの共通事項をまとめると、「労働契約の不履行等に対して損害賠償額を定めたり、罰金や違約金を徴収してもよいのか?」ということです。
では、さっそく詳しく確認していきましょう。(Q1からQ3の解答は記事の最後に!)
この手当は残業代の計算に含めないとダメですか?

「残業代を計算するときに、〇〇手当や××手当も含めないといけないですか?」
割増賃金、いわゆる残業代の計算で問題となるのは、(割増賃金計算の)基礎に算入される賃金と除外される賃金です。というのも、残業代の単価が変わってくるからです。
労基法では、割増賃金の基礎から除外される賃金の種類が限定されている(限定列挙)ので、それ以外の賃金は必ず計算に含めなければなりません。
除外される賃金は7種類ありますが、その中でも特に「住宅手当」の取扱いに注意が必要でしょう(誤解されているケースが多くあります)。
そこで今回は、割増賃金の基礎賃金には具体的にはどういった賃金が算入されて、どういった賃金が除外されるのか、詳しく確認していきたいと思います。
育休明けの退職、支給した賞与を返還させてもいいですか

Aさんは上司の信頼が厚く、周囲からも慕われている。育休取得後も職場に復帰するつもりでみんな心待ちにしていたが、育休明けすぐに退職してしまった。これからは、育休明けすぐに退職した場合、育休中に支給した賞与を返還させて、いい加減にならないようにしたい。
**
産後復帰を期待していたので育休明けすぐの退職にショックを受け、「復職するといって育休を取っても、いざ無理となったら辞めてもいい(Aさんもそうだったし)」といった雰囲気になるのを回避したい会社側の心情もわかります。
とはいえ、育休期間中に支給した賞与を会社に返還させることに問題はないのでしょうか。さっそく、詳しく確認していきましょう。
育休中の社員の人事評価を会社はどう考える?

上期の人事評価が5段階評価で最高ランクのS評価の社員。下期の評価期間中ちょうど育休を取得していたので勤務実績がない。年度の評価として、最低ランクのD評価をつけると、法律的にマズイのだろうか?
**
会計年度の上期・下期と連動して人事評価を行う企業は多いでしょう。業績(社員の努力)とインセンティブ(ご褒美)の関係がわかりやすいからです。そのため、半期の評価期間と育休期間がかぶっていて、出勤ゼロの社員への評価をどうすべきか、悩まれるケースも多いようです。
評価いかんによっては、育児・介護休業法が禁止する「不利益な取扱い」に抵触するのではないか?というのが、一番の懸念事項でしょう。
そこで今回は、育児休業中の社員の人事評価を会社はどう考えるべきなのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
間違いやすい年俸制における残業代の計算

年俸制では、その人の年収を決定してから月給と賞与に振り分ける。
賞与は残業代計算の基礎に入れなくていいから、年俸制にすると人件費削減になるんじゃないの、スゴイ発見( *´艸`) (人事担当者談)
**
社員の年収に占める賞与の比率は高いので、企業にとって賞与が人件費管理のポイントといえます。そのためこのような発想になりがちです。
とはいえ年俸制にしても、労基法の定める管理監督者などに該当しない限り、会社は社員の労働時間を把握して、残業代(割増賃金)を支払わなければなりませんし、年俸制の賞与部分が残業代の算定基礎に含まれるかどうかが問題です。
そこで今回は、年俸制における残業代(割増賃金)の計算について詳しく確認していきたいと思います。
社員の退職後に不正発覚、懲戒処分と退職金はどうなる?

退職後にその社員の不正が発覚した。懲戒処分にしたいところだが、すでに辞めた社員のことを言っても仕方がないのか・・・(管理職談)
**
このような場合、ご心中、察するに余りありますが、法律的に懲戒処分はできないのでしょうか。
懲戒処分とは企業秩序を乱したことに対するペナルティーなので、あくまでも会社に在籍していることが前提だからです。
ただ、退職した社員について「懲戒処分にするべきなのか?」という悩みが深くなるのは、退職金の不支給もしくは返還についての問題があるときです。
そこで今回は、社員の退職後に違反行為が判明したとき、懲戒処分と退職金の問題にどう対応すべきか、詳しく確認していきたいと思います。
ミスした社員からの減給の申出に会社はどう対応するか

うちの部のエース社員が取引先との大事なイベントでミスをした。取引先に迷惑をかけることになり、本人も責任を感じている。「今月の給料から(損害額を迷惑料として)引いてほしい」との申し出があったが、会社としてどう対応するべきだろうか?(直属の上司 談)
**
失敗や挫折の経験は、次に進むためのステップです。逆に「失敗がない」のは、新しいことにチャレンジしていないからともいえます。
ですが、仕事上の失敗に思い悩んだ社員からの減給の申出に、「けじめとして本人の意向を汲むべきなのか?」と、判断に迷う上司です。
そこで今回は、ミスした社員からの減給の申出に会社はどう対応するべきなのか、減給に関する労基法の規制を確認しながら詳しく確認していきたいと思います。
毎年の賞与支給はお決まりのもの?

当社では、これまで6月と12月にボーナスを出してきたが「毎年必ず6月と12月に賞与を支給しないといけない」となるのかな?業績が悪い年に賞与の支給はキビシイから、減額したり、不支給にすることは、法律的にアウトになるの? (スタートアップ会社 役員 談)
**
ほとんどの社員にとって賞与は「支給されて当たり前のもの」という感覚かもしれません。
ですが「賞与の支給がお決まりのもの」ということなら、会社にとっては支給すること自体がリスクとなる可能性もあります。いまの時代では、毎年イケイケどんどんで業績が伸びていくとは限らないからです。
そこで今回は、毎年の賞与支給はお決まりのものとして慣行化してしまうのか、あわせて減額や不支給はダメなのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
社員の給料にあたるもの、あたらないもの

新年度に向けて、就業規則をはじめとする規程の見直しにあたられている企業も多いかもしれません。
たとえば出張について。旅費の水準は、それぞれの企業での出張の実情に応じて考えるべきですが、実は、出張旅費など実費弁償的なものは労基法で定める賃金にあたりません。
とはいえ、給料と実費弁償的なものを混同してしまっているケースは意外と多いのではないでしょうか(これには理由があるのですが)。
社員に関係するお金面については、きちんと整理して把握しておきたいものですよね。
そこで今回は、出張の旅費・日当をはじめ、そもそもどのようなものが社員の給料にあたるのか、またはあたらないのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
管理職の役職手当と割増賃金の関係を就業規則に定めていますか?

社内では管理職として処遇してきたが、労働基準監督官の判断では「労基法に定める管理監督者には該当しない」とのこと。
本人には、時間外や休日労働の対価的な意味も込めて、今まで役職手当を支払ってきた。管理監督者に該当しないということなら割増賃金の支払いが発生する。今まで支払ってきた役職手当を割増賃金に充当できるのだろうか・・・
**
このように、役職手当を割増賃金に充当できないことになれば、企業経営に少なくないインパクトを与えることになります。そうならないためのポイントは就業規則の書き方にあります。
そこで今回は、役職手当と割増賃金の関係を就業規則に規定するポイントについて、詳しく確認していきたいと思います。
社員の非行調査中に退職金を支払わないのはダメですか

もうすぐ退職の社員に背信行為の疑いが発覚。退職金の支払いをしばらく保留にすると法的にダメなのだろうか?(ある会社の総務課長談)
**
会社は背信行為の疑いについて、事実関係を確認する必要があります。
とはいえ背信行為の事実が判明してから、いったん支払った退職金を返還してもらうのは大変です。
退職金は退職社員にとって「先立つもの」なので、その支払いをめぐる問題が発生することは少なくありませんが、就業規則にあることを明記しておくことで、無用な問題を回避することができます。
そこで今回は、社員の非行調査中に退職金の支払いを留保することはできるのか、そして就業規則に明記しておくべきことについて詳しく確認していきたいと思います。
社員の届出ミスvs会社の支払い義務、諸手当の支給はどうなる?
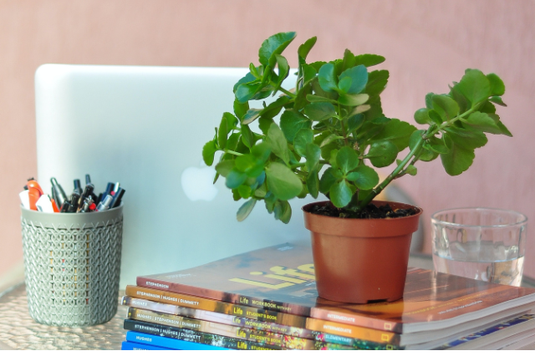
「届出を忘れていて、要件に該当する手当をずっともらっていません。以前の分の手当をもらえませんか♪(*´з`)」・・・本人の落ち度に、会社側が遡って支給しないといけないの?(総務の担当者談)
**
就業規則(賃金規程)に定められた手当の支給条件に合致した場合には、社員が申請用紙に記入して提出し、会社は本人に手当を支給する・・・という流れが通常は考えられます。
ところが、こどもが生まれたのに届出をしてこない人もいて、社内の世間話などをキャッチして、慌てて担当者が本人に確認する・・・といったっケースもよくあるようです。届出ミスに対して担当者のファインプレーがいつも実現するとは限りませんよね。
そこで今回は、社員の届出ミスがあった場合、会社は遡って手当を支給するべきなのか、詳しく確認していきたいと思います。
人事担当者が悩みがちな賃金実務のよくあるギモン

「給与計算は大変なのに、他部署の人からみると”誰にでもできるルーティンワーク”と思われがちで割に合わない作業だわ~(;´∀`)」
↑人事担当者のココロの叫びです。
給与計算をはじめとする賃金実務は、決して単純作業ではなく、効率性と丁寧さが必要で、工夫のしがいがあるクリエイティブな仕事です。
会社のコスト面にも大きく関わるため、給与から控除される税金や保険料の知識が必要なだけでなく、自社の賃金体系をしっかり把握しておかなければならないからです。
そこで今回は、賃金実務のあるあるギモンについて詳しく確認していきたいと思います。
- たとえば「19時03分」とタイムカードの打刻があれば、本当に1分単位で残業の計算をしないといけないですか?
- 給与の振込先金融機関を会社が指定するのはダメですか?
ハラスメントにならない人事評価のポイント

「新入社員も入ってきたことだし、うちのチームリーダーたちにマネジメントに必要な法律の基礎知識を身につけてもほしい」
入社や人事異動の季節である春、部下をもつにあたって必要な法律上の知識を身に付けさせたい、と考える経営者、人事担当、上司の方は多いようです。
このご時世、部下の人事評価を行うときに知識が足りないためにセクハラやパワハラ、マタハラとなってはいけないから、とのことでした。
そこで今回は、ハラスメントにならない人事評価のポイントとして、下記の3点を詳しく確認していきたいと思います。
- 人事評価を正しく行うための条件
- 部下の年休をどう取り扱うか?
- 妊娠、出産した社員への対応
賃金の見直しは諸手当のチェックから始まる

「毎月、特定の人に〇〇手当を支給しているけれど、なんのために支給しているんだろう・・・」(←給与計算担当者のココロの声)
手当の目的や意義がよくわからないまま「昔から出しているのでなんとなく」支給していることはありませんか?
また、同一労働同一賃金の観点からも「なぜその手当を(正社員に、あるいはパートに)支払うのか」正社員とパートの諸手当のあり方を精査しなければなりません。
さらにいうと、諸手当のあり方を考えずに賃金制度や人事制度を見直そうとしてもあとあとややこしいことになりがちです。
そこで今回は、「諸手当のあり方」を考えるポイントとして、下記の3点を詳しく確認していきたいと思います。
- 手当を支給する目的や意義を再確認し、
- それらをよく検討した結果として手当をやめるとしたら、
- どんなことに気を付けなければいけないのか?
新しい賃金制度へ移行するステップ

人事制度(人事評価と賃金制度)を刷新したいが、うまく移行できるか心配だ。給料が上がる人はうれしいかもしれないが、反対に下がる人に対してどう対応すればいいのか。社員は納得してくれるだろうか。
クリアしなければならない問題を考えると、うちの会社が制度を新しくするのは無理な話なのだろうか?
**
人が生活していくためにお金は必ず必要なので、賃金は社員のやる気に少なくない影響を与えます。賃金は人材マネジメントの中核となるものであり、どのように扱うかで会社の成長に大きく関わると言えます。
そこで今回は、新しい賃金制度へ移行するにあたって社員の理解を得るために必要な、下記の手順を詳しく確認していきたいと思います。
- 新しい資格等級へ移行する
- 新しい給料へ移行する
- 法律的な条件をクリアする
課題がわかる賃金分析の3つのポイント

自社に合った賃金制度をつくりたい、と経営者の方からよくお伺いします。とは言っても、今の制度にどんな問題や課題があるのか具体的にはわからない。だからどういった制度が自社には合って、合わないのか、何を基準に見極めるといいのか・・・などと思案されていることも多いようです。
そこでまずは、自社の賃金実態がどうなっているかを把握することから始めてみましょう。月給、賞与、年収総額について、年齢や役職、人事評価などの観点から詳しくみてみると、どんなことがネックとなっているのか、検討しなければならない問題や課題に気付くことができます。
では、現状の賃金実態をつかむための分析ポイントを、詳しくみていきましょう。ポイントは大きく分けて次の3つです。
- 世間水準と比較してみる
- 人事評価や役職に見合っているか確認する
- モデル賃金を設定してみる
これらを確認するプロセスで、自社に合った賃金制度のカタチが見えてきます。では、さっそく確認していきましょう。
賞与による年収管理をうまく運用するコツ

年俸制では支給する額が最初から決まっているから、賞与で年収調整するのが難しい。会社の経営状況が悪いときに、賞与で調整しづらいのはデメリットと感じる。(飲食店経営オーナー 談)
**
年収は月給と賞与によって決まり、年収に占める賞与のボリュームは大きいもの。社員にできるだけ還元したいという思いはありながらも、会社としては業績についても考えなければなりません。
実は、賞与には会社の業績をみながら総額人件費の管理を行うとともに、社員の年収も管理する機能があります(←年俸制の場合も例外ではありません)。
そこで今回は、年俸制における場合も含めて、賞与と年収管理の関係について詳しく確認していきたいと思います。
資格等級と月給をどうリンクさせる?

社員の給与はみんなが納得できるよう、職務や役割をもとに決めたい。レベルの近い社員を集めてグループにしたのが資格等級というのか。これにもとづいて社員の賃金を決定すればいいんだな。・・・今いる社員を資格等級にどう当てはめていいんだろう・・・
**
人事制度を整備するとき、「社員の格付に私情をはさみそう」「せっかく作った資格等級も結局活用できないままになってしまうのでは」といった不安があり、資格等級にもとづいて社員それぞれの月給を決めるにはどうすればいいのか、と悩みが生まれがちです。
そこで今回は、資格等級にもとづいて月給を決めるには、具体的にどのようにするといいのかをみていきたいと思います。
若手もベテランも納得できる社員の給与の決め方

「社員の給与を決めるとき、真っ先に考えるべきことは?」
まず会社として検討するべきは「その人件費は適正なのか?」です。目標とする利益(せめて赤字にならない)をしっかり出せて、企業の支払い能力に合っているどうかを検討しなければなりません。
そうすると「適正な人件費から昇給額を設定していくと、若手の昇給を低く抑えざるをえない。採用時の賃金をどれくらいにすればいいか?」という課題がでてくるかもしれません。
社員の役割や貢献度に見合った賃金にしたくても、社員の月給を考えるとき、若手にもベテランにも納得してもらうため、時には年齢や勤続年数についての「オプション」を検討することも必要となるでしょう。
そこで今回は、社員の月給を決めるとき考えたいポイントについて、詳しく確認していきたいと思います。
役割と貢献度に応じた資格等級をつくるには

「働く人の価値観が変わったので、時代に合った働き方や賃金のあり方を見直したい」とのご相談が最近増えています。
これまでは終身雇用制や年功制が多く採用されていましたが、今や、同一労働同一賃金の議論から能力で評価する人事システムが提唱されるなど、人材マネジメントのトレンドは大きく変わろうとしています。
「自社において大切な役割とは何か」「会社に貢献するとはどういったことなのか」を今までよりも明確にすることが必要でしょう。
実務的には、仕事の難易度、貢献度などで資格等級として設定して、その資格等級で求められる役割や行動を示すことになります。
そこで今回は、具体的な資格等級のつくり方について詳しく確認していきたいと思います。
理想的な配分を実現する賞与制度とは

「仕事を頑張ってくれた人に会社の利益を還元したいけれど、どうすればみんなの納得を得られて、法律的にもクリアできるのかな?」
社員の月給をいったん上げると下げるのは法律的に難しく、会社への貢献度によって昇給を考えるなら人事評価を整える必要があります。
「えーーーっ、手間がかかるなあ、もっと簡単な方法ないの?」という声が聞こえてきそうです(;´∀`)
そこで、社員の短期間の頑張りを報いるため、賞与で思い切って評価するという方法があります。
ただし賞与は諸手当と比べると社員の年収に占める比率が高いので、社員に与えるインパクトは小さくないですし、賞与の特色(生活費の補填、社員の年収コントロール、社員へのメッセージ性)といったものについてもあらかじめ考えておく必要があります。
そこで今回は、理想的な配分を実現できる賞与制度のあり方について詳しく確認していきたいと思います。
台風が来たとき勤怠と賃金の支払いをどう処理する?

9月に入り、青空の高さやイワシ雲をみるとさわやかな秋の気配を感じます。とはいえ、台風シーズンの真っただ中。
大型で強い台風が朝の出勤の時間帯に接近すると、社員の通勤に影響が出ます。休校や休園となった、こどもの面倒を見なければならない社員もいるかもしれません。
そのためこの季節になると、「交通機関の混乱に通勤途上の社員が巻き込まれないようにしたいが、その場合、勤怠や賃金の支払いはどう処理するとよいのか」とのご相談をお聞きします。
そこで今回は、台風が来たときの勤怠と賃金の取り扱いについて下記の2つのケースで詳しく確認していきたいと思います。
- 始業時刻の開始前に公共交通機関が停止していたとき
- 勤務時間中に公共交通機関に影響が出たとき
賞与の支給要件に「出勤率」を設ける場合の注意点

「この半年間で欠勤が多かった社員とちゃんと働いている社員が同じ賞与額っていうのは、やっぱりナイよなあ・・・」
公務員の賞与支給日は法律や条例で定められていますが、民間企業ではいつに支給しなければならないなど、ガイドラインがあるわけではありません。
「(賞与自体を)支払うのか支払わないのか」「いつ」「どんな計算方法で」といった賞与の支給要件は、自社独自のルールで決められるものです。
ですが、それゆえに「こんな支給要件でいいのか?」と悩まれる経営者や人事担当者の方は多いようで、特に出勤率についてのご相談をいただきます。
そこで今回は、「出勤率」を賞与の支給要件として設ける場合の注意点について、詳しく確認していきたいと思います。
会社が研修費用を取り戻せるとき、ダメなとき

「もっと頑張ってくれると思って期待していたから、高い費用をかけて研修に行かせたのに。こんなに早く辞めるなんて・・・( ;∀;)」
接遇マナーや電話応対、PCスキル・・・新年度のはじめに新卒・中途を問わず、新入りの社員に研修を実施する企業は多いでしょう。そんななか、研修を終えてすぐに退職する社員が出てきてしまいました。
ノウハウや技術を学んで、そのスキルを社内の仕事に活かしてもらうために研修に行かせたのに・・・せっかくかけた費用をどうしてくれるんだ、それなら受講費用を返してほしい!!
社員に対する期待が高いほどこんな気持ちになりがちですが、コンプライアンスに対する意識が高まっている今の時代、会社としては法律面をまずは把握しておきましょう。
そこで今回は、会社が研修費用を取り戻せるときとダメなときについて、詳しく確認していきたいと思います。
通勤手当の見直しは不利益変更にあたるか
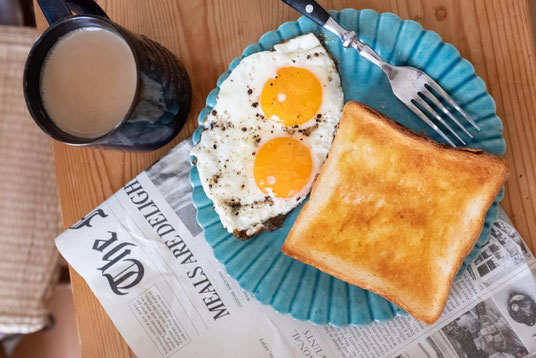
社員が定期券を紛失するのが心配で1か月ごとに通勤代を支給してきたが、今は万が一なくしても再発行してもらえるIC定期券がある。同業のA社さんでは、マイカー通勤の社員の通勤代をガソリン価格の変動から定期的に見直しているらしい。うちも1か月定期代相当を支払ってきたところを、いちばん安い6か月定期代相当に見直そうか。
**
通勤手当として定期券相当額を支給している場合は多いでしょうが、冒頭の例のように、コスト削減のため通勤手当を見直したいと考える会社もみられます。1か月定期の額と6か月定期の額では、後者の方が高い割引率だからです。
とはいえ、6か月定期券相当額への通勤手当の見直しは、社員にとって不利益変更とならないのかが気にかかる点ではないでしょうか。
そこで今回は、通勤手当の見直しで会社が気を付けないといけない点について詳しく確認していきたいと思います。
家族手当の見直しで気をつけるべきこととは

社員の生活費の一部を補助するために、家族手当を支給している会社は多いと思います。家族手当の内容は「配偶者がいる社員に」「子どもがいる場合」など会社によって様々でしょう。
各社で共通するのは、「会社は社員の生活面に配慮して処遇を考えているので、安心して働いてほしい」とのメッセージを伝えようとしていることです。
ただ、最近では家族手当の支給要件を見直したいと考える企業も増えてきているようです。その背景には、家族構成の変化、共働き家庭が増えてきたこと、行政による児童手当の支給があること、国が(会社の支給する)配偶者手当の見直しを提言していること、などがあるかもしれません。
そこで今回は、家族手当の減額や廃止など見直しを行うときに会社が気をつけるべき点について、詳しく確認していきたいと思います。
ライバル企業へ転職する社員の退職金をどう考える?

うちのライバル企業へ転職する社員にも、退職金を払わないといけないのだろうか。心情的にやりきれないから、退職後の一定期間は競合他社で働くのを禁止にしてしまおう。(スタートアップ企業経営者 談)
**
「競合他社への転職を知らずに退職金を支払う事態を避けたい」というのが、会社側のホンネでしょう。
社員を育てるにしても、時間、労力、教育費など何かしらのコストがかかるので、ライバル企業への転職に対して経営陣の気持ちのおさまりがつかないのもわかります。
ただ、ここで問題となるのが競業避止義務と退職金の支払いについてです。特に、下記のような点が問題になってきますので、詳しく確認していきたいと思います。
- 退職後の競業避止義務を社員にどこまで課すことができるのか?
- 退職金の不支給は有効なのか?
手当を廃止する前に考えておきたいこと

会社が社員に支払う毎月の給料は、基本給にプラスして、家族手当や役職手当をはじめいろいろな手当を支給している場合が多いでしょう。
とはいえ、「以前は何か意味があったのだろうが、今となっては支給の意味がわからない・・・」といった、支給目的のわからない手当は、みなさんの会社にはありませんか?
そんなときは手当を見直す、もしくは廃止するタイミングです。
とはいえ、慌ててすぐさま手当の支給をやめるのはいったんストップにしておきましょうか。というのも、手当を廃止する前に、ぜひとも考えていただきたいことがあるからです。
そこで今回は、いま支給している手当を廃止に不向きる前に検討しておきたいことについて、詳しくみていきたいと思います。
賞与で社員にメッセージを届けるには

6、7月は賞与の支給時期にあてている会社さんも多く、賞与に関するご相談がよくあります。
頑張ってくれた社員にできる限り賞与として還元したいけれど、原資を確保するのに苦労する、とのお話も伺います。
けれど経営者がせっかく工面して支給した賞与も、社員にとってはもらって当たり前…とはよくあること。
せっかくの賞与ですから、社員へのメッセージをこめられるツールとしてうまく活用することを考えてみませんか?
今回は、賞与で社員にメッセージを届ける方法についてお伝えしたいと思います。
年俸制と歩合制のメリット・デメリット

社員の給料を考えるうえで年俸制や歩合制を導入したい、とのご相談をいただくことがあります。
年俸制や歩合制といえば「人件費が管理しやすい」「本人の成績や会社の業績に応じた支払い」などの点にメリットがある、と思われるからでしょう。
もちろんメリットだけでなく、デメリットもあります。
そのため、デメリットを上回るメリットがあるか、自社の現場の実情にあっているか、今いる社員のモチベーションはあがるのか、などを考えたうえで導入について判断することがポイントです。
そこで今回は、年俸制と歩合制のメリットとデメリットについて詳しく確認していきたいと思います。
退職金を支給する目的を答えることができますか?

退職金について、経営者や人事担当のみなさんのご関心が高いのは、次のような内容です。
「法律で退職金を支給しなければいけないと決まっているのですか?」
「どのくらい払うと、世間並ですか?」
「退職金制度がある、と求人広告に載せないと、人材を獲得するのに不利になるでしょうか?」
中小企業では、「人材マネジメント」と「財務」というふたつの側面に留意しながら退職金制度について考える必要があります。
いちばん大切なのは、自社にとってどういった目的で退職金制度を設けるのか?という問いかけに対して明確な答えを用意することです。
そこで今回は、退職金を支給する目的がなぜ明確でないといけないのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
