身元保証人が見つからない新入社員に会社はどうする?

当社では、入社時に身元保証契約書を提出してもらっているが、新入社員が「身元保証人が見つからない」と言ってきた。親や親戚とは疎遠になっているそうだ。人生観や価値観が昔とは変わってきているから、こういったことは今後もありそう。どうすればいい?
**
身元保証契約は、身元保証人と会社との契約(社員本人との契約ではない)であり、その目的は、簡単にいえば、社員が会社に損害を与えた場合にそれを賠償することにあります。
とはいえ、社員のライフスタイルが多様化しているため、身元保証契約書の取扱いに頭を悩ませる人事担当者さんです。会社として、身元保証についての考え方を見直すべきなのかと思案します。
そこで今回は、入社時に悩ましい身元保証契約書の取扱いについて、詳しく確認していきたいと思います。
デスクで泣き続ける新入社員に会社はどう対応する?

仕事への理解を深めさせようと、教育係の先輩社員が新入社員に質問して答えさせていると、注意されたと思ったのか突然泣き出してしまった。すでに何回か研修期間中泣き出すことがあったらしく、その都度研修が停滞したそう。どうすればいいの・・・
**
デスクで泣き続ける新入社員を前に、「自分がパワハラしたみたい・・・」と先輩社員は困り顔。注意もできなくなってしまったそうで、頭を抱える人事担当者です。
新人教育では、委縮したり、仕事への苦手意識を持たないよう、新入社員の不安に寄り添った対応が求められます。とはいえ、泣き続ける新入社員のために場が凍り付いたり、本来の仕事が滞ったりするのは考えものです。
そこで今回は、泣き続ける社員が職場に与える影響と会社のとるべき対応について、詳しく確認していきたいと思います。
採用面接でシングルマザーに家族のことを聞いてもいいの?
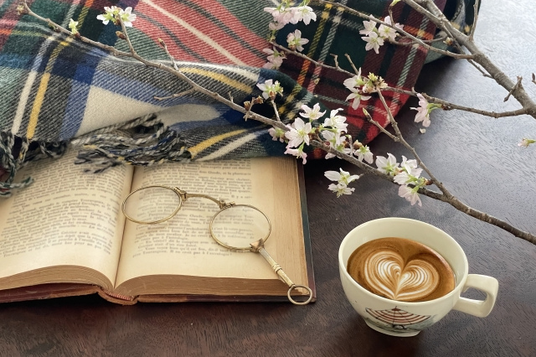
求人募集の応募者が、履歴書の「本人希望記入欄」にシングルマザーである旨を書いてきた。お子さんが急に熱を出したとき、面倒をみてくれる人は身近にいるのかな。お子さんが小さいならなおさら心配だ。とはいえ、採用面接で家族のことについて聞いちゃダメだよね、どうすればいいの?
**
採用基準に該当しそうな人材からの応募に喜ぶ人事担当者ですが、面接で確認したいけれど「聞けない」状況に直面し、頭を悩ませています。
採用時の面接において家族のことを聞く行為自体が、厚生労働省による採用差別禁止の行政指導の対象とされているからです。
そこで今回は、採用面接でのシングルマザーへの確認事項で会社が注意すべき点について、詳しく確認していきたいと思います。
新入社員の親が就業規則の閲覧を要求してきます

「労働条件の通知に〇〇の記載がないが、どうなっているのか。確認するために就業規則を見せてもらいたい。そもそも就業規則は社員に渡すものじゃないのか?」
新入社員のAさんの親御さんからの電話があり、対応に戸惑う人事担当者です。というのも、子の働く環境を心配してなのか、今回に限らずしばしば人事部に電話があるからで、対応する担当者も疲労困憊ぎみなのでした。
とはいえ会社で働くのは本人(子)であって、親は部外者ですから会社としてどのように対応するといいのでしょうか。
そこで今回は、新入社員の親御さんから就業規則の閲覧を要求されたとき、とるべき会社の対応について詳しく確認していきたいと思います。
雇用契約と労働契約ではどこがどう違うの?

採用サイトのオープン前に企業データや採用データを更新しなきゃ。そういえば、採用とは「労働契約の成立」っていうよね。・・・じゃあ、雇用契約とはどう違うんだろう?
**
採用の広報活動の解禁を前に、就職サイトの原稿を見直す人事部員のBさんです。採用フローや選考スケジュールを入念にチェックしながら「採用とはどういうことか」と考えているうちに、雇用契約と労働契約の違いについて気になったのでした。
というのも、「採用」とは社員を雇い入れることで、法律的には「労働契約の成立」とされていますが、実務において雇用契約と労働契約を意識的に区別して使い分けてはいないからです。
そこで今回は、「雇用契約」と「労働契約」の違いについて詳しく確認していきたいと思います。
新入社員のメンタル不調に会社はどう対応するべき?

新入社員のAさんがメンタル不調で出勤できなくなった。些細なミスに対して皆の前で立たされたまま先輩から大声で長時間叱責されたり、「こんなミスして給料泥棒」など人格否定もあった様子。人知れずかなり残業もしていたようで、今後どんな対応をとるといいのか?
**
新入社員のメンタル不調、長時間労働、パワハラ問題・・・これからの対応に頭を悩ませる人事担当者さんです。
給与計算のためタイムカード上の記録は把握していたものの、労働時間マネジメントは所属部署に任せきりでしたし、先輩の暴言、執拗な非難についても、現場の指導方針に口出ししまいと一任してきたからです。
新入社員は仕事に不慣れなことから長時間労働になりやすく、新入社員に対する指導は一般社員に対するものより慎重さが求められます。
そこで今回は、パワハラ的な指導による新入社員のメンタル不調に会社がとるべき対応について詳しく確認していきたいと思います。
採用選考は会社が自由にやってはダメなの?

性別の回答を強要しない配慮が必要とか、プライバシー性の高い「配偶者の扶養義務」といった情報を把握するのは好ましくないとか、採用選考のキホンをアップデートするのは大変だ。一緒に働く仲間を選ぶのだから会社の好きにしてはダメなの?
**
採用選考の面接官をやることになり、「面接官の心得」について人事部からお達しがあった営業課長さん。自分が学生の時とは様変わりした、採用選考時において配慮すべき事項に戸惑っています。
とはいえ、民間の私企業が社員を採用するにあたって、何か特別に採用を強制されるような法律上の拘束があるかというと、そうではありません。
そこで今回は、採用選考を会社の好きにしてはダメなのか、詳しく確認していきたいと思います。
採用内定って法的にはどんな位置づけになるの?

「最終面接も済んで、やっと採用内定が出せそうだ。・・・この内定者って、入社していないからまだうちの社員じゃないよね。それなら法律的にはどんな取り扱いになるんだろう?」
人事部員として初めて採用活動に関わり、達成感に浸りつつもふとギモンに思う若手社員です。
採用内定者は、卒業を迎えるまでは学生なので労働義務を負っていませんし、もちろん給与も支払われていない身分なので、労基法で保護される「労働者」には該当せず労基法の適用は受けません。
これから人事担当者として内定者フォローを行い、内定者の不安を解消して、無事入社につなげることがミッションなので、採用内定者の法的地位が気にかかるのでした。
そこで今回は、採用内定者が法律上どのように取り扱われるのか、法的位置づけについて詳しく確認していきたいと思います。
整理解雇のあと即行で採用活動してはダメですか

部門の縮小で整理解雇することになった。事業の再構築のため特別な専門分野の人材を早く採用したいけれど、整理解雇してすぐは法的にマズイんじゃないか。整理解雇が無効になってしまうかも・・・?
(メーカー勤務、新規プロジェクトマネジャー 談)
**
整理解雇とは、事業活動の縮小や再構築により生じる余剰人員に対して行われる解雇のことをいいます。
整理解雇が有効であるには「人員削減の必要性」が求められますが、人減らしのために解雇を実施するのに、すぐに採用活動を行うと「人員削減の必要性がほんとうにあったの?」と法的に問われるのでは・・・というのがマネジャーの悩みです。
そこで今回は、整理解雇のあとすぐに新規採用を行うとその解雇は無効になるのか、詳しく確認していきたいと思います。
職場ではごくフツーのこと、労働慣行ってなんですか

「うちの会社では、コレコレこういうルールでこうやっているの。早く慣れてね(^^♪」
10月に中途入社したばかりのAさん、職場の先輩からいろいろ説明を受けているところです。ただ、「職場のルール」について前の会社とはずいぶん違う点もあり戸惑っています(新卒で入った会社のルールを「常識」だと思っていることは多いですよね)。
このような「職場のルール」、実際上の取扱いが職場や会社との関係において、規範化し法的な拘束力が問題となるものをいわゆる「労働慣行」と呼びます。
そこで今回は、労働慣行として法的効力が認められるのはどんな場合なのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
職種ごとに試用期間の長さを変えてもいいですか

「営業職、現場職、事務職ではそれぞれ仕事内容が違うから、新人の職場や仕事に慣れるペースが同じはずがない。それなのに試用期間の長さが一律でいいのかな?職種別に試用期間の長さを設定するほうがいいんじゃないの?」(メーカー勤務 営業課長 談)
試用期間は新入社員が仕事や職場にうまく適用できるのか、向き不向きの判定を行うとともに、教育を行う期間でもあります。
試用期間では冷静なジャッジメントも必要ですが、新人を職場や仕事になじませることも大切なので、仕事内容を考えないで試用期間の長さが同じでいいのか?とギモンを覚える課長さんです。
そこで今回は、試用期間の長さを職種別に設定しても問題ないのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
人員整理でまず採用内定の取消しをやってはダメですか

景気後退で一部の部門で人員を削減し、事業を縮小せざるを得ない局面だ。だが、今いる社員には生活がある。まだ社会人になっていない採用内定者の内定取り消しをまず行うのはどうだろうか・・・
**
既存社員の整理解雇を行うより、内定取り消しを行うほうが経済的なダメージは少なく、人員整理が比較的緩やかに進むのでは・・・と頭を悩ます経営幹部。
とはいえ、景気悪化時を乗り越えて会社の再建に向かうとき、将来を担う若手社員がいないのでは企業の経営は立ち行かなくなるおそれが考えられます。また、法律面で採用内定の取消しには慎重を期する必要があります。
そこで今回は、事業縮小や人員整理を理由とする採用内定の取消し問題について詳しく確認していきたいと思います。
電話での口約束だけでも採用は成立するの?

「口約束であっても採用は成立する、と聞いたのですが、じゃあ、電話で簡単な面接のやりとりをして、顔を合わさないまま採用することもできるのですか?」
はい。
・・・このままだとシンプルに終わってしまうので、もう少し詳しく続けましょう。
採用が決定したということは、労働契約が成立したということです。労働契約は基本的に当事者の合意のみで成立するので、口約束だけでも成り立ちます。
ですが、それだけですとあとあと「言った、言わない」「思っていたのと違う」などと、トラブルに発展しがちなのは想像に難くありません。会社側には事前の対策が必要です。
そこで今回は、そもそも採用とは具体的にどういうことなのか、また会社があらかじめ注意しておきたい点について詳しく確認していきたいと思います。
協調性のない新入社員、試用期間を延長できますか

最近入った社員は乱暴な発言やふるまいがあるトラブルメーカー。周囲からも反感を買っている。うちの試用期間は3か月だが、さらに様子をみるために延長しても問題ないよね?(小売店店長 談)
**
通常、企業では試用期間といういわばテスト期間を設けて、その間に実際の働きぶりや言動をチェックし、最終的に社員として雇用するのかを決めています。採用面接だけでは、その人の資質、性格、スキルなどが社員としてふさわしいかどうかを適切に判断できないからです。
とはいえ、試用期間は労働契約という合意にもとづくものであるので、会社側の一方的な意思で試用期間を延長することはできません。
そこで今回は、試用期間の延長はどんな場合に認められるのか、また試用期間における協調性のない社員への対応について、詳しく確認していきたいと思います。
採用選考時に健康診断を行わないとダメですか

「入社試験のときに健康診断を実施しないといけないのかな?」
就業規則において、採用選考時に履歴書や職務経歴書とともに健康診断書(3か月以内に受診したもの)の提出を求めることが規定されているので、こんな疑問を感じる人事担当者の方は多いかもしれません。
労働安全衛生法では「雇入時の健康診断」について規定していて、会社に対して安全配慮義務を課している(罰則付き)ので、どうもややこしくなってしまいがちです。
というのも、雇入時の健康診断について「労働者を雇い入れるときは(行わなければならない)」としていますが、採用選考時に実施することを義務付けたものではないからです。
そこで今回は、採用時における健康診断で気をつけるべき点について、詳しく確認していきたいと思います。
本社採用でも最初は現場で働くことを明示するべきですか

うちの新入社員は、配属先がどこであろうと工場勤務からスタートだ。当社の製品をよく知ってもらうための、いわゆる工場実習。本社採用であっても1年程度の工場勤務があるけれど、初めにに明示しておかないとダメなのかな?
**
新人研修の一環で、現場での実習を行う企業もあり、工場などでの現場研修が終わると、本社採用者は本社に戻ります。
そのため、労働契約時に明示することが義務付けられている「就業の場所」「従事する業務内容」は本社に関するものだけでいいのか、それとも研修とはいえ現場での勤務についても明示するべきなのか?と判断に迷われるケースも多いようです。
そこで今回は、本社採用者にも現場での勤務があることを労働契約時に明示しておくべきなのか、について確認していきたいと思います。
1年間の有期契約で最初の3か月を試用期間にできますか

うちには1年契約の契約社員がいるけれど、最初の3か月間を試用期間にしても法律的に問題ないのかな? (営業課長談)
**
勤務態度の悪い人は3か月で契約解除にしたいが、優秀な人に3か月で辞められるのは困るので、上司として試用期間の設定を悩んでいます。
試用期間中の労働契約は、一般的には「解約権留保付の本採用契約※」と考えられています。採用時の面接だけでは企業側のチェックが難しいからです。(※社員として不適格とジャッジしたときは解約できる権利が留保されている労働契約)
とはいえ、法律でいろいろな制約が課されているので、解雇は簡単にはできません。
そこで今回は、1年契約の契約社員(1年間の有期雇用契約)で最初の3か月間を試用期間にできるのか、詳しく確認していきたいと思います。
本採用しないのは解雇になりますか?

Dさんの試用期間中の言動をみていると本採用するには問題がある。本採用しないというのは、解雇になるのか? (小売店の店長談)
**
試用期間中に社員としての不適格性が判明し、そのまま社員としての雇用は難しいので本採用しない場合には、会社から「あなたは本採用しません」と、本人に意思表示しなければなりません。
とはいえ、その際に「(試用期間の)期間満了」なのか「労働契約の打ち切り(解雇)」にあたるのか、判断に迷うケースは多いようです。
そこで今回は、本採用拒否は解雇にあたるのか、またどんな場合なら本採用拒否が正当となるのか、詳しく確認していきたいと思います。
採用のミスマッチを削減する現実的な方法とは

入社後たった半年の社員が「思っていたような仕事じゃない」と辞めていった。人手が足りないので、欠員補充の募集をかけなければならない。なるべくミスマッチを避ける方法はないのか・・・
**
少数精鋭で採用を行っている企業では、採用段階でのミスマッチを少なくする必要性が高くなります。とはいえ、面接や試験ではその仕事への向き・不向きを(企業も働き手も)十分に把握できないもの。
実際に仕事をやってみることで、企業と働き手の双方ともみえてくるものはあるのではないでしょうか。そのため、実際の仕事ぶりによって判断し、選考を行うこともひとつの方法です。
そこで今回は、適性や働きぶりを実際にみて、採用のミスマッチを少なくする方法「中途採用者向け」&「新規学卒者(学生)向け」について、詳しく確認していきたいと思います。
見習い期間は「試用期間」と同じ意味ですか?

企業の採用面接を受けてみたものの、顔を見合わせる面接官たちの反応を見る限り、企業側としては希望していた人材とは少し違うよう。
そのため面接官のひとりから「まぁ、いいわ。あなた、まず“仮採用”ね」とのお達しがあった。
なんとか入社にこぎつけたものの、先輩からは「おい、“見習い”。これやっておいて」と雑用が山積みにされる毎日・・・。
**
こんな場面、コメディタッチのドラマやマンガなどで見かけませんか?
ここでふと思うのは、「“仮採用”や“見習い”というのは、試用期間にあたるのか?」という疑問です。
“仮採用”や“見習い”という言葉は、確かに普段のオフィス内や就業規則でも用いられていますが、果たして試用期間と同じ意味なのでしょうか。それでは、さっそく確認していきましょう。
入社時の身元保証契約でどんな責任が問われますか

うちでは、入社時に身元保証契約書を提出してもらっている。新入社員から「身元保証契約にサインするとどんな責任がかかるのですか?」と質問されたけれど、そんなに深く考えたことなかったなあ( ;∀;)
(メーカー勤務6年 人事担当者 談)
**
身元保証契約は、社員本人との契約ではなく、身元保証人と会社との契約です。(冒頭の質問も↑社員を介した身元保証の依頼を受けた人からのものと考えられますね)
その目的は、簡単にいうと、社員が会社に損害を与えた場合にそれを賠償することにあります。ゆえに社員に身元保証契約書を求める企業は多いですが、「どこまで責任が問われるのか?」と問いに対して答えに窮する場面もあるのではないでしょうか。
そこで今回は、採用時に社員に求める身元保証契約とはどんなもので、どんな責任が発生するのか、詳しく確認していきたいと思います。
職種限定の採用でなければどんな部署への異動もOK?
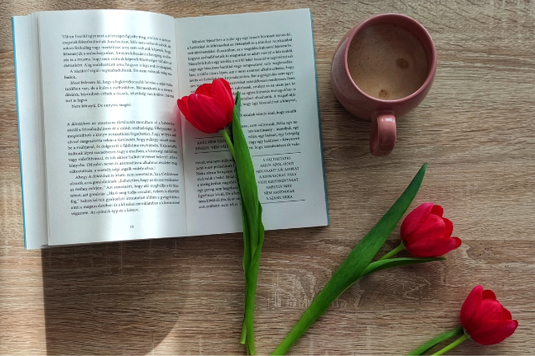
職種を限定しないで採用した場合、入社後はどこの部署や職種に異動させても問題ないはず。とはいえ「そんなこと聞いてなかった」と辞められるとマズイなあ・・・(メーカー勤務 採用担当者 談)
**
今年は、新型コロナウィルスの影響で採用計画を変更せざるを得ず、秋になっても採用活動を積極的に行う企業もあるようです。
オンラインなど対面ではない採用活動では、なんとなくの雰囲気や、あいまいな言い回しでは誤解を招きかねないので、説明内容に苦心することもあるかもしれません。
法律的にも説明の根拠を把握しておきたい、と思われるのは企業として当然のことでしょう。
そこで今回は、職種を限定しない採用の場合、どんな部署・職種への異動命令も認められるのか、詳しく確認していきたいと思います。
自宅待機の新入社員の試用期間はいつからスタートする?

世の中の経済状況が芳しくないとき、業績悪化のため新入社員に自宅待機を命じざるをえない場合もあるかもしれません。
採用決定者に入社日が到来してからも自宅待機を命じる場合、試用期間はいったいいつからスタートするのか?と、判断に迷われることもあるのではないでしょうか。
通常でも、新入社員はこれから始まるオフィスライフを目の前にして、不安を感じやすいものです。それなのに、自宅待機で入社する会社からの情報がほとんど入ってこなければ、ますます不安な気持ちを募らせてしまいます。
そこで今回は、自宅待機中の新入社員と適切なコミュニケーションをとっていくため新入社員の試用期間はいつからスタートするのか、について詳しく確認していきたいと思います。
中途入社の社員に試用期間は適用されますか

今度入社してもらう中途採用のAさん。管理職としての採用だから、試用期間の適用はどうなるんだろう?そもそも中途採用者は新規学卒者じゃないんだから試用期間はなくてもいいのかな?(人事担当者談)
**
平社員での中途入社の場合は試用期間の適用があって、管理職での中途入社なら適用がないのか?と判断に迷ってしまう人事担当者さんです。
というのも、試用期間は「新しく学校を卒業した人の新規採用にまつわる問題」として、通常は考えられているからです。
試用期間は新入社員の教育を行うとともに、向き不向きの判定を行うという2つの機能を備えていますが、新規学卒者ではない中途採用入社の社員の場合はどうなるのでしょうか。
そこで今回は、中途入社の社員にも試用期間の適用があるのかどうか、詳しく確認していきたいと思います。
入社時に必要書類を出さない社員への対応はどうする?

「入社時に、所定の必要書類を提出しない者がいた場合、会社としてどのように対応するといいですか?書類の内容は家族関係などプライベートに関わるものなので、強く言っていいのか対応に悩みます( ;∀;)」
コンサルティングのなかで、「採用選考時の提出書類」と「採用決定時の提出書類」をきちんと分けておきましょう、といったことをお話ししていると、このようなトピックをお伺いすることがよくあります。
企業は採用選考において、選考のため必要となる適正な書類を、応募者に求めることになります。さらに採用決定時には、会社の手続きで必要ないろいろな書類の提出を、追加して求めるのが通常です。
そこで今回は、採用選考時と採用決定時の提出書類の区別に触れながら、採用決定(入社)時に必要書類を提出してこない社員への対応について、詳しく確認していきたいと思います。
新入社員を子会社へ出向させるのはダメですか

うちの子会社は、就活生の知名度がないために採用活動で苦戦している。子会社の名前で求人をしても人材の獲得が難しいので、親会社である当社で募集して、採用してからすぐに子会社へ出向させるというのはどうだろうか? (グループ本社 採用担当者 談)
**
いまは、求職者が有利な売り手市場で内定を辞退する学生もいるため、予定の採用人数を集めるべく夏採用というかたちで、8月下旬ごろまで採用活動を続ける企業もみられます。
そんななか「業績はよいのに学生の間では知られていない」ということで、新規学卒者の獲得に苦戦する現象は、特にBtoB企業で起こりがちです。
そこで今回は、親会社による求人と子会社への出向において気をつけるべきことについて詳しく確認していきたいと思います。
試用期間は新入社員を育てる期間

いよいよ4月、新社会人の真新しいスーツ姿をみると、こちらまで気の引き締まる思いがします。新入社員の会社や仕事への適性をみるために、試用期間を設けている場合は多いでしょう。
セミナーや研修のなかで、この試用期間について
「この新入社員とはもう一緒にやっていけそうもない、と感じた場合には試用期間中であれば、簡単に辞めてもらえるのですか」
との質問をいただくことがあります。
試用期間は新入社員側の問題、として捉えがちかもしれません。
実はこの期間は、上司や先輩社員が〇〇するべき期間でもあるのです(答えは記事のタイトルにありますが・・・)。
そこで今回は、上司や先輩社員が試用期間にやるべきことについてみていきたいと思います。
問題行動を起こした採用内定者の内定を取り消せますか?
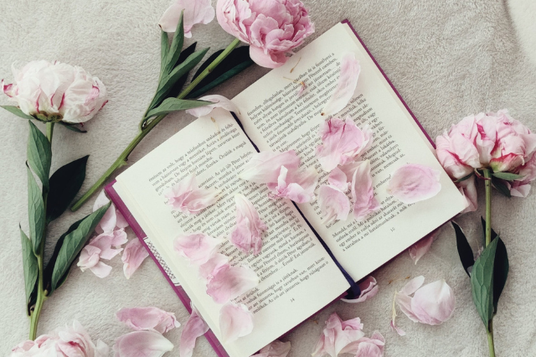
もし、採用内定者が入社日までになにか問題になるようなことを起こした場合は内定を取り消してもいいのかな?でも、問題行動を起こして悪いのは本人なのに、そこまで会社が考えないといけないものかしら?
"(-""-)"(採用担当者談)
**
そろそろ新入社員を迎える準備で慌ただしくなる時期ですが、採用担当者を悩ませるのが採用内定者の内定取消し問題です。
ひとくくりに採用内定者といっても、法律的には「採用予定者」と「採用決定者」に区分されます。会社は採用内定の取消しを行って問題がないかは、「労働契約の成立」が問われるので、「採用予定者」と「採用決定者」とに分けて考えなければならないからです。
そこで今回は、問題行動を起こした採用内定者の取消し問題について、詳しく確認していきたいと思います。
採用内定者に就業規則の適用はアリかナシか

みなさんの会社の就業規則の1ページ目を開いてみてください。
そこには「この規定は、就業規則に定める当社の従業員に適用する」とのように、就業規則の適用範囲が定められていると思います。
さて、ここで問題です。いったい何時の時点から、「当社の従業員」に該当するのでしょうか?入社してから?それとも試用期間が終わってから?・・・取扱いに悩むのは「採用内定者」ではないでしょうか。
採用されることが内定しているとはいえ、「当社の従業員」かというとそうとも言えないような。 「当社の従業員」に該当しないなら就業規則は適用されないのか?これから採用されるので「見込みの従業員」として準用されるのだろうか?・・・思考が堂々巡りになりそうです。
そこで今回は、採用内定者に就業規則の適用はアリなのか、それともナシなのかについて詳しく確認していきたいと思います。
採用の応募書類で気をつけたい個人情報の取扱い

「採用の応募書類は個人情報でいっぱいです。個人情報の保護に気をつけるといっても、具体的にはどうやって扱えばいいのか・・・」
新卒者と入社時期を同じ4月に合わせられるよう、1月に募集をかける企業は多く、意外とこの時期は採用市場が活発です。
企業の採用活動では、当然のことながら、さまざまな書類(データ)の提出を応募者に求めることになります。そのため、企業の採用担当者さんから採用の応募書類に関してご相談いただくことがあります。
応募書類にはたくさんの個人情報が記載されていますし、採用面接を実施すればそれ以外からも個人情報を得ることになります。
そこで今回は、採用活動で応募者から提出される書類を企業はどのように取扱うべきなのかについて、詳しくみていきたいと思います。
新入社員への指導がパワハラにならないか心配です

「今日から新人がうちの部署に配属される。いまの若者たちに新人指導がパワハラと受け取られないか心配だ・・・」
上司や先輩社員は、単に部下へ業務命令をすればよいというものではなく、就業規則を守ってコンプライアンスにかなった命令を出し、職場を円滑にマネジメントする責任と義務があります。その他にも仕事のやり方、ルールやマナーについての指導・教育が求められています。
そのため部下のモチベーションを落とさないよう、どんな言動がパワーハラスメントとなるのか、事前に把握しておきたい管理職、上司の方はたくさんいらっしゃることだと思います。
そこで今回は、部下のマネジメントにまつわる次の3点について詳しく確認していきたいと思います。
- なぜ会社がパワハラ対策をしないといけないのか
- どこまでが教育指導でどこからがパワハラになるのか
- どんな言動がパワハラになるのか
紹介採用で社員にインセンティブを与えるときの注意点

いま、採用方法を広げるために社員が自分の知人や友人を紹介する「紹介採用(リファラル採用)」を検討するケースがあります。
即戦力を求めて、企業の規模を問わず採用競争が激化しているので、人手不足の時代によい人材を確保することに頭を悩ます企業が多いのがその一因です。
会社としては何とかして人材を確保したいので、協力してくれた社員にご褒美(インセンティブ)を与えて紹介採用を促進したいとの考えが生まれます。
とはいえ、何をインセンティブにするといいのか、またそれは法律に適っているのか、判断に迷う場面も多いようです。
そこで今回は、紹介採用に協力してくれた社員へのインセンティブについて、実務上注意しておくべき点を確認していきましょう。
インターンシップ実施で気をつけたい3つのポイント

思っていたような仕事じゃなかった、と新人があっさり辞めてしまう。入社前にインターンシップで職場の雰囲気やうちの仕事内容を知ってもらってはどうだろう。見学とか体験的なものにして、アルバイト程度の日当を支払おう。・・・もし学生さんがケガしたら労災保険の対象になるのかな?(メーカー勤務 採用担当者 談)
**
学生に職場体験の機会を提供する制度、インターンシップをまさにいま、実施中の企業もあるかもしれません。
とはいえ、冒頭のような気がかりな点があって実施をためらうケースも多いようです。そこで今回は、インターンシップ実施で気をつけたい下記の3点について詳しく確認していきたいと思います。
- インターンシップ中のケガは労災になる?
- インターンシップでミスマッチを防ぎたいが実施する余裕がない
- そもそもインターンシップ生が集まるかどうか不安
採用面接でやってよいこと、やってはいけないこと

「コンプライアンスが厳しいなか、採用面接でやってよいこと、やってはいけないことの違いがわからない」
年間単位で企業の採用動向をみると、一般的に3~4月、9〜10月に新規求人が増えるようです。年度の区切りで退職する人の欠員補充、下半期からの事業展開のため、人材を獲得したいニーズが高まるのでしょう。
企業の求人が増加していて人材獲得の競争が高まる現状では、下半期に向けた採用募集を今の時期から準備しておいても遅くはありません。そのため、冒頭のようなお悩みは早めに解消しておきたいですよね。
採用活動については会社に広い裁量が与えられていますが、無制限に採用の自由が認められているわけではありません。
そこで今回は、企業の採用担当者の方のお悩みあるある「採用活動における注意点」を詳しく確認していきたいと思います。
採用に困らない会社の共通点

新規学卒者は会社ランキングに掲載されるような会社にしか入りたがらない。中途者だとより高い給料をもらえる会社しか眼中にないだろう。人手不足で売り手市場のなか、人材を獲得するのは至難の業だ・・・
(某メーカー企業の採用担当者談)
**
生活するうえでお金は大切なので、家族構成や年齢を考えたときに給料額というのは、求職者にとって重要な要素なのは間違いありません。ですが、本当に働き手にとって「お金しか重要でない」のでしょうか?
企業の採用活動が思うようにいかないとき、どうしても給料面のせいにしがちですが、多額の広告費をかけたり、世間相場よりもべらぼうに高い給与額を提示しなくても、人材獲得に悩まない会社もあります。
そこで今回は、人材争奪戦が繰り広げられる採用市場で人材獲得に困らない会社の共通点をみていきたいと思います。
採用広告に載せた給与額を必ず支払わないとダメですか?

「いい人に来てもらいたいから、求人広告に載せる初任給を高めに設定しておこう。実際にそうするかは人を見てから判断しよう・・・」
人手不足の時代では、より熱心に働いてくれる人に来てほしいもの。
そのため、たとえば求人広告で初任給について「課長職と同等の給料を支給」と書きながらも、実際に支給するのは同社の課長クラスの平均を下回る最低ランクというのではどうでしょうか。
課長クラスの給料には違いありませんが、入社した社員からすると「思っていたのと違う!」と感じるかもしれませんし、法律的にも問題がないかが気になりますよね。
そこで今回は、求人広告の内容と実際の待遇に差があっても法律的に問題ないのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
本当に若手男性社員を採用する必要があるのか?

「男性社員を採用したいのに、売り手市場で給料が見合わないのか応募がなくて困っています。できれば30代までの人がいいのに・・・」
コンサルティングでこんなお話を伺いました。退職者の補充を行うべく、前任者が「30代男性社員」であったので、後任者も同世代の男性を採用したいとのことでした。
同じようなことを複数の企業でお聞きするのですが、本当に30代の男性しかこなせない仕事内容なのでしょうか。担当する仕事の内容をよくよく見直してみると、実は、年齢や男女の性別関係なくできる仕事だと判明するケースもよくあるからです。
「この仕事は30代男性社員が担当する仕事だ」というのは、もしかすると単なる思い込みだということも多いのかもしれません。
そこで今回は、ぜひ欲しいと思っている若手の男性社員(でも採用難)は本当に必要なのか?について改めて考えてみたいと思います。
人手不足を乗り切る再入社制度のポイント

「うわっ、エラーが出た。どうしよう?こんなとき旦那さんの仕事の都合で辞めたAさんがいたら頼りになったのに・・・(;´Д`)」
いまはどの業界でも人手不足でなかなか採用が難しいため、結婚・妊娠・出産・介護などのライフイベントで退職した、有能な社員に職場復帰してもらいたい、と考える企業は増えてきているようです。
確かにもともと自社で働いていた経験者であれば、扱う商材から社内の雰囲気まで理解していますし、会社にしてもすでに本人の性格やスキルを把握しているので、頼りになる働き手です。
最近は再入社について制度化した会社も、見受けられるようになりました。そこで今回は、再入社制度を設ける際に考えておきたいポイントを確認していきたいと思います。
幹部社員や専門職社員の能力不足にどう対応する?

取引先の要望に応えようと毎日忙しく、常に人手が足りないと感じる。ここに新人が入ってきても、十分な時間をかけて丁寧に仕事を教える余裕はない・・・
即戦力を求める場合、中途採用で幹部社員や専門職社員を投入しようとするのは自然の流れです。ですがここで問題が。
採用したものの、実際の働きぶりをみると期待したような能力の発揮は全くみられず、業務への適性にしてもどうも疑問を感じる・・・
即戦力が欲しくて一般社員よりも良い条件で採用したのに、逆に彼・彼女らのフォローで手間取るなら、「どうすればいいのか、このままでは雇い続けるのは難しい」と悩まれる場合もあるかもしれません。
そこで今回は、幹部社員や専門職社員の能力不足に会社としてどのように対応すればよいのか、について詳しく確認していきたいと思います。
試用期間の延長で判断を先送りにしていませんか?

社員を採用したものの、当社に合った人材なのか、今後期待通りの働きをしてくれるのか自信がない。それなら、試用期間は長いに越したことがない。3か月?いやいや短い、6か月にしてみるか・・・
【―それから6か月後―】
来週には試用期間が終わるが、本採用してよいのかピンとこない。あともう少し時間があればわかりそうな気がする。よし、期間を延長することにしよう・・・
***
「いまいち(本採用の)決め手に欠ける」程度では、本採用拒否の十分な理由といえません。この状況で試用期間を延長しても、問題を先送りにしているだけかもしれません。
そこで今回は、問題を先送りしない試用期間の在り方について詳しく確認していきたいと思います。
