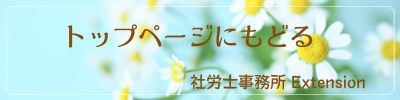うちの始業は9時。だが、フレックスタイム制を導入してから9時に出社する社員が激減してしまった。朝イチの顧客からの電話が鳴りっぱなしになることもあり(電話に出る人がいない)、いっそ「出勤は定時の9時、退勤はそれぞれの自由」ということにしようか?
**
業務効率アップや時間の自己管理意識を上げるためにフレックスタイム制を採り入れたのに、制度の意図通りに運用されない・・・頭を抱える課長さんです。
顧客対応や社内コミュニケーションに支障が出てはいけないため、本来の始業時刻である9時に出社を求めたいと考えています。
そこで今回は、退社は各人の自由でいいけれど、定時9時出社を求めるフレックスタイム制は法的に問題ないのか、詳しく確認していきたいと思います。
そもそもフレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは1か月以内の一定期間について総労働時間(所定労働時間)を定め、その期間中の各日において、社員が自由に自分の意思で始業・終業時刻を選択して勤務するものです。本来は始業・終業時刻が決められた定型的勤務であるところを、労使協定の手続きと就業規則への規定を行うことで、特別にフレックス勤務が認められるものです。
一般的には、必ずその時間帯は勤務しなければならない時間帯(コアタイム)と、その時間帯であれば社員がいつ勤務してもいい時間帯(フレキシブルタイム)、標準となる1日の労働時間(年休を取得した際に支払われる賃金の算定の根拠となる労働時間)が決められています。
コアタイムを設けた場合には、これを正当な理由なく守らなかった社員について、「コアタイムの遅刻、早退、欠勤」制度を設けることは差し支えありません。コアタイムは社員にとって必ず勤務しなければならない時間だからです。
そこで、「コアタイムの遅刻、早退が2回に及んだときは、1日分の欠勤として減給制裁の扱いとする(賃金カットする)」旨を、就業規則に規定することもできます。また、コアタイムの遅刻、早退、欠勤を、昇給・賞与・昇格などにかかる人事評価の査定対象とすることも問題ありません。
9時に出社させたい、実務的にどうなる?

前段でお伝えしたようにフレックスタイム制は、始業時刻と終業時刻を社員自身が選択できることを要件にしています。始業時刻または終業時刻の一方についてだけ社員に選択させるのはダメなので、冒頭の例のように「出勤は定時の9時」と始業時刻を固定することは認められません。
では、朝の9時に顧客対応で必要な人員を確保するにはどうすれば・・・その解決策のひとつにコアタイムを9時以降に変更することが考えられます。その際、フレキシブルタイムのスタートをより早く7時から8時にする、もしくはコアタイム以外を完全にフリーなフレキシブルタイムにする必要があります。
というのも、通達において「フレキシブルタイムが極端に短い場合、コアタイムの開始から終了までの時間と標準となる1日の労働時間がほぼ一致している場合など、基本的には始業と終業の時刻を社員の決定にゆだねたことにならないので、フレックスタイム制の趣旨に合わない」との旨が定められているからです。
コアタイム、フレキシブルタイムについては、就業規則に規定しておく必要がありますから、コアタイムの変更に伴い、所定の手続きを経て従前の就業規則の変更を行うことになります。また労使協定にも定めなければならないので、就業規則の変更に伴い労使協定の改定も必要となります。
**
フレックスタイム制はひとつの労働時間制(働く要件)なのであって、「フレックスタイムで働く権利を社員が持っている」ということではありません。
会社には、フレックスタイム制とはいえ、社員の労働時間を把握しなければならない義務があるので、時には個別の指導も必要でしょう。社員の制度に対する理解不足を補っていくということです。
制度を上手に活用するため、管理職や人事担当者には社員にまかせっきりにしないで、労働時間の把握をしっかり行うことが求められます。


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事