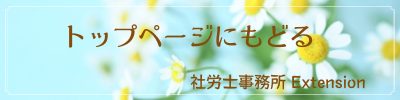うちの仕事には、ゆくゆくは○〇の資格があったほうがいい。ただ、入社してからは色々忙しいので「入社前に取っておくんだった」とみんな口を揃えて言っている。いっそのこと内定期間中に資格取得を奨めてみようか。インセンティブとして、資格を取って入社した人の試用期間を通常より短くする、というのはどうだろうか?
**
学生の身分でさほど忙しくないと思われる内定期間中に、会社が奨める資格を取得してもらうと合理的なのでは?と考える上司です。
とはいえ試用期間の短縮について、内定中に資格を取得して入社してきた人とそうでない人に差をつけて問題はないのか?とのギモンが頭をよぎります。
そこで今回は、内定期間中に会社が奨める資格を取得した新入社員の試用期間を短縮しても問題はないのか、詳しく確認していきたいと思います。
試用期間とは

試用期間は新入社員の教育を行うとともに、向き不向きの判定を行うという2つの機能を持っています。採用面接では社員としての適格性を適切に判断するのは難しく、試用期間を設けて実際の働きぶりや言動をみることで、最終的に社員として雇用するかどうかを決定するからです。
つまり試用期間とは、社員として会社に貢献するために必要な基本知識や仕事のやり方、技術を習得させながら、職場での人間関係に順応できるのか、またそこで能力を発揮できる資質を備えているのかを判定する期間だといえます。
試用期間制度を定めるかは、原則として、企業の自由であり実際のところ様々でしょう。試用期間について「〇〇か月でないとダメ」といった法的な規制はないからです。
ただ、試用期間中の労働契約が法律的にどんなものかというと、一般的には「解約権留保付の本採用契約(社員として不適格とジャッジしたときは解約できる権利が留保されている労働契約)」として解釈されています。
試用期間中の働き手は、解約権が留保されているという不安定な地位に置かれているので、試用期間の長さは合理的なものでなければなりません。不必要に長い場合は公序良俗に違反すると判断されることもあります。
資格をとった人の試用期間を短縮してもいいの?

前段でお伝えしたように、試用期間中の働き手は不安定な地位に置かれています。そこで、入社前に資格を取得した人には一定の適格性があるということで、この期間を短縮することはそれなりの合理性があり、働き手にとってもメリットがあるので、法的な問題はありません。
そこで「資格を取得した人とそうでない人の扱いを変えてもいいの?」とのギモンが浮かぶかもしれません。
これについては、資格を取得しなかった人に対して優遇措置がとられていないというだけであって、就業規則に定められている通常の試用期間が適用されているということです。そのため、特段の不利益を与えるものではないので問題はありません。
ただし、入社前に資格を取得しなかった人に対して、たとえば試用期間を通常よりも延長するなど与える不利益が大きい場合は問題となる可能性があります。事実上、入社前の資格取得を強制していることになるからです。
会社が資格取得を奨励すること自体は問題ありませんが、内定期間中は学生の身分であり、学業優先の配慮が求められるため、資格取得を強制する要素が強くなると問題となるおそれがあり、注意する必要があります。
**
「試用期間はどのくらいの長さにするのが妥当?」
あるあるのギモンですよね。改正前の労基法第14条が「労働契約の期間を定める場合には1年を超えてはダメ」としていたことから、もっとも長いものでも、最高で1年と解釈するべきだろう、と考えられてきました。
実際のところ1年は長すぎるのではないか、という問題もありますが、判例上、1年が長すぎるので無効だとする取扱いはなされていません。
とはいえ実務上では、試用期間の長さは法律で決められているわけではありませんが、3か月から6か月程度が一般的だといえます。


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事