
関連会社である当社に、本社から3年にわたって出向してくれていたAさんが、うちに転籍してくることになった。労働契約を結ぶにあたって諸々の条件を調整中だが、年次有給休暇はどうなるんだろう?
**
はじめての転籍社員の受け入れにあたり、大わらわになって準備に取り組む人事担当者さんです。とりわけ、年休の付与にあたって頭を悩ませています。
3年間の在籍出向期間についても、年休の算定における「継続勤務」に通算するべきなのか?というのが悩みのポイントです。
そこで今回は、在籍出向後に出向先企業に転籍した場合、年休付与日数をどうカウントすべきなのか、詳しく確認していきたいと思います。
年休付与にかかる継続勤務とは
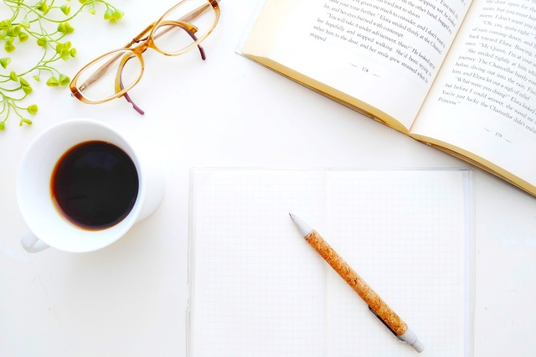
入社後、最初に年次有給休暇の権利が発生するのは、入社日から6か月間継続して勤務した場合です。
つまり、最初の年休の発生要件は、「6か月間継続勤務して全労働日の8割以上出勤したこと」になります(以降1年間継続勤務して全労働日の8割以上出勤すること)。
ここで、「1年間継続して勤務した」「2年6ヵ月継続して働いた」など、「継続」して働いたとは、どういう状態のことを指すのかが問題となります。
これについては行政通達によって、下記のような内容が示されています。
- 継続勤務とはその会社における在籍期間(雇用契約が存続する期間)のこと
- 継続勤務かどうかは、勤務の実態に即して判断すること
- 次の場合、実質的に雇用関係が継続しているなら勤続年数を通算すること
- 定年退職による退職者を引き続き嘱託社員として再雇用した場合(退職金を支給している場合を含む)*ただし、退職と再採用の間に相当の期間があり、雇用関係が途絶えている場合を除く*
- 日雇い労働、2ヵ月以内の期間労働、4か月以内の季節労働、試用期間中の労働、これらに従事する者でも、実態からみて引き続き雇用されている場合
- 臨時工が1ヵ月ごとに雇用契約を更新されて6ヵ月以上に及び、その実態からみて引き続き雇用されている場合
- 在籍出向の場合
- 休職から復職した場合
- パート社員などを正社員に切替えた場合
- 会社が解散し、社員の待遇を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合
- 社員全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後改めて一部の社員を再採用したが、事業の実態は人員を縮小しただけで、従前とほとんど変わらず事業を継続していた場合
「在籍出向→出向先へ転籍」の場合はどうなる

在籍出向は、出向元の社員としての地位を持ったまま出向先で働かせるものなので、出向元と出向先の両方で二重の労働関係が成立します。出向社員は、出向元企業の社員であると同時に、出向先の社員でもあるということです。
前段でお伝えしたように、年休の継続勤務については実質的にみて雇用関係が継続しているか、という観点から判断されることになります。
出向期間中は、出向先との間に雇用関係の実態があり、そのまま同一企業に転籍した場合、在籍出向の期間を通算する必要があります。
ただし、在籍出向から転籍に至るまでに相当な期間が空くと、「継続」勤務が「中断」されることになります。この「相当な期間」が果たして、どのくらいの期間のことをいうのかが問題ですが、これは単に期間の長さだけで決めることはできません。
- 再雇用(転籍)の手続きがきちんとなされているか
- (再雇用までの)期間の目的
- 確実に再雇用(転籍)されるのか
- 再雇用(転籍)の実態
上記の点を総合的にみて判断することになり、一概に何日間なら中断と決められていません。
(これについて、「30日〈解雇予告〉」「14日〈民法の期間の定めのない雇用契約〉」なら中断と認められる、と法律の趣旨からさまざまな見解があります。個別の事案については、所轄の労働基準監督署に相談されることをお勧めします。)
**
出向社員の転籍に際して、年次有給休暇の付与にかかる勤続期間は元の企業と転籍先で通算するのか、という問題は後になってトラブルに発展しがちです。
曖昧なままにしておかず、しっかり協定しておく(元の会社、転籍先、社員の三者間協定が望ましい)ことが大切です。


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事





