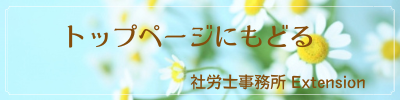パート社員のAさんには、お店の繁忙に合わせて週3日、火曜に4時間、木曜に5時間、金曜に6時間来てもらっている。本人の都合で休むのはもちろん構わないけれど、金曜日に限って年休が多い・・・ちょっとモヤモヤするんだけど(;´Д`)
**
1日の所定労働時間が長い(つまりお店が忙しい)日に限って、年休を取得するパート社員への対応に困惑する店長さんです。
お店が忙しいのに人手が足りないのも困りますし、「時給の金額×その日(年休日)の所定労働時間数」がパート社員の年休当日の給与となるので、「(所定労働時間の長い日に休むのは)ワザとなの?」との疑念が湧いてくるからです。
そこで今回は、所定労働時間が日によって異なるパート社員の年休問題について、詳しく確認していきたいと思います。
年休日の賃金はいくらになる?

年次有給休暇中の賃金については、就業規則に定めることによって、「平均賃金」または「通常の賃金」を支払うことになります。労使協定によって健康保険の「標準報酬日額」に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによることになります。
【原則】就業規則の定めによる場合
①平均賃金
②(所定労働時間労働した場合に支払われる)通常の賃金
【例外】労使協定で定めた場合
③健康保険法定める標準報酬日額に相当する金額
年休日の賃金は、就業規則の絶対必要記載事項(どんなときでも必ず書いておかないといけないこと)としての「賃金」に該当するため、上記の①~③のいずれを選んでも、これを就業規則に規定しておく必要があります。
実務上は、上記②によることが多いでしょう。この場合、時給制の賃金については、「その金額にその日の所定労働時間を乗じた金額」で計算した金額となります。つまり時給制のパート社員の場合、本人の時給の金額にその日(年休を取った日)の所定労働時間数を乗じた金額が、パート社員の年休当日の給料となります。
所定労働時間が長い日に休むパート社員への対応は

前段でお伝えしたように、1日の所定労働時間が日によって異なるパート社員が年休を取得した場合、年休日の所定労働時間が6時間であれば6時間分の、4時間であれば4時間分の賃金を支払うことになります。
所定労働時間の長い日に年休を取得されると、会社側の負担は避けられません。「1日〇時間、週〇時間労働」といった原則的な労働時間制ではなく、1日の所定労働時間が異なるという変則的な労働時間制を設定した以上、このような副作用は避けられないということになります。
「せっかく休むなら所定労働時間の長い日に休んだほうがおトク♪」と、パート社員を誤った方向性に導かないためには、1日あたりの所定労働時間について極端な長短をつけないほうがよいといえます。
そもそも1日の所定労働時間が異なるという変則的な労働時間制を設定するのは、仕事の繁忙に対応するためなので、忙しい日の年休申請について「なるべく他の日に変更してほしい」との希望を本人にお願いすることも必要でしょう。
(↑時季変更権が行使できるような要件が備わっていないときに行う「時季変更の申込み」にあたります。会社側の「申し込み」(お願い)に社員が応じて他の日に変更することで合意できれば、社員の承諾によって年休日の変更が成立することになります。)
**
場当たり的にパート社員に働いてもらっていると思わぬ問題が発生します。年休日の取扱い、年休日の賃金計算を誤ったりするなど、管理コストを増やすことになりかねません。
そのため、「1日の勤務時間や週の勤務日数はどうするのか」「社会保険や雇用保険の適用のある基準まで働いてもらうのか」「希望年収(就業調整)をどのくらい聞き入れるのか」「どんな業務内容、職種にするのか」といったことを考えたうえで、はじめにパート社員の労働条件をきちんと決めておくことが大切です。


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事