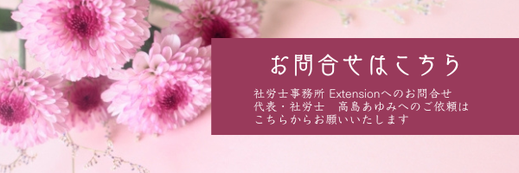組織改編によるポストの廃止で、解雇となる社員がいる。年休の残日数は前年分を合わせて40日あるので、解雇予告期間中に消化しきれないだろう。会社都合の解雇なので、会社は何か特別な対応をとらなくてもいいのかな・・・
**
会社都合による解雇にあたって、対象社員の年休の取扱いに悩む人事担当者さんです。会社都合で解雇するのだから、何もしないままでいいわけないよね・・・と考え込んでいます。
会社都合による解雇の場合、年休の残日数について買い上げを行ったり、年休をすべて消化できるよう解雇日を繰り下げるといった対応が必要なのでしょうか。
そこで今回は、会社都合で社員を解雇するとき、消化しきれない年休について特別な対応が必要となるのか、詳しく確認していきたいと思います。
解雇予告期間中の年休

社員がもつ年次有給休暇の請求権は、法律上は労働義務の免除を求める権利のことであり、労働義務のある日(=営業日)についてのみ認められるものです。
社員が退職して会社との労働契約の関係が終了すれば、会社に対して労働義務の免除を求める根拠はありません。「会社と社員」という関係が消滅し、その関係の存続を前提とする年休の請求権も消滅するからです。
労基法では、「年休は原則として社員の希望どおりに与えなければならない」とされています。例外的に「事業の正常な運営」を妨げる事由がある場合には、時季変更権の行使によって拒むことができるだけです。時季変更権を行使するには、変更して与える他の日がなければならないので、退職日を超えて時季の変更を行うわけにはいきません。
したがって解雇予告期間中であっても、労働契約の関係があり、労働義務のある日があれば、年休の請求は当然可能です。ただし、解雇予告期間中ですから、時季変更をするについても、ほとんど変更の対象にできる期間はないと考えられます。
会社都合で解雇する社員の年休の取扱い

前段でお伝えしたように、解雇によって労働契約関係がなくなれば、未消化の年休があっても「年休をとりたい」と請求することはできません。
では会社都合による解雇の場合、年休の未消化分を買い上げしたり、解雇日を繰り下げるといった何か特別な対応が会社には求められるのでしょうか。
結論から申し上げると、解雇日までに消化できない年休について、労基法上何か特別な取り扱いをしなければならないという義務は会社にはありません。もちろん、解雇日までの労働義務のある日に年休の請求があれば、会社は付与しなければなりませんが、それでも消化できない年休について買い上げをしたり、解雇日を繰り下げたりしなくても労基法上は問題ありません。
とはいえ会社都合で解雇する場合、社員の納得や理解を得るというプロセスはとても大切です。解雇の合理性が問われることを考えると、人材マネジメント上会社ができることはやっておくべきでしょう。
会社都合による解雇に対する納得(解雇に異議を述べない)につなげるため、会社から金銭的な補償や再就職の支援を行うことが一般的にあります。それと同様に、年休の未消化分について、労基法上の義務はないとはいえ、年休の買い上げや解雇日の繰り下げといった措置を取ることは十分に考えられます。
**
日本では、解雇に至る前に退職勧奨が行われる場合が多いです。会社と社員との間で話し合いによる解決を図るためです。
解決手段として、会社による金銭的な補償(退職金の上積みなど)や再就職支援を提示することも行われています。
なお退職勧奨による退職の場合、退職理由は「自己都合」ではなく「会社都合」になります(もちろん、対象社員の自由な意思決定を妨げる退職勧奨はダメです)。


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事