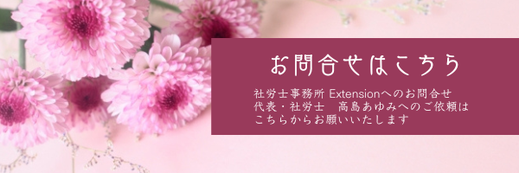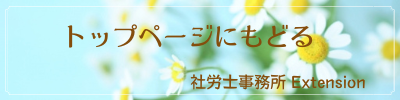来年度から役職定年制度を導入することになった。課長以上の職位を対象にして、55歳を解任年齢とすることになったが、役職を降りたシニア社員には割増賃金の支払いが必要となってくるのかな?
**
課長以上は労基法上の管理監督者として割増賃金を支払っていなかったけれど、役職定年後の取扱いはどうなるのか・・・と、ギモンが頭をよぎる人事担当者さんです。
役職定年とは、年齢などで一律に役職を解く制度です。役職者の在任期間が長いと、若手社員の昇進が遅れ、人事の停滞を招くことがあり、制度を導入する企業もみられます。
そこで今回は、役職定年後のシニア社員に割増賃金の支払いが必要になるのか、詳しく確認していきたいと思います。
管理職と割増賃金

管理職には、労基法における労働時間・休日に関する規定の適用はありませんから、時間外または休日労働に対する割増賃金の支払い問題は発生しません。
それは下記のような立場にあるため、一般社員と同じような労働時間規制の保護をしなくてもよいと考えられるからです。
- 経営者と一体的な立場であり、経営者に代わって一般社員をマネジメントする立場にある
- 一定の業務をマネジメントする地位にある、もしくは同等の地位(スタッフ職)にある
- 会社と社員の間にある、使用従属関係による拘束力が一般社員に比べて弱い
- 労働時間(始業、終業時刻など)について厳しい拘束がない
ここでいう管理職(管理監督者)とは、一般的には部長や工場長など、経営者と一体的な立場にたって、社員の労働条件の決定やそのほかの人材マネジメントにあたる人のことを指します。
とはいえ、「部門長だから(管理監督者に)該当する」「係長だから該当しない」ということではなく、その会社における役職の名称にとらわれず、実態に即して判断しなければなりません。
では役職定年によって役職を降りたシニア社員には、労基法における労働時間・休日に関する規定の適用はどのように考えるとよいのでしょうか。
役職定年後の割増賃金の支払いは?

管理職には労基法における労働時間・休日に関する規定が適用されない、というのは前段でお伝えしたように、従事する業務の実態に即して判断されるものであって、「部長だから」「課長だから」といった役職の肩書が問題なのではありません。
社員を課長に昇進させたからといって、労基法における労働時間・休日に関する規定が適用されない「管理監督者」に該当するものではありませんし、逆に役職定年によって課長職を降りたからといって該当しなくなるとも言えません。
あくまでも役職や地位、資格等級の名称にとらわれることなく、仕事内容、責任と権限、実際の勤務状況、賃金等の待遇面を総合的にみて、管理監督者に該当するかどうかを判断しなければなりません。
役職定年によって課長職を降りた場合も、その後に従事する仕事内容、責任と権限、実際の勤務状況、賃金等の待遇面を総合的にみて、管理監督者に該当するかが判断され、労基法における労働時間・休日に関する規定の適用の有無が決まります。
そこで経営者と一体的立場にある管理監督者と判断されなければ、労基法における労働時間・休日に関する規定は適用除外となりませんので、割増賃金の支払いが必要となります。
**
役職定年制度の難しい点は、役職を解いた後の配置問題です。多くの場合、役職者のこれまでの知識や経験、人脈などを活かすために、役職を務めていた元の職場に配置されます。
ですが、これまでの部下の同僚(もしくはその部下として)として働くことになるので、本人のモチベーションが落ちたり、元上司・元部下の関係がギクシャクしがちになります。
こういったことを理由に他の職場に配置するケースもありますが、いずれにせよ役職定年制度は、シニア社員のセカンドキャリアに大きな影響を与える制度といえます。


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事