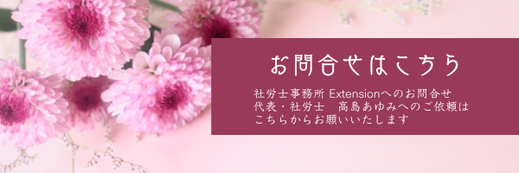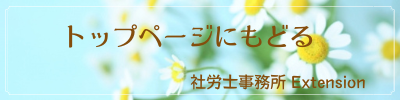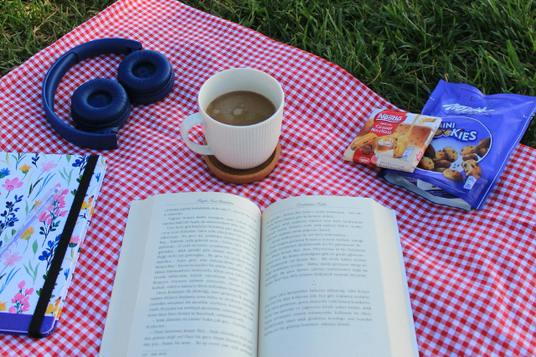
当社では、時効が成立した年休を買い上げてきた。取得しそびれてしまっている人も多かったからだ。とはいえ世の中の流れを受け、できるだけ年休を取得してもらおうと買い上げ制度を廃止することになった。今まであった制度を廃止することに、何か問題はないのかな?
**
時効成立後とはいえ、買い上げという取扱いではなく、できるだけ年休を取得させるという方向で検討を進める人事担当者さんです。
従来の制度を廃止することで、社員にとって不利益変更の問題は生じないのか?と判断に迷っています。
そこで今回は、年休の買い上げ制度の廃止に不利益変更の問題は発生しないのか、詳しく確認していきたいと思います。
年休の買い上げとは

年休の買い上げとは、社員が取得できなかった年休を会社が一定の金銭で買い取り、行使できなかった年休請求権に応じて、会社が補償的な取扱いをすることです。
社員の心身の疲労を回復させ、働くためのモチベーションを支えることが年休の本来の目的です。
年休と金銭を引き換えにすると、心身の休養と疲労回復は果たせないため、労基法では買い上げによって年休を実際に与えない行為を禁止していますが、下記の場合は違法になりません。
- 法定日数を超える部分の休暇日数分
- 時効によって消滅した休暇日数分
1.は、法律の最低基準を上回る会社独自の休暇のため、労基法の規制が及ぶところではなく、買い上げる旨を就業規則で定めても問題ありません。
2.は、そもそも時効で消滅するため、買い上げても法律に抵触しません。
とはいえ、もし買い上げる金額が高額なら(1日分の給料より高いなど)、年休を取得するよりも金銭的な魅力があるので、「年休をあえて取らない」という行動に社員を誘導しかねません。「生産性を上げて労働時間を短く、かつ利益もしっかり獲得する」という方向が理想的です。
制度の廃止で問題はないか

年休は、心身の疲労や働く意欲を回復させ、人間らしい生活を営むための社員の権利のひとつです。実際に休ませることが必要なため、労基法では「休暇を(実際に)与えなければならない」と会社に義務づけています。
そのため、時効成立後の年休であっても買い上げるという取り扱いはせず、できるだけ年休を取得させるという方向でマネジメントするものといえます。
「行使できなかった年休請求権に応じて、会社が補償的な取扱いをしてあげたい」ということなら、時効消滅する年休を積み立てて(年休の積立制度※)、本人の疾病による長期療養など治療と仕事の両立に活用するのもひとつの方法です。※年休の積立制度は、2年間で時効消滅する法定の年次有給休暇の残日数を、一定日数(通常は30~60日)に達するまで積み立てることを認める制度です(あくまでも消滅した年休の救済が制度の趣旨)。
年休の買い上げ制度の廃止に伴い、時効消滅する年休についての考え方を「金銭に換算」から「本来の目的の延長線上で活用」に変更する点で、労基法の定める本来の趣旨に合致しているといえます。
単に制度を廃止するだけでなく代替の措置をとり(年休制度の積立制度の導入など)、年休の取得率アップに向けた取り組みが実際にみられる場合、不利益変更の問題は生じないと考えられます。
**
世の中の流れと逆行するとはいえ、年休を買い上げざるを得ない場合もあるでしょう(自社製品の特需のためどうしても休めなかった社員に対するフォローのため買い上げた、など)。
ただし、それが当たり前のことになってしまうと、将来的に会社にプラスになるとは言い切れませんから、よく検討したいですね。


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事