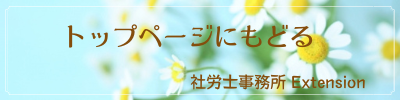人手不足なので、子育て中の主婦の人にもパートでいいから来てほしい。育児や家事に充てる時間を確保してもらうためにも、勤務時間の希望を聞いて柔軟に対応したい。とはいえ、パートさんの数だけ勤務時間がバラバラになるなら、就業規則にどう定めたらいいの?
**
主婦層にも求人に応募してもらいたいので、家庭や子育てとの両立が無理なくできるようにと考える店長さんです。
ですが、たとえばパート社員を10人採用したとして、10通りの勤務時間を就業規則に書くのか?これからさらにパート社員が増えたとして、その都度勤務時間を書き足さないといけないの・・・?勤務時間の章だけでものすごいボリュームになってしまう・・・と悩んでいます。
そこで今回は、パート社員によって始業・終業時刻が異なる場合の就業規則の定め方について、詳しく確認していきたいと思います。
労働条件の明示は重要

就業規則の記載事項には、どんな場合であっても必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項と、定めをする場合においては必ず記載しなければならない相対的必要記載事項があります。
「始業および終業の時刻、休憩時間、休日」については、絶対的必要記載事項となっているため、就業規則に必ず記載しなければなりません。
また会社は、労働契約の締結に際して社員に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないことになっています。一定の事項については、書面の交付により明示する必要があり、この書面で明示すべき労働条件には、「始業および終業の時刻、休憩時間、休日」が含まれています。
現在では多様な働き方のニーズが高まっているので、詳細な労働条件について明確な合意がないままで社員を働かせていると、後々トラブルに発展するかもしれないリスクがあります。
社員に納得して働いてもらうためにも、また無用なトラブルを回避する点からも労働契約時における労働条件の明示は重要といえます。
パートの勤務時間がバラバラで就業規則はどうなる?

同じ職場で始業・終業の時刻が社員の勤務態様(日勤、夜勤、シフト制など)、職種等によって異なる場合には、就業規則にそれぞれの勤務態様または職種ごとに規定しておかなければなりません。
一般的に、複数の勤務パターンが決まっている場合は、就業規則にそのパターンを記載したうえで、個別の労働契約においてそのいずれかのパターンの始業・終業時刻を明示することになります。
ただし、パート社員のうち本人の希望によって勤務態様または職種別に始業・終業の時刻を画一的に定めないことにする者については、就業規則では基本となる始業・終業の時刻を定め、具体的には各人ごとに個別の労働契約等で定める旨の委任規定を設けることでよいとされています。
つまり、就業規則に基本となる始業・終業の時刻を記載し、あわせて「具体的な始業・終業時刻は個別の労働条件通知書に定める」といった旨を記載することになります。
なお、休憩時間、休日についても同様の考え方をとることになります。
**
「パートとアルバイトってどう違うの?」とのギモンをお聞きすることがあります。
パートタイマーやパート社員という法律上の呼称はありませんが、一般的にパート・有期雇用労働法でいうところの「短時間労働者」がこれにあたります。
またアルバイトについても特に法律上の定義があるわけではありませんが、本業が別にあって副業として臨時的、短期の業務に就く者をいいます。たとえば、学生が働くような場合です。学生は昼間に学校へ通学することが本業なので、その就業はアルバイトとなります。


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事