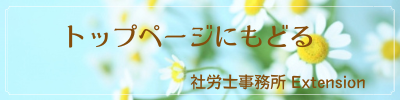「社員の給与を決めるとき、真っ先に考えるべきはなんだろう?」
まず会社として検討するべきは「その人件費は適正なのか?」です。目標とする利益(せめて赤字にならない)をしっかり出せて、企業の支払い能力に合っているどうかの検討が必要です。
そうすると「適正な人件費から昇給額を設定していくと、若手の昇給を低く抑えざるをえない。採用時の賃金をどれくらいにすればいいのか?」という課題がでてくるかもしれません。
社員の役割や貢献度に見合った賃金を決定することがトレンドだとしても、社員の月給を考えるとき、若手にもベテランにも納得してもらうにため、時には年齢や勤続年数についての「オプション」を検討することも必要となるでしょう。
そこで今回は、社員の月給を決めるとき考えたいポイントについて、詳しく確認していきたいと思います。
若手社員の月給に配慮したい

確かに毎月の給料は、競合他社との比較の対象になります。社員にしても同世代の友人と比較するかもしれません。採用市場において人材獲得の競争力を高める重要な手段といえます。
若手人材を確保するには、20代から30代半ばまでの昇給水準を高めに設定しておかないと他社と比較した際に見劣りする可能性があり、離職の原因になることもあります。
特に20代前半の場合、給料額だけを考えると、毎日会社へ通勤して職責を果たすよりも、気楽なアルバイトを掛け持ちするほうがいいのではないか?との発想を持ってしまうこともあるようです。
こんなとき、オプションとして、若手社員に年齢を考慮した昇給加算を考えてみるのもひとつの方法です。
たとえば「40歳までの社員には別途いくらかの昇給額を加算する」といった処置です。41歳以上には、年齢というよりも実力で昇給を勝ち取ってほしい、とのメッセージをこめることもできます。
ベテラン社員のモチベーションを保ちたい

前段の続きで言うと、41歳以上は年齢を考慮した昇給加算がなくなります。もちろん昇格できれば問題はないのですが、昇格基準に満たない場合、給料が頭打ちになってしまいます。
制度のポリシーとしてはその通りなのですが、長年勤めたにも関わらず少しも昇給がないと仕事へのモチベーションが維持できるのかと、心配される経営者の方もいらっしゃるかもしれません。
その対応策として、長年勤めてもらった功績へのインセンティブとして、1年あたり500円の昇給を行うのもひとつです。
「500円程度でやる気なんか引き出せるのか?」と思われるかもしれませんが、これはどちらかというと引き止め策が目的です。「(昇格基準には至っていないが)長年コツコツ仕事をやっていることについては、会社は見ているよ」とのメッセージです。
1年あたり500円の昇給なら10年間でも5,000円ですから、コストへの影響も、社員の役割や貢献度に見合った賃金を決定するトレンドへの影響も、それほど気にすることはないと思います。
なお勤続年数への配慮は、中途採用者が入社してきたときにその効果がよくわかるでしょう。たとえば、30歳で同い年の社員でも、22歳で入って9年目社員と中途採用で1年目社員が同じ給料では、前者のモチベーションが下がってしまうかもしれませんよね。
人材の定着率に悩む場合、いちど検討してみるのはいかがでしょうか。
その他月給で考えておくべきポイント

冒頭でお伝えしたように、月給をきめるときまず会社として考えるべきは、支払い能力に合っているかどうかです。
そのうえで、「社員が生活できるか」「ポジションを明確に示すことができるか」「仕事内容に応じたものになっているか」「社員のやる気を引き出せる程度のものか」について、検討していくことになります。
そもそも生活ができないような水準では、社員は腰を据えて働くこともできません。
また資格等級におけるひとつ上のポジションへの昇格は、自分の働きぶりが評価され、ステップアップのために仕事の難易度、処理量、求められるアウトプットの質などのグレードが上がるということです。
それなのに等級間の格差が小さければ、昇格のメリットを感じることはできませんし、「働きぶりを認められた!」と思えないので社員のテンションも低いままでしょう。
もう一度、社員の月給を検討するときのポイントをまとめましょう。
- 目標の利益を出せるか
- 社員が生活できるか
- ポジションを明確に示せるか
- 仕事内容・程度に応じた程度になっているか
- 社員のやる気を引き出せる程度のものか
**
毎月の給料を考えるとき、「これは(社員にとって)高いのか、低いのか」といった額の多寡に気をとられてしまいがちですが、これらの要素を踏まえて総合的に検討することが大切です。
今回は、年齢や勤続年数についての「オプション」についてお伝えしましたが、このように月給を決めるにあたって、選択肢はいろいろあります。どれがよくて、どれならダメ、というのはありません。
自社にマッチした月給の決め方へのヒントになればと思います。


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事