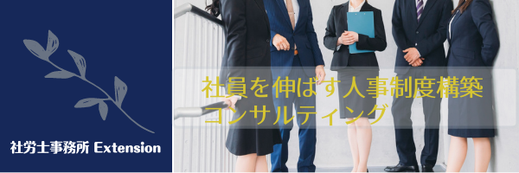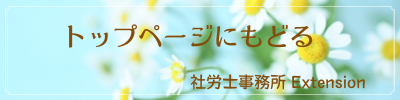新規学卒者は会社ランキングに掲載されるような会社にしか入りたがらない。中途者だとより高い給料をもらえる会社しか眼中にないだろう。人手不足で売り手市場のなか、人材を獲得するのは至難の業だ・・・
(某メーカー企業の採用担当者談)
**
生活するうえでお金は大切なので、家族構成や年齢を考えたときに給料額というのは、求職者にとって重要な要素なのは間違いありません。ですが、本当に働き手にとって「お金しか重要でない」のでしょうか?
企業の採用活動が思うようにいかないとき、どうしても給料面のせいにしがちですが、多額の広告費をかけたり、世間相場よりもべらぼうに高い給与額を提示しなくても、人材獲得に悩まない会社もあります。
そこで今回は、人材争奪戦が繰り広げられる採用市場で人材獲得に困らない会社の共通点をみていきたいと思います。
給料の高い企業は魅力的?
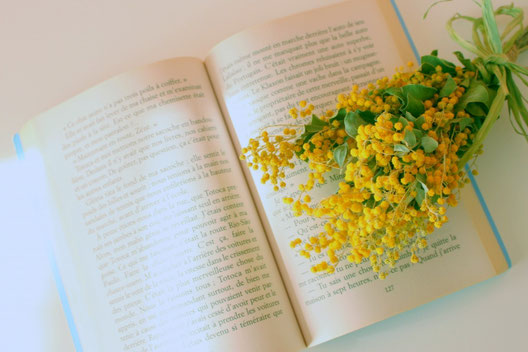
人材獲得に成功している会社とは、「給料以上のものがこの会社にはある」と考えているような会社です。
お金のために来る人を、誘引するような採用方法をとっていないのです。「お金を上回る会社の魅力」に、価値を感じる人が来てくれるような、会社づくり(そしてそれを社内外にアピールすること)を常に考えています。
会社を伸ばすには、良い人材を獲得する必要があります。そのためには給料を上げることではなくて、社員が失敗を恐れずチャレンジできて、働きがいのある環境をまず整えることからだ、と考えているからです。
たとえば「週休3日制」「週3日ノー残業デー」といった新しい働き方を求めている人は、給料に大きなこだわりを持っていません。給料ではない魅力を会社に求めています。
たとえば「まだ幼いこどもと一緒の時間をたっぷり過ごしたい」「家族の闘病、通院に寄り添いたい」「人生100年、自分の市場価値を高めるために学び直しで大学院に行きたい」ということで、こういった働き手の事情に理解があって柔軟に働ける環境を探しているのです。
採用活動では、会社の社風や価値観(働き手の事情に対して寛容であり前向きに働き方を考える、など)を明らかにして、それを求める人にアピールすることがとても大切です。
採用面接は伸びる会社の生命線

就職活動の経験があれば、みなさん実感されることと思いますが、自分に合う会社もあれば合わない会社もあります。世間的に有名であったり、素晴らしいと評される会社であっても、合わない人には合わないのです。
今は「自由な働き方」に憧れる人が多いのかもしれませんが、「自発的にチャレンジングな目標を立てるのはキビシイな・・・」と感じる人には、丁寧に指示を受けながら管理される働き方が合っているのかもしれません。
体育会系のような熱い社風の会社であれば、自然になじめる人は居心地が良いと感じるでしょうが、なじめないひとには厳しい環境かもしれません。
よって、社員の採用面接において、会社が持つ文化や社風にその人(入社希望者)がどれだけフィットしているのかを見極めることはとても大切です。会社の価値観に合わないのに、人が足りなくなるかもしれないので頭数合わせでとりあえず採用しておく、という事態は避けるべきです。意識の低い人を採用してしまうと、せっかく働きがいのある環境をつくっても水を差しかねないからです。
会社を伸ばすには採用面接は生命線です。採用面接を成功に導くには、会社の価値観を明らかにして、社内で共有しておくことがポイントです。
中途採用より未経験者を育てる

また、企業の採用活動を難しくしている要因のひとつに、人手不足が挙げられます。そのため人材紹介においては、経験者の紹介手数料が年収の40~50%となることもあるようです。
とはいえ、2016年の労働力調査によれば、若年無業者(ニートなど15~34 歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない者)は57万人と、前年に比べ1万人の増加となっています。
(総務省統計局 労働力調査よりhttp://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/index.pdf)
企業が求めるスキルと、彼らが持っているスキルのミスマッチが起きている状況がわかります。
そこで、中途採用市場における経験者の採用コストが高騰するのなら、教育費をかけて若手の未経験者を育てるのもひとつの方法です。若手の未経験者を育てることは、人手不足による採用難の打開策といえます。
**
人への投資は、今すぐに花開くものではありませんが、必ず将来的には会社を支える資産になります。
人材争奪戦が過熱している今の時代、「億単位(もしくはそれ以上)もする設備投資と比べれば教育コストは安いもの」と考えてみるのも、人材獲得問題を乗り越えるひとつの考え方かもしれません。


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
■提供中のコンサルティング
■顧問契約・単発のご相談を承っています
■役に立つ無料コンテンツ配信中
■ブログの過去記事